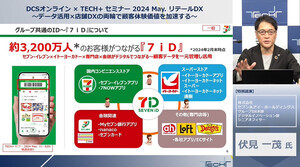宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月26日、イプシロンSロケット第2段モーター「E-21」の地上燃焼試験中に起きた爆発事故について、調査状況を報告した。原因の特定にはまだ至っていないものの、輸送時の振動またはイグブースタの溶融により、推進剤や断熱材が損傷し、異常燃焼が発生した可能性が浮かび上がってきた。
この事故は、2023年7月14日、JAXAの能代ロケット実験場(秋田県能代市)で発生した。現在開発中の新型固体ロケットであるイプシロンSの第2段モーターの性能を確認するために行ったが、燃焼開始後、約20秒付近から燃焼圧力が予測より高くなり始め、約57秒で爆発。モーターの破片は四散し、試験を行った真空燃焼試験棟は激しく炎上した。
JAXAは同31日に、調査状況の第一報を報告。燃焼圧力は仕様の範囲内であったため、直接の原因とは考えられず、何らかの理由で想定外の高温が発生したことにより、モーターケースが許容温度を超過、構造の強度を維持できなくなり、爆発に至った可能性が高いことが明らかになっていた。
第2段モーターはどこから壊れたのか。前回の報告では、耐圧容器となるモーターケースと、燃焼ガスの噴射口となるノズルが可能性として残っていたが、その後の調査により、ノズルの設計不良は可能性から排除。壊れたのはモーターケースであると特定した。
さらに、モーターケースの前方ドーム、側面の平行部、ノズル側の後方ドームなどに分割して部位の特定を進め、後方ドーム側から壊れたことも分かった。加速度・歪とも、前方側より後方側の方が早く変動していること、爆発直前に推力が増加していることなど、試験時に計測されたデータと整合していることが決め手となった。
では、後方ドームはなぜ壊れたのか。爆発の原因は前述のように想定外の高温と考えられているが、その理由としてあり得るのは、推進剤の損傷とインシュレーション(断熱材)の損傷である。いずれにしても、損傷した場所で燃焼が拡大し、高温を引き起こすのだが、詳細FTA(故障の木解析)で分析した結果、要因を2つに絞り込んだ。
1つは、輸送時の振動。推進剤は、モーターケース内に充填されているが、変形による干渉を避けるために、前方側と後方側には少し隙間が入っているという。推進剤側とモーターケース側にはそれぞれインシュレーションが貼られているのだが、第2段モーターは縦置きで輸送しており、振動で推進剤が上下に動き、接触した可能性が考えられる。
第2段モーターは、愛知県の武豊町で充填され、トラックで能代まで陸送した。輸送コンテナ内にはセンサーを設置しており、最大2G程度の加速度がかかっていたことが分かっているが、特に問題になるものでは無かったという。過去の強化型イプシロンでも同様に縦置きで輸送していたが、異常が発生したことは無かった。
ただ、イプシロンSのE-21は推進剤の量が増えており、この隙間の設計も少し変更されていた。JAXAは具体的な隙間の状況については非公表としたが、この設計変更が要因となった可能性はある。
そしてもう1つは、イグブースタという部品の一部が溶けて飛散したというシナリオだ。今回の事故後、周囲に四散した破片は大部分を回収したものの、このイグブースタの先端部は見つからなかった。爆発時の衝撃で破損した可能性もあるが、もし燃焼中に溶けていた場合、以下のようにして爆発に繋がった可能性が考えられる。
イグブースタは、推進剤の点火器であるイグナイタを構成する部品の1つである。ロケットのような大きな固体モーターは一度で点火するのが難しいため、まず小さい火種を作り、それを段階的に大きくしていく方法が採用される。イグブースタは、その最初の火種となる部分で、ここからイグナイタ→推進剤と着火する仕組みだった。
イグブースタは金属製だが、本来は燃焼後も形状が残っている設計になっており、もし燃焼中に欠損したのであれば、想定外の高温が加わった可能性がある。溶融した金属がイグナイタ外に流れ出て、燃焼ガスに乗って後方ドーム側に移動、そこで推進剤かインシュレーションに当たって損傷を引き起こした、というシナリオだ。
イグブースタ自体は新規開発品ではない。H-IIAロケットの固体ロケットブースタ(SRB-A)や、H3ロケットの固体ロケットブースタ(SRB-3)でも使われており、これに問題があったとは考えにくい。しかし、モーターごとにイグナイタの設計は異なり、E-21でも新しい設計になっていたため、イグブースタへの加熱量が過大だった可能性がある。
JAXAは今後、さらなる追加検証(解析、試験)を行い、原因を特定する方針だ。イプシロンSの初打ち上げ時期については、今のところ2024年度後半から変更されていないが、原因の特定が進めば、必要な対策も固まるので、新たな打ち上げ時期がどうなるか、見えてくることになるだろう。
なお、SRB-A/SRB-3への影響についてだが、今回の原因調査の進展により、どちらも懸念は無いと結論付けた。隙間形状がE-21とは異なるほか、輸送も横向きであるため、接触が発生しないことを確認。またイグナイタの設計が異なり、イグブースタが溶融しないことも解析で確かめたとのことだ。