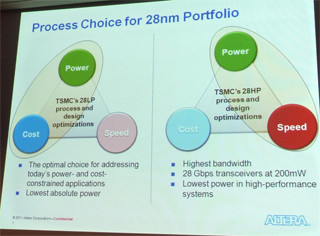Alteraは、米国にて3月28日(米国時間)より開催されているGlobalpressのElectronics Summit 2011のキーノートスピーチとして29日(同)、「The Optical Future」と題した講演を行い、同社が研究を続け、近い将来実用化する可能性を持つ光伝送技術の紹介が行われた。
無線、有線問わずネットワークの伝送速度は年々高速化してきたが、このままバンド幅が限界無く向上していくとどのような未来になるだろうか。例えば、フルHDの動画を瞬時にダウンロードできたり、携帯電話で3Dのビデオカンファレンスを行ったり、立体映像のe-Mailメッセージを送れたり、リアルタイムにビデオ監視システムで感知した危険を明示したりできるようになると、同社では説明している。
現在、メトロネットワークやコアネットワークで用いられてきた光伝送技術は家庭にまで到達し、携帯電話やスマートフォンの基地局でも用いられるようになってきた。しかし、データセンター間や国をまたぐ場合といったノード間はそうした光伝送だが、それらの機器のシャシーにはプリント基板が用いられ、LANケーブルなどの銅線がそれら基板をつなぐため、光伝送の速度に比べて、そうした場所がボトルネックとなり伝送速度の遅延を生じさせている。
また伝送速度が上昇していくことで、半導体チップで生じているような銅配線の伝送損失の問題や伝送距離の問題が生じてくるほか、信号をノイズから保護するために配線が複雑化したり、高品質なプリント基板を用いなくてはならなくなるなどの課題が今後生じてくる。
現在、一般的なプリント基板はFR4(4層)だが、10Gbpsを超えた伝送速度では損失が増大、30Gbpsになると10Gbpsの3.5倍の損失となる。こうした伝送損失は高品質なプリント基板(例えばパナソニック電工の低誘電率・低誘電正接・高耐熱多層基板材料「MEGTRON 6」)などを用いることで対応が可能だが、30Gbpsにおける損失を帳消しにしてFR4基板での10Gbps程度の損失程度にしようと思うと実に5倍のコストがかかるという。
また、もし通信モジュールや半導体のパッケージを変更して解決ができるとしても、大幅な変更により従来のシャシーにそのまま用いることはできず、結局はシステムごとの入れ替え、ということとなり膨大なコストが要求されることとなる。
Alteraでは、これまでも伝送速度の向上に対応して、ノイズを押さえ込み、きれいな波形を維持するためにイコライゼーション機能(同社最新ハイエンドFPGA「Stratix V」ではデシジョンフィードバックイコライゼーション機能)をハードウェア搭載してきたが、銅配線が将来的に用いられる場合、ハードウェアとしてのそうした機能が限界に到達し、機器として実用的な活用が不可能と判断し光インターコネクトの、技術開発を行っているという。
半導体メーカーの光インターコネクトと聞くと、チップ内部の素子同士を光でつなぐといったものが想定されるが、同社が提示するものは、あくまで安価なFR4を用いることを前提に、チップ間(Chip-to-Chip)もしくはチップ-バックプレーン間(Chip-to-Backplane)、光モジュール間(Card-to-Card)などで低損失化や伝送距離の延長、伝送速度の向上などを実現するために光インターコネクトを用いるという。
気になるのは光インターコネクトを実装するコストだ。IntelがAppleのMacBook Pro向けにThunderbolt(Light Peak:開発コード名)を提供するが、この規格は現行の世代は銅配線を用いているが、元々の構想は光インターコネクトで接続することが想定されており、次世代バージョンでは光インターコネクトになることが見込まれている。こうなると、必然的にコンシューマレベルで光接続が当たり前となり、技術が一般化することで光関連のコストは低減することとなる。
Alteraとしては、こうして手ごろな価格となった光関連部品を用いることで、トランスミッションからサービスプロバイダ、ワイヤレス基地局、エンタープライズネットワーキング、光回線終端装置(ONU)までデータパスのすべてを光で対応させることで、バンド幅のスケーラブルな増加が実現できるようになるとし、単なるFPGAベンダとしてではなく、どうやってシステムとして活用してもらえるか、といったことまで含めたソリューションとしての提案を将来的には行っていく方針を示している。
では、具体的にどうするのか。まだコンセプトモデルも出ていない状態なので、同社からの詳細な説明はないが、パッケージにダイレクトに光ケーブルが接続される形となる。言い方を変えると、通常、半導体のパッケージはダイから金線などでパッケージと接続され、ピンやボールで基板などとつながるが、そうした電気的な部分を極力避けて、光-電気の変換ロスを抑える、いわばダイに光インタフェースをつけるような形となる。
こうした技術は単に光ケーブルのインタフェースを用意して、つなげればできる、というものではなく、同社では、「それに見合ったトランシーバ速度とシグナルインテグリティを実現することが鍵となる」と説明しており、それができるのがこれまでFPGAに搭載してきたさまざまな同社の技術であると強調する。
また、パッケージに接続される光ファイバも現在では72芯のものなどもあり、1本の光ファイバですべてのトランシーバをカバーすることも可能となるため(現在、同社のFPGAの最大トランシーバ搭載数は66個)、複雑にパッケージから光ファイバがつながるといったことも避けられ、これによりラインカードの消費電力を大きく低減することが可能になるという。例えば、従来の100G CFP 光モジュール(2Fibers)の消費電力は電力効率の高いもので24W(100Gbps時)だが、光ファイバをダイレクトに接続することで、1Gbpsあたり12.5mW、100Gbpsで1250mW(1.25W)と桁違いの電力低減が可能になるとしており、ラインカードとしての消費電力は70~80%削減することも可能になるとしている。
同社では、今後、こうした技術を多くのパートナー企業とともに実用化に向けて開発していくとしており、そうしたパートナーといっしょにソリューションとしての提供や、光インターコネクトを活用するためのガイドラインの策定などを進め、2011年の後半には目に見える形でのデモを実施したいとしている。
また、日本のシステム機器ベンダなどに対しても、設計技術や実装技術の先端を走っている企業が多いことから、世界に先駆けて、こうした技術に着目してもらい、すでに活用されている光ファイバへの適用なども含めて、活用していってもらいたいとコメントしている。