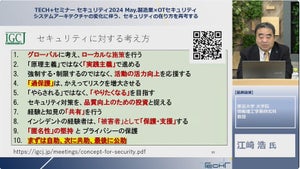閉塞した都市と力強い大自然はコインの裏表のようなもの
これまで一貫して、閉塞された世界でさ迷う人々の姿や、暴力による破壊や再生を描いてきた映画監督 豊田利晃。彼が4年の充電期間を経て完成させた新作『蘇りの血』が公開される。『蘇りの血』は豊田監督の作品においても、かなり異質な作品だ。本作はこれまでの現代の都会や近郊都市を舞台にした作品群から一転、歌舞伎や浄瑠璃の演目にもなっている「小栗判官」をモチーフに、ひとりの男の死と蘇りを描いた寓話なのだ。この最新作に豊田監督はどのような想いを込めたのだろうか?
――豊田監督4年振りの新作となる『蘇りの血』が公開されます。久々の監督作品ですね。
豊田利晃(以下。豊田)「『空中庭園』以降、映画を撮れない状況にあったのですが、やっぱり"映画を撮りたい、映画を撮らずにはいられない"という気持ちが強かったですね」
――『ポルノスター』や『ナインソウルズ』といった作品にも、寓話的な要素はありましたが、あくまでも現代劇でした。今回、過去の時代を舞台に、生と死をテーマにした寓話というか神話を正面から取り上げた理由は?
豊田「去年の春に熊野を旅して、壷湯という温泉に立ち寄ったんです。そこで、小栗判官の話を知りました。この話は、蘇りをテーマにした生と死の話なんですが、『昔の人は生死を悪い意味ではなく、良い意味で今より軽く考えてる』と僕には感じられたんです。何ていうか、この物語を知ったとき、自分自身が楽に感じられたんですよ。今、日本の自殺者が5分にひとりという状況の中で、こういう死を軽く扱う題材を投げる事ができたら、観客も楽になるんじゃないかと思ったんですよね」
――神話・寓話的印象を強調している部分として、時代設定もあやふやですね。
豊田「いわゆる時代劇でない、どの時代かわからない寓話をやりたかったんです。僕はこれまで、ずっと閉塞した社会で生活する都市生活者の話を描いてきました。『その閉塞感の突破口は何処にあるのか?』と考えたとき、エコロジーではない自然の力、荒々しさ神々しさや、それから得るエネルギーが、渋谷みたいな町の真裏にあって、そういう力が閉塞した社会を突破するヒントになると感じたんです。それで、この作品に辿り着いたんです。僕自身の蘇り、社会の蘇りという意味においても……」
蘇りの血
|
|
|
|
闇の世界を支配する大王(渋川清彦)が君臨する砦に天才按摩オグリ(中村達也)が招かれる。その大王のもとには、テルテ姫(草刈麻有)が囚われていた。忠誠を誓わないオグリは大王に殺害されるが、やがて「餓鬼阿弥」として現世に蘇る。大王のもとを逃げ出したテルテ姫は、オグリと再会するのだったが……。人間の再生と愛の始まりの物語 |
|
セリフではなく、映像で伝える
――これまでの、監督の描いてきた都市を舞台にした物語と違い、ロケーションも自然がほとんどでした。
豊田「自然とのセッションはやっぱり面白かったですね。撮影も、『どの森を選ぶか』から始まりますからね。通常の時代物のほとんどは、原生林でなく、植林で撮影されているんです。僕は本当の原生林でやりたかった。木ひとつのチョイスにしても、こだわりました」
――登場人物たちも寡黙で、セリフよりも映像で伝えるという意図が感じられました。
豊田「極力意識してセリフは少なくしました。あと、映画音楽は映像の後ろにあるのですが、時々、映像の前に出てセリフのように語る。そういう映画にしたかったんです」
――豊田監督はdipのヤマジカズヒデさんを起用していたり、今回もTWIN TAIL(※本作の主演である中村達也と豊田監督が在籍するバンド)が音楽を担当するなど、「音」に関してはかなりこだわりがあるように感じるのですが。
豊田「音と映像の融合っていうのはパワーがあると思います。その部分に関しては、僕は得意なほうだと思いますよ(笑)。僕も音楽が好きだし、音楽が良い映画が好きです。でも、いつかは音楽がない映画も撮ってみたいですね」