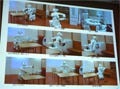--フェルプス氏は、知財には特許、著作権、商標、企業機密の4つがあると言っていますが、経済環境が減速しているなかで、とくに重要なものはありますか?
フェルプス それは、経済環境とはあまり関係がありません。すべてを持っている必要があります。だが、例えば、IT業界のなかで大切なのものに著作権がある。保有している情報を保護してくれるのが著作権です。マイクロソフトにおいても、著作権は重要なものに位置づけています。そして、同時に多大な研究開発活動を行っており、その成果は特許で保護されることになる。
また、商品を市場に出していくという点では商標が重要です。世界に向けて自らの商標は打ち出し、これを不正に利用されることがないようにしなくてはならない。さらに、企業機密はその企業にとっては生命線ともいえるもので、企業が持つ顧客リストやコカ・コーラ社のコーラの作り方などもそれに当たります。
知財における4つの要素は、それぞれに役目が違います。どのような経済環境下にあっても、4つが一緒になって機能することが必要です。それによってエンジンがきちんとした形になり、車が走ることになる。現実を見ると、大手の企業はすべてを組み合わせて使っている。こっちを使う、あっちを使うという選択ではないといえます。
--日本では、特許の申請数が減少しています。研究開発費が削減されているのが要因ではないかといわれていますが。その点への懸念はありますか?
フェルプス 米国でも特許の申請数は減少しています。確かに経済環境が悪いので、企業は研究開発投資を削減していますし、それが影響しているのかもしれません。
その一方で、研究開発は進めているが、特許取得にかかわるコストが高いため、企業が特許取得の件数を少なくしようという動きも影響しています。ちなみに、マイクロソフトは、研究開発投資額は前年度の80億ドルから、95億ドルに増やしています。いくら経済活動が減速傾向にあっても、研究開発費用を削減することはなく、企業活動に必要な投資だと考えています。
--もし、フェルプス氏が標準的な企業に在籍していた場合、この経済環境下において、経営幹部に対して、知財戦略の観点からどんな意見をいいますか?
フェルプス 一般的な中規模企業に在籍していたとすると、まず最初にやらなくてはならないのは、研究開発から出てくる成果と特許申請の間に、適正なバランスが保てているのかということを確認します。例えば、世界のどこで特許を申請しているのか、どのエリアまでをカバーしているのか、どの特許にお金をかけているのかを俯瞰することが必要です。
分析をした結果、これまでのように、多くの国で特許申請をしなくていいという結果になることもある。そうすれば、特許に関わる費用を削減することができる。
むしろ、やってはならないことは、やみくもに開発投資を削減するという判断です。必要なのは、特許戦略におけるバランスであり、研究投資から出てくる成果と知財に対して、どの程度の保護をしていくべきかを判断することでしょう。
そして、大企業の場合には、もうひとつ責任が加わってくる。政府との働きかけにより、知財の保護に関して、効率性が高く、コストを抑えられるように活動を行う必要がある。例えば、日本では経団連の知財委員会のなかに入り、効率的な知財保護の実現に向けて、働きかけるといった作業などがそれにあたります。
多国籍企業は、米国でも、欧州でも、中国でも同様のことをしなくてはならない。また、企業は、どの特許に対して保護するのか、どれを企業機密とするのか、そして、どれを公に開示するのか。責任を持った選択をしていかなくてはならない。経済環境が悪化したからといっても、単に研究開発投資を減らすということだけが選択肢ではありません。