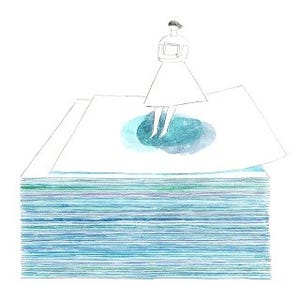恋愛の話をするのが大好きな人たちがいる。いや、恋愛だけではない。人の私生活がどうなっているか、仕事は大丈夫なのか、お金はあるのか、健康なのか、最近何を買ったか、そんなことを訊きたがる人たち。
乃莉はそういうことに、興味がないわけではなかったが、自分がそれらの興味の対象にされると、返事をする声がこわばった。特に、恋愛のことについて。
どんな人に恋をしているのか、いまどんな状況にあるのか、誰かに話したい、吐き出したいという気持ちが乃莉にもなかったわけではない。数年前までは素直に話していた。ときには訊かれもしないのに、自分から。
きっかけは、少しの違和感だった。乃莉が藤田という年上の男とつきあい始めた頃、そのことを親しい女友達一人だけに話した。その日は、彼女と二人で飲んでいて、二軒目の和食の店で、だんだんお客さんが減ってゆく店内でのんびり話しているうちに、ふと気が緩んで話してみたくなったのだった。
大事な友達だと思っていた。信頼もしていた。いい話だから、黙っていなくてもいいと思ったのかもしれなかった。けれど、親しくもない他人から「聞いたよ、藤田と付き合ってるんだって?」と不意に言われると、暗闇から矢で射られたような気分になった。そして「どっちから好きになったの?」なんていう質問を、上手にはぐらかすこともできないほど、全身が凍り付いてしまうのだった。
乃莉は、藤田とのことについて、もう誰にも話さないことに決めた。
乃莉にとって、恋愛は楽しいものでもあったが、同時に不安でたまらないものでもあった。ずっと同じ関係が続くとは限らない。相手の気持ちが変わらないとは限らない。 藤田は決して恋多き男ではなかったし、信頼に足る人柄だとも思っていた。
ただ、乃莉は人の心が、変わらないものだとはどうしても思えないのだった。何かを「プレゼントしようか?」と言われるたびに、それが楽しかった日々を思い起こさせる悲しい思い出に変わってしまう未来が頭をよぎった。
自分に自信がない、というのとも、相手を信頼していない、というのとも少し違うような気がした。好きな相手から好かれていることの蜜をたっぷりと味わいながら、どこかで「続くはずがない」と醒めた気持ちで思っている、そんな感覚だった。
二人は夜はよく、乃莉のマンションで過ごした。週末の夜はのんびりできるから、乃莉はいつもより少し良いおつまみ、藤田の好きな黒いオリーブやパルミジャーノ・レジャーノを用意して、藤田は何かお酒を買ってくる、というのが「いつものこと」になっていた。
テレビで深夜にやっている映画を観るともなしに観ていると、藤田は、主演女優が好きなのだ、と言った。あまりそういうことを言わない男だったので、乃莉はソファに寝そべったままふざけてじゃれつき、床に座った藤田の肩を器用につま先でつついたりした。
そして次に藤田に会うとき、その主演女優が着ていたのと同じような、黒いロングコートを着ていった。近所の古着屋で見つけた男物のコートだった。藤田は「似合う似合う」と笑った。
そして、その日が不意に訪れた。乃莉は、別の男に恋をしてしまったのだった。
乃莉と藤田が別れた、という話はまたたく間に友人関係に知れ渡った。藤田が行きつけの店で、酔って話したらしかった。
藤田には何の非もないし、藤田が浮気ひとつしない誠実な男だということは、誰もが知っていた。乃莉だって浮気などしない女だったが、これまで恋愛の話をしなかったことが仇となって「あの子、藤田さんのこと全然話さなかったもんね、あまり好きじゃなかったんじゃない?」「見た目は真面目そうなのにね」と、さんざんに言われている、と「仲がいいと思っていたはずの女友達」がわざわざ密告してくれた。
気分が悪くなるだけの話を、なぜわざわざ言いにくるのだろう、と思った。悪いのは自分のほう、とみなされることはわかっていたし、藤田に恨まれるのはかまわない。けれど、そんなことをなぜ人に言われなければならないのか、乃莉はやはり理解できなかった。
乃莉は好きになった男とうまくゆかないまま、四月を迎えた。冬物をまとめてクリーニングに出そうとしたとき、あの男物の黒いコートが目に入った。
腕に抱えてみると、まるで男の身体の抜け殻を抱いているような気分になった。不意に、その抜け殻に顔をうずめて、乃莉は泣き出した。そして、その瞬間にたくさんのことを知った。
藤田と別れて、傷ついていないわけではなかったこと。自分が選んだことでも、傷つくときは傷つくのだということ。自分が心変わりをする人間だから、相手の気持ちがずっと続くことを信じられなかったこと。そして、自分はこんな人間で、そのままの自分でこれからも生きていかなければならないこと。
相手との関係が、いつまでも変わらない、なんて思えないまま、ひっそりと複雑な気持ちを胸に抱いて、編み物に別の色の毛糸を一本まぎれこませるようにして、恋愛の物語を編んでゆくのだろうということ。
誰に語らなくても、涙のあとのついた黒いコートは、乃莉の物語を知っていて、ただそこにじっと横たわっていた。乃莉は、長年扱いかねていたものがすっきりと晴れていくような爽快感を味わいながら、そのコートをクリーニング用の紙袋に入れた。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望