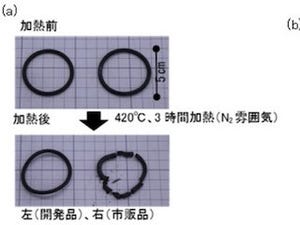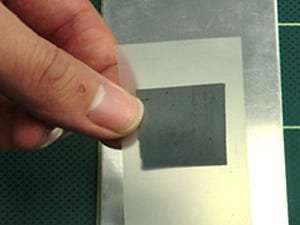産業技術総合研究所(産総研)は9月12日、スーパーグロース法で作成した単層カーボンナノチューブ(SGCNT)量の免疫細胞内での経時変化を測定し、SGCNTが生分解されることを確認したと発表した。
同成果は、産総研ナノチューブ実用化研究センター CNT評価チームの張民芳 主任研究員、岡崎俊也 研究チーム長(兼)同研究センター 副研究センター長らと日本ゼオンで構成される研究グループによるもの。詳細は、2017年9月12~15日に京都大学で開催された「第53回 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム」にて発表された。
その優れた特性からCNTは幅広い分野で活用されるようになってきているが、その一方で、CNTが環境へ暴露し、動物や人体に吸収されて免疫組織に蓄積する可能性があり、健康への有害な影響への懸念ももたれるようになっている。CNTは急性毒性が低いとされているが、長期的な安全性を明らかにすることが重要であり、中でもCNTの生分解特性の解明は、その長期安全性を議論する上で必須の課題とされていた。そうした状況の中、CNTの生分解特性についてはこれまで複数の研究報告がなされていたものの、そのほとんどが定性的な議論であり、詳細は不明となっていた。
今回、研究グループでは、CNTが近赤外領域に光吸収帯をもつ特性を利用して、細胞内に取り込まれたCNT量を定量的に評価する実験を実施。その結果、実験に用いた培養マウスの免疫細胞(Raw264.7)、ヒト白血病細胞株(THP-1)、初代細胞(マウス肝臓のクッパー細胞)ともに、どの免疫細胞でも20~50%のSGCNTが細胞内で分解されることが判明したという。また、SGCNTの生分解メカニズムの解明を目指し、SGCNT取り込み後の免疫細胞内の活性酸素の発生量の測定も実施。その結果、細胞内SGCNTの残存量と活性酸素の発生量の減少傾向が一致していることを確認。このことから、SGCNTの免疫細胞内の生分解は活性酸素によると考えられること、ならびにSGCNT取り込み後4日が経過した免疫細胞の活性酸素発生量は、コントロール細胞(SGCNTの添加なし)での発生量と同じで、細胞の総タンパク質量の経時変化もコントロ-ル細胞とほとんど同じであることも確認したことから、SGCNTの分解残さ物は細胞への毒性が低い可能性があることが示されたとする。
なお、研究グループでは、今回得られた研究結果をもとに、CNTアライアンスコンソーシアム事業において、日本ゼオンと共同で、SGCNTの生分解性とそのサイズ、表面修飾などの物理化学的特性との関連を明らかにし、CNTの生分解性の予測や制御を可能にする方法を開発していくとしている。