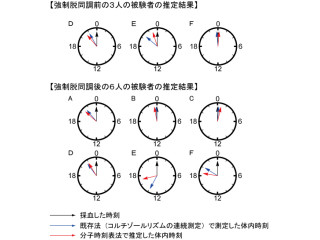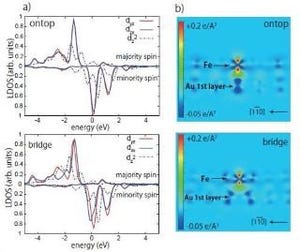理化学研究所(理研)と東京大学物性研究所、九州工業大学は9月4日、非磁性体である銀の中に効率よく純スピン流を流すことができるスピン蓄積素子を開発し、10μmの距離をスピンが拡散伝導する現象を観測したほか、外部からの磁場で純スピン流の向きを一斉に1回転させ、出力信号を変化させることに成功したと発表した。
成果は、理研基幹研究所 量子ナノ磁性研究チーム 大谷義近チームリーダー(東京大学 物性研究所教授)、福間康裕客員研究員(九州工業大学 若手研究者フロンティア研究アカデミー 准教授)、井土宏研修生(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 博士後期課程)らによるもの。詳細は英国の科学雑誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。
近年、スピントロニクスの開発が急速に進められている。その中心となる材料は強い磁気を持つ強磁性体(磁石)で、例えば2枚の強磁性体層に極薄の絶縁体層を挿入したトンネル磁気抵抗素子は、HDDの再生ヘッドやMRAMのメモリ機能部として実用化されている。これらスピントロニクス素子は、電荷の流れ(電流)とスピンの流れ(純スピン流)の両方(スピン偏極電流)を利用している。
一方、強磁性体と非磁性体の複合構造であるスピン蓄積素子を用いると、電流は流れずスピンだけが流れる純スピン流を生成することができる。スピンの緩和時間は電荷の緩和時間よりも数桁長いために、純スピン流を利用すると省電力の電子素子の実現が期待できる。同研究グループでも2011年、強磁性体であるパーマロイ(鉄とニッケルの合金)と非磁性体である銀の間に、低抵抗の酸化マグネシウム層を挟んだナノサイズのスピン蓄積素子を作製し、効率的に純スピンを生成する技術を確立していた。しかし、現在広く利用されている半導体トランジスタ素子のように、外部信号を用いて純スピン流を制御するには、非磁性体中の伝導特性を解明し、その伝導やスピンの向きを制御する技術の開発が必要となっていた。
そこで今回、純スピン流の生成効率をさらに向上させるため、2011年に作製したスピン蓄積素子において、パーマロイ/酸化マグネシウム層/銀の接合を1カ所から2カ所に増加し、両界面に電流を流してスピン注入を行った。さらに、銀中を拡散する純スピン流を検出側電極だけに導くため、反対側に伸びる銀細線を切断。これにより、従来の構造と比較して純スピン流の生成効率と出力信号を3.2倍に向上させ、金属材料を用いたスピン蓄積素子では世界最高クラスとなる出力信号を得ることに成功したという。
次に、銀中の純スピン流に対して垂直方向の磁場を与え、スピンの回転運動を誘起させたところ、磁場の増加とともに、検出側電極でのスピン回転角度が増加し、約0.3Tで1回転した。
1次元のスピン拡散伝導モデルを用いた理論的な解析により、180度回転した後のスピン蓄積信号(ΔRπS)が減少する理由は、検出電極位置に到達したスピンの向きが不均一であるためと分かった(図3赤線)。さらに、拡散距離の増加とともに、銀中を流れるスピンは外部の磁場に応答して、そろって回転するようになることが分かった。
|
|
|
図3 スピン蓄積素子の検出側電極位置におけるスピンの伝導時間の分布。スピン注入側電極と検出側電極間距離Lが1.5μmと10μmのスピン蓄積素子におけるスピンの伝導時間の分布。L=1.5μmの場合には、伝導時間の分布が広がっており、スピンの向きが時間に依存して分布している。L=10μmの場合には、伝導時間のバラつきが小さく、スピンが一斉に回転している |
今回、この集団スピンの回転運動は、これまでにスピン拡散伝導モデルを用いて解析された金属や半導体、グラフェンなどのすべての物質中で普遍な現象であることが明らかとなった。また、作製した素子では、銀中のスピンは回転してもスピン蓄積信号の減衰が少なかった。つまり、高い性能指数(ΔRπS/ΔR0S)で回転運動をしている。その伝導速度0.047m2/sは、次世代のトランジスタ素子への応用が期待されているグラフェンの0.01m2/sよりも高速なことが分かった。
|
|
|
図4 スピンの回転運動の性能指数の拡散距離依存性。スピンの拡散距離(L)が緩和長(λN)に対して長く伝導する(L/λNが大きくなる)ほど、スピン蓄積信号の減衰が少ない(一斉にスピンが回転できる)ことが分かる。本研究で作製したAg中のスピンは、他の材料と比較して高い性能指数を実現している |
今回、スピン蓄積素子の構造を改良することで、純スピン流の生成効率と出力信号の向上に成功した。スピン蓄積素子は次世代の超高密度HDDを実現するための再生磁気ヘッド技術として期待されており、その実用化が待ち望まれている。また、純スピン流の拡散伝導現象の普遍性を明らかにし、純スピン流の回転に必要な磁場や拡散距離の長さ、および素子の出力信号を計算することも可能になった。そのため研究グループでは今後、電場などを用いて非磁性体中を流れるスピンに有効磁場を作用させる手段を開発することができれば、外部信号による出力信号の制御が可能となり、シリコンやグラフェンなどの半導体技術を上回る高速動作のスピントランジスタやスピン演算素子の実現が期待できるとコメントしている。