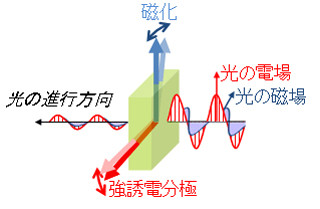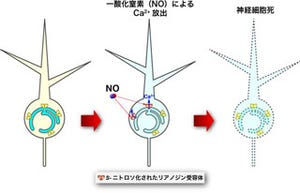東京大学(東大)と米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループは、独自手法によって連続大量合成した高品位の3層カーボンナノチューブ(CNT)を厚さ数十μmに組織化して柔軟な自立膜を作製し、これをリチウム電池のプラス極として単独で機能させることに成功したことを発表した。同成果は、東大の山田淳夫教授、野田優准教授、山田裕貴助教およびMITのYang Shao-Horn准教授らによるもので、英国王立化学協会の学術雑誌「Energy&Environmental Science」(オンライン版)に掲載された。
現在のリチウムイオン電池のプラス極には、高価なレアメタルを含み、700℃以上の高温で合成されるLiCoO2やLiNiO2、LiMn2O4などのセラミックスが使われており、電池製造原価の半分程度を占めている。
また、これらの重金属は毒性リスクがあり、環境中への排出許容濃度の法的基準が厳格に定められており、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、スマートグリッド用など、蓄電池の大規模な社会導入に当たっては、資源戦略や毒性リスク、製品ライフサイクルにおける総合的環境負荷低減効果を考慮する必要性が指摘されていることから、構成材料の"セラミックスフリー化"の実現は、電池技術が最終的に目指すべき方向とされている。
こうした要請に対し、地球資源の制約がなく、バイオマスから生産、再生可能な理想的なプラス極材料としてLixC6O6(2<x<6)などの有機分子が提案されており、ゆっくりと数回の充放電を繰り返す限りは、セラミックス材料と同等以上の特性が報告されている。しかし、電極応用にむけては、分子同士を高密度に凝集させ分子の間の電子の流れを確保することや、分子の構造を安定に保つことが課題となっていた。
研究グループは、有機分子の強固な凝集体として位置付けられ、連続導電経路も確保できるCNTに酸素による単純な表面化学修飾を施すだけで、リチウムと高電圧で反応可能になるというMITの研究に注目したが、容易に入手可能な10層以上の導電性多層チューブでは、リチウムが近づくことのできない内部の多くのカーボン原子が無駄になってしまうほか、剛直で変形しないため、電極形成には糊で固める必要があり、糊が化学修飾した表面部分を覆ってしまう問題があり、これまでのMITの研究でもプラスとマイナスに帯電させる化学処理を行った多層チューブを、導電フィルム上に交互に堆積させる非工業的手法で長時間かけて組織化した、2μm以下程度の薄膜でしか電極機能が確認されていなかった。
一方、単層ナノチューブであれば柔軟で自立膜の形成も可能であるが、炭素原子の"巻き方"によって金属になったり半導体になったりするばかりでなく、化学修飾を行うと唯一の"グラフェン"層が破壊され、導電性が失われるという課題や、作製が極めて困難で、1g当たりの価格が10万円前後となり、実使用に適用することが困難であるといった課題があった。
そこで今回の研究では、野田准教授が開発した画期的連続製造プロセスにより大量合成した「長尺3層ナノチューブ」によって、これらの問題の解決を試みたという。従来の基板上への単発CVD成長ではなく、反応炉内でセラミックスビーズを反応ガスにより流動化させ、反応ガス種を切り替えることで、ビーズ上への制御された触媒ナノ粒子の付着、触媒上での直径と長さの揃ったナノチューブの高速成長と、ナノチューブの粉体状態での分離・回収を繰り返し、大量の高純度試料を連続的に得るというもので、今回は、チューブの平均直径が3層相当に、各チューブが0.4mm程度の長尺となるように条件を制御した。
3層ナノチューブでは、最外層に酸化還元機能のための化学修飾を施しても、内部の2層は常に金属状態を保持するため、この3層構造は電極機能を発揮するための最も効率的な最小構造であるという。また、長尺で柔軟性も併せ持つ3層ナノチューブを用いれば、形状に自由度を持たせつつ高強度な自立膜を組織することができ、膜内での導電経路も効率的に形成されるとも考えた結果であるという。
この高品位長尺3層ナノチューブへの化学修飾法と自立膜作製法を東大とMITが共同開発、その結果、従来比約10倍の導電性を有しながら、約10倍の厚み(約20μm)の柔軟な自立厚膜電極が作製され、この電極は、1.5V-4.5Vの高電圧で動作し、現在のリチウムイオン電池に実用化されているセラミックス材料と同等レベルの電気を、高速で可逆性良く蓄えることが可能であることが確認されたという。
少なくとも1000回の繰り返し使用ではまったく劣化しない。柔軟な自立厚膜の状態で機能することが確認され、現在のリチウムイオン電池において、電極の固定と電子の供給のために使用されている導電助剤やバインダー(糊)のみならず、金属集電フィルムも使用する必要がなくなることから、電池のエネルギー密度をさらに高めることも可能になるという。
なお、研究グループでは今後、実用展開に向けた最適化を進めることで性能を向上させ、実用展開につなげていきたいとしている。