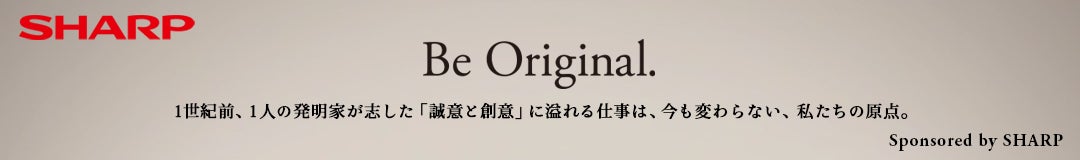年齢や性別、文化の違いや障がいの有無にかかわらず、誰にとってもわかりやすく、使いやすい「ユニバーサルデザイン」。多様性が求められる現代において、その重要性はますます高まっていますが、“だれもが使いやすい”を実現するのは容易ではありません。
そんな中、家電メーカーのシャープは、ユニバーサルデザインの実現を目指して「ユーザー中心設計」に注力しています。高齢者や障がい者の方々の声を製品に反映するなど、より多くのユーザーが快適に使用できる製品の開発に取り組んでいるのです。
今回は同社を直撃し、製品開発のために実施されている2つの調査の現場に潜入することに!「高齢者と視覚障がい者を対象にしたホットクックの使いやすさに関する調査」、「ターゲットに近いユーザーを対象としたスティック掃除機(試作機)の使いやすさに関する調査」の様子に密着。地道な開発の裏側をご紹介します。
潜入の前に……そもそもシャープが注力する「ユーザー中心設計」とは?
シャープは「品質第一 私たちの心です」という品質スローガンのもと、顧客のニーズと要望に応え、安全性・品質・信頼性に配慮したより良い商品・サービスの提供に向けて継続的に取り組んでいます。
その中で、商品・サービスの“使いやすさ”を向上するための専門組織として全社横断的な役割を果たしているのが、「品質推進部UCD(User-Centered Design)チーム」。全社のユーザー中心設計の支援やユーザビリティマインドの醸成をミッションに掲げて日々活動しています。
なお、ユーザー中心設計とは、国際規格(ISO9241-210)で規定されている人間中心設計の考え方のこと。シャープはユーザー中心設計の基本方針に基づき、企画段階から徹底的に現状を把握するのはもちろん、完成後も評価と改善を繰り返し、これまで使いやすくて魅力的な商品・サービスを生み出してきました。
このユーザー中心設計を実現するうえで欠かせないのが「ユーザー調査」です。
ユーザー調査の現場に潜入!高齢者や障がい者の“生の声”を聞く
今回取材するのは2つのユーザー調査。まず潜入したのは高齢者と視覚障がい者の方による「ホットクック」の調査現場。
商談室にいたのは、ユーザー調査に応募した65歳~79歳の高齢者の方々。ホットクックの基本操作について「ユーザビリティテスト」が行われました。各操作のゴールだけ設定し、まずは直感的に操作できるかどうかを調べた後に、使いやすさの評価や感想などをインタビューします。
思いのほかスムーズに操作することができましたが、初見では一部手間取るところも確認されました。
次は、視覚障がい者(ほぼ全盲)の方々が参加。盲導犬と一緒に訪れる方もいました。高齢者と同様のところで手間取っている方もいましたが、操作部が見えないためにより難しいことが、課題として浮き彫りになりました。
その他の操作は、操作ボタンが触ってわかる形状であったり、凸点や凸バーが付いていたりするため、手慣れた様子で順調に進行。
ただ、液晶画面を見ながらのボタン操作において、表示が見えないユーザーは、操作手順を記憶する必要がありました。表示が見えずとも快適に操作ができる工夫が必要なことなど、さまざまな気づきを得られました。
続いて潜入したのは「スティック掃除機」のユーザー調査現場。実施場所はシャープ社内にある、カメラ4台が備えられた「インタビュールーム」です。
この日は、ターゲットに近いシャープの女性社員を対象に、スティック掃除機の新製品に関する「ユーザビリティテスト」を実施。それぞれ持ち手部分の角度が異なる試作機を手に取り、握り具合や身体にかかる負担を細かくチェックしていきます。
部屋にはマジックミラーが設置されていて、奥の「観察室」では、液晶モニターとマジックミラー越しに開発関係者らが状況を観察します。
真剣な眼差しで見守り、机上では発見できなかった課題を抽出していました。
この他にも、使いやすさを客観的に評価・分析する方法として、目の動きを追跡するアイトラッキングや生体計測・動作解析などを駆使することもあるのだとか。また最近では、視覚障がい者との対話やブレインストーミングを通じてインクルーシブ・デザインへの理解を深め、事業での活用イメージを具現化する「インクルーシブ・デザイン体験ワークショップ」が定期的に開催されているそうです。
シャープはこうして、一般ユーザーはもちろん、高齢者や障がい者などのユーザーの“生の声”を吸い上げ、製品に反映しているのです。
ユーザー中心設計を浸透させ、今ではユニバーサルデザインに配慮した商品・サービスも多数!
ここからは「品質推進部UCD(User-Centered Design)チーム」に所属する社員の皆さんに詳しく話を聞いていきましょう。
【プロフィール】
佃 五月さん
2001年のUCDチーム立ち上げ時から携わる。チームのリーダーとしてシャープのユーザー中心設計推進を牽引。
宮田 尚巳さん
デバイス事業の品質部門から、2013年にUCDチームに異動。主にユーザー調査全般や集合研修を担当し、チームの取り組みで中心的な役割を担っている。
土井 彩容子さん
2024年6月に中途入社。ITメーカーでアジャイル開発におけるユーザー調査に従事していた経験を活かし、主にeラーニング研修や社内情報発信を担当。
――今では各社がユニバーサルデザインを目指していると思いますが、シャープのユーザー中心設計にはどのような特徴がありますか?
 |
当社は2011年に「UCD8原則」を制定し、設計目標に対する意識を全社で共有していますが、使いやすさだけでなく、「使ってみたいと思うかかどうか」や「長く使い続けたいと思うかどうか」にまで配慮しているのが特長です! 商品・サービスの操作性をはじめ、webサイトやカタログ、開梱方法や取扱説明書、お手入れや保守・サポートなどにもユーザー中心設計を取り入れています! |
――商品・サービスの操作性については、具体的にどういったことに配慮しているんですか?
 |
全自動洗濯機を例に挙げると、操作ボタンに付いている点字や凸点・凸バーを触ればスタートや停止がわかるようになっていたり、報知音によって聴覚でメニューが一巡したことに気づけたりする仕様で、視覚障がい者の方でも確実に情報を入手していただけるように設計しています! |
――これまでシャープがユーザー中心設計で作った商品・サービスの事例をいくつか教えてください!
 |
音声で操作できたり、音声で作り方を案内してくれたりする「ヘルシオ」「ホットクック」「テレビ AQUOS」などが代表的な事例です!(2025年3月現在) |
-

※Google TV は、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、Google LLC の商標です。Google、YouTube、Google Cast、Google Meet、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
 |
また、マルチコピー機も該当します! |
 |
視覚障がい者向けに音声ガイダンス機能を搭載したハンドセットを備え付け、コイン投入口や証明書排出口などに点字シールを貼ったり、杖置きを設置したりしました! また、車いすユーザーを想定したテストを重ねて使いやすくしたり、日本語を読めない外国人アルバイトの方が操作やメンテナンスに困らないように動画やイラストだけの説明でも操作手順がわかるかを確認したりするなど、ユニバーサルデザインを視野に入れた改善も進めました! |
――商品やサービスの種類が多岐にわたりますが、どのようにしてユーザビリティマインドを醸成しているのでしょうか?
 |
社内での取り組みのひとつとして、UD体験実習の機会を設けています! |
 |
車いすやアイマスク、色弱模擬フィルタや白内障ゴーグル、イヤーマフ、軍手といったツールを用いて高齢者や障がい者の生活を疑似体験することで、自分事として捉えてもらえるようにしています! |
 |
例えば、高齢者の疑似体験ツールである白内障ゴーグルを活用して、さまざまな商品の操作部の表示などの見やすさを確認し、改善にも取り組んでいます。 |
 |
そして、ユーザー中心設計を実践できる人材(ユーザビリティエンジニア)育成を目的として、各レベルに応じた研修プログラムを提供しています!初級ユーザビリティエンジニア研修の修了者(2024年4月時点)は約8,000名、中級の修了者は約230名で、今後さらに増やしていく予定です! |
 |
加えて、ユーザビリティに関するさまざまな情報を掲載している社内向けのWEBサイトでの情報発信に努めていて、社員に向けたメルマガも定期的に発信しています! |
――ユーザー中心設計を浸透させていく中で、大変なことはありますか?
 |
売れる商品・サービスを作るのが大前提としてあって、そのうえでいかにユーザーに優しい製品にできるかどうかが難しいところです。 特定のユーザーの使いやすさを追求した結果、どこまで対象を広げられるか、ユーザー中心設計からユニバーサルデザインにもつながる話ですが、大変だからこそチャレンジする価値があると考えています! |
――すでにシャープには、ユニバーサルデザインに配慮した商品・サービスがたくさんありますよね。
 |
一般財団法人 家電製品協会によるユニバーサルデザイン配慮項目は全部で6つ。以下のシャープ製品が、それぞれの項目に当てはまる「ユニバーサルデザイン配慮家電製品」の一例として挙げられます! |
配慮はさり気なく。誰もが使いやすくて魅力的なのが、ユーザー中心設計の本質
ユーザー中心設計やユニバーサルデザインの商品・サービスは、何も高齢者や障がい者の専用のものではありません。一般の方も含めた、誰もが使いやすくて魅力的なのが本質と、佃さんたちは力を込めました。
スタイリッシュでスマートな商品・サービスでありながら、配慮はさり気なく。身の回りを見てみれば、すべての人に寄り添うシャープの“小さな優しさ”に出会えるかもしれません。
Photo:田中 大介