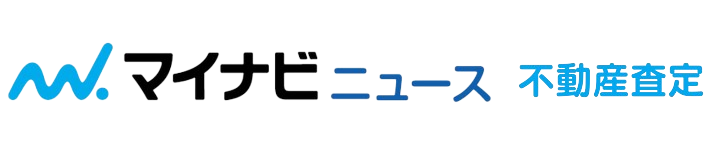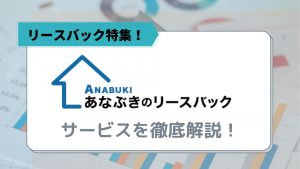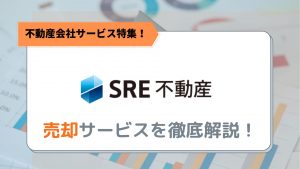多くのお金が動き、今後の生活にも影響を与える不動産売却。検討を始めても、何から始めたらいいか迷い、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。ですが、少しでも流れと注意点を知っていれば、スムーズで安心な取引につながります。
この記事では、不動産売却の一般的な流れに沿って、各ステップにおける注意点、基礎知識や重要ポイントを解説。さらに、空き家相続、離婚、リースバック・リバースモーゲージといったケース別の注意点にも触れています。不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
1.売却を決めたら必ず押さえておくべき注意点
売却方法には大きく、「仲介」「買取」「個人売買」「任意売却」の4つがあります。それぞれの特徴と注意点をまとめました。
「仲介」は仲介手数料が発生
仲介の注意点として、売買契約が成立すると、仲介手数料が発生することが挙げられます。
仲介手数料は成功報酬とサービスに対する手数料です。仲介とは、不動産会社が売主と買主の取引の間に入り手続きや成約をおこなう売却方法で、専門知識や司法書士との連携により、スムーズな取引が可能になります。
仲介手数料は法律で上限が定められており、国土交通省が告知しています。2025年3月時点の仲介手数料上限は以下の通り※です。
| 売買価格 | 上限仲介手数料 |
|---|---|
| 売買価格 | 上限仲介手数料 |
| 800万円以下 | 33万円 |
| 800万円超 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
※ 令和6年7月より、「低廉な空き家等の売買または交換の媒介における特例」適用により、800万円以下の取引における仲介手数料の上限が一律33万円以下となりました。
参考:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額
例えば、1,000万円の不動産を売却した場合、(1,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税 = 39万6,000円(税込) が仲介手数料の上限となります。
「買取」は査定額が相場よりも低め
買取では、相場の6~8割を目安に低く査定される傾向があります。「買取」とは買主が不動産会社となる売却方法で、不動産会社は、将来的な再販価格、転売リスク、場合によっては残存物の整理の費用等を織り込むため、低めの売却価格となります。
買取には「即日買取」と「買取保証付き仲介」があります。
「即日買取」は、不動産会社が提示した価格に売主が合意した時点で売却ができるのに対し、「買取保証付き仲介」は、一定期間販売活動を行い、買主が見つからなかった場合に買取りを保証するものです。
短期間の確実な売却が可能であるほか、買い手探しや内覧の手間と仲介手数料の支払いがないなどのメリットがあります。買取を検討する場合は、複数の不動産会社の査定を受けて査定価格を比較することがメリットを最大化するコツです。
「個人売買」は専門知識が必要
売り主と買い主が直接不動産売買を結ぶ「個人売買」は、仲介手数料を省ける一方で、契約書作成・登記・税務処理など、専門的な知識が必要です。これらに不備があれば損害賠償問題に至る可能性があります。
親族や知人など決まった買い手に不動産を譲りたい場合、個人売買が選択肢となるでしょう。しかし、適正価格より明らかに低い価格での売却には贈与税が課される可能性や、親族間売買という理由で住宅ローンが組めない場合があります。
売買の合意が取れている買い手がいる場合に仲介手数料を抑えられる不動産会社もあるので、トラブルを避けるために他の売却方法も同時に検討するとよいでしょう。
「任意売却」でも必ず競売を避けられるとは限らない
「任意売却」は、住宅ローンの返済が滞り、金融機関から残債の一括返済を求められた際の対応策として選択される売却方法です。
入札による競売と比べて、相場に近い価格で取引でき、引き渡し時期や売却条件をある程度調整できるメリットがあります。また、競売のように情報が広く公表されず、プライバシーが守られます。
しかし、金融機関の同意が不可欠であり、時間を要することから、競売開始に間に合わない可能性があります。任意売却の検討を始めたら早い段階で金融機関に連絡をし、売却活動に着手することが必要です。
不動産の売却方法には、それぞれメリットとリスクがあります。「売却価格」「スピード」「手間」「費用」 のバランスを考え、自身の状況に最適な方法を選択しましょう。
2.事前準備での注意点
完売活動を始める前の準備段階では、査定、売却費用の資金計画、土地の境界の確認、不動産価格の相場の調査が重要になってきます。ここでの準備をしっかりしておくことが、今後の不動産会社の選定や、売買契約締結で失敗をしないために効果的です。できることから早めに準備をしましょう。
不動産の名義は売り主本人か確認しておく
不動産を売却するには、登記上の名義人が売り主本人であることが必要です。名義人でない場合、所有権移転登記ができず、売買契約を成立させても取引を完了できません。
特に、相続した不動産では「相続登記」が未了のケースに注意が必要です。相続登記を完了させないと不動産売却ができません。また、共有名義の場合、他の共有者全員の合意が必要となるため、単独での売却はできません。
売却活動をスムーズに進めるために、まずは登記簿謄本を取得し、名義を確認しましょう。必要に応じて相続登記や名義変更を早めに行うことが、トラブル回避につながります。
また、名義が売主本人でも、引っ越しや離婚・結婚などで住所や名前に変更があった場合は必ず変更登記をしなくてはならないので注意しましょう。
売却期間の希望を明確にし、計画的に進める
売主によって売却理由が違うため、希望売却期間は様々です。「住み替えの期限が決まっている」「早く現金化したい」など、売却に求めるスピードによって最適な売却方法が変わります。
実際に、不動産売却には一定の時間を要します。ある調査では、マンション、戸建て、土地で、査定から成約までそれぞれ平均7〜8ヶ月、8〜9ヶ月、1〜12ヶ月かかったという結果が示されています。また、時間にもっと余裕を持てば良かったという後悔も報告されています。
このような実態を踏まえ、売却を検討し始めたら早めにスケジュールをたて、余裕を持った計画を進めることが成功の鍵となります。
参考:不動産売買における期間について|すまいステップによる不動産売却の実態調査 | 株式会社Speeeのプレスリリース
【住み替えで不動産売却をした方に調査】売却についてもっとも多い後悔は「もっと早く売却を始めれば良かった」
売却の費用を把握する
不動産の売却金額が全て手元にのこるわけではありません。売却価格によっては支出が上回ることもあるため、事前に想定される費用を把握しておくことが重要です。例として、以下のような費用が考えられます。
| 内容 | 価格の目安 | |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う対価 | 売却価格に応じた価格 |
| 印紙税 | 売買契約書に係る税 | 200円~48万円※1 |
| 譲渡所得税 | 不動産売却益に対する税 | 譲渡所得額×15~30%※2 |
| 住民税 | 不動産売却益に対する税 | 譲渡所得額×5~9%※2 |
| 復興特別税 | 所得税額に比して化される税 | 所得税額×2.1% |
| 登録免許税(売買を原因とする場合) | 不動産登記申請に係る税※3−1 | 固定資産税課税台帳価格×1.5%(土地)固定資産税課税台帳価格×2%(土地以外)※3−2 |
| 登録免許税(抵当権抹消する場合) | 住宅ローンを売却時に返済する場合に必要な税 | 1,000円/件(土地、建物は別扱い) |
| 繰上げ返済等手数料 | 住宅ローンを売却時に返済する場合に金融機関に支払う手数料など | 数万円〜※4 |
| 司法書士への報酬 | 司法書士を通して売却前に名義変更や、抵当権抹消登記をした場合など売主負担の場合 | 約3万〜10万円※5 |
| 測量費用 | 必要に応じて土地の境界を確定する費用 | 約30万円〜 |
| その他諸費用 | 引っ越し費用、ハウスクリーニング費用、不用品処分費用、解体費、 | 状況による |
※1平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書に対する軽減措置対象の場合
※2不動産の保有年数による。特例による控除の適用の場合あり。詳細は後述。
※3−1 売主負担の場合
※3−2 平成31年から令和8年3月31日まで
※4金融機関ごとに、住宅ローンのプラン、金利、残債の金額などの条件により異なる。
※5司法書士報酬は自由なため、ばらつきがある。また、作業の内容や資産価値も報酬額に影響する。
売却代金が該当不動産の取得費用と売却費用の合計を上回った部分を「譲渡所得」といいますが、譲渡所得が発生する場合は税金の支払いが必要になります。また、空き家を 更地にして売却する場合の解体費用、境界確定が求められた場合の測量費用などの追加コストも考慮しなければなりません。
また、あらかじめ諸費用を把握していると、売買契約や移転登記に関わる印紙税、登録免許税は買い主負担か売り主負担となっているか契約内容のチェックに役立ち、トラブル回避につながります。
土地の境界を確認する
多くの場合、土地の境界が定まっていなければ土地の売買が成立せず、後のトラブルにつながるので、早い段階で確認しましょう。
売買契約書の多くには、売主側の「境界明示義務」が記載されています。法的義務ではありませんが、境界が不明確だと所有権が完全に移転できず取引が困難となる可能性があります。このため、安全性の確保を目的として境界明示義務は広く採用されています。
土地の境界の登録の有無は、地積測量図で確認できます。地積測量図が存在している場合は法務局に登録されており、請求すれば全国の登記所、郵送、オンラインで受け取ることが可能です。いずれも料金は数百円です。
土地が登記申請された年代によっては地積測量図が存在しないケースがあります。その場合は、少なからぬ費用はかかりますが、「土地家屋調査士」に依頼して、境界を確定することが必要です。
一般的に境界線は引き渡しまでに明示が求められます。もし境界確定が必要な場合は1ヶ月〜3ヶ月程度の時間がかかるため、早めに対応することをおすすめします。
査定に備えて相場を下調べする
近隣の類似物件の成約事例を閲覧し、相場の感覚を掴んでおきましょう。基準を設けることで、査定額の妥当性を判断しやすくなります。
中古物件の成約データの調査は、不動産ライブラリ、レインズマーケットインフォメーション等を活用することをおすすめします。
両者とも最終的な取引事例を公開していますが、レインズでは、マンションか戸建て、都道府県、地域を選択すると、面積と取引価格の分布がグラフで示され、不動産ライブラリでは不動産取引の指標となる地価公示、各種統計が閲覧できるなど機能に特徴があります。また、チラシや情報誌などで売り出し価格等の情報を収集し、比較するのもよいでしょう。
参考:不動産情報ライブラリ
REINS Market Information
3.査定での注意点
不動産会社に仲介や買取を依頼する場合、まず査定をして価格を決定します。査定は複数社の比較検討がおすすめです。また、査定価格の高さだけでなく、算定の根拠、担当者の信頼性なども査定時におけるポイントです。
査定は複数社に依頼する
机上査定では、1社の査定だけでなく、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが大切です。複数社から情報を得ることで、不動産価格の目安の把握や、査定額、対応の違いを経験でき、納得のいく誠実な不動産会社への依頼につながります。
不動産会社にはそれぞれ得意な物件や対応エリアがあります。一般的に、大手は全国規模の販売網と豊富なノウハウが強みで、地元密着型の不動産会社は地域の市場に精通し、きめ細かい対応が期待できます。
一括査定サイトを利用すると、無料で一度に査定依頼ができます。売却希望物件が遠方でも、地元密着型の不動産会社や対応エリアであれば大手から同時に査定を受けられるため、効率的です。
査定価格を見極める
高い価格が良い査定とは限りません。高い査定を信用して、売れ残って価格を下げざるを得なくなるといった失敗は避けたいものです。そのため、査定額の根拠をしっかり確認することが大切です。
通常、査定価格は売出しから3ヶ月で売れることを基準に算定されます。ただし、売主の希望によっては、早期売却を希望すれば査定額はやや低めに、時間をかけてでも高く売りたければ査定額は高めになる傾向があります。また、不動産会社や担当者によっては、契約を取りたいがために相場以上の高額査定を提示する場合もあるため、注意が必要です。なぜその価格なのか説明をしっかり受けましょう。
また、コミュニケーションを通じて、販売力や専門性、熱意を判断し、信頼できる不動産会社と担当者を選ぶことが納得いく売却活動のカギとなります。
訪問査定では不動産会社に具体的な質問をする
査定時には具体的な質問をし、算定根拠を明確に提示してもらうことが大切です。不明点があれば積極的に質問し、具体的な売却活動の計画について相談することで、信頼できる不動産会社や担当者を見極めることができます。
査定には、過去のデータや入力情報を基に算定する机上査定と、実際の物件を確認し詳細に評価する訪問査定があります。机上査定は初期の参考に適していますが、売却を進めるには訪問査定が必要です。
訪問査定では、物件の状況確認のために必要な書類をあらかじめ準備すると査定がスムーズに進みます。戸建て・マンション・土地など物件の種類や、ローンの有無、権利関係の複雑さによって必要書類が異なるため、事前に不動産会社へ確認するとよいでしょう。
主な査定時必要書類
| 書類 | 入手場所 |
|---|---|
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局・登記所窓口、郵送、オンライン |
| 地積測量図 | 法務局・登記所窓口、郵送、オンライン |
| 公図 | 法務局・登記所窓口、郵送、オンライン |
| 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書 | 役所または出張所の窓口または郵送 |
| 建物図面(間取り図など) | 法務局・登記所窓口、郵送、オンライン |
| リフォーム履歴書 | 自宅 (リフォーム会社発行) |
| 住宅ローン残高証明書・ローン返済予定表 | 自宅(金融機関発行) |
また、査定価格の精度を高め、売却後のトラブルを防ぐために、建物や設備の不具合など査定に影響を与える可能性のある情報は正直に伝えることが重要です。これらを伝えておかなければ、契約時に「契約不適合責任」として売主の責任になる可能性があります。情報の透明性を確保することで売却後のトラブルを回避し、円滑な取引につなげましょう。
4.媒介契約での注意点
不動産会社の仲介を選択した際、3種類の契約があります。大きな違いは、複数社と契約できるか、売り手が買い手をみつけた時に個人売買が可能か、レインズに登録義務があるかです。条件の違いが販売活動に影響してくるので、それぞれの特徴を押さえて自分にあった選択をしましょう。
メリット・デメリットから自分に合った媒介契約を選ぶ
| 媒介契約の種類 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への重ねての依頼 | X | X | ◯ |
| 自ら発見した相手との取引 | X | ◯ | ◯ |
| レインズへの登録義務 | ◯(契約から5日以内) | ◯(契約から7日以内) | 任意 |
| 契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法令による定め無し |
| 業務の処理状況報告義務 | ◯(1週間に1度以上) | ◯(2週間に1度以上) | 任意 |
| 売買又は交換の申込みがあった場合の遅滞ない報告 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 契約満了後2年以内に不動産会社を通して知り合った相手と当該不動産会社を通さずに売買契約を結ぶ行為 | X | X | X |
仲介では売主が不動産会社と契約して、不動産会社が買主を探す販売活動を始めますが、その契約を「媒介契約」と言います。媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、情報公開や買主の見つけ方などに違いがあります。
専属専任媒介
売主は契約した1社にしか仲介を依頼できません。売主自ら買主を見つけてきて取引をする「自己発見取引」が認められていません。禁止事項に違反すると仲介手数料相当の違約金と、それまでにかかった広告費などの諸費用が請求されることがあります。
また、依頼された物件をレインズに登録する義務と、1週間に1回以上売主に進捗を報告する義務があります。
制約が多い反面、成功報酬が確約されていることから、不動産会社側は販売活動を積極的に行ってくれることが期待されます。
なお、契約は3ヶ月以内ですが、不動産会社が義務、努力を怠っているなどの理由により途中解除が可能です。また、合意により3ヶ月以内の契約更新もできます。
専任媒介契約
ほとんどの点で専属専任媒介と共通していますが、違いは、進捗の報告義務は2週間に2回以上という点と、「自己発見取引」が可能である点、レインズ登録の期限です。自己発見により契約を終了した場合にも、それまでにかかった広告費は請求されます。
一般媒介契約
売主は複数の不動産会社に仲介依頼が可能で、買主を自分で発見し取引することも可能です。原則として他の不動産会社と仲介を依頼した場合に報告する義務がありますが、特約の定めがあれば必要はありません。
レインズの登録義務はありませんが、任意に登録し、買主を探してもらうことは可能です。また、契約期間について、法律による制約は設けられていません。
専属専任媒介契約、専任媒介契約と比べて自由度が高く、同一物件を扱う不動産会社の存在が競争力を促したり、より広範に買主に情報が届く可能性があります。一方で、自社で制約に至らない場合全ての時間と費用が無駄になることから、意欲の低下につながることも考えられます。
不動産会社との情報共有が大切
どの媒介契約でも「申し込みの遅滞ない報告義務」があります。この義務は、買受申込書、口頭、メールなどの手段を問わず、売買・交換の意思が明確に示された場合に発生します。
ただし、実務上、提示価格が売主の希望額に満たない場合や条件が合わない場合、すぐに報告されないケースもあるため、売主側も積極的に状況を確認することが重要です。
また、内覧や問い合わせなどの義務ではない情報も共有してもらうと、売却活動の参考にもなります。
囲い込み防止にレインズを活用する
「囲い込み」とは、不動産業者が他業者からの問い合わせや購入希望者の情報を売主に伝えず、自社での成約を優先し、売り主の売却の機会を損なう行為です。しかし、レインズ(不動産流通標準情報システム)を活用することで、この囲い込みを回避できます。
レインズは物件情報のデータベースで、登録された物件情報が全国の不動産業者で共有されます。これまで、専任媒介契約の不動産会社が、物件情報の登録を怠ったり、申込みの受付情報を偽って問い合わせを回避するなどして囲い込みをおこない、問題視されてきました。
このような状況を受け、2025年1月から売り主自身がレインズの登録状況をチェックしやすいようにシステムが改修されました。売り主は不動産会社から交付されるレインズ「登録証明書」の二次元コードから売り主専用画面にアクセスし、物件のステータスを随時チェックできます。
取引状況を確認して、覚えがないのに「売り主都合で一時紹介停止中」など表示されたら、不動産会社に問い合わせすることができます。
一般媒介契約ではレインズ登録の義務はありませんが、売り主の希望があれば登録を依頼することも可能です。情報の一般公開に抵抗がなければ、広く買い手を募る手段として検討の価値があります。
媒介契約締結後も能動的に売却活動をおこなうのが失敗を防ぐコツです。また、担当者とコミュニケーションをとることで、信頼関係を築くことにつながるほか、売却活動中の不動産会社の様子を見て、契約の継続か終了かの検討材料にもなります。
5.売り出し開始後の注意点
不動産会社による販売活動が始まり、買い主と具体的に話を進める段階での注意点です。これから契約に向けて買い手にアピールし、購買につなげることと、契約後のトラブルを回避する準備に注力しましょう。
内覧では、内覧者の注目ポイントを押さえて清潔感をアピール
内覧時の印象は、買い手にとって重要です。しかし、生活感のない部屋は理想的でもありますが、生活をしていたり、荷物の多い空き家だと負担を考えただけでもストレスの原因となります。
しかし、少し努力することで、良い売却条件を諦めずにすむかもしれません。内覧者が特に気にするポイントから取り組み、清潔感、整理整頓をこころがけ、場合によってはプロのサービスの利用も検討しましょう。
内覧者の気にするポイントと掃除のコツを以下にまとめました。
| 玄関 | 靴を片付けてなるべく広くみせることが大切です。ホコリを掃除し、明るく清潔な印象を作りましょう。 |
| リビング | 余計なものはこの機会に処分し、生活感を抑え、すっきりした印象にしましょう。大切なものが多い場合はトランクルームを利用し、売却後に移動させることも一つの手です。クッションやブランケットを整え、清潔感を出すのも大切です。 |
| キッチン | 食器類や出しっぱなしのキッチン用品、調味料を片付け、シンクやコンロの汚れを落としましょう。食品を扱う場所なので、衛生面には特に気を付けましょう。 |
| 水廻り(浴室、洗面台、トイレなど) | 髪の毛を徹底して取り除き、カビや水アカを落として臭いもチェックしましょう。他人のつけた汚れは不快感を強く与えるので、念入りに掃除する必要があります。 |
| ベランダ | 荷物置き場になっていたら要注意です。内覧者にとって、眺望や洗濯物を干す環境は大事なチェックポイント。ベランダの片付け、不用品の整理と、窓ガラスの清掃をおすすめします。 |
また、内覧の際、どこまで見せるか、どこまで触れても良いかなど、内覧者に伝えておきたい希望があれば、不動産会社を通して事前に伝えておくとよいでしょう。
知っている物件の事実は全て伝える
知っている限りの物件情報を伝えなくてはなりません。物件の情報を買主に適切に伝えなかった場合、「契約不適合責任」を問われ、大きな損失を招く可能性があるからです。
契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容と異なる場合に、売り主が負う責任です。契約不適合責任を問われると、買い主から建物の修繕、設備の交換、不足していた土地の引渡しなどを求められる可能性があります。場合によっては減額や、損害賠償、契約解除に応じなければなりません。
例えば、雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下、埋没物、自死、再建物不可物件、近隣との境界に関するトラブル等の権利関係などが事前に告知されなかった場合が該当します。
内覧は、購入希望者に物件の魅力を直接伝える絶好の機会であるため、少しでもよく見せたいという気持ちが働くかも知れませんが、不具合は漏れなく伝えましょう。
また売り主は、知らなかった欠陥についても責任を負う可能性があるため、物件の状態を十分に把握しておくことが重要です。
売買契約締結後のトラブルを回避する方法として、以下が考えられます。
不動産会社に正確に情報を伝え、物件状況報告書を作成する。
売主が認識している物件の欠陥や不具合は、些細なことでも不動産会社に伝えましょう。不動産会社は、買い主への情報提供、契約手続き、物件調査など、重要な役割を担います。正確な情報提供は、トラブル防止と円滑な取引に繋がります。
そして、「物件状況報告書」を作成し、買い主に開示した情報を明確にすることをおすすめします。
「物件状況報告書」は物件の状況を、建物、土地、周辺環境その他の項目について、過去の履歴や告知すべき現況を売主の責任で記すものです。
注意したいのは、覚えていない項目についてです。なんとなくチェックしてしまった項目や、他人に任せて記入したことが事実と異なっていた場合でも責任を問われるリスクがあります。関係書類を探し出して過去の履歴を確認する、現在の状況を点検するなど、トラブルを回避するために最大限の努力をしましょう。
既存住宅状況調査(インスペクション)を実施する
「既存住宅状況調査(インスペクション)」は、専門家が建物の状態を診断するサービスで、売り主が状況を把握できない物件の深部まで調査できるため、売却前の確認に有効です。
調査により物件状況報告書の正確な記載ができます。また、買い主に契約前に重要事項説明書に調査結果が記載されることから、買い主の安心感につながり、売却がスムーズになるメリットがあります。
費用は物件の種類や広さによって異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、調査項目と合わせて比較検討しましょう。
調査には報告まで約2週間かかるため、契約直前に慌てることなく進められるよう、売却活動の初期段階までに完了させるのが望ましいです。特に、販売情報公開時に結果を提示できれば、より多くの買主にアピールができるので理想的です。スケジュールを考慮し、早めに準備を進めましょう。
特約を利用する
売買契約に、売り主の責任範囲を明確にする特約条項を設けることも有効です。例として「契約不適合特約免責事項」「容認事項」があります。
「契約不適合特約免責特約」とは、売買契約書に記載もなく事前の説明もなかった欠陥が仮に見つかったとしても、売主は責任を追わない内容の特約です。ただし売主が知っていた欠陥を隠したり、宅建業者や法人が売主の場合は、これらの特約が無効になることがあります。
「容認事項」とは、物件の既存の欠陥を買主が承知した上で購入することを確認し、売主の責任を免除する条項です。容認事項を契約書に記載していても、事前に買主に説明する義務があるので、しっかり買主の理解を得ることが大切です。
買い手との話の内容はメモや書面に残す
買い主との話の内容はメモや書面を残し、契約までに買い手と具体的な取り決めを完了させることが大切です。
内覧などで、物件のちょっとした不具合を口頭で伝える、家具をそのまま譲ると口走る、価格の値下げに応じるなど、口約束は買主と認識のすれ違いの原因になります。
客観的な判断が難しいため、「言った・言わない」のトラブルは解決が困難です。こうした問題を避けるためにも、メモや書面を残し、契約までに買主と具体的な取り決めを完了させることが大切です。
6. 売買契約締結の注意点
買い手が見つかり、条件に合意したら、売買契約書を締結します。売買契約書とは、不動産売買における売り主と買い主の合意内容を明文化した契約書です。売り主と買い主が署名・捺印することで、契約内容への最終的な合意が正式に確定します。重要な書類となるため、細部までしっかりと確認しましょう。また、契約解除のリスクやトラブルの回避方法を理解しておくことで、安心して取引を進めることができます。
売買契約書を隅々まで読み込む
売買契約書が作成されたら、売買契約書を細かく確認することが重要です。契約日前に入手し、しっかり目を通すことでトラブルを未然に防ぐことができます。
特に、物件情報、支払条件、権利関係、解約条件、責任範囲について注意を払いましょう。不明点があれば、不動産会社や司法書士に相談しましょう。
売買契約書の様式は不動産会社により細部が異なりますが、共通する項目が記載されています。以下のチェックポイントを確認するようにしましょう。
不動産の表示
「不動産の表示」に記載されている、住所・面積などの物件情報が正確であるかを、登記簿の内容と照合して確認しましょう。表記の誤りがあると、所有権移転登記ができないなどのトラブルにつながる可能性があります。
売買代金と支払い条件
売買代金が合意した金額か、また、手付金・残代金の金額と支払い期日が正確に記載されているかを確認しましょう。特に手付金の額や支払い方法については、契約解除の条件に関わるため注意が必要です。
原則として、所有権移転登記・残代金支払い・引き渡しは同日に行います。異なる日が指定されている場合、管理責任を売り主と買い主のどちらが負うかといった問題や、約束通りに引き渡せるかなどのリスクがあるため、慎重に検討しましょう。
抵当権等の抹消
売却する不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、売り主は買い主に引き渡す前に抹消手続きを完了させる必要があります。通常、契約書に「所有権移転時までに抹消する」と明記されているため、余裕をもって金融機関に連絡し、必要書類を期限までに準備しましょう。
土地の境界の明示
土地の境界についての取り決めを確認しましょう。売り主による境界の明示が一般的であり、境界が確定しているかを確認することが重要です。
契約によっては境界非明示の合意もありますが、境界が曖昧なままであると、将来的に隣地所有者と紛争が生じる可能性があります。特に古い物件では境界を確認し、必要に応じて境界確定測量を実施しましょう。境界を明示することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
解約の条件
売買契約の解除条件を確認し、万が一の際に売り主・買い主のどちらがどのような負担を負うのかを把握しておきましょう。代表的な解除条件には「手付解除」と「融資利用の特約」があります。
「手付解除」とは、買い主が手付金を放棄する、または売主が手付金の倍額を返還することで解除可能です。期限に注意しましょう。
「融資利用の特約」とは、買い主の住宅ローンが通らなかった場合の解除条件で、契約が解除される条件があるか確認し、融資元の金融機関の記載がはっきりしているかも合わせて確認しましょう。
免責事項
売り主の契約不適合責任について、どこまで責任を負うか確認しましょう。特に中古物件の場合、「契約不適合責任を負わない」特約や「容認事項」を設けることも可能ですが、その場合は買い主への説明責任があります。特約を設ける場合は、不動産会社や司法書士に相談し、買い主に十分な説明を行いましょう。
公租公課の清算
固定資産税、都市計画税、管理費、インフラ負担金などの公租公課は、引き渡し日を基準に売主と買主で清算します。
関東では1月1日、関西では4月1日を基準とする慣習があります。念のために起算日の記載、計算方法や負担割合を事前に把握し、清算時のトラブルを防ぎましょう。
印紙税、登録免許税の負担
契約書に貼付する印紙代は、折半するのか、どちらかが負担するのかを確認しましょう。また、所有権移転登記にかかる登録免許税は、一般的に買い主の負担ですが、どちらが負担するのかを明確にしておきましょう。
付帯設備表・物件状況報告書
「付帯設備表」は、照明器具、エアコン、給湯器など、引き継ぐ設備を明確にする書類です。故障時の責任範囲も明記しましょう。
「物件状況報告書」は、建物の修繕履歴や現状を説明する書類です。虚偽や記載漏れがあるとトラブルの原因になるため、慎重に確認しましょう。
どちらも作成は任意ですが、事実と異なる記載や、後から発覚した不具合により、売り主が責任を負うケースを防ぐため、よく確認していないのにチェックするなど曖昧な記載は避け、正確な情報を伝えることが重要です。
仲介手数料等の一部を準備し、支払い方法を確認する
仲介手数料は、売買契約締結時と引き渡し時に半額ずつ支払うのが一般的です。ただし、不動産会社によっては支払い時期が異なる場合があるため、媒介契約書の記載内容を確認し、資金の準備をしましょう。
支払いは現金が原則ですが、不動産会社によっては振込対応しています。持ち歩きが不安な場合は、振込が可能か事前に相談しましょう。なお、通常、振込手数料は売り主負担となります。
7. 決裁・引き渡しの注意点
決済・引渡しの流れを、当日前後に分けて説明します。売買契約締結から引き渡しまで通常1ヶ月間。慌てることのないように流れをしっかり把握しましょう。
引き渡し日までに引越しを済ませる
原則として決済日が引き渡し日です。引き渡し時には、買主がすぐに全てを使える状態にしなくてはなりません。そのため売主は引越し業者の手配、荷造り、火災保険解約、ライフライン停止手続きを完了させる必要があります。
それと並行して、決済日に必要な書類を、各方面に申請し、期限までに手元に集めておかなければなりません。
決済・引き渡し当日の手順を押さえる
決済当日は、主に登記と支払いが行われます。流れを押さえることで、必要書類と支払いの準備がしやすくなります。
以下が概要です。
1. 買い主、売り主、不動産会社担当者、司法書士など、複数人が立ち合い、まず司法書士によって書類確認、本人確認を行います。
2. 買い主による残金の振り込み、または住宅ローンの実行によって支払いをおこないます。
3. 売り主はこれを受けて領収書の発行・所有権移転登記申請をしますが、多くの場合は司法書士が代行します。抵当権があれば、ここで抵当権抹消登記を同時に申請します。
4. 固定資産税、都市計画税、インフラに関わる費用などの、公租・公課の清算を日割りで行います。起算日から引き渡し日前日までは売主負担、引き渡し日以降は買主負担となり、売主負担分を買主に支払います。
5. 必要書類と鍵の引き継ぎを売主から買主に行います。
6. 仲介手数料の残金、司法書士への支払いは、当日支払うのが一般的なので、資金の準備も必要です。
当日に必要書類がなくて登記ができなかったり、手続きが未了で引き渡しが滞ると、契約ができません。計画的に準備をすることが大切です。
以下の表は、決済時に必要となる代表的な持ちものです。ケースによって異なりますが、参考にしてください。
| 身分確認・印鑑関係 | ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)・実印(登記手続きに必要、共有名義の場合は全員分が必要)・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)・銀行届出印 |
| 登記・法務関連 | ・登記関係書類(登記済権利証または登記識別情報)・住民票・戸籍謄本(必要な場合あり)・抵当権抹消書類(住宅ローンが残っている場合に必要)・登記費用(抵当権抹消登記などがある場合) |
| 税金・費用関連 | ・固定資産税評価証明書・固定資産税納付書・収入印紙(売買金額に応じて必要)・仲介手数料(通常、半金を契約時に支払う)・司法書士への報酬・通帳・銀行キャッシュカード(売買代金の振込先確認のため) |
| 物件・設備関連 | ・売却物件の鍵(室内・共用部・駐輪場・駐車場など)・管理規約(マンションの場合)・建築・分譲時のパンフレット・設備の取扱説明書・保証書・建築確認通知書・境界確認書・測量図(必要に応じて) |
| 買主への引継ぎ資料 | 買主に引き継ぐ書類(管理組合関連・設計図・設備類の説明書など) |
8.確定申告の注意点
不動産の売却により利益が出た場合と損失が出た場合で、確定申告での作業が異なるので注意しましょう。基本的に売却で利益が出たら確定申告をして納税し、損失が出たら確定申告は不要ですが、控除を受けて納税が不要な場合や、損失をほかの所得から控除できる場合などは必要となります。
ここでは、不動産売買の納税に必要な計算の基本と、売却に関わる控除を、それぞれの注意点とともにまとめました。
譲渡益がでたら納税が必要
「譲渡所得」がプラスになる場合、税金が発生し、確定申告が必要です※。確定申告は原則、売却の翌年2月16日〜3月15日、住民税の納付は確定申告後の6月頃です。
※控除前の譲渡所得について確定申告が必要。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
「譲渡所得は」以下のように計算されます。
譲渡所得=譲渡価格ー (取得費+譲渡費用)ー特別控除控除価格
譲渡所得に関わる項目は以下の通りです。
| 譲渡価格 | 取得費 | 譲渡費用 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 売った土地や建物の購入代金(建物の場合は減価償却適用)、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費など。取得費が不明な場合は売却費用の5% | 仲介手数料、印紙税、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用など |
この利益に対してかかる税金は「譲渡所得税」と「住民税」 があり、税率は売却物件を売却した年の1月1日時点で保有年数が5年以下(短期譲渡所得保有)か、5年を超える(長期譲渡所得保有)かによって異なります。「特別復興所得税」は全ての保有年数の不動産について、譲渡所得税額に2.1%を乗じた額となります。
譲渡所得税=譲渡所得x30%または15%
住民税=譲渡所得x6%または9%
| 保有年数(売却年の1月1日時点) | 譲渡所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 |
| 5年以下(短期譲渡所得保有) | 30% | 9% | (譲渡所得税額)×2.1% |
| 5年超(長期譲渡所得保有) | 15% | 5% | (譲渡所得税額)×2.1% |
取費用
取得費用とは、不動産の購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物は期間が経過することによって価値が減少するとみなされ、建物の取得費を計算する場合は、建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数
償却率は建物の構造等によって変わります。
| 区分 | 木造 | 木造モルタル | (鉄骨)鉄筋コンクリート | 金属造①※1 | 金属造②※2 |
| 償却率 | 0.031 | 0.034 | 0.015 | 0.036 | 0.025 |
※1「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物
※2「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4㎜以下の建物
たとえば、1,000万円で購入した木造家屋を6年間保有した場合、現在の取得額は1000万円- 1000万円 x 0.9 x 0.031 x 6 = 832万6千円となります。
譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、土地や建物を売るために支払った仲介手数料や、印紙税で売主が負担したものなどが含まれます。
控除例:マイホーム特例
自分が住んでいた家屋を売却した場合、保有年数にかかわらず譲渡所得から3,000万円が控除される特例があります。譲渡所得が3,000万円に満たない場合は譲渡所得が控除額の上限です。
長期保有物件を5,000万円で売却し、取得価格3,000万円、譲渡額100万円であった場合、マイホーム特例が適用されない物件であれば、譲渡所得は1,900万となり、譲渡所得税285万円、住民税95万円、復興特別所得税約6万円の計約386万円が納税するところですが、住み替えの場合納税が発生しません。
注意したいのは、特例高控除を受けるには一定の要件を満たす必要や、併用できない控除があることです。以下のマイホーム特例適用条件を参考にしてください。また、特別控除の適用を受けるには申請と確定申告が必要です。
| 1. 売却資産の形態が、右の項目のいずれかに当てはまるもの | ①現に自分が住んでいる家屋 ②以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) ③上記①または②の家屋とともに売ったその敷地や借地権 ④上記①または②の家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまるもの。・その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 ⑤家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(これらの土地の場合は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用していてもかまいません。) ・上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 ・上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 |
| 2. 右の要件を全て満たすもの | ・売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 ・売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 ・売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 ・親子や夫婦など「特別の関係がある人」※1に対して売ったものでないこと。 |
| 併用が不可な控除について | 過去3年以内にマイホーム特例の控除を利用した場合、住宅ローン控除は使えない。住宅ローン控除を使っている間、他の不動産売却で税金軽減を使うと、その年は住宅ローン控除が使えない。 |
| マイホーム特例の適用除外 | ・この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 ・居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 ・別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋 |
| 長期譲渡所得の軽減税率との併用 | 売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えているなど一定の要件を満たした場合は、3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、軽減された税率の適用が可能。 課税長期譲渡所得金額所得税住民税6,000万円までの部分10%4%6,000万円を超える部分15%5% |
| 買換え(交換)の特例との併用 | 不可 |
※1「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる。
参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁
土地や建物を売ったとき|国税庁
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
住替えで譲渡所得で損失が出たら、他の所得と損益通算も可能な場合がある
長期譲渡所得に該当する場合で、マイホームを譲渡したときに損失が出た場合、一定の要件を満たして確定申告を行えば、その他の所得税からその金額が控除でき、それでもまだマイナスな場合はその年の翌年以降3年に渡り控除を続けられるという制度があります。住宅ローンの有無で内容が異なります。
マイホーム売却の譲渡損失が生じた場合の特例
主な適用要件は次の通りです。
| 譲渡資産(旧居宅) | ・譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること・現に居住している、または過去に居住していた家屋やその敷地・過去に居住していた家屋の場合、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに譲渡しているもの・建物を取り壊すなど敷地のみ売却の場合も一定条件で適用(例:家を取り壊して1年以内に売却し、他の用途に使っていないなど)・災害で滅失した場合、発生日あるいは住まなくなってからから3年を経過する年の12月31日までに売るもの |
| 買換資産(新居宅) | ・売却の前年1月1日~翌年12月31日までに取得した、床面積50㎡以上の国内の住宅・取得翌年12月31日までに居住開始が決まっているか、予定である・取得した年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンを有すること |
| 適用外 | ・売却相手が親族(親・子・夫婦など)・2年以内に他の特例(長期譲渡所得の軽減税率の特例、マイホーム特例、買換え(交換)長期譲渡所得の課税の特例)を適用済みである場合・敷地面積500㎡超の部分の損失・所得が3,000万円を超えていると繰越控除は不可 |
住宅ローン残債があるマイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合の特例
ローン残高を下回る価格で売却して譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たせば、ローン残高から売却代金を差し引いた額を控除し、さらにその損失を繰越控除することができます。
マイホーム売却の譲渡損失が生じた場合の特例とは異なり、新居に買い換えている必要はありません。
| 譲渡資産(旧居宅) | ・令和7年12月31日までに売却すること ・譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること現に居住している、または過去に居住していた家屋であること。 ・過去に居住していた場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しているもの ・建物を取り壊すなど敷地のみ売却の場合も一定条件で適用(例:家を取り壊して1年以内に売却し、他の用途に使っていないなど) ・災害で滅失した場合、発生日あるいは住まなくなってからから3年を経過する年の12月31日までに売るもの ・譲渡前日まで売却するマイホームに住宅ローンの残債があり、マイホームの譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること |
| 適用外 | ・売却相手が親族(親・子・夫婦など) ・2年以内に他の特例(長期譲渡所得の軽減税率の特例、マイホーム特例、買換え(交換)長期譲渡所得の課税の特例)を適用済みである場合 ・3年以内にマイホームの譲渡損失 ・ローン残債がある場合のマイホームの譲渡損失による控除を受けている場合・所得が3,000万円を超えていると繰越控除は不可 |
参考:土地や建物を売ったとき|国税庁
No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき|国税庁
No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき|国税庁
何かと費用のかかる不動産売却。そんな中、住宅の売却を促進するような控除があると心強いのではないでしょうか。上手に確定申告の機会を利用し、売却物件の事情に合った仕組みをつかって経済的負担を減らしましょう。
その他状況別の注意点3選
この章では、手続きや判断に状況別の配慮が必要なケースを、「空き家相続」「離婚」「リースバック・リバースモーゲージ」に注目して紹介します。
空き家の相続登記は済ませておく
相続した不動産を売却するには、まず「相続登記」を完了させる必要があります。なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があるので期限には注意しましょう。
共同相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要があります。兄弟が離れて住んでいるなどやりとりに時間がかかる場合は、売却の遅れにつながるため、早めの対応が重要です。なお、相続登記が未了でも売買契約自体は可能ですが、引渡しまでに登記が完了しないと契約不履行となる恐れがあるため、注意が必要です。
売却時には「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」などの税制優遇を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できます。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は相続した空き家を一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合に、最大3,000万円の譲渡所得税控除を受けられる特例です。
適用要件の例として、
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・耐震改修や建物の解体をして譲渡前、あるいは譲渡された年が属する翌年の2月15日までに行うこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・っ他の利用をしていないこと
・1億円以下であること
などがあります。
先祖由来の土地などの取得額不明の土地は、取得額を売却額の5%とします。このような場合、控除の適用がなければ、高額な取引では多額の譲渡所得税が発生するので、特例の利用の効果は大きいと言えます。
一方、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」は、相続税の一部を譲渡取得費に加算し、課税対象の譲渡所得額を抑えることができます。取得費が増えることで、譲渡所得税の負担が軽減される場合があります。特に、先祖由来の土地など取得費が不明な土地は、売却額の5%を取得費となり、高額の土地ではこの特例を適用することで節税効果が高くなる可能性があります。
相続不動産の売却は、登記や税制の手続きが煩雑で、時間を要することもあります。早めに売却計画を進めることが重要です。
参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
離婚に伴う不動産売却は、タイミングとローン残債をチェック
離婚に際して不動産を売却する場合、特に売却のタイミングや住宅ローンの残債に注意して、どのように合意するかを慎重に検討することが重要です。
売却のタイミング
不動産を売却するタイミングは、離婚前と離婚後のどちらにするかを考える必要があります。離婚前に売却を完了させると、資金を確保できるため、新たな生活にスムーズに移行しやすいといえます。しかし時間に余裕がない場合、相場より低い価格で売ったり、買取といった手段を用いることで金銭的に損をするかもしれません。
離婚後に売却する場合は、離婚後もやり取りが続き、精神的な負担になる可能性があります。また、固定資産税や維持管理費が発生し、支払い分担の問題も生じるかもしれません。その一方で、時間をかけて適正価格で売却できる可能性が高まるというメリットもあります。
また、不動産の名義が夫または妻の単独である場合、離婚前に売却し、その売却代金を一方が受け取ると、贈与と見なされて贈与税の対象となる可能性があります。しかし、離婚後の財産分与として売却代金を分ける場合は、贈与ではなく財産の清算と扱われるため、税金は発生しません※。
住宅ローンの残債の確認
売却前に、住宅ローンの残債が売却額でどの程度カバーできるのかを確認することが重要です。早い段階で不動産査定を行い、資金計画を明確にしておくことで、売却時のトラブルを防げます。
住宅ローンの返済義務は、契約上の名義人にあります。売却代金でローンを完済できる場合は問題ありませんが、売却額がローン残債を下回る場合、差額の支払いが問題になります。名義人が単独で責任を負うのが原則ですが、負担の割合について当事者で取り決めを決めることも可能です。
夫婦の共同名義でローンを組んでいる場合は、双方が債務者となっているため、離婚後に売却活動を行う場合は連帯して返済義務を負うことになります。どちらかが家を出て行き返済が滞るといったトラブルを防ぐ等の理由から名義を単独にすることを検討したり、売却資金がローン完済に足りない場合は補填割合を協議する必要があります。
自己資金で不足分を補うことができない場合は、任意売却を検討する方法もあります。ただし、金融機関の判断によるため、必ずしも認められるとは限りません。
不動産売却に関する決定は、名義人やローンの契約状況によって異なります。単独名義か共同名義か、住宅ローンの残債があるかどうかによって、売却方法や代金の分配、残債処理の進め方が変わるため、具体的な協議が不可欠です。まずは状況を整理し、双方が納得できる形を探ることが重要です。
参考:法務省:財産分与
※No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁
リースバック・リバースモーゲージは将来の影響も考慮する
リースバック・リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら資金を調達できる手段として利用される制度です。しかし、どちらもメリットとリスクがあり、通常の売却や融資との比較をして、慎重に検討する必要があります。
リースバックは売却価格、賃料、契約期間、悪質勧誘に注意する
リースバックは、売却価格が相場より低くなりやすい点と、賃料の支払い能力が今後も必要となる点に留意しましょう。また、賃貸借の契約期間を契約前に把握することが重要です。
リースバックとは、自宅をリースバック業者に売却し、売却代金を受け取った後も賃料を支払いながら住み続ける仕組みです。生活費、住宅ローンやその他債務返済、高齢者施設への入居資金確保などが主な利用動機となっています。
契約形態には「定期借家契約」「普通借家契約」があり、主流である定期借家約款は基本的に更新がなく、契約期間が2~3年であることがほとんどです。契約終了時に退去となるか、再契約の交渉をしますが、賃料の値上げ交渉のリスクもあります。
賃貸の年数が長期にわたる場合、賃料の合計が売却価格より高くなることがあるので、今後の居住年数と賃料、売却価格のバランスの確認が必要です。
トラブルを防ぐためには、契約内容を十分に確認し、いつまで自宅に住み続けられるのかを契約前に確認し、退去要請のトラブルを防ぎましょう。
なお、買い戻し特約つきのサービスもありますが、一般に売却価格よりも高く設定されています。
以下がリースバックのメリットとデメリットです。
| メリット | ・生活環境を変えずに、すぐにまとまった資金を得られる・売却代金でローン返済により住み替えのためのローンが組める・固定資産税や維持費を支払わなくてよい・将来の自宅の処分について考える必要がなくなる |
| デメリット | ・売却代金が相場より低い傾向にある・賃料を支払い続ける必要がある・自由に部屋や設備を変えられない・定期約款契約で更新を拒否され、意思に反して退去させられたり、賃上げを要求されたりする可能性がある |
また、一部の業者が長時間の勧誘や嘘の説明で強引に売却契約を結び、解約を拒まれたり高額のキャンセル料を言い渡されるなどのトラブルが相次いでいます。売買契約は一度結ぶと解除は難しいので注意が必要です。商品の特性と契約内容を熟知した上で利用しましょう。
リバースモーゲージは、相続人への負担、金利・資産価値変動、利息総額に注意
リバースモーゲージは、将来にわたって不確実性が高いことに注意しましょう。
リバースモーゲージとは、自宅を担保にした借入で、借入の上限を資産価値に基づいて設定します。通常、生存中は元金の返済は不要で、利息のみを毎月支払う形態が一般的です。
契約者の死後、元金が一括返済されます。借入人の死亡後に売却された担保の売却額の不足分を相続人が支払う「リコース型」と、支払いが不要な「ノンリコース型」がありますが、リコース型であれば、売却価格で返済ができなかった場合、相続人に負債が引き継がれるので注意しましょう。
また、社会福祉協議会と民間機関運営のタイプがあり、民間の商品は選択の範囲が広いことが特徴です。しかし、商品によっては、一定期間ごとに資産評価が見直され、限度額が変動することや、変動金利型であれば、金利上昇時に支払いが増えるリスクがあることをあらかじめ考慮しておかなくてはなりません。
一般的に利息は生涯にわたって支払い続けることも重要なポイントです。その間に利息の支払い総額が膨らんでしまうことと、借入上限額に達することが考えられるので、注意が必要です。
以下がリバースモーゲージのメリットとデメリットです。
| メリット | ・高齢でも借入ができ、老後の資金も捻出できること・生存中の負担の低さ・所有権を維持されているのでリフォーム等も自由に行える・自宅を残す必要がない場合にも一つの選択肢となる |
| デメリット | ・ 「リコース型」では、売却価格が借入額を下回ると相続人が負担する必要がある。・ 商品によっては、一定期間ごとに資産評価が見直され、限度額が変動する。・変動金利の場合、金利上昇時に支払いが増えるリスクがある。・長生きして借入限度額を超えると、それ以降の融資は受けられず、利息のみ支払いが続く |
リバースモーゲージの条件は金融機関と商品によってさまざまです。自分に合ったサービスを受けられる反面、仕組みや商品ごとのリスクを把握して慎重に計画をたてる必要があります。
リースバック、リバースモーゲージとも不動産を手元に残しながら現金化できる手段ですが、しくみと契約内容をよく理解し、必要性とリスクを検討することが重要です。
まとめ
不動産の売却を決めたら、早めに行動し、計画的にスケジュールを立てることが大切です。
まずは情報収集を行い、信頼できる不動産会社を見つけて契約を結びます。媒介契約後は、境界の明示や物件状況の確認を進めながら売却活動を行い、内覧の準備や売買契約に必要な書類の整理を進めます。
売買契約を締結した後は、契約解除のリスクを頭の片隅に据えつつ、手続きを進めます。必要書類を揃え、決済・引き渡しに備えます。状況によっては抵当権抹消に必要な書類を準備し、引っ越しを済ませ、いよいよ決済・引き渡しの日を迎えます。
その後、確定申告では、適用要件を満たす特別控除の中から最も節税効果の高いものを選び、申請・納税を行います。
不動産売却は人生において大きな節目となるため、不安を感じるかもしれません。しかし、事前に流れや注意点を押さえておけば、不安の軽減とリスク回避につながります。
早めの準備と計画的な対応で、後悔のない不動産売却を実現しましょう。
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。