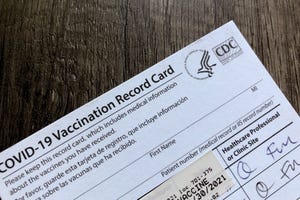Microsoftがデスクトップ仮想化を用いてWindows 10またはWindows 11のデスクトップ環境をクラウドからクライアントにストリーミング提供する「Windows 365 Cloud PC」を発表した。法人市場向けの"クラウドで動くWindows"、クラウドPCの月額定額制サブスクリプションサービスである。同社はWindows 365を「新しいパーソナルコンピューティング」とアピールしている。
私は昨年秋から断続的に同社のクラウドゲーミングサービス「Xbox Cloud Gaming」を使い続けている。ゲームをクラウド側で処理して端末に映像をストリーミングする。"クラウドで動くXbox"だ。十分なネット回線があれば、ゲーミングPCやXboxシリーズのゲーム機を持っていなくてもXboxゲームを遊べる。昨年秋にサービスが始まった時は対応デバイスがAndroidのみだったが(iOSアプリはApp Storeの審査ガイドラインを満たさなかった)、6月末にWebブラウザのサポートが追加され、PC、iPadやMacでもプレイできるようになった。
これまで手元のデバイスの処理能力に頼っていたことを、レスポンスで劣るクラウド経由にしてそのメリットが勝るのか。法人向けと個人向け、PC用OSとゲームという違いはあるが、Microsoftのクラウドゲーミングを使ってきたユーザーの視点からWindows 365の価値について考えてみる。
ゲーム体験という点でブラウザで使うCloud GamingはゲーミングPCやゲーム機に及ばない。Cloud Gamingの要件はダウンロード速度が10Mbps以上。それほど厳しくはないものの、自宅のネット環境でも720pの映像を維持できずに崩れることがあり、操作の遅延を感じることもある。そしてゲームを始める時に30秒前後、長い時は1分近くローディングに時間がかかる。短いようで、ゲームを始める前に待たされる時間は過ぎていくのが遅く、けっこう苦痛なのだ。
ただ、遊びやすく感じるていることも多い。映像の質が低下することはあっても、プレイがドロップすることはなく安定している。データ量も30分で1.5GB程度。以前試したクラウドゲーミングの競合サービスが軽く6GBを超えていたのに比べると効率的に動作している。ローディング時間も、昨年秋に試した時は45秒前後から1分以上だった。それに比べると、短期間で大幅に短縮している。20秒以内になってくれたら、逆にインストールすることなく色んなゲームを遊べるメリットの魅力が上回りそうだ。最近の大作ゲームは巨大である。例えば、Xbox版の「Halo 5:ガーディアンズ」はインストール時のファルサイズだけで46GBを超える。あれもこれもとインストールすることはできない。
ローディング時間がもっと短くなって、映像や遅延が向上したら、クラウドゲーミングがゲーミングの主流に「なるかもしれない」と思わせるものはある。しかし、今はまだゲーマーにそう実感させるレベルではない。だから、「ゲーミングPCまたはゲーム機」と「クラウドゲーミング」のどちらかを選べと言われたら、私は前者を選ぶ。
それなのに、今もXbox Cloud Gamingで遊び続けている。
なぜかというと、Microsoftは米国など22カ国において、Cloud Gamingを独立したサービスではなく、同社のゲームサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass Ultimate」に含めて追加料金なしで提供しているからだ。
Game Passは月額料金でゲーム遊び放題のサービスだ。Ultimateプランでは、Windows PC向けのゲームとXboxシリーズ向けのゲームの両方が遊び放題であり、そこにCloud Gamingが加わって、遊べるデバイスがモバイルPCやタブレット、スマートフォンに広がった。7月1日時点でPC用とコンソール用の計385タイトルがプレイできるようになっており、そのうちの271タイトルがCloud Gamingでも遊べる。
単体のサービスだったらCloud Gamingを契約しなかっただろう。でも、ゲーミングPC/Xbox用のゲームサービスに含まれるから、じっくり遊びたいゲームはPCにインストールし、カジュアルなゲームやちょっと体験してみたいゲームの時にCloud Gamingを使っている。
長い目でみたら、クラウドゲーミングには大きな可能性がある。しかし、現状ではまだクラウドゲーミングの短所が目立つ。そこでMicrosoftはCloud Gamingを独立したサービスとして提供せず、Xbox Game Passに含めてゲーミングPCやXboxと併用できるようにすることで、クラウドゲーミングの短所を補って今ある長所のみを満喫できるようにした。
そのしたたかな戦略はWindows 365の提供からも見てとれる。管理の容易さ、確実な動作、セキュリティ、アップデートの手間からの解放、多様な端末が利用可能といったメリットは個人ユーザーにも価値がある。しかし、処理能力が問われる生産性ではローカルPCのWindowsに分があり、個人向けのクラウドPCが用意されたとしても現状で移行を考える人はそれほど多くはないだろう。しかし、ハイブリッドワークのニーズを満たす法人向けのソリューションなら優れた管理性の価値は大きく、オフィスで使うPCと長所を活かし合う補完的なソリューションになる。それを"トロイの木馬"にクラウドPCの体験を広めながら、「新しいパーソナルコンピューティング」が広く受け入れられる時を待つ。
今のMicrosoftのクラウドサービス戦略は、2008年にNetflixが米国で映像ストリーミングサービスを開始した時を思い出させる。当時、一般家庭のネット環境やモバイル環境は高品質な映像コンテンツを安定して配信するのに十分ではなかった。そこでNetflixはストリーミングサービスを単体で提供せず、まずはオンラインDVDレンタルで追加料金なしで利用できる補足的なサービスとして開始した。DVDが届くのを待ちたくない時、貸し出し中でDVDをすぐにレンタルできない時にストリーミングが使われたのだ。そこから少しずつストリーミング配信の体験者を増やし、ネット環境の向上と共にサービスを向上させ、視聴者の増加に伴ってストリーミングサービスを独立させた。それからストリーミングが映画やドラマを家庭で楽しむ方法の主流になるのはあっという間だった。今や映像品質でDVDを上回る4K HDRをストリーミングで楽しめる。
ストリーミングが未来の映像エンターテインメントという壮大なビジョンを掲げつつも、DVDレンタルと競争せず、DVDレンタルに満足している人達に何もあきらめさせずに目標へと近づいていく長期的なアプローチを採っていたから、Netflixはストリーミング配信の環境が整った時に爆発的な成長を遂げることができた。それと同じしたたかな戦略を採っているから、Microsoftのクラウドサービスへの期待が高まる。