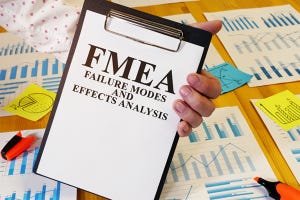重大な故障の未然防止やノウハウの蓄積に活用できるFMEA(Failure Mode and Effects Analysis)について、前回は、FMEAの概要と種類について解説した。
後半となる今回は、実際にFMEAを実施する際の流れと、それぞれの工程における注意点を紹介する。
FMEAを実施する際の流れと注意点
前回の記事でも紹介したように、FMEAのフォーマットは企業ごとにノウハウを反映させているため、実施する際にもフォーマットに合わせた進め方が構築されている。ここでは、基本的な流れと、各項目を実施する際に抑えておくべき注意点を解説する。
1.各項目の点数を定義
はじめに、各故障モードが発生した際の影響を数値化するために必要な、以下の3つの項目について、点数付けの定義を行う必要がある。
- 故障が発生した際の厳しさ
- 故障検知の可能性
- 故障の発生頻度
多くの場合、各項目について1点から10点までの十段階で点数付けがされる。この点数がFMEAにおいて影響の大きさを判断する指標になるため、その点数の定義は重要な意味を持つ。
各点数に、その点数を付与する場合の定義を設定する必要があるが、その定義づけは簡単ではない。その理由は、以下が考えられる。
- さまざまなアイテム、機能、故障モードで共通の定義
- 誰が担当しても、同じ点数が付けられるような定義、表現
できるだけ誤解を生まずに、幅広い範囲で共通に使用できる定義の構築は難しい。しかし、一度定義をすれば、製品が変わっても長く使用することになるため、有識者も含めできるだけ早く構築し、必要に応じて最低限の見直しをしていく形が望ましい。
2.実施対象の明確化(各対象の機能確認)
点数の定義完了後、もしくは平行して、FMEAを実施する際の解析対象を明確にする必要がある。また、それぞれの対象がどのような機能を持つのかについても、合わせて整理しなければならない。
対象の明確化をする際に難しいのが、どの程度の粒度で分類すればいいか? という点である。例えば、複数の部品を組み合わせたシステムFMEAを実施する場合には、そのシステムを構成する機能単位で実施する案が考えられる。
システムを上段において、構成部品すべてについて実施していると、時間がいくらあっても足りない。そこで、並行して各部品に対するFMEAを実施することで、全体を補完することが可能だ。
粒度を検討する際には、必要な要素や故障モードの抜け漏れが起きないようにすることを前提に、組織の状態や開発期間のバランスを取って選定することが必要である。
3,故障モードの整理
各アイテムに対して、故障モードの選定も必要不可欠だ。
抜けもれなく故障モードを抽出する際に、故障モードの分類が役に立つ。故障モードは、故障の性質(機械的、電気的、化学的など)や故障の発生部位、故障の発生状況に分類できるため、これらの観点で抽出することで抜け漏れが生じる可能性を低減できる。
また、特に重点的に実施する必要がある要素として、新規設計・新規適用の要素、境界部分、類似製品の不具合事例などが挙げられる。これらの要素は、従来品で分かっている要素よりも抜け漏れが発生しやすいため、複数人での議論や異なる切り口からの確認など、丁寧に抽出を行うことが重要だ。
4.各故障モードに対する評価実施
各アイテム、故障モードにおける厳しさ、検知の可能性、発生頻度に対して、評価(点数付け)を実施していく。評価をする際には、各アイテム、機能に対する深い理解と、正常時には発生しない状況に対する想像力が重要となる。
頭の中だけで考えるのは難しい場合が多いため、多少手間に感じたとしても、各故障が生じた場合の影響を図示するのが効果的だ。この手間を怠ったことで適切な点数付けができず、想定外の事象が発覚したタイミングで多大な工数をかけ、信用を失ってしまうのでは、本末転倒である。
この段階で、知識・経験のあるメンバーが参加することで、この後に実施するレビューを効率的に、高い精度・品質で実施できる。
5,関係者レビュー
FMEAの帳票を埋めたら、品質に関する責任者を交えて関係者レビューを実施する。全項目に対するレビューを実施するのは多大な時間が必要になるが、可能な限り実施する方がいい。
もし、開発期間が限られ、予定を合わせるのが困難であれば、評価点数の高いものを優先して実施するなどの工夫が必要となる。また、説明内容を速やかに理解してもらえるように、作成するFMEAの資料側での工夫も効果的だ。
レビューをする際の注意点として、なぜこの点数をつけたのかがわからなくなり、うまく説明できない場合がある。個人で作成をしている段階で、点数を付けた根拠を明確に残しておくことで、説明性の向上とノウハウの蓄積に繋がる。
6.設計・製造プロセスへのフィードバック
FMEAによって、対処すべき問題点が明確になったら、速やかに設計・製造プロセスへのフィードバックを行う。設計変更後の状態で再度FMEAを実施し、問題点の解消を確認でき、さらに変更による新たな問題点の発生がなければ、該当の項目に対しては完了となる。
設計・製造プロセスへのフィードバックを行う際には、該当製品だけでなく類似製品を含めて検討を実施したり、今後の製品開発用にノウハウとして蓄積したりすることが重要だ。
FMEAの実施と次の世代への継承を継続していくことで、高い品質の製品を開発できる。
まとめ
前回に引き続き、今回はFMEAを実際に実施する際の流れと注意点について、実際に経験した困りごとや注意点なども合わせて解説した。
品質に関するミスは一瞬で大きな事故に繋がる可能性があり、一度でも起こしてしまうと顧客の信用を失ってしまう。時間はかかるが、品質トラブルを避け、設計ノウハウを蓄積するために、地道に取り組んでいくことが重要だ。