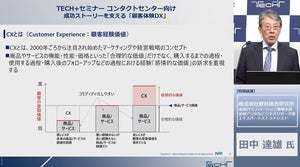前回は、「CX」が注目される背景からCX向上につながる活動とは何かということを解説しました。今回は現場が抱える顧客対応の課題や、顧客対応の負担を減らすヒントを紹介していきます。
CXの向上に重要なのは、顧客のニーズを理解したり、サービスの正しい価値を伝えたり、顧客のニーズに応える施策を展開したり、といった顧客と相対する際の基本的な顧客対応ばかりです。
しかし、時としてこの基本的な活動が現場の負担になることも。今回は現場が抱える顧客対応の課題や、顧客対応の負担を減らすヒントを紹介していきます。
現場が感じる顧客対応の課題
CXに重要なのは基本的な顧客対応ばかりですが、時として現場では負担になることもあります。
例えば、迅速で丁寧な行動は必要に迫られている件数が少ない場合であれば問題ありませんが、同時多発的に問題が発生し対応する件数が増えると、どうしても対応が遅れる可能性があります。この対応の遅れにより、顧客にとっての当たり前の活動である迅速な対応に支障をきたすようになります。そのような遅れやそもそもの対応漏れが起こると、顧客の問題はどんどん悪化していきます。
問題が悪化すると、発生するのは顧客からの「クレーム」です。その内容も大小あるのですが、時には対応者に罵詈雑言を浴びせてくる顧客もいます。このような顧客に対しては誠実な対応もなかなか聞き入れてもらえず、何とか怒りを収めていただくための業務負荷が発生してしまいます。
罵詈雑言の内容によっては、対応者の心を傷つけてしまうことにもつながります。また、顧客に損失が発生した場合、賠償などの話になることもあります。こうなると現場での対応は非常に困難となり、管理職や会社単位での対応が求められてしまい、さらなる業務負荷が増えてしまいます。
このようなことが頻発し、業務負荷が肥大化していくと最終的に離職者が増えてしまうことにもつながります。顧客が当たり前と思っている活動をいかに効率的に対応していくか、もCXを向上させるキーポイントといえるでしょう。
効率的な顧客対応とは
とはいえ、顧客対応の効率化と言葉にすれば簡単に聞こえますが、実行に移すとなかなか難しい側面もあります。ここで効率的に顧客対応を行うための手段別の工夫をいくつかご紹介します。
効率化にむけた対応手段別の工夫
顧客対応の手段によって効率化にむけた工夫の方法は変わります。ここでは、電話、メール、チャットといった代表的な3つの手段で紹介します。
1. 電話
顧客対応の手段で最も活用されているのが電話です。電話はその場で手軽に顧客と会話ができるため、簡単に短時間で密なコミュニケーションを取ることができます。
一方で、電話でのコミュニケーションはお互いの手が空いている時間に限られるため、時間的な制限が発生すること、顧客の疑問に臨機応変な対応が求められるため、慣れていない対応者にとっては回答の確認に時間がかかってしまうこと、などで効率性が落ちてしまうこともあります。そんな電話での効率化の工夫としては、以下の2つです。
テンプレート化したメモを準備する
テンプレート化したメモは情報の整理に役立ちます。顧客対応時には今の課題から製品・サービスの使い方を聞いてくる顧客もいれば、製品・サービスの使い方をまず聞いて、そのあとのやりとりで課題を教えてくれる顧客もいます。
このようにさまざまな顧客の対応を行っていると、その後の対応時に情報が整理されておらず何を対応すればいいのか分からなくなり、結果として、また電話にて問い合わせ内容の再確認を行うなどの手間が発生してしまいます。
あらかじめ確認する内容を記したメモを準備して電話対応に臨めば、どんな順番で話しても確認した内容をあるべき箇所に記載しておくだけで情報が整理されますので、電話での対応に加えて、その後の対応も効率化させることが可能です。よくある質問に対するスクリプトを用意する
多くの顧客と相対していると、顧客から出てくる質問に対して傾向がみられるようになります。こういったよくある質問に対する回答を予め用意しておけば、新人のメンバーであってもスムーズに適切な対応が可能になります。
チーム全体の効率化にはこのようなスクリプトが必要不可欠ですので、まずは顧客対応の経験豊富なメンバーのよくある質問に対する回答を文字起こしするところから始めてみましょう。
2. メール
顧客対応の手段でより手軽にコミュニケーションを図ることができるのがメールです。電話とは異なって時間的な制限がないのが最大の特徴です。顧客にとっては営業時間外や休日であっても問い合わせや質問を伝えることができますし、製品・サービス側も顧客の空いている時間を抑えることなく回答をお伝えすることができます。
また、文書化されているので記録として残ることも特徴の1つです。顧客とのやりとりを後から確認することができるので、トラブル発生時の証拠としても役立ちます。一方で、メールボックスが整理されていない場合、問い合わせメールが埋もれてしまい、対応遅れや漏れといったトラブルにつながりやすいといったデメリットもあります。そんなメールでの効率化の工夫としては、以下の2つです。
メールボックスを整理する
上述のデメリットでも紹介した通り、メールボックスが整理されていないとメルマガや外部業者とのメールなど有象無象のメールのなかにある問い合わせメールに対応していかなくてはいけません。
そのような状況は確認漏れのリスクもありますし、対応すべき問い合わせメールを探すといった非効率な業務も発生してしまいます。メールボックスの整理に関しては、フォルダを項目毎に分けて受信時に該当フォルダに振り分けるという設定がおすすめです。Gmailであれば「ラベル」を使った振り分け管理。Outlookであれば「仕分けルール」を設定した振り分け管理で整理することは可能です。よくある質問に対するテンプレートを用意する
電話で紹介したスクリプトと同じパターンですが、メールに関してもよくある質問に対する返信用のテンプレートを用意するといいでしょう。どの年次のメンバーでも時間をかけることなく対応できるだけでなく、メールの作成時間に関しても短縮できるので、チーム全体の効率化に役立ちます。こちらも経験豊富なメンバーの返信を参考にテンプレートを作り上げていきましょう。
3. チャット
チャットは、昨今の顧客対応で活用されはじめてきた手段です。電話と同様にリアルタイムなコミュニケーションが可能になるだけでなく、同時間帯に複数の顧客の対応が可能になることから、顧客対応のなかでも効率的な手段であると認知されています。
ただ、いくつかのデメリットもあります。そのうちのひとつは、簡単な質問にしか対応できないことです。より複雑化された問題はチャットだけでの解決は難しく、上述の電話やメールを活用しなければ適切に解決まで導くことができません。また、同時間帯に複数の顧客に対応するということは、その分メンバーの負担は増加するため、結果的に効率悪化につながる恐れもあります。そんなチャットでの効率化の工夫は以下の2つです。
よくある質問に対するテンプレートを用意する
上述した2つの手段と同様に、よくある質問に対するテンプレートを用意しましょう。チャットの場合、顧客も素早い対応を求めているケースが多いです。
テンプレートを準備することで、対応が素早くなるだけでなく、メンバーの負担軽減にもつながります。これからチャットを導入するようなパターンであれば、これまでの電話やメールで受けていたよくある質問をもとにテンプレートを作成すると効果的でしょう。AIチャットボットを導入する
こちらは費用が発生してしまうのですが、AI対応のチャットボットを導入することで有人対応していた稼働を削減し効率化を進めるという方法です。
特に簡単な質問であればAIでも十分対応可能なため、顧客対応の品質が低下することもないでしょう。ただし、AI対応といっても、はじめから簡単な質問でも完璧に対応できるわけではなく「学習期間」が必要になりますので、導入の際には注意しましょう。
CX向上は「人力だけ」では難しい
顧客対応を効率化させつつ、CXを向上させるには人力だけでは不可能です。時には、テクノロジーの力を借りることも必要です。
そこで次回は、顧客対応を効率化に寄与するテクノロジーの活用について紹介します。