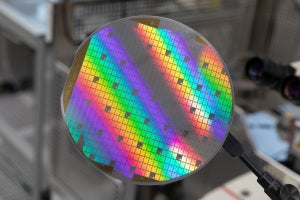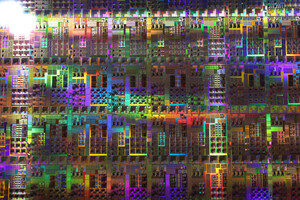ボッシュは5月21日、日本市場における2023年の売上高ならびに事業戦略に関する説明会を開催。ハードウェアのみならずソフトウェアに注力していくことを強調した。
ボッシュの日本国内における2023年度の第三者連結売上高は前年比23%増の約4200億円となったという。ボシュのクラウス・メーダー代表取締役社長はこの業績について「2023年は特別な1年だった。新型コロナウイルス感染症の収束によるロジスティックスのチェーンが再び機能し始めたこと、ならびに2022年に整備した栃木工場におけるiBoosterの生産およびむさし工場の電動パワーステアリング製品の最終組み立てがフル稼働を始めたこと、そして円安効果という3つの大きな要因が追い風となった」と、好調の要因を説明する。ただし、2024年度については、「同じことが起こるとは思っていない」との見方を示しつつも「ただし顧客からいくつかのプロジェクトを勝ち取ることができたことから、前年比で微増との見ている」と、比較的順調に事業が成長していることを説明した。
ハードのみならずソフトにも精通するボッシュ
100年に一度の大変革を迎えていると言われる自動車産業。自動車を構成するコンポーネントも大きく変化しようとしている。これまで、自動車はブレーキやステアリング、エンジンなどさまざまな機能の集合体のような考え方で設計されていたが、近年は全体のアーキテクチャを俯瞰して構築する必要が生じてきた。そのため、従来からのハードウェアのみならず、各種ハードウェアを協調させつつ制御するためのソフトウェアの存在が重要になってきている。
そのため、自動車がスマートフォンのようにソフトウェアが主体となる「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」の考え方が、次世代の自動車の主流となるとされており、同社もそこに注力。ボッシュ・グループもソフトウェアを主軸とした自動車開発に向かう市場トレンドに対応すべく、同社グループ最大の事業セクターとなる「ボッシュ モビリティ」を立ち上げ、同セクターで研究開発に携わる全従業員の50%をソフトウェアエンジニアとするなど、ソフトウェア開発に注力する姿勢を見せている。
そうした同社ソフトの中核をなすのが車体制御を統合制御するソフトウェア・パッケージである「ビークルモーションマネジメント(VMM)」だという。
ボッシュの専務執行役員でビークルモーション事業部 事業部長ならびにボッシュ モビリティの東アジア・東南アジア地域セクターボード 最高執行責任者 兼 最高財務責任者を務める松村宗夫氏は、「自動車はこれまでの各機能ごとにECUを搭載して制御する分散型アーキテクチャから、高性能なSoCを中核に据えた集中型アーキテクチャに移行することが予想されている。このセントラルECU上で各機能を制御するソフトがVMMで、単に各機能を制御するだけでなく、快適性や安定性、効率性といったことを車両全体で考慮できるようになり、どんなドライビングシチュエーションであっても、ユーザーの運転体験を最適化できるようになる」と、VMMがユーザーに提供する価値を説明する。
また、自動車(OEM)メーカー各社によって、やりたいことや開発における思想が異なることから、そうしたそれぞれのOEMが必要とする機能だけを提供できるようにするモジュラー化、ソフトウェアのポータブル化が重要とするほか、「ボッシュが提供するアクチュエータをすべてのOEMが採用するわけではないため、他社のハードにも対応する必要もある」と、ソフトがハードに依存しないことも重要であるともする。
松村氏は「シャシーの制御のみならず、ソフトをセントラルECUにインテグレーションするサービスも提供していくことで、システムソリューションの実現を図っていきたい」と、ボッシュとしてソフトウェアに注力する姿勢を協調する。
また、VMMは、あらゆるアクチュエータに対応可能だが、そういたタイプや数に依存しない柔軟な開発が可能になるため、自由度を高めた設計が可能となるほか、ドライバーからのインプットに対してソフトが介在することとなるため、ダイレクトにブレーキやハンドルとドライバーが連動することがなくなり、例えば車体を走行状態から停車するためにブレーキをかけた際、強くブレーキをかけてしまうことで車体が前方に沈む力が働いて、それが元に戻る際に衝撃が生じるいわゆる「カックンブレーキ」といったことを自動で防ぐことも可能となる。
さらに、こうしたソフトウェアの進化に対応できるハードウェアとして、ブレーキ装置とペダルの連結を分離した「デカップルドパワーブレーキ」を開発。2024年より量産を開始したほか、ブレーキバイワイヤについても2024年中の量産開始を予定しているとする。
業界横断のコラボでより安全なモビリティ社会の実現へ
ボッシュの取締役副社長でボッシュ モビリティの東アジア・東南アジア地域セクターボード プレジデント 兼 最高技術責任者のクリスチャン・メッカー氏は、「ボッシュはSDVの開発を推進するソフトウェア企業として、他社製ハードウェアでも動作可能なスタンドアロンソフトウェアの開発も進めている」と、ボッシュとしてソフトウェアを重視している姿勢を強調。日本でもハードとソフトを分離したソリューションの提供に関するニーズが高まりを見せているとし、ボッシュとしても、今後より多様化していくニーズに寄り添っていき、これまで以上に柔軟なソリューション提供を目指すとしている。
加えて、「目まぐるしく変化する自動車産業における顧客ニーズに対応していくためには幅広いソリューションを提供することが重要になってくる。すでにボッシュではブレーキ、ステアリング、パワートレーンといったものから、センサ、車載コンピュータ、ソフトウェアまで現代の主要コンポーネントを一貫体制で開発しているほか、顧客に革新的なソリューションを提供するべく、自動車システムサプライヤの領域を超えて、業界横断のコラボレーションを展開している」とし、例としてマイクロソフトと、安全なモビリティ社会の実現に向けた生成AIの活用に関する取り組みを進めているとする。
「現在の運転支援技術でも人や物体、車体といった検出は可能だが、それらの検出データを元に事故につながる可能性がどの程度あるのか、といった判断はまだできない。例えば、道路にボールが転がってきたとき、それを追いかけて子供も飛び出してくる可能性があるということは人間のドライバーであれば、これまでの経験や教習所などでならった知識などを用いて考えることができる。しかし、現在の運転支援システムはボールを認識できたとしても、そこまでの判断はできない。これが生成AIを活用することで、より人間の思考に近い結果を導き出すことができるようになる。ボッシュとマイクロソフトの協業は、自動運転のレベルを次の段階に引き上げることを期待するもので、これによりより安全な道路環境の実現につながることが期待できる」ともし、単なる自動車を開発するために必要なものを手掛けるだけでなく、あらゆる先進技術の活用に向けた活動を活発に進めているとする。
なお、同社では、今後も日本のモビリティ市場の発展に貢献していきたいとしており、そのためにも開発体制の強化を進めていき、顧客の要望に柔軟に応えられるように技術力の向上を図っていくとしている。