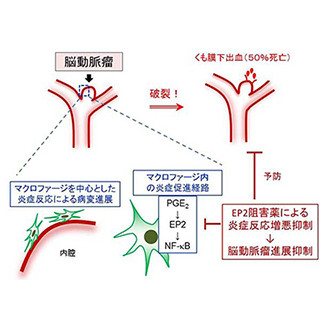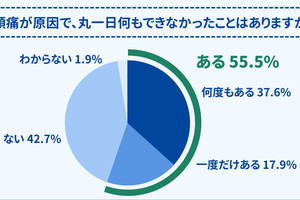名古屋市立大学(名市大)は12月8日、くも膜下出血の術後集中治療管理において、脳脊髄液を排出する「脳脊髄液ドレナージ」を持続的に1日150mL行う「持続型」よりも、8時間ごとに1日3回間欠的に1回50mLずつ1日合計で150mL排出する「間欠型」の方が、意識障害の遷延(せんえん)・増悪などを来す「慢性水頭症(続発性正常圧水頭症)」(くも膜下出血後に併発することが多い疾患)の発症率が低くなる可能性があること発表した。
同成果は、名市大 脳神経外科学講座の山中智康氏、同・間瀬光人教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、中枢神経の体液とバリアシステム関する全般を扱う学術誌「Fluids and Barriers of the CNS」に掲載された。
くも膜下出血は、現在でも死亡率が高く、生存しても意識障害や片麻痺、失語症など、重度の後遺症をきたしやすい疾患として知られている。その初期出血量が多いほど、発症時の症状が重いほど、慢性水頭症を発症しやすいことが知られていたため、出血によって赤くなった血性髄液をできるだけ多く排出した方が慢性水頭症の発症予防に効果があると考えられてきたという。
しかし近年、脳脊髄液の総排出量は慢性水頭症の発症とは関連しておらず、むしろ脳脊髄液ドレナージは短期間にとどめて、できるだけ早く抜去した方が慢性水頭症を発症しにくいという研究成果が欧米の研究チームから報告されるようになり、こうした報告を受けて研究チームは、脳脊髄液を24時間排出し続けることが、くも膜下腔の癒着を促し、逆に慢性水頭症の発症リスクを上げているのではないかという仮説を立て、2007年より脳脊髄液ドレナージの持続型と間欠型の比較を実施してきたという。
実際の研究内容としては、2007年2月から2022年11月までの期間に、名古屋市立大学病院において、発症から72時間以内に破裂脳動脈瘤に対して開頭クリッピング術もしくはコイル塞栓術の急性期治療が行われたくも膜下出血の患者252人中、脳脊髄液ドレナージが行われた204人を対象とし、持続型に対する間欠型の慢性水頭症の予防効果を、ロジスティック回帰分析による多変量オッズ比にて算出、Cox比例ハザードモデルで慢性水頭症の発症頻度の比較が行われたという。また、慢性水頭症との関連が考えられる因子として、(1)くも膜下出血の重症度、(2)急性水頭症、(3)脳脊髄液ドレナージの初期圧設定、(4)脳内血腫合併の有無について、2群に分けて間欠型の慢性水頭症の予防効果の検証が行われたという。
対象となった204人のうち、136人(67%)に持続型が行われ、68人(33%)に間欠型が行われた。2群間では、性別、年齢、脳動脈瘤の部位に統計学的に有意な差異はなかったが、くも膜下出血発症時の重症度と急性水頭症の併存については、持続型が行われた群の方が有意に重症かつ急性水頭症の合併頻度が高かったという。
また、持続型が行われた136人中74人(54%)、間欠的ドレナージが行われた68人中22人(32%)が慢性水頭症を発症。持続型に対する間欠型慢性水頭症発症の多変量オッズ比は0.25だったとするほか、間欠型による慢性水頭症の予防効果については、層別化解析では、くも膜下出血発症時の重症度が重症群、脳脊髄液ドレナージの初期圧設定が高い群、脳内血腫合併群の方が高かったとする。一方、くも膜下出血発症時に急性水頭症を併発していた患者群においては、間欠型の慢性水頭症予防効果は認められず、急性水頭症を併発していない群においてのみ、間欠型の効果が確認されたとした。
研究チームによると、くも膜下出血後の血性髄液は、できるだけ多く排出した方が良いとの考えかた、24時間持続的に脳脊髄液ドレナージするのが一般的なくも膜下出血後の術後管理として定着していたが、持続型は患者をベッド上に臥床位で拘束せねばならず、リハビリテーションが進まず、下肢筋力低下を来しやすく、回復を遅らせる一因となっていたという。
しかし、今回の研究によって、脳脊髄液ドレナージは持続的に行うよりも間欠的に行う方が慢性水頭症の発症が抑制される可能性が示されたことから、間欠型であれば、患者は排出していない時間帯にベッドから離床してリハビリテーションを行うことができ、早期回復にもつながる画期的な慢性水頭症の予防法となる可能性があると研究チームでは説明。ただし、今回の研究は前向き観察研究だが、ランダム割付試験ではないため、研究チームは今後、持続型と間欠型をランダム割付試験で検証するとともに、頭蓋内圧モニターを併用して科学的根拠を裏付けて、研究を発展させていきたいとしている。また、これまで、くも膜下出血後の慢性水頭症の予防法は確立しておらず、脳脊髄液ドレナージを間欠的に行う手法は、脳神経外科医の固定観念を覆す画期的かつ簡便な方法であり、社会的意義は大きいと考えると研究チームではコメントしている。