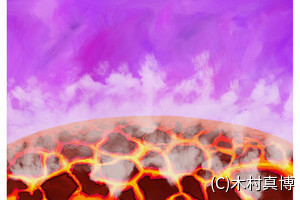京都産業大学(京産大)は11月16日、これまで京産大 神山(こうやま)天文台で開発してきた可視光線波長域で動作する小型の補償光学装置「CRAO」を、同天文台の口径1.3m「荒木望遠鏡」に装着し、同装置によって可視光線波長域で星像を大幅に改善することに成功したと発表した。
同成果は、京産大 理学研究科の坂部健太大学院生を中心に、フォトクロス、国立天文台(NAOJ)の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、9月18日に開催された日本補償光学情報交換会による研究会「第19回 補償光学研究開発のための情報交換会」にて発表された。
地球大気はいうまでもなく、人類をはじめとする生物が生きていくのになくてはならないものだ。しかし天文観測においては、宇宙から届いた星の光を、波長によっては吸収してしまい、地上まで届いても常に歪ませるなど、“邪魔者”のような存在である。星は瞬いて見えるが、あれは大気の影響を受けてシーイングが常に変化しているからである。星は宇宙で見れば瞬かないが、分厚い地球大気の底に住む我々は、この瞬きから逃れられない宿命にある。それは、シーイングが抑えられるため、すばる望遠鏡をはじめとする複数の大型地上望遠鏡が経ち並ぶハワイ島マウナケア山頂(標高約4000m)の高所であっても同じで、同山頂であっても典型的なシーイングサイズは約0.7秒角程度だという。
そのためこれまで、解像度を高めるためのさまざまな手法が考案・実装されてきており、その重要な技術の1つが、ガイド星を用いて、時々刻々と変化するシーイングに対して瞬間的に反射鏡の形状を変化させ続け、星の像をシャープな像へと復元する補償光学だ。ガイド星の数は限られているため、開発当初は限られた天体にしか適用できなかったが、近年は上空約90kmにあるナトリウム層に向けてレーザを照射して人工ガイド星を作り出すことで、その課題を克服。これにより、大半の天体に対して補償光学を適用できるようになったのである。
補償光学装置は、1990年代後半にNAOJによって開発され、世界中の天文学者に公開された技術だ(すばる望遠鏡での第一世代「36素子波面補償光学装置(AO)」のファーストライトは2000年12月)。当初は赤外線波長域で利用され、大きな観測成果を挙げてきた(マウナケア山頂での解像度約0.6秒角をAOは0.06秒角まで高めた)。
そうなると当然可視光域での適用も期待されるが、波長が短いため技術的なハードルが非常に高くなり、実現例は多くないという。特に日本国内は大気の状態が悪いこともあり、絶えず変動する地球大気によって歪んだ星像を、地球大気の影響を受ける前の状態に近付けることは容易ではないとする。そうした中で、課題の克服と、中小口径望遠鏡向けの小型・安価な補償光学装置の実現を目指して開発を続けてきたのが研究チームである。
今回の研究では、レンズを用いた屈折式の光学系によって装置全体の小型化が達成され(従来の補償光学装置に比べて装置面積が3分の1程度)、また同装置で重要となる波面センサや可変形鏡に市販の光学部品を用いることで、製作費用を200万円程度と、大型望遠鏡のものに比べておよそ50分の1程度にまで抑えることに成功したという。
このようにして開発されたCRAOは、絶えず変動する地球の大気によって歪んだ星像を、数ミリ秒で高速に補正し、ぼやけた星像をシャープに改善することに成功。神山天文台での平均的なシーイング・サイズ(星像のボケ)は2~3秒角(1秒角は3600分の1度)だが、今回、最良の場合で約0.6秒角まで星像を改善できたとする。上述したようにマウナケア山頂そのものの解像度が0.7秒角ほどなので、それとほぼ同等にすることにできたことになる。
なお研究チームは、実際にCRAOを適用してみずがめ座の連星「ζ(ゼータ) Aqr」の観測を実施。連星は2.4秒角離れているが、従来ならぼやけてしまって2つの星を分離できなかったのだが、CRAOによる補正が行われることで星像がシャープになり、明確に分離できていることが確認された。
こうした星像改善によって、より狭い範囲に星からの光を集中させられると、CRAOと組み合わせたさまざまな天文観測装置による観測において、より暗い天体の観測も可能になるという。現在、CRAOでは最短3ミリ秒程度で星像を補正しているが、今後、さらに短い時間で補正を行うことで、さらなる性能向上も期待できるとしている。