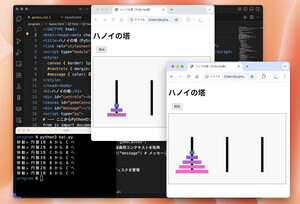米国にとって命綱ともいえる軍事衛星を、ロシア製エンジンを積んだロケットで打ち上げる--。
そんな倒錯した状態が始まって10年以上が経った2014年、米国とロシアの関係悪化によって、米国がロシア製エンジンを使えなくなる可能性が出てきた。そこで米国は、このロシアへの依存からの脱却を目指して、新たなる次世代ロケット「ヴァルカン」の開発と、そしてそのヴァルカンを宇宙へ打ち上げる、新型ロケット・エンジンの開発を決定した。
ヴァルカンに搭載されるエンジンは現在、2つの米国企業が開発に挑んでいる。ひとつはAmazon創業者ジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙企業「ブルー・オリジン」。もうひとつはアポロやスペースシャトルをはじめ、米国の宇宙開発の黎明期からこんにちまで、その歴史を支えてきた「エアロジェット・ロケットダイン」である。両者はそれぞれ異なるエンジンを独自に開発し、最終的にどちらか1社のエンジンが選ばれる。
新進気鋭のベンチャーと、老舗中の老舗の名門企業という対照的な2社が挑む新型エンジン開発。はたして勝つのはどちらか、そして無事にロシア製エンジンからの脱却は叶うのだろうか。
ロシアより大推力と高信頼性をこめて
そもそも米国がロシア製の高性能エンジンを輸入することになったきっかけは、1990年代にまでさかのぼる。
冷戦中は敵対していた米国とソビエト連邦(ソ連)だが、1991年にソ連が解体され、ロシア連邦が成立すると、その状況は一変する。もともと宇宙開発においても、両者は最大のライバルながら、ときどき共同ミッションも行うなどそれほど悪い関係ではなかったが、冷戦後はさらに雪解けが加速。1990年代にはソ連時代に打ち上げられた宇宙ステーション「ミール」に米国の宇宙飛行士が滞在したり、米国のスペースシャトルにロシア人飛行士が乗り込んだりといったことが行われた。
さらに1998年に国際宇宙ステーションの建造が始まると、両者の関係は切っても切れないものとなり、米国とロシアがそれぞれ打ち上げたモジュールがつながり、ひとつの宇宙ステーションを形作るまでになった。そこに両国はもちろん、欧州や日本などの宇宙飛行士も滞在し、さらに彼らがロシアの宇宙船に乗って地球との間を行き来する光景は、もはや日常になっている。
そんな宇宙開発における雪解けムードがさらに広がり、ロシア製のエンジンを米国が輸入するということにまで発展した。
1990年代初期、米国の技術者がロシアにわたり、そのエンジン技術にほとんど初めて目の当たりにした。そして1995年、米国のロケットエンジン開発の大手企業だったプラット&ウィットニー(現在のエアロジェット・ロケットダイン)は、その中から「RD-120」というエンジンを米国に持ち帰って、燃焼試験を行った。RD-120は、ウクライナ製の「ゼニート」ロケットの第2段に使われているエンジンで、ケロシン(灯油)と液体酸素を使う、比推力(燃費)のよい高性能エンジンのひとつとして知られている。
そしてプラット&ウィットニーは燃焼試験の結果、実際にその高性能さを確認。1996年にはRD-120を開発したロシアのエンジン開発大手エネルゴマーシュとの間で、同社製エンジンを購入することで合意を結んだ。米国にとっては高い性能のロシア製エンジンは、技術的にはもちろん、商品としても魅力的であり、一方のロシアにとっても、財政難の中で外貨は少しでも欲しいところだった。
どのエンジンを輸入するかにあたっては、候補としてRD-120のほかに、「RD-170」と「RD-180」というエンジンがあがった。RD-170はケロシンと液体酸素を使う世界で最も強力なエンジンで、ロシア最強のロケットとして知られる「エネルギア」の第1段に使われていた。RD-180は、そのRD-170を半分にしたようなエンジンで、高い効率などはそのままで、推力(パワー)は約半分になっている。
プラット&ウィットニーは検討の結果、RD-120はロケットの第2段向けエンジンであること、そしてRD-170は推力が大きく強力すぎることから、RD-180を購入することを決定。エネルゴマーシュとの共同出資でRD-180の輸入、販売を担当するRD AMROSSという会社が立ち上げられ、さらにNASAのマーシャル宇宙飛行センターには、RD-180の燃焼試験ができる立派な試験設備も建設された。
1997年には、航空・宇宙大手のロッキード・マーティンが、このRD-180を自社のロケットに採用することを決定。既存の「アトラスII」というロケットに組み込むような形で、2000年に「アトラスIII」というロケットが開発された。
アトラスV
こうした流れと並行して、米国空軍は1994年に、軍事衛星など米国の政府系衛星を打ち上げるロケット、いわゆる「基幹ロケット」の新型機を開発する「EELV(Evolved Expendable Launch Vehicle)計画」を立ち上げた。
当時、米国の基幹ロケットは、どれも1960~70年代に造られたものを改良して運用しており、性能が徐々に時代に追いつかなくなっていた。また信頼性の向上、コストダウンできる余地にも限界があった。
このEELVの開発にはいくつかの企業が応募し、その中からロッキード・マーティンと、もうひとつの大手であるボーイングの2社が選ばれた。
この中で、ボーイングは「デルタIV」というロケットを開発。デルタIVは液体酸素と液体水素を推進剤に使うロケットで、スペースシャトルの開発でつちかわれた技術が投入されている。
一方、ロッキード・マーティンは「アトラスV」というロケットを開発した。同社は2000年にアトラスIIIを開発していたが、アトラスIIIでは要求された打ち上げ能力に足らないこと、またそもそもロシア製エンジンの実証機という位置づけだったことから、ロケットの構造やブースターなどを刷新した新しいロケットが開発された。ただ、同社はこのアトラスVでも、やはりロシア製のRD-180を採用した。
デルタIVもアトラスVも、ともに2002年に初飛行し、2017年6月現在、デルタIVは35機が、アトラスVは71機が打ち上げられ、おおむねすべて成功している。両社は当初、それぞれ独自にロケットを運用していたが、2006年に共同出資でユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)という会社を設立し、現在はULAがデルタIVとアトラスVの製造から打ち上げまでを担っている。
両機の打ち上げ数を見てもわかるように、どちらかというとアトラスVのほうが主力として活躍している。これには、デルタIVは製造や運用が複雑で、アトラスVよりコストが高いという欠点があるという事情がある。
アトラスVは、偵察衛星や軍用通信衛星、NASAの科学衛星や探査機、そして米空軍の無人スペースシャトル「X-37B」など、米国の政府政府系衛星を数多く、宇宙へ送り続けている。そしてそのすべてを支えてきたのが、ロシア製のRD-180だった。
米国の宇宙輸送でのロシア依存は、こうして始まり、そして現在まで続いている。
始まったロシア依存
そもそもなぜ、米国はロシア依存を始めることになったのか。その理由は、1970~80年代の米国のロケットをとりまく環境にある。
1970年代といえば、スペースシャトルの開発が始まった時期であり、そして1980年代はスペースシャトルの運用が始まった時期にあたる。米国では飛行機のように何度も再使用できるスペースシャトルは次世代の宇宙輸送手段としてもてはやされ、打ち上げごとに使い捨てていた当時の基幹ロケット、すなわちデルタIVやアトラスVの先代、先々代にあたるロケットの生産を止めるところまでいった。
しかし、スペースシャトルは当初考えていたほどの信頼性も低コスト化も達成できず、さらに1986年には「チャレンジャー」事故が発生したことなどから、米国は基幹ロケットの生産を再開。しばらくはそのまま古いロケットを使い続けていればよかったものの、1990年代になって限界が訪れ、それがEELVを開発する動機となった。
ところが、1980年代にスペースシャトルの開発や運用へ傾倒していたことから、新しいロケットを開発するのに必要な技術が、いくつか抜け落ちてしまっていたのだった。
その最たるものが、RD-180のような、ケロシンと液体酸素を推進剤とする、そしてロケットの1段目向けの強力な推力を出せるエンジンの技術だった。よくスペースシャトルの功罪について語られるとき、「その開発や運用に費やした時間とお金をつぎこめば、米国もRD-180のような強力なエンジンが開発できたかもしれない」といわれるのは、こうした1980年代のエンジン開発における停滞があったためである。
もちろん厳密には、ロケットを造る技術の、何もかもすべてが失われたわけではない。たとえばスペースシャトルを開発した経験から、同じように液体酸素と液体水素を使うエンジンの開発技術は伸び、それはデルタIVのエンジンとして実を結んでいる。
また、当時の米国に液体酸素とケロシンのエンジンを造る技術がまったくなかった、というわけでもない。たとえば既存のエンジンの改良や能力向上といったことは行われたし、またRD-180でさえ、ロシアから買った設計図をもとに米国で生産することは不可能ではないとされた。
しかし、1980年代の停滞を経ての1990年代から、米国内でRD-180のような強力なエンジンを新たに開発すること、あるいは米国版RD-180を生産することにかかるコストや時間、そして信頼性を確立する手間は膨大なものになり、不可能ではないものの現実的でもなかった。一方、ロシアからエンジンを買えば、すでに性能も信頼性も保証されているものが手に入るし、そして価格も安い。さらにいえば外貨獲得のためロシアはどんどん売ってくれる。
純粋に自国の技術を育てるという点でいえば、たとえ何年かかってでも、米国でRD-180級のエンジンを開発、あるいはRD-180そのもの生産するほうがよいのは間違いないだろう。しかし時間やコストなど、さまざまな要素を総合的に判断したとき、「ロシアからエンジンを買う」という選択は、当時としてはそれほど間違ったものではなかった。そして2000年代を通してほんの数年前まで、たしかに間違いではなかった。
ところが2014年、状況は一変する。
(次回は7月28日の掲載予定です)
参考
・Sutton, George P. History of Liquid Propellant Rocket Engines. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006, 911p.
・http://engine.space/dejatelnost/engines/rd-180/
・Atlas III
・New Atlas III Rocket to Debut with Launch of Commercial Satellite | International Launch Services
・Evolved Expendable Launch Vehicle > Air Force Space Command > Fact Sheets