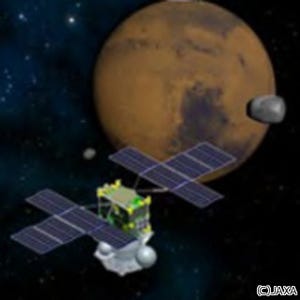皆既日食が起こると、太陽の周囲に、真珠色に淡く輝く部分が見える。これは「コロナ」と呼ばれる高温の大気で、その温度は100万℃もの、猛烈な熱さをもっている。
ところが、太陽の表面の温度は6000℃しかなく、さらにコロナは太陽表面から数百kmから数千kmも離れている。にもかかわらず、なぜコロナは太陽の表面より、100倍以上も高温になっているのだろうか。
この不思議な現象は「太陽コロナ加熱問題」として、数十年間にわたって多くの研究者を悩ませ続け、そして現在も未解決のままだ。
その謎を探るべく、国立天文台と宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所は、2013年に日本の太陽観測衛星「ひので」と、米国の太陽観測衛星「IRIS」(アイリス)による共同観測を実施し、さらにスーパー・コンピューター「アテルイ」による数値シミュレーションを組み合わせた研究が行われ、そして2015年8月24日、その研究成果が発表された。
はたして、太陽コロナ加熱問題に終止符は打てるのだろうか。
連載の第1回となる今回は、「太陽コロナ加熱問題とはなにか」について見ていきたい。

|

|

|
|
JAXA宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 准教授 清水 敏文(しみず・としふみ)さん |
名古屋大学 太陽地球環境研究所 岡本 丈典(おかもと・じょうてん)さん |
国立天文台 ひので科学プロジェクト Patrick Antolin (パトリック・アントリン)さん |
太陽コロナ加熱問題
8月も下旬に入ると、いくぶんか過ごしやすくなるが、それでも毎日うだるような暑さが続いている。この時期ばかりは太陽からさんさんと降り注ぐ光を恨めしく思うが、実のところ多くの生命にとってなくてはならない、天からの恵みである。
この太陽からの光は、太陽中心部の「核」と呼ばれる部分で、水素を燃料とした核融合反応が起こり続けていることによって生み出されている。そのエネルギーは莫大なもので、核の温度はおよそ1600万℃にもなる。その核の外側には、厚さ約30万kmの「放射層」と呼ばれる領域があり、核で生じた熱が輻射によって外に向かって流れている。ここでも約800万℃と、想像を絶するほどの高温だ。
さらにその外側には厚さ約20万kmの「対流層」があり、ここでもまだ70万℃もある。そしてその外側には、私たちが肉眼でまぶしく見える、「光球」と呼ばれる表面層があり、ここまで来ると温度は約6000℃ほどにまで下がる。
その光球のさらに外側には「コロナ」という部分がある。コロナは皆既日食が起きたときなどに、太陽の周囲で淡く輝いて見える部分で、その色は「真珠色」とも例えられ、息を呑むほど美しい。
コロナは太陽表面から数百kmから数千kmも離れている。にもかかわらず、コロナの温度はどういうわけか、約100万℃もあるのだ。
6000℃も100万℃も、人間の感覚からするとどちらも「熱い」のだが、それはともかく、これほど桁違いに温度が違うのはおかしな話である。いったいどういう仕組みで、これほどまで熱くなっているのか。そしてそれはどうやって維持されているのか。
これが「太陽コロナ加熱問題」として、太陽の本格的な観測が始まってから現在まで、長年にわたって多くの科学者を悩ませてきた謎であった。
これまで、その謎を解く鍵が太陽の磁場にあるのではないか、ということはわかっていた。たとえば、100万℃以上のガスがあるとX線が放出されるが、そのX線を使って太陽を観測したところ、黒点のあるところで特にX線が強いこと、つまり100万℃以上のガスがあることがわかった。
黒点というのは、太陽の表面に見える黒い斑点のような部分で、太陽表面より温度が1000℃ほど低いために黒く見えている。この黒点はまた、強力な磁場ももっている。つまり、X線が強いところに黒点があり、そして黒点は磁場が強いことから、太陽コロナ加熱問題に磁場がなんらかの形で絡んでいるのは間違いない、とされていた。ただ、それ以上のことは長い間わからずじまいだった。
「ナノフレア加熱説」と「波動加熱説」
現在、太陽コロナ加熱問題では、大きく2つの仮説が議論されている。
ひとつは「ナノフレア加熱説」と呼ばれるものである。太陽の表面ではフレアという爆発現象が起きており、そのうち小さなものがマイクロフレア、さらに小さなものがナノフレアと呼ばれている。今の技術ではナノフレアを観測することはできないものの、ナノフレアによって生じているエネルギーによって、コロナが加熱されているのではないか、という仮説である。
そしてもうひとつが「波動加熱説」である。太陽の表面にはあちこちに磁場が生えてきており、その磁場が揺すられることで、波のエネルギーとして太陽表面からコロナにエネルギーが運ばれ、コロナの中で熱になっているのではないか、という仮説である。
ただ、どちらの仮説にも一長一短があった。たとえばナノフレア加熱説では、ナノフレアによって発生するエネルギーをすべて足しても、コロナを加熱するために必要なエネルギーには足らないことが判明している。また波動加熱説は、光球からコロナへと波動が伝播する様子が観測されていないし、上空に伝播した波がどのように散逸し、コロナを過熱しているのかがわかっていなかった。
どちらの現象も直接観測することが難しいため、決着は付かないままだった。そんな中、2006年に太陽観測衛星「ひので」が打ち上げられたことで、大きな進展が生まれた。
「ひので」が捉えた太陽コロナ中の磁場の動き
「ひので」は「ひのとり」、「ようこう」に続く、日本にとって3機目の太陽観測衛星として、2006年9月23日にM-Vロケット7号機で打ち上げられた。衛星には可視光とX線、そして極紫外線を観測できる、3種類の先進的な望遠鏡が搭載されており、太陽のコロナの活動や磁気活動を詳しく観測することができると期待された。
太陽コロナの波動加熱説を証明する場合、磁場そのものが肉眼では観測できないことが大きな課題だった。だが、2007年に「ひので」は、「プロミネンス」を利用し、コロナ中の磁場の動きを観測することに成功した。
プロミネンスは、望遠鏡などで見ると、まるで炎が噴き出しているように見えることから「紅炎」とも呼ばれるが、その実態では炎ではなく、100万℃の太陽コロナ中に浮かぶ1万℃ほどの"低温"のガスである。
その起源は光球の外側、またコロナの内側にある、「彩層」と呼ばれる部分にある濃いガスである。プロミネンスは周囲のコロナよりも100倍ほど重いが、コロナ中の磁場がハンモックの役割を果たし、このガスを浮かせることで噴き上げられている。

|
|
左の写真はNASAの太陽観測衛星「SDO」が極端紫外光でとらえた太陽全面画像。炎が噴き出しているように見える。右は太陽観測衛星「ひので」が可視光で撮影した太陽プロミネンス。 (C)NASA/JAXA/NAOJ |
つまり、コロナ中の磁場を直接観測することは困難でも、磁場に束縛されたプロミネンスの様子を観測することで、コロナ中の磁場の性質や振る舞いを調べることができる。
そしてその結果、磁場が上下に揺らぎながら横に移動していることが発見された。こうした磁場を伝える波のことを「アルヴェン波」と呼ぶ。太陽でアルヴェン波が観測されたのはこれが史上初のことで、世界的な大発見となった。
さらに、観測されたアルヴェン波の波動は、コロナの加熱に十分なだけのエネルギーを持っていることもわかった。

|

|
|
「ひので」が捉えた太陽コロナ中の磁場の動き (C)岡本 丈典(JAXA/現 名古屋大学)、Patrick Antolin |
コロナ加熱問題と波動 (C)岡本 丈典(JAXA/現 名古屋大学)、Patrick Antolin |
これで波動加熱説が確かめられ、コロナ加熱問題は見事解決――とは、しかし、そうは問屋が卸さなかった。
(続く)
参考
・http://hinode.nao.ac.jp/news/1508Hinode-IRIS/
・http://www.nao.ac.jp/news/science/2015/20150824-hinode.html
・http://hinode.nao.ac.jp/panf/
・http://hinode.nao.ac.jp/news/1508Hinode-IRIS/Press2015_dist_Hinode-IRISrev.pdf
・http://www.nasa.gov/feature/goddard/iris-and-hinode-stellar-research-team