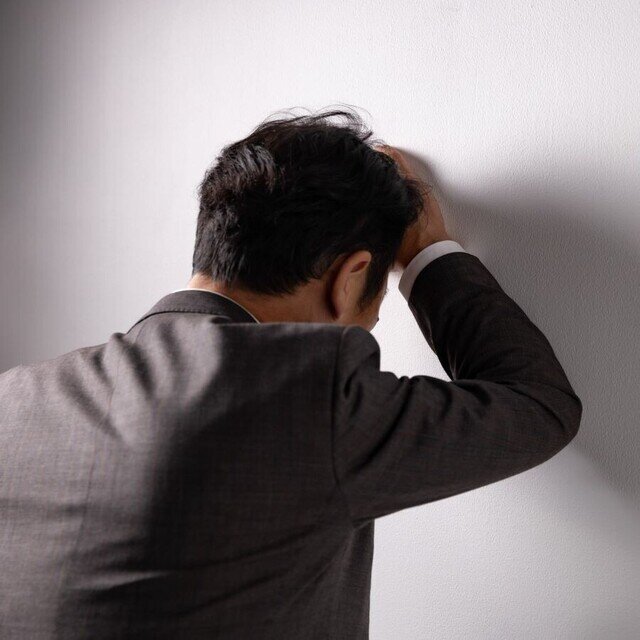第4回では、ビジネスリーダーによる職場のマネジメント手法をテーマに、チーム自体がプロアクティブかどうかを見極めるための考え方、そしてチーム状態に応じた打ち手について説明しました。
最終回である第5回では、第4回までに述べた方法論の実践に当たって、ビジネスリーダーの皆様がまさに「リーダー」として、職場、そして部下を牽引することが重要であるという点について解説します。
強い組織づくりの主役である「管理職」
本連載ではここまで、個人やチームのプロアクティブ行動の活性化に向けた様々なアプローチを紹介してきましたが、こうした取組は主に管理職の方々が担われることになるでしょう。プロアクティブ人材の育成にあたって「部下に寄り添い働きかける」ことこそ重要であることは、これまでの連載を通じておわかりいただけたと思います。
管理職は部下の保有するスキル・知見を最大限活用し、部門の成果を上げるという責任を有しています。裏返せば部下の知識・スキルの向上、職務へのアサイン、コラボレーションの促進、成果に導くためのガイドといった権限を有しているということです。
つまり管理職は、部下に対してその行動や志向に働きかける権限と責任が公式化されている唯一の主体と言えるのです。こうした背景で、管理職はプロアクティブ人材の育成に取り組む上で欠かせないピースと言えるのです。
また個の力を組織の成長に結びつけるという意味でも管理職の働きは非常に重要です。経営トップが掲げるビジョンと、社員が有する多様な知恵の橋渡し役を管理職が担うことで、環境変化に強い強靭な組織が実現できると言われています。VUCAと呼ばれる激動の時代を生き抜く上でも、管理職の重要性が叫ばれています。
「マネージャー」ではなく「リーダー」として振る舞っているか?
管理職の役割にはマネージャーとリーダーの2側面があります(図1)。
多くの管理職の方々になじみがあるのは「対処すべき問題が組織から与えられ、問題に対し組織を統制し解決に導く」マネージャーとしての役割でしょう。「業績・目標のモニタリングや部下のコントロール」、「他部門との調整」や「職場で日々起こる問題の報告や対処」と言えばピンと来るのではないでしょうか。
一方、リーダーとしての役割は、「チームや部門の将来を展望し“自ら”問題を提起し、不確実な未来にチーム全体で挑む」というものになります。
例えばパーパス策定や全社長期ビジョンの策定をきっかけとして、管理職“自らの強い想い”のもと変革的な自組織のビジョンを創り、これに基づき創発的なチーム活動をリードするような動きです。
さて、多くの管理職は「マネージャーとしての業務に多くの時間を取られている」のが実態ではないでしょうか。近年、管理職の負荷増大が社会問題化しています。負荷増大の要因としては人手不足、部下や職場の抱える問題の複雑化、対処しなければならないリスクの多様化などが挙げられますが、こうした問題対処は全てマネージャーとしての職務です。
プロアクティブ人材の育成に当たってはこの状況は問題です。細かく解説するには紙面が足りない為直感的に捉えてほしいのですが、マネージャー的な対処で果たして個人は活性化し、チームのコラボレーションは進むでしょうか。挑戦や活性化といったテーマにおいて、「あなたに自律的になってほしいのでその原因を探る」というアプローチより、「自分はこういうことはやりたいので一緒にやらないか」というアプローチのほうが有効そうな印象を持ちませんか。
プロアクティブ人材を育成するためにはまずは管理職がリーダーとして部下を牽引することが求められているのです。自らが先導的なテーマを出した上で部下を(対話しながら、対立も恐れず)巻き込み鼓舞することでプロアクティブ行動を喚起し、コラボレーションの火をつけるという動きが求められるということです。
リーダーの素養を高めるための第一歩
日本ではリーダーとしてのスキル・経験が育ちづらいと言われます。自らが組織全体のありたい未来を創造するという視点は、相当の上級管理職にならなければ要求されないため、リーダーとしてのスキルや経験に乏しいのは当然のことです。そこで本稿の最後にリーダーとしての素養を高めるための第一歩についてご紹介したいと思います。
それは、小規模な創発チームをまずは組成してみることです。自身や自組織の将来について、自身の右腕や信頼できる部下と真剣に対話するのです。飲み会などでの「できたらいいなあ」というレベルの放談ではなく真剣に、夢を語り合うのです。そしてビジョン実現に向けて二人三脚で具体的な活動を細々とでも恒常化させていくのです。
多くの人は「仕事の場で、自己実現を語り合う」ということにそもそも慣れていません。そのためまずは「自分が信頼できる」小規模なチームから始めることをおススメします。高い心理的安全性のもとで建設的な議論を重ね、またフィードバックを受けることでリーダーとしての素養を磨いていくということです。
また継続的な実践を重視しているのは、「自身がリーダーとして振る舞うということはどういうことか」ということを経験学習的に自分のなかで概念化させることが非常に重要だからです。
リーダーとして振る舞う場を明確に切り分けておくことは、リーダーとしての自分の成功体験を概念化するのに非常に有効です。
皆さんの職場が、それぞれの個性が発揮されつつ建設的な対話がなされるような、創発的な空間となることを祈り、この連載を締めくくりたいと思います。