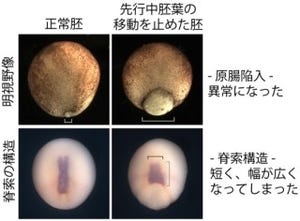基礎生物学研究所(NIBB)は2月26日、ニワトリおよびマウスを用いた研究から、「脳由来神経栄養因子(BDNF)」の「プロセシング」がタンパク質「SPIG1」によって制御されていることを明らかにしたと発表した。
成果は、NIBB 統合神経生物学研究部門の鈴木亮子研究員、同・野田昌晴教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月26日付けで米神経科学会誌「The Journal of Neuroscience」オンライン版に掲載された。
BDNFは神経細胞の生存や分化、さらに神経回路の形成や記憶・学習の基盤である「神経シナプス可塑性」の調節などに関わる重要な分泌性因子だ。従って、その分泌異常や機能不全は、うつ病、統合失調症といった神経疾患の原因となることが知られている。
BDNFは、神経細胞内で前駆体BDNFとして合成された後、分泌前あるいは分泌後に「プロテアーゼ」により切断修飾を受けて成熟体BDNFになる仕組みで、その過程を「プロセシング」という。これまでに、このBDNFのプロセシングに関わるプロテアーゼはいくつか報告されたが、プロセシングを調節する仕組みについては十分明らかにされていなかった。
また、これまで統合神経生物学研究部門では、動物個体の発生過程でおこる網膜内領域特異化の分子機構と、その後の視神経の視覚中枢への領域特異的な神経結合形成の分子機構を研究してきた。まず、発生期ニワトリ網膜において「鼻耳軸(前後軸)」、あるいは背腹軸方向の発現量に差のある分子のスクリーニング(選別)を行い、網膜内で領域特異的に発現する多数の分子を同定。
この中に、網膜の背耳側の領域の神経節細胞に多く発現する分子として発見されたのがSPIG1だ。SPIG1は、「フォリスタチン様ドメイン」、「プロテアーゼ阻害ドメイン」、「EF-handモチーフ」、および「免疫グロブリン様ドメイン」から成る分泌因子であることはわかっていたが、その生理的役割はこれまでまったくわかっていなかったのである。
そこで研究チームは今回、まず発生期のニワトリ網膜においてSPIG1遺伝子の発現を抑制(ノックダウン)させることから、その機能解明を開始することにした。SPIG1遺伝子をノックダウンさせた結果、網膜から脳の視中枢(視蓋)へ投射する視神経細胞の軸索から、多くの側枝が異所的に生じることが判明したのである(画像1・2:発生12日目)。
正常な発生では、投射の形成過程において、正しい位置で側枝の形成が起こるだけでなく(画像1・2:発生14日目)、不適切な側枝は除去され正しい位置に形成された側枝だけが残る「リファイメント」現象が起こる仕組みだ。しかし、SPIG1遺伝子をノックダウンさせると、このリファイメントも起こらず、間違った場所にシナプスが形成されたのである(画像1・2:発生18日目)。
次に網膜を構成する細胞の培養がシャーレ上でなされ、その結果、SPIG1遺伝子をノックダウンした神経節細胞の軸索には、視蓋上で観察されたのと同様に、多くの側枝が形成されるのが確認された(画像3)。このことから、成熟体BDNFが神経軸索の側枝形成を促すことが知られていることから、SPIG1がBDNFの分泌・プロセシングの過程に関与することが推測されたというわけだ。
そこで、BDNFの働きを抑える遮断抗体「anti-BDNF抗体」を培地に添加したところ、SPIG1遺伝子をノックダウンした神経軸索から形成される側枝は、濃度依存的に減少することが判明(画像4)。これらの結果から、SPIG1遺伝子の発現を減少させると、神経節細胞から分泌される成熟体BDNFが増加することが示唆されたというわけだ。
研究チームは、培養細胞実験および生化学実験により、SPIG1は細胞内で前駆体BDNFと同じ分泌顆粒内に存在すること、SPIG1は前駆体BDNFに高親和性で結合することを解明。また、神経細胞にBDNFをSPIG1と共に共発現させると、成熟体BDNFの発現が細胞内と細胞外で減少することから、SPIG1は前駆体BDNFから成熟体BDNFへのプロセシングを抑制することも明らかにした。つまり、ニワトリの網膜-視蓋投射系で認められたSPIG1遺伝子のノックダウンによる表現型は、視神経軸索内のBDNFのプロセシングが異常をきたし、成熟体BDNFが異常に多く分泌されるようになったためと考えられるという。
さらにマウスにおいても、SPIG1がBDNFのプロセシングの調節に関わっている証拠が見出された。マウスの海馬の「錐体細胞」において、成熟体BDNFは神経スパインの数を増加させることが報告されている。そこで、SPIG1遺伝子欠損マウスの海馬におけるスパインの数を解析したところ、予想通り、野生型と較べて有意に増加していることが判明した。
SPIG1遺伝子欠損マウスにおいては、野生型マウスに較べて前駆体BDNFの発現量が減少し、成熟体BDNFの発現量が増加していることが確認されている。また、それに伴いBDNFの受容体「TrkB」の活性化(リン酸化レベル)が亢進しており、その結果、スパインの数が増加したと考えられるとしている(画像5~7)。
今回の研究により、不明な点が多く残されている脊椎動物における領域特異的神経結合形成のメカニズムおよびスパイン形成のメカニズムの一端が明らかになった(画像8・9)。BDNFの分泌異常は、統合失調症、うつ病など、さまざまな精神・神経疾患との関連性から、注目されている。そして、脳内においてBDNFが適切に働く上で、SPIG1がそのプロセシングにおいて重要な調節を行っていることも明らかになった形だ。