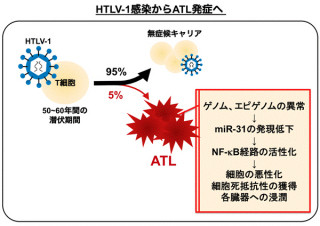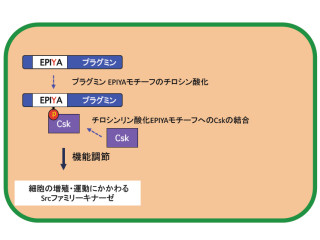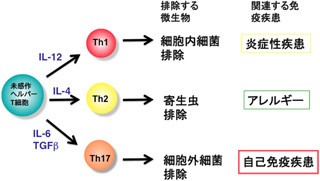科学技術振興機構(JST)と東京大学は3月14日、モデルと実験を用いた解析によって、「シグナル伝達分子」の分解や不活性化などの「負の制御機構」が、抗がん剤などの薬剤の濃度と、これに対する細胞の応答の強さとの関係を表す「感受性」の変化を制御していることを発見したと共同で発表した。
成果は、東大大学院理学系研究科の黒田真也教授らの研究グループによるもの。本研究は、JST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「生命システムの動作原理と基盤技術」研究領域における研究課題「シグナル伝達機構の情報コーディング」の一環として行われ、詳細な研究内容は、英国時間3月13日発行の英科学誌「Nature Communications」に掲載された。
細胞外のホルモンや成長因子、栄養などの環境変化の情報は受容体などを介して細胞内に伝わっていき、最終的に細胞の応答を導く。そうした情報を細胞内に伝える経路はシグナル伝達経路と呼ばれ、一般に多数の分子からなる連鎖的な生化学反応によって構成されている。
シグナル伝達経路は多数の分子(シグナル分子)の連鎖的な生化学反応によって構成され、上流分子による下流分子の活性化を通じて、情報を下流へ伝えている仕組みだ。
ある刺激に対して特定の分子が応答する時、分子の活性化時間パターンの最大値(ピーク強度)は応答の強さの指標としてよく用いられる(画像1・上)。また、一般的に刺激が強いほどシグナル分子の応答も強くなると考えられており、最大応答の50%の応答を引き起こす刺激濃度は、その分子の感受性の指標となる形だ(画像1・下)。この濃度が小さいことは、より微量の刺激で十分な応答が起きることを意味するので、その分子は刺激感受性が高いといえる。
また、シグナル伝達経路の阻害剤は抗がん剤などとして利用されており、阻害剤に対するシグナル分子の感受性は阻害剤の効果の指標の1つだ。つまり、感受性が強いほど阻害剤が効果的であることを意味している。しかしこの感受性がどのような仕組みによって決定されているかは不明だった。
さらに、多くの生化学反応は「逐次一次反応」という基本的構成要素を含んでおり、逐次一次反応の持つ特性が、多くの生化学反応に当てはまることが期待されている。なお逐次一次反応とは、経路の下流分子が上流分子の量に従って活性化(合成)され、自分自身の量に従って不活性化(分解)されるという、連続した2つの一次反応からなる生化学反応の基本的枠組みのことだ。
黒田教授らは2010年に先行研究「細胞内シグナル伝達経路の信号処理特性を解明-薬剤が意図したものと逆の応答を引き起こし得るメカニズムを解明-」を発表したが、今回の研究はその後続に当たる。
その先行研究において、逐次一次反応を介して信号が伝達される時、上流分子のピーク強度が同じ場合でも、上流分子の時間パターンによってピーク強度の伝達効率が異なるために、下流分子のピーク強度が変化するという現象が見出された具合だ(画像2)。
つまり、上流の信号が強いほど下流分子も強く応答するという、従来信じられていた暗黙的な概念が間違っていることがわかったのだ。ただし、上流分子の時間パターンとピーク強度の伝達効率の定量的な関係や、その関係の一般性については不明のままだった。
刺激濃度を変えると上流分子の時間パターンが変わる場合には、下流分子へのピーク強度の伝達効率も刺激濃度に応じて変化し、上流分子と下流分子とで感受性に違いが生じる可能性がある。
そこで黒田教授らは、まず上流分子の時間パターンや逐次一次反応の特性とピーク強度の伝達効率との定量的な関係を詳しく調べることにした。次に、この定量的な関係に対する刺激濃度の影響を調べることで、刺激感受性の変化やその仕組みを明らかにすることを目指したのである。さらに、刺激の代わりに阻害剤を用いて、阻害剤感受性の変化についての調査も行ったというわけだ。
まず、逐次一次反応を含むシグナル伝達経路の簡単な数理モデルが作成され、シミュレーションが行われた。その結果、上流信号の時間パターンの「時定数」が経路の時定数より小さい時、ピーク強度の伝達効率が減衰することが見出され、その関係式を導いた(画像3の実線)。
時定数とは特徴的な時間のスケールのことで、上流信号の時定数はここでは一過的な信号の時間幅を指す。シグナル伝達経路の時定数は、経路下流の分子が追従できる上流分子の時間変化の早さの上限に相当する。経路の時定数より早く変化する信号に対して、経路の下流分子は十分に追随できず、信号がうまく伝わらなくなるというわけだ。
なお、経路の時定数は経路の負の制御の強さによって決まるため、経路の負の制御がピーク強度の伝達効率に影響していることが判明している。ちなみに負の制御とは、シグナル伝達分子を分解したり、不活性化したりする反応のことだ。シグナル伝達分子の合成や活性化(アクセル)とは逆に、信号を抑制するブレーキの役割を果たす。
シグナル伝達分子は上流分子により活性化されることで信号を下流へと伝えていくが、正しい信号伝達のためには、負の制御によりシグナル伝達分子を適切に不活性化して、信号強度を適切な範囲に調節することが必要だ。
実際、負の制御に関わる遺伝子が欠けると、細胞ががん化しやすくなることが知られている。また、負の制御が弱いほど経路の時定数が大きくなるので、上流分子の早い変化に対して下流分子が十分追随できなくなり、信号がうまく伝わらなくなってしまうというわけだ。
この減衰特性の理論的予測を実証するため、複数種類の培養細胞に対し、刺激をさまざまな濃度で投与して、多数のシグナル伝達経路の分子の活性化の時間パターンが測定された。
これらの実験データから、測定した110経路のうち49経路では逐次一次反応の特性が強く表れていることが確認されたのである。さらに、これらの経路では伝達効率の実測値と理論値が一致していた(画像3)。
このようにして、減衰特性の実証と共に、この減衰特性が細胞の種類や刺激の種類によらず、多くのシグナル伝達経路で生じていること、つまり一般性を示すことができたというわけである。
そして、刺激濃度を変えたシミュレーションの結果、刺激濃度が高くなると上流信号の時間パターンの時定数が小さくなり、ピーク強度の伝達効率が減衰することもわかった。
つまり、上流分子が最大応答を示すような高い刺激濃度の時よりも、50%の応答を示す刺激濃度の時の方が伝達効率は高くなっていたのである(画像4・中)。その結果、上流分子が50%の応答を示す刺激濃度でも、下流分子は50%以上の応答を示し、下流分子が50%の応答を示す刺激濃度(画像4・下の青点)は上流分子が50%の応答を示す刺激濃度(赤点)よりも低くなって、感受性が向上した。

|
|
画像4。(上)刺激濃度に対する上流分子の応答(実線)と最大の50%の応答を示す刺激濃度(点線)。(中)刺激濃度が高いほど信号の伝達効率は低下する。(下)下流分子の応答は上流分子の応答と伝達効率のかけ算で表されるため、下流分子が50%の応答を示す刺激濃度(青点線)は小さくなる。このように伝達効率の変化のため下流分子の刺激感受性が向上する |
またシグナル伝達経路の負の制御(逐次一次反応の分解反応)が弱いほど経路の時定数が大きくなるため、伝達効率の減衰が強まり、刺激感受性の向上の度合いが強くなることが判明。
シグナル伝達経路は最終的に遺伝子発現へつながるが、遺伝子発現過程では逐次一次反応の特性が強く表れる場合が多いことや、シグナル伝達経路と比べて負の制御が弱いことから、細胞は遺伝子発現の過程を介することで自身の刺激感受性を向上させている可能性が示唆されたのである。
このメカニズムが抗がん剤などの感受性に対してどのように作用し得るかを明らかにするために、上記の数理モデルに阻害剤の効果を組み込んでのシミュレーションも行われた。
すると、刺激濃度を変えた時とは逆に、阻害剤濃度が低いほど、上流信号の時間パターンの時定数が小さくなったのである。その結果、ピーク強度の伝達効率の減衰のため、阻害剤感受性は経路の下流で低下することが判明した(画像5)。つまり、阻害剤が下流分子ほど効きづらくなるというわけだ。
またシグナル伝達経路の負の制御が弱いほど感受性の変化の度合いが強くなることや、不可逆的阻害剤を用いると感受性が低下しないことも確認された。
この阻害剤感受性の低下を実証するため、細胞のがん化に関与する「Akt経路」に注目した。Akt経路は、成長因子「EGF」を受けて活性化する。EGF受容体からシグナル伝達分子「Akt」を介して、S6という分子まで信号が伝わる仕組みだ。ちなみに、EGF受容体に対する阻害剤は抗がん剤としても用いられており、実験ではこの阻害剤を培養細胞「PC12」に与え、AktとS6の活性化の様子を測定した。
その結果、Aktの下流分子に当たるS6では、Aktよりも阻害剤感受性が低くなってたのである(画像6)。つまり、実際に阻害剤が下流分子ほど効きづらくなることが明らかになったというわけだ。こうして、実際の細胞内でも阻害剤感受性の低下が生じていることが実証されたのである。
今回の研究により、シグナル伝達経路の負の制御(画像7・上)が、ピーク強度の伝達効率の減衰(画像7・中)を介して、刺激や阻害剤に対する感受性を制御する(画像7・下)ことが判明した。この刺激感受性や阻害剤感受性を決める基本的な仕組みを考慮することで、薬剤に対する感受性をより正確に予測することが可能になると考えられると、黒田教授らはコメントしている。

|
|
画像7。(上)シグナル伝達経路の概要。下流分子の分解や不活性化の反応は経路の負の制御に相当する。(中)信号伝達効率は、上流分子の活性化の時間幅が小さいほど減衰していく。この傾向は、経路の負の制御が弱いほど強まる。(下)経路の負の制御は、信号伝達効率の減衰を介して刺激や阻害剤に対する感受性を制御する仕組みだ |
また、阻害剤の効果は下流へ行くほど弱まることも明らかとなった。新しい抗がん剤を開発する際には、シグナル伝達の最も上流に当たる受容体に対する阻害剤が候補となることが多いが、今回の結果から、そうした阻害剤は本質的には細胞の応答を効率よく阻害できない可能性があることを示唆している。
さらに、今回の結果によって、標的分子に一度結合するとほとんど離れないような不可逆性の強い阻害剤を用いることで、下流における阻害剤感受性の減弱を抑止できる可能性も示唆された。以上のことを踏まえ、黒田教授らは今回の成果は薬剤開発などの分野における活用が期待できるものと述べている。
そして、本研究により、遺伝子発現の過程を介することで細胞は刺激に対する自身の感受性を増強している可能性が示唆された。また、負の制御の強さはタンパク質分解酵素などの負の調節因子の活性・発現量を反映すると考えられるので、細胞はこのような分子の活性調節を介して、刺激や阻害剤に対する自身の感受性を制御できる可能性があるという。黒田教授らは、これらの知見は今後の研究で検証される必要があるとした。