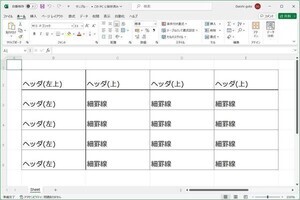IBMは8月17日(現地時間)、DNAの自己組織化を活用して配線プロセスを実現する半導体技術を開発していることを明らかにした。IBMと米カリフォルニア工科大学の共同研究により実現されたもので、22nmプロセス以降のパターン形成を高額な露光装置を用いずに実現する可能性が出てきた。
同技術は、長い一本鎖DNAと短いDNAを混ぜ合わすことで複雑な形状を自己組織化させる「DNA origami」と呼ばれる技術を応用したもので、既存の半導体製造装置を用いて実現可能としており、IBMでは電子ビーム(EB)による描画もしくは通常の露光装置技術として用いられる光リソグラフィ技術を用いて要求される大きさと形状のDNA origamiの構造を実現したとしている。
百万本単位で接合されたカーボンナノチューブを含んで自己組織化したDNA分子を足場として活用することで、、カーボンナノチューブやナノワイヤ、ナノ粒子を含んだ微細な回路基板を構築することが可能であり、IBMではこれにより、より大きな構造と結合可能な機能素子の実現に向けた可能性が出てきたとする。
また、テンプレートの素材および埋め込む際の条件を解明したことで、DNA origamiを構成する部分以外に余分に構築されることがないとするほか、相補的塩基対形成を活用することでDNAを要求した2次元形状として折り重ねることができ、短い部分の素子構造は6nm程度にすることができるとしている。
なお、IBMのScience&TechnologyマネージャのSpike Narayan氏は、同技術に関して、「ムーアの法則実現のためのプロセス微細化は、開発費が膨大な額となっているが、今回のこの技術を用いることで、配線プロセスの低コスト化が可能になる可能性がある」とコメントを述べている。