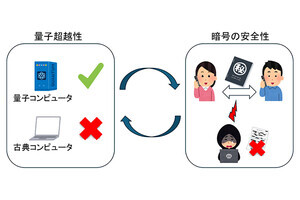安全で、充放電による劣化がほとんどない薄膜バッテリー
(2)のデモンストレーションは、将来のモバイル機器用バッテリー技術として注目を浴びている、薄膜型全固体電池の応用例である。薄膜型全固体電池で温度センサーと無線通信モジュール(ZigBeeモジュール)を動かし、温度センサーの測定値を無線で送信して見せた。
現在のスマートフォンやタブレットなどに使われているリチウムイオン電池は、「電解液」と呼ぶ液体を内蔵している。リチウムイオン電池は充放電を繰り返すと充電容量が低下するといった劣化の問題や、曲げたり衝撃を与えたりすると電解液が漏れだして発火する恐れがあるといった問題を抱えている。
これに対して全固体電池は電解液の代わりに電解質の固体を使うため、充放電の繰り返しによる劣化がほとんどなく、電解液が漏れだす心配がないという特長を備える。他にも、薄膜型の全固体電池は折り曲げられるという特徴も有している。
そこで展示ブースでは、試作した薄膜バッテリーを減圧下に置いてもふつうに動作することを示した。電解液を使用した一般的なリチウムイオン電池だと、電解液が漏れ出して事故に至る恐れがある。全固体電池である薄膜バッテリーでは、そのような恐れがないことを実際に見せていた。

|
左は薄膜バッテリー(赤色のワニ口クリップで挟んでいるサンプル)と温度センサー、無線モジュールを格納して真空ポンプで減圧する容器。右は無線モジュールの信号をUSBモジュールで受信して表示するノートパソコン |
高価な磁気シールドなしで生体の磁気を捉える
(3)のデモンストレーションは、生体が発生する微弱な磁気を、超高感度の磁気センサーであるトンネル磁気抵抗素子(TMR)で簡便に測定できることを示した。脈波が動いたときに発生する微弱な磁気を捉えて見せた。
生体が細胞レベルで活動することによって、微弱な磁気を発生することは古くから知られている。この生体磁場を測定することでヘルスケアや医療などに応用することが期待されてきた。ただし、生体が発生する磁気は非常に弱く、測定には超高感度の磁気センサーを必要とする。
現在のところ、生体磁場を実用的に測定できる磁気センサーは、超伝導を利用した「SQUID(スクイド)」と呼ぶセンサーだけである。SQUID磁気センサーは超伝導状態を維持するために、極低温の環境下に置く必要がある。そのため、極低温に冷却するためには高価な液体ヘリウムを使わなければならない。
また、地球が発生する磁場(地磁気)や環境に存在する磁気(電気鉄道の送電線や電子機器などが発生する磁気)などは生体の発生する磁場よりもはるかに強いので、高価な磁気シールドによってこれらの雑音となる磁気を遮蔽してから、SQUID磁気センサーによって生体磁場を測定するのが一般的である。
一方、トンネル磁気抵抗素子(TMR)を磁気センサーに使った測定は、室温で実行できるため冷却の必要がない。したがって、高価な液体ヘリウムが不要になる。また、生体と磁気センサーをぎりぎりまで近づけることができるので、高価な磁気シールドを使わなくても微弱な生体磁場の測定が可能になる。このように将来が非常に有望な磁気センサーなのだ。
なおこのデモンストレーションは、東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻の安藤研究室と、東北大学発のベンチャー企業であるラディックスの協力によって実施された。またトンネル磁気抵抗素子の作製には、アルバックの製造装置が採用されている。
温度変化によって抵抗値が大きく変わる機能性材料
(4)のデモンストレーションは、アルバックが得意とする機能性材料に関するものである。機能性材料である酸化バナジウム(VO2)の薄膜をホットプレートに置き、加熱する。酸化バナジウムは、室温では比較的高い抵抗率を示しているが、加熱していくと80℃近辺で抵抗率がおよそ4桁も下がる。
温度の変化によって抵抗率が大きく変化する性質を利用して、赤外線カメラや温度スイッチなどの用途を開拓したいとする。
アルバックのテクノロジーが生み出すさまざまな可能性を少しはお分かりいただけただろうか。きっとIoTの未来が見えてくるはずだ。また同社のWebサイトでも、製品情報の詳細が載っているので一度ご覧になってみてはいかがだろうか。
アルバックのHPはこちら
https://www.ulvac.co.jp/
(マイナビニュース広告企画:提供 アルバック)
[PR]提供: