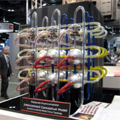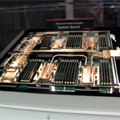2010年3月12日に東京大学の安田講堂で「計算科学技術と次世代スーパーコンピューティング基盤」フォーラムが開催された。このフォーラムではスーパーコンピュータ(スパコン)の事業仕分けの時に文部科学省(文科省)側で説明を行った一人である倉持大臣官房審議官、ジャーナリストで、東大大学院情報学環 特任教授、理化学研究所(理研)の次世代スーパーコンピュータ アドバイザリボードメンバーである立花隆氏が登壇してスパコンプロジェクトについて講演を行った。また、理研の横川氏および南氏、富士通の井上氏および堀田氏から次世代スパコンでのハード、ソフトの開発内容に関して説明が行われた。
事業仕分けの内幕
ご存じのように次世代スパコンは、2009年に実施された政府の事業仕分けで「廃止に近い縮減」と判定されたのであるが、その後、各界からのアピールを踏まえた大臣折衝で予算金額的には110億円の削減で推進が決まった。次世代スパコンの当初のターゲットは平成24年6月のTop500に10PFlopsを登録して世界一を取ることであったが、米国の対抗システムの開発状況からこれを平成23年11月に10PFlops達成に前倒しする必要があると判断され、この110億円は完成時期の前倒しの費用増分として積まれていたものであるという。
この費用を削減してしまったので10PFlopsの達成時期は元の平成24年6月となり、米国のプロジェクトがコケない限りLINPACKで世界一は難しくなったが、本当に問題となるのは実アプリの性能であり、こちらの開発を頑張って世界トップクラスの性能を実現すれば良いという考え方である。
そして、従来は供給者側の視点で開発を行っていたものを利用者側の視点で見直し、多様なユーザニーズに応える革新的ハイパフォーマンス コンピューティング インフラストラクチャ(HPCI)を構築すると説明されたが、富士通が作るシステムは変わっていないようであり、また、どういう点が革新的であるのかは今回の講演からはよく分からなかった。
立花氏は、アドバイザリボードのメンバーとして当初から理研の次世代スパコンの開発にかかわっており、決定の内幕や事業仕分けについて興味深い話を聞くことができた。次世代スパコンは当初の富士通案は単独で10PFlopsを達成出来る案で、理研内部では富士通単独案でほとんど決まりかけたのであるが、立花氏も知らない事情で急転してNEC、日立を加えたオールジャパン3社体制でスカラ、ベクトル複合システムに決まった。しかし、予算は増やせないので、2種類のシステムを開発するための増加分の費用はメーカー各社の持ち出しとなったとのことである。しかし、金融危機に伴い経営が悪化したNEC、日立が撤退して、もとの形に戻ったという。
また、事業仕分けに関しては、議員はスパコンを知らず、民間議員もスパコンを使ったことのある人は2人だけで、それも主流の人ではないという。その非主流の人が自分の説を主張して議論を引っ掻き廻した。立花氏は、小泉政権の科学創造立国という旗で科学技術予算が聖域化していたが、これに手を突っ込みたいという財務省のシナリオに政治家が乗ったという見方である。そして、「科学技術費削減 亡国の道」と題する同氏が読売新聞に書いた論説を示した。