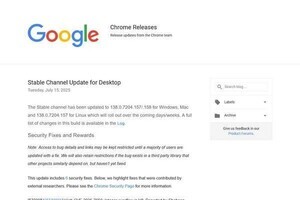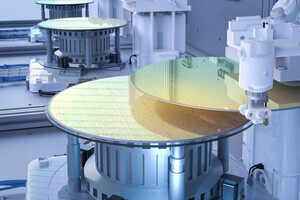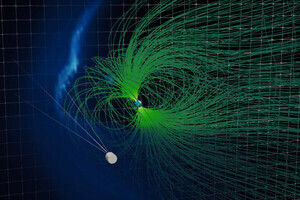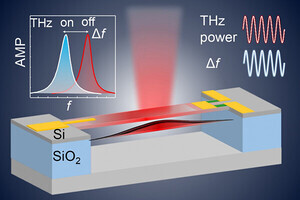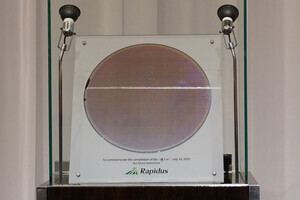電通国際情報サービス(ISID)とシビラは8月9日、電通と共に、教育分野においてブロックチェーン技術とDAOプロトコルを活用してコミュニティの可視化と長期的な関係維持を実現する共同プロジェクトを開始すると発表した。8月10日から岡山県で、8月17日に広島県でそれぞれ1泊2日で開催するサマースクールにおいて実施するもので、対象は小学4年生以上から中学3年生までの子ども35人とその家族。
DAOとはDecentralized Autonomous Organizationの略であり、自律分散型組織を指す。
今回のプロジェクトでは、落合陽一氏のSDGs(持続可能な開発目標)サマースクールにおいて、受講履歴を証明するトークンを配布することで、従来の学歴では捕捉できない生徒と講師の関係性をブロックチェーン技術で可視化すると共に、イベント参加者が将来にわたって繋がり合える環境を提供し、その検証を行う。
同スクールは、課題解決型の人材育成を目指してSDGsをテーマに開催するもの。 参加する小・中学生が社会の課題認識を共有し大局的な視野で人生の目標を定め、キャリアを歩むことを期待しているという。
そのような社会的に意義のある人生を歩む生徒たちに対して、進学先やキャリア形成の違いを超えて繋がり合えるDAOプロトコルを利用したチャット空間を提供することで、彼らが社会課題の解決に向けた相互協力の場として活用できる仕組みを実現するとしている。
国や企業などの中央管理者を置かず、スマートコントラクトやデジタルアセットなどを利用して組織が自律的に運営するDAOの概念は、ブロックチェーン技術の進展により多様な領域に応用できる可能性が広がっているという。
これを教育の領域に応用することにより、「どの研究者から教えを受けたか」「いつ、どんな仲間と、何を学んだか」といった多様な学びの軌跡を、中央管理者無しに耐改竄性を備えた情報として可視化できるとしている。
さらに、こうした学びの場を共有した者同士が、相互に信頼しうる形でコミュニティを形成し、将来にわたり繋がり合うことも可能になるという。
今回の実証実験に電通が加わることで、任意のテーマでコミュニティを組成するインセンティブ設計について検討を行い、そこに参加して講師や他の受講生と会話できる仕組みにサステナブル性を担保するためのコミュニケーションデザインを担うという。
ISIDとシビラは情報技術面からの検証を担い、教育の領域におけるDAOプロトコルの受容性を評価するとのこと。