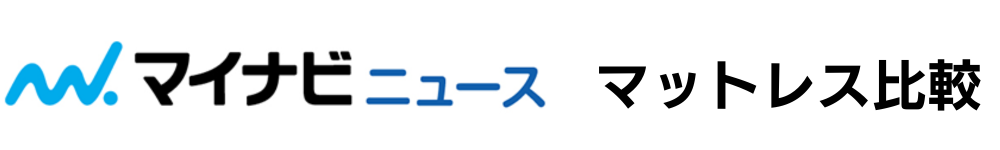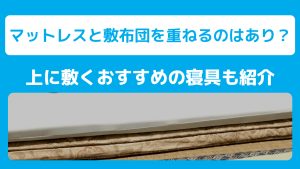手軽に使える寝具として有名な敷布団。
敷布団は素材によって様々な寝心地や特徴を見せる寝具です。
素材はどんな種類があるの?
敷布団を衛生的に使う方法を知りたい!
本記事では敷布団の素材の種類やフローリングで寝る際のおすすめの方法を紹介します。
素材を変えるだけで今まで体験できなかった寝心地を体験することが可能です。
敷布団の新たな表情を発見したい方はぜひ参考にしてみてください。
敷布団の素材の種類と特徴

本項目では敷布団の種類と特徴について紹介します。
敷布団には綿や洋毛、ウレタンやポリエステルなど、さまざまな種類があり、素材ごとに特徴が異なります。
敷布団の素材に注目することで、理想的な寝心地や扱いが楽な敷布団に出会える可能性があるでしょう。
敷布団の素材に注目したい方は、本項目をぜひ参考にしてみてください。
綿(コットン)
綿(コットン)といえば天然繊維素材の代表です。
普段着ているTシャツなどに採用されていることの多い素材です。
そんな馴染み深い素材であるコットンは敷布団として使用すると、どのような特徴があるか見ていきましょう。
コットンは繊維の先端が丸みを帯びているため、柔らかくチクチクしない肌触りが特徴です。
ちょっとした繊維の質感で肌荒れを起こしやすい方でも比較的安心して使用できます。
また洗濯も可能なので、衛生的に使用することも可能です。
一般的な成人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われています。
そのため敷布団が洗濯可能かどうかは衛生的に使用する上でとても重要です。
一方でコットンはへたりやすく、使用と共に寝心地が変化する場合がある点に注意が必要です。
購入時の寝心地を気に入って購入する場合は、使用と共に違和感を感じる可能性もあります。
またコットンTシャツをイメージすると分かりやすいと思いますが、シワになりやすいことも特徴です。
日頃のベッドメイキングや収納の際にはきちんと畳むなどのお手入れが必要となります。
羊毛(ウール)
羊毛(ウール)は保温性の高い天然素材です。
ウールは冬場に活躍するニットにも使用されることが多いことからも、保温性の高さが伺えます。
そんなウール素材の敷布団にはどのような特徴があるのか見ていきましょう。
ウール素材はニットやコートに使用されていることからも分かるように、非常に保温性が高いことが特徴です。
冬場に活躍することはもちろん、適度な吸湿性もあるため夏場でもある程度快適に寝ることも可能です。
またシワになりにくいため、普段のベッドメイキングが苦手な方でも綺麗な状態を保つことが可能です。
ウールは汗や皮脂の匂いを消臭する天然の消臭効果がある点が特徴です。
軽く水に濡らしたタオルで叩くだけで消臭効果が戻るため、快適な睡眠環境を整えることが可能です。
しかし、ウール素材は水洗いが不可であることが多いです。
軽い汚れであれば水に濡らしたタオルで叩くなどの対処で十分ですが、ひどい汚れの場合はクリーンングが必須となります。
また毛玉ができやすいので、見た目には注意を払う必要があるでしょう。
虫食いが起きやすいというデメリットもあるため、シーズン終わりにクリーニングを行うことは必須です。
ウレタン
ウレタンは柔軟性や伸縮性に優れているため様々な製品に使用されている合成樹脂です。
敷布団だけでなく、クッションや靴底など使われている商品は多岐にわたります。
ウレタンにはどのような特徴があるのか見ていきましょう。
ウレタンは身体の形状にフットしながら沈み込みため、腰痛に悩んでいる方におすすめです。
寝返りも打ちやすいため、腰にストレスをかけることなく睡眠をとることが可能です。
また耐久性も高いため、きちんとお手入れを行えば長い期間使用することができるでしょう。
ウレタンは硬さの選択肢が非常に多いことも特徴です。
ウレタン素材を選べばあなた好みの硬さの素材にきっと出会えるでしょう。
一方で低反発ウレタンの場合、通気性が悪く夏場には寝苦しいと感じる可能性があります。
また通気性が悪いとカビやダニなどの原因となるため、日々のお手入れが重要になります。
高反発ウレタンの場合は硬いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
元々柔らかめの寝心地が好みの方は避けた方がいいでしょう。
ポリエステル・ポリエステル綿
ポリエステルは最も馴染み深い合成繊維の1つです。
敷布団だけでなく、衣料品やペットボトルなどにも使用されているため私たちがほぼ毎日触れている素材と言ってもいいでしょう。
そんなポリエステルを使用した敷布団にはどのような特徴があるのか見ていきましょう。
ポリエステルは軽量であるため、普段から敷布団を収納する方にとっては非常に扱いやすいことが特徴です。
また水洗いが可能で、洗濯後もシワになりにくいためお手入れも簡単に行えます。
耐久性も十分あるため、日頃からお手入れを欠かさなければかなり長い期間使用することが可能です。
敷布団の寿命は日ごろのお手入れによって変化します。
しっかりとお手入れをすることで長く使用できるため、お手入れのしやすさは重要です。
一方で通気性はあまり良くないので、寝苦しさを感じる場合もあります。
また静電気が発生しやすいため、起床時に髪の毛が乱れてしまう可能性もあるでしょう。
【機能別】敷布団の種類の選び方

敷布団には様々な素材や機能があり、製品も多数展開されています。
本項目では【機能別】敷布団の種類の選び方を紹介します。
敷布団は種類が多すぎて、どれを選んでいいのか分からない!
このような方は本項目を参考にしてみてください。
あなたが敷布団に最も求める要素によって選ぶべき素材や機能は変わってきます。
敷布団選びに悩んでいる方は本項目をぜひ参考にしてみてください。
【吸放湿性重視】羊毛素材・吸汗速乾機能付き
吸放湿性重視の方は羊毛素材・吸汗速乾機能機能付きの敷布団がおすすめです。
ウールは湿気を吸収することが優れているだけでなく、湿気を蒸発しやすいため蒸れにくいことが特徴です。
暖かさを連想されやすいウールですが、単に温かいだけでなく蒸れにくいため通年で快適な寝心地を叶えていくれます。
また消臭効果もあるため、においが気になりにくいという特徴もあります。
一方で水洗いが不可であるため、お手入れが大変というデメリットがあります。
虫食いの可能性も高いため、定期的なクリーニングは欠かせません。
また寝具の蒸れの原因の多くは汗です。
そのため吸汗速乾機能付きの敷布団を使うことで、蒸れを感じにく睡眠環境が手に入るでしょう。
また汗をすぐに乾かすことで衛生的に使用することも可能です。
【寝心地重視】体圧分散機能付き
寝心地を重視する方は体圧分散機能付きの敷布団がおすすめです。
体圧分散性とは、身体にかかる圧力を分散させる性質のことを指します。
体圧が分散されないと、身体の一部分に圧力が集中してしまい以下のような問題が発生することがあります。
- 腰痛の悪化
- 肩こりや起床時の筋肉のハリ
- 床ずれ
腰痛や肩こりに悩まされている方は、体圧分散性の高い敷布団を選ぶと良いでしょう。
敷布団はマットレスと比較して薄いため、体圧分散性の低いものが多く存在します。
そのため、マットレスと同等の寝心地を求める方は体圧分散性に注目してください。
腰痛や肩こりの改善には体圧分散性だけでなく、寝返りの打ちやすさも重要なポイントです。
寝返りの打ちやすさは硬さが重要なので、硬さにも注目すると良いでしょう。
【耐久性重視】固綿素材・ウレタン素材・厚み8㎝以上
耐久性を重視する方は固綿素材・ウレタン素材・厚み8㎝以上の敷布団がおすすめです。
固綿はポリエステルやウールに熱加工や樹脂加工を施した素材です。
一般的な綿素材はへたりやすく寝心地が変化しやすいですが、加工を施した固綿はへたりにくいことが特徴です。
綿素材の寝心地はそのままに耐久性も意識したい方におすすめです。
固綿は加工が施されているため、綿素材のように選択することはできません。
今まで綿素材を使用していた方はお手入れ方法が変わる点に注意が必要です。
またウレタン素材は他の素材と比較して耐久性が高いことが特徴です。
さらに軽量であるため、日頃のお手入れもしやすく非常に長持ちしやすい素材といえます。
しかし低反発ウレタンは通気性が悪いので、湿気対策は必須となります。
ウレタンには低反発と高反発が存在します。
寝心地が大きく変わるため、実際に寝心地を確認してから購入することをお勧めします。
また耐久性を求める場合は厚みにも注目しましょう。
薄い素材は使い続けるうちにへたってしまい今までとは異なる寝心地になる場合があります。
耐久性を求める場合は8cm以上を1つの目安として購入すると良いでしょう。
【衛生面重視】抗菌防臭機能付き・防ダニ機能付き・洗濯可能
衛生面を重視する方は抗菌防臭機能付き・防ダニ機能付き・洗濯可能の敷布団がおすすめです。
寝具は毎日使用するため、細菌やニオイが気になることの多いアイテムです。
最近は抗菌防臭機能付きの敷布団が増えているため、基本的にはこの機能がついた敷布団をおすすめします。
日頃のお手入れを楽にしたい方は消臭スプレーを検討してみてください。
最近は抗菌機能つきの消臭スプレーも販売されているため、日常的なお手入れとして有効です。
また防ダニ機能も衛生面を重視する場合には欠かせません。
特にダニは一度発生してしまうと、対処が難しいため発生させないことが何よりも大切です。
敷布団はダニ本体だけでなく、ダニの糞や死骸などのアレルゲンと触れる機会が多いため、防ダニ機能付きの敷布団を選ぶと安心です。
ダニの発生原因として湿気が多いことも挙げられます。
防ダニ加工がされていても、湿気対策は欠かさずに行いましょう。
敷布団を衛生的に保つ最も有効な方法の1つとして洗濯が挙げられます。
ニオイなどは消臭スプレーなどで対処できても、シミや汚れは選択で対応できない場合もあります。
そのため衛生面を最重視する方は選択可能な素材を選ぶと良いでしょう。
しかし洗濯可能な敷布団は限られているため、購入前の確認は忘れずに行いましょう。
フローリングに敷布団を敷いてもいい?

敷布団をフローリングに直接敷いている方もいると思いますが、敷布団は直接敷くのではなく下にマットなどを引くことをおすすめします。
もちろんフローリングに直接敷布団を敷くことは可能ですがいくつか注意点が存在します。
- 湿気が溜まりやすいため、定期的に畳む必要がある
- フローリングが傷つく可能性がある
- 底つき感を感じやすい
- 掃除がしにく
直接敷く場合はこれらの注意点が存在するため、使い勝手としては低下してしまいます。
快適な使用感を求める場合は、マットなどを下に敷いた方がおすすめです。
フローリングに敷布団を敷いて寝る際のおすすめの方法

敷布団を直接フローリングに敷くことのデメリットは理解できたと思いますが、具体的な対策を知ることも大切です。
本項目ではフローリングに敷布団を敷いて寝る際のおすすめの方法を紹介します。
今まで直接フローリングに敷いていた方は、お手入れの楽さや寝心地の違いを実感できるでしょう。
あなたの重視するポイントに合わせて、おすすめの方法を実践してみてください。
除湿シートを敷く
フローリングに敷布団を敷いて寝る際におすすめの方法1つ目は除湿シートを敷くことです。
除湿シートは敷くだけで、布団の中に籠る湿気を吸収するためダニやカビの対策になります。
敷布団は寝汗などで水分を多く吸収してしまい、湿気が溜まった状態になりやすいため除湿シートを用いることは非常に有効です。
除湿シートは使い続けると湿気や汗を吸収しきれずに不衛生な状態となってしまうので、定期的な手入れが必要です。
衛生的に使用したい方は吸湿センサーがあるものや使い捨てのものを選ぶと良いでしょう。
除湿シートは薄くて軽いものが多いため今回紹介する方法の中で最も気軽に行うことが可能です。
部屋のスペースが限られている方や手軽に湿気対策を行いたい方におすすめです。
一方で除湿シートは薄いものが多いため、寝心地の改善に関してはあまり効果がないと考えて良いでしょう。
寝心地の改善を期待する方は他の手段を考えると良いでしょう。
すのこやい草を活用する
フローリングに敷布団を敷いて寝る際におすすめの方法2つ目はすのこやい草を活用することです。
すのこは空気の通り道を確保することで、い草は調湿性によって湿気が籠ることを防ぐことが可能です。
それぞれカビやダニに対する手段としては有効といえます。
すのことい草はそれぞれどんな特徴があるの?
と疑問に感じた方もいらっしゃると思いますので、それぞれの特徴をまとめました。
まずはすのこのメリット・デメリットからみていきましょう。
すのこはい草と比較して硬めなので、底つき感を感じにくいことが特徴です。
敷布団の底つき感が気になるという方はすのこを使うと有効的です。
また木の香りを感じることができ、リラックスできるというメリットもあります。
一方で通気性の良さと熱伝導性の低さゆえに、寒い時期には底冷えを感じる可能性があります。
すのこは軽い素材であるため、ある程度の厚みがあっても簡単に扱うことが可能です。
折りたたみ式や並べるタイプも存在するので、あなたの住居スペースに合わせて選択することが可能です。
続いてい草のメリット・デメリットを見ていきましょう。
い草のメリットはサラサラとした手触りが挙げられます。
湿気の多い時期や汗をかきやすい夏場でもさらっとした感覚を味わうことが可能です。
また空気浄化作用があるため、寝室の空気を綺麗にする効果もあります。
一方で使い続けると変色することや薄いため底つき感の改善は期待できないことがデメリットとして挙げられます。
い草は使い続けるとささくれのように繊維が飛び出してしまうことがあります。
この状態を放置すると刺さってしまう可能性もあるため、カット処理をする必要があります。
布団の下にマットレスを敷く
フローリングに敷布団を敷いて寝る際におすすめの方法3つ目は布団の下にマットレスを敷くことです。
マットレスは敷布団よりも厚さと反発力があるため、寝心地を大きく改善することが可能です。
一言にマットレスと言ってもたくさんの種類が存在します。
あなたのこだわりに合ったマットレスを選ぶことが大切です。
マットレスのデメリットとしては重くてスペースを圧迫してしまうことが挙げられます。
もし部屋のスペースを確保する目的で敷布団を使用していた方は上記した2つの手段の方が向いています。
一方で部屋のスペースが十分ある方はベッドへの移行を検討してもいいかもしれません。
腰痛持ちの方やハウスダストによるアレルギーがある方はベッドの方がおすすめです。
ベッドにも敷布団にもメリット・デメリットが存在します。
それぞれの特徴を比較して、あなたのライフスタイルに合った方を選ぶことが大切です。
敷布団種類のよくある質問・Q&A
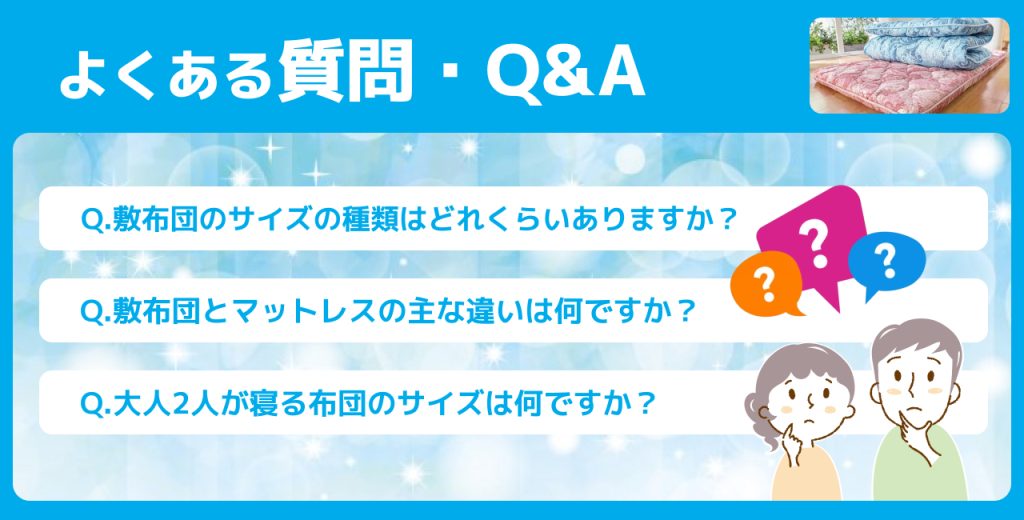
まとめ
本記事では敷布団の素材の種類やフローロングで寝るおすすめの方法を紹介しました。
敷布団はスペースの確保に有効的なだけでなく、素材や機能を適切に選ぶことでマットレスにも劣らない寝心地も発揮します。
現在、マットレスを使用している方も、敷布団の方が合っているライフスタイルの方もいらっしゃるかもしれません。
敷布団を検討している方は本記事をぜひ参考にしてみてください。