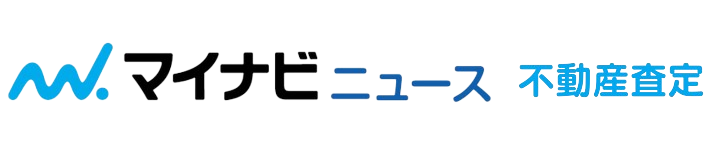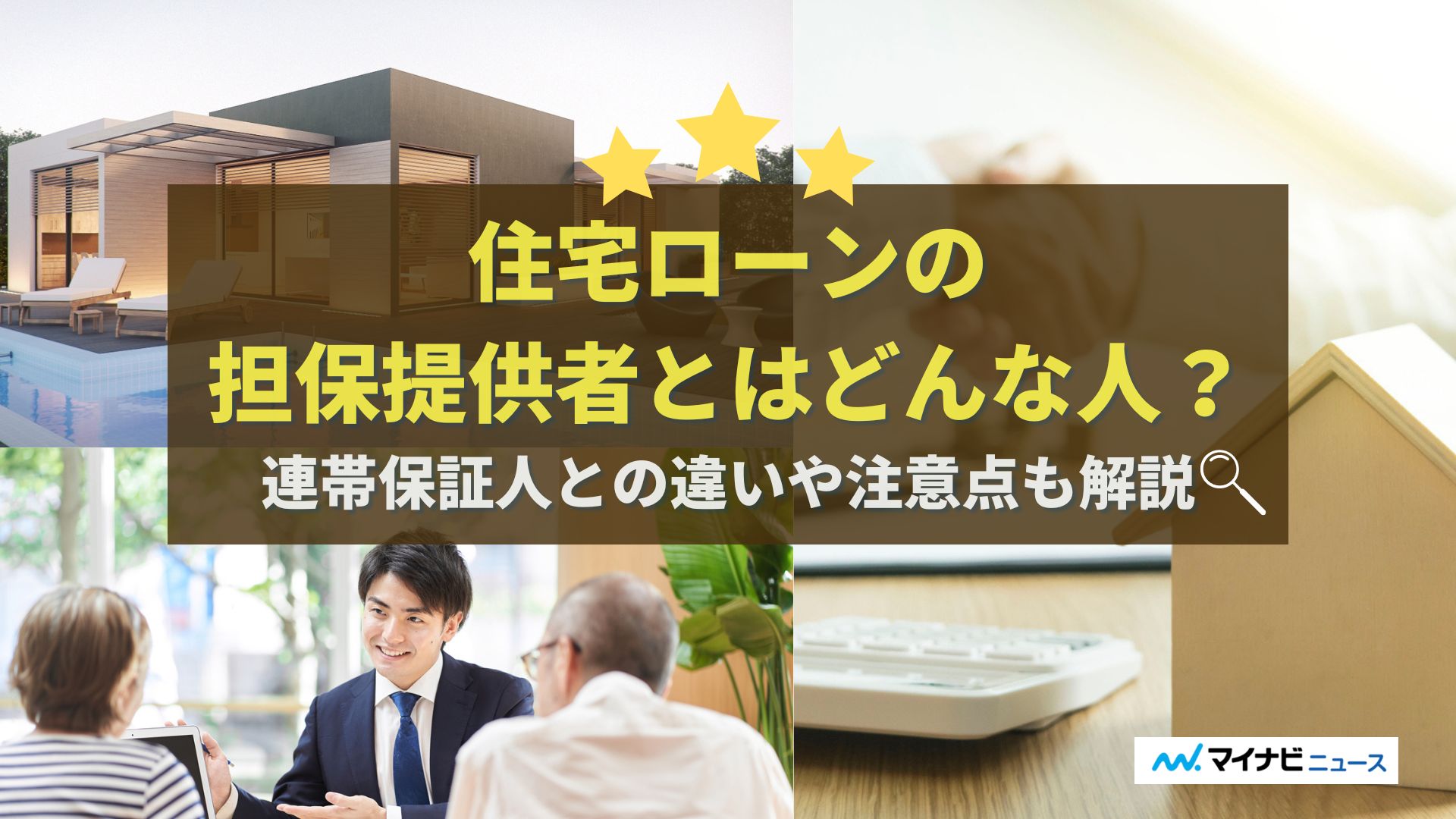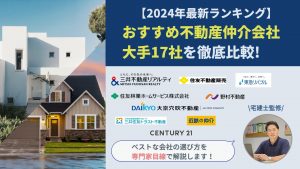住宅ローンを利用する際は、貸し倒しを避けるために金融機関は支払いの保証を設定します。担保提供者は保証の1つで、債務者のために担保を提供します。連帯保証人という言葉は聞き覚えがあっても、担保提供者はなじみがない人が多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、担保提供者とはどのような存在なのかや住宅ローンのために必要になるケース、連帯保証人との違いなどを解説します。
住宅ローンは、一度契約すると何十年も支払いが続きます。少しでも不安材料をなくすために、契約前の参考にしてください。
- 担保提供者とは、住宅ローンの返済が滞った際に、債務者の代わりに提供された担保を通じて金融機関の損害を補填する人のことです。直接の返済義務はなく、物上保証人とも呼ばれます。
- 担保提供者が求められる主なケースは、住宅ローンが夫婦共同名義である場合や、親が所有する土地に住宅を建てる場合、または担保として十分な資産がない場合などです。これらのケースでは、金融機関がリスク管理のために担保提供者を要求することがあるようです。
- 担保提供者の選定には注意が必要で、親族間での説明責任が重要です。金融機関も担保提供者への説明義務を負っており、候補者にはリスクが十分に理解されている必要があります。また、連帯保証人との違いとして、担保提供者は財産を提供するのみで返済義務は伴わない点が挙げられるでしょう。
- 家づくりの進め方のアドバイスや、自分に合う建築会社・不動産会社を紹介してもらえる
- 日本最大級の不動産・住宅情報サイトのLIFULL HOME’Sが運営。利用満足度99.5%(※)
- 住宅ローンや費用に関しても相談可能。ファイナンシャルプランナーの無料紹介も
理想の家づくり・住まい探しを、専門家に相談しながら進めていきましょう。
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
担保提供者に関する基礎知識

担保提供者とは、いったい何をする人なのでしょうか。誰かに頼む場合は、詳細を知って説明できるようになっていなければ相手は同意してくれません。そこで担保提供者の基礎知識として、求められるケースや誰がなれるのか、担保にできるものなどを解説していきます。
担保提供者とは何か
担保提供者とは、住宅ローンの債務者が返済できなくなった場合に、損害を担保として設定したものを差し出すことで補填してくれる人のことをいいます。物上保証人とも呼ばれ、その他のローンでも設定される場合があります。
担保提供者になった人は直接債務を負うことはありませんが、担保にしたものは住宅ローンの滞納で売却されてしまい、手元に戻ってきません。相手は債務者を信頼して担保を提供してくれているので、不慮の事情がない限りは計画通りに返済しましょう。
担保提供者を求められるケース
住宅ローンは保証料を支払い、滞納に備えて保証会社を設定することが一般的です。わざわざ担保提供者が必要なケースとは、どういったときなのでしょうか。
次の3つのケースで住宅ローンを申し込むと、担保提供者の設定を求められます。
| 担保提供者を求められるケース | 理由 |
| 住宅ローンが夫婦共同名義 | 住宅の一部を配偶者が所有して金融機関が住宅全てを売却できないため |
| 親が所有する土地に住宅を建てる | 担保としての価値が建物部分だけでは不足するため |
| 担保となるものを所有していない人が多額の住宅ローンを組む | 債務者の滞納に備えるため |
いずれのケースでも、金融機関がスムーズな融資の回収を行うために担保提供者を求めます。
担保提供者の範囲
担保提供者は誰にでも頼めるものではありませんが、債務者と次の間柄であれば金融機関は了承してくれます。
| 担保提供者の範囲 | 備考 |
| 配偶者 | 離婚しても担保提供者の責任は続く |
| 婚約者 | 住宅ローンの契約前に入籍が前提 |
| 両親 | 配偶者の両親は対象外になる場合がある |
| 子ども | 就労済みでも未成年は対象外になる場合がある |
| 兄弟・姉妹 | 兄弟・姉妹での同居などで使える |
| 同性のパートナー | 任意後見契約をして公正証書を作成済み |
担保提供者になれるのは債権者の親族が基本で、友人や知人などの第3者は同意を得られたとしても認めてもらえません。また金融機関によっては範囲が異なるため、確認してから候補となる人に相談しましょう。
担保として提供できるもの
提供してもらう担保は、融資を回収できるほど高額であれば何でもよいというわけではありません。金融機関が想定している担保は、主に以下のようなものです。
- 不動産の抵当権
- 債券や株式などの有価証券
- 普通預金・定期預金
- ゴルフ会員権
- 企業間の売掛債権
- 企業が所有する商品
住宅ローンでは何千万円もの融資を受けるため、現金化しやすく高額なものが対象になっています。
現実問題として、担保になるほど高額なものは不動産以外では厳しいかもしれません。企業勤めの人では売掛債権や商品は関係なく、有価証券などは手持ちの資金だけで購入することになります。
不動産だけは融資を受けて購入できるため、相談相手が所有している可能性もあるでしょう。
配偶者が担保提供者になるメリット
担保提供者になってもらうための相談は、いくら親族でもリスクを負わせることになるため気軽にはできません。配偶者の場合は、担保提供者にならないと住宅ローンを利用できない状況なので、納得してもらいやすいでしょう。
しかし、配偶者に担保提供者になってもらうメリットは基本的にありません。いくら債務を負わなくてよいとはいえ、得るものはないため他の親族に相談する場合でも信頼が重要です。
担保提供者に配偶者を設定しておけば、不動産を勝手に売却されることを防ぐことができます。しかしそのような状況は婚姻生活が破綻しかけているため、メリットとはいいにくいでしょう。
配偶者が担保提供者になるデメリット
担保提供者の配偶者は、債務者と共に担保にした不動産で暮らしていることが一般的です。
しかし返済が滞ると不動産の所有権を失い、競売にかけられたら新しい住まいを探さなければなりません。ただし滞納によって信用情報に傷が付き、新たに住宅ローンを組むことは難しいでしょう。
また担保提供者としての責任は離婚後も継続します。元配偶者が住宅に住んで債務者が出て行ったとしても、滞納が起きると抵当権がないため引っ越しが必要です。
担保提供者の審査について

担保提供者になってくれる人がいても、金融機関の審査を通過しないと住宅ローンの契約はできません。審査は返済能力を判断するためには当然のことですが、実は担保提供者も対象です。
ここでは、担保提供者に行われる審査の内容や提出する書類について紹介していきます。自身の住宅ローンのためにお願いする立場なので、相手に説明できるようになっておきましょう。
提供される担保の審査
金融機関が想定している担保を提供してもらっても、目標額の融資が受けられるかどうかは審査次第です。
滞納が続いたときに売却を想定しているため、現在の市場価値がそのまま担保の価値とはなりません。売却が容易で、数十年後でも価値がなくなりにくいものが高く評価されます。
例えば普通預金や定期預金は、預金額がそのまま価値となります。他の担保では、金融機関が設定した割合を掛けて現在の市場価値よりは低くなります。また有価証券は、倒産がない国債や未上場株式よりも上場株式の評価が高いです。
担保提供者も審査
担保提供者を設定して住宅ローンを契約する場合には、債務者自身だけでなく担保提供者も審査の対象になります。住宅ローンの契約の多くは、金融機関の店頭で関係者の合意のもとに書類を作成します。そのため、担保提供者は次の2点をクリアしなければなりません。
- 金融機関が定める担保提供者の年齢上限を超えないか
- 契約時に店頭まで来ることができるか
1つめの条件は、高齢だと認知症などで判断能力の衰えがあるため、年齢の上限を定めています。定年間際に、両親を担保提供者に設定して住宅ローンを組む場合などでは、あからじめ金融機関で年齢の上限を聞いておきましょう。
両親の判断力がしっかりしていても、遠方に住んでいてけがによる車椅子生活などで店頭に来られない場合は、審査に通らないことがあります。融資を受けられるだけの担保を提供してもらえるというだけで、安心してはいられないということです。
審査に必要な書類
住宅ローンを申し込むためには、次の書類を用意する必要があります。
| 書類名 | 入手先 |
| ローンの申込書 | 住宅ローンを組む金融機関 |
| 個人情報取扱いの同意書 | 住宅ローンを組む金融機関 |
| 本人確認書類(住民票や住民票記載事項証明書) | 担保提供者が暮らす地域の役場 |
不動産を担保として提供してもらう場合は次の書類も必要です。
| 書類名 | 入手先 |
| 提供する不動産の売買契約書 | 不動産会社 |
| 提供する不動産の重要事項説明書 | 不動産会社 |
| 提供する不動産の図面 | 不動産会社・建築会社 |
| 建築確認申請書(戸建ての場合) | 不動産会社・建築会社 |
| 建築確認済証・建築確認通知書(戸建ての場合) | 不動産会社・建築会社 |
担保提供者の本人確認書類は、発行から1ヶ月以内などの期間が設けられる場合があるため、過ぎてしまわないように注意しましょう。
また同性のパートナーを担保提供者にする場合は、任意後見契約や合意契約の公正証書も必要です。最寄りの公証役場で原本を入手しておいてください。
担保提供者と連帯保証人の違い

担保提供者よりも連帯保証人のほうが聞き覚えがあるという人は多いでしょう。どちらもリスクを負うという観点では共通ですが、返済義務や責任の範囲、住宅ローンの控除について次のような違いがあります。
| 返済義務 | 責任の範囲 | 住宅ローンの控除 | |
| 担保提供者 | なし | 担保の提供 | なし |
| 連帯保証人 | あり | 完済できるまで | なし |
ここで紹介する違いを把握して、自身の住宅ローンではどちらがよいのかを判断しましょう。
返済義務
担保提供者に返済義務はなく、債務者が住宅ローンの滞納を続けても担保を引き渡すだけです。よって担保は失ってしまいますが、それ以上の損失は起きません。
一方連帯保証人には返済義務があり、拒否したり債務者へ請求したりすることは不可能です。連帯保証人は、収入に余裕がなくギリギリの生活を送っていても、住宅ローンの残債を支払わなければなりません。
金融機関から住宅ローンを組む条件として、担保提供者か連帯保証人の設定を提示されたら、可能な限り担保提供者を選択したほうが、相手からの同意を得られやすくなります。
責任の範囲
担保提供者であれば、責任の範囲は担保の提出だけです。担保を売却したにもかかわらず住宅ローンが完済できない場合も、不足分を請求されることはありません。
連帯保証人の場合は、住宅ローンの完済まで支払いの責任を負うことになります。万が一、債務者が何かしらの事情で早期に滞納が発生してしまうと、何千万円もの負債がのしかかることになるでしょう。
身近に担保を持っている人がいなくても、気軽に連帯保証人を依頼することは危険です。他の金融機関での住宅ローンも調べて、連帯保証人なしでも契約できないか検討してください。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、借入金を使って毎年の所得税を減税できる制度です。担保提供者も連帯保証人も住宅ローンの契約書に名前を連ねますが、適用させるためには次の条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを使っている住宅に6ヶ月以上住んでいる
- 住宅の床面積の半分以上が居住用
- 築年数が20年以内(耐火建築なら25年以内)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 住宅は親族などから購入していない
- 住宅ローン減税を適用させる前年や前々年に、居住用財産を譲渡する際に使える特例を受けていない
担保提供者も連帯保証人も条件を満たさないため、住宅ローン控除は受けられません。特に連帯保証人は、返済を全て肩代わりして毎月支払っていても、節税にはつながらないというわけです。
担保提供者を選ぶときの注意点

担保提供者になってもらうということは、自身の住宅ローンに対してリスクを負わせてしまうことになります。金融機関が指定する範囲から適当に選び、ろくに説明もしていないでいると、滞納したときにトラブルが起きてしまうでしょう。どうにかして解決できても、担保提供者になってくれた人とは気まずい関係になります。
そのような事態を避けるためにも、次の3点に注意して担保提供者を選んでください。
- 担保提供者と連帯保証人を兼任する可能性
- 親に依頼する場合はリスクを説明する
- 金融機関には担保提供者への説明義務がある
担保提供者と連帯保証人を兼任する可能性
住宅ローンの滞納で担保を売却しても、融資額を回収しきれないことがあります。そこで未回収のリスクを避けるために、担保提供者に連帯保証人も兼任させる契約を迫られるかもしれません。
兼任した人は、担保を失うリスクと不足分を支払うリスクを両方背負うことになります。夫婦共同名義の住宅ローンなどで兼任を求められますが、もしものときには担保提供者のほうが損失はより大きいです。
兼任するかどうかは必ず契約書に明記されて、一度契約してしまえば勘違いしていたと言っても通じません。契約書は細部まできちんと確認するようにしましょう。
親に依頼する場合はリスクを説明
一緒に住むことになる配偶者には、他の人に依頼するよりも担保提供者になってもらいやすいでしょう。しかし親に依頼する場合は、リスクの説明をしっかりしておかなければ多大な迷惑をかける恐れがあります。
特に連帯保証人まで兼任してもらう場合は、返済の全責任を負う覚悟があるのかを確認しておきましょう。現在は収入が安定していても、数十年後はどうなっているかわかりませんし、もし災害で住宅を失ったり景気の悪化で収入が落ちたりしても、住宅ローンの返済は続きます。
リスクを隠して契約書へのサインを迫ることは避けてください。考えられる限りのリスクを具体的に説明して、同意を得るようにしましょう。
金融機関には担保提供者への説明義務
住宅ローンを初めて利用する債務者が、担保提供者へリスクの説明を行っても、十分にできているか不安になります。他に相手がいない状況で同意がもらえなければ、住宅ローンを組めずに困ってしまうでしょう。
しかし担保提供者への説明義務は金融機関も負っています。専門知識を持った担当にも説明してもらい、過不足なくリスクや責任の範囲を相手に自覚してもらってください。
担保提供者なしでも、債務者の年収や勤続年数などで住宅ローンが組める場合があります。いきなり担保提供者を求めてくる金融機関であれば、契約するのは注意したほうがよいでしょう。
担保提供者に関するQ&A

担保提供者の基礎知識について見てきましたが、実際に住宅ローンの手続きを始めると新たな疑問が浮かんできます。そこで、担保提供者を設定するときによくある疑問を詳しく解説していきます。
まとめ

住宅ローンを組むために担保提供者を設定するには、相手に責任やリスクを正確に説明する必要があります。滞納による担保回収が契約から数十年後に起きることもあり、完済するまで担保提供者になった人は安心できません。
連帯保証人にまでなってもらうと負わせるリスクが増えてしまうため、できるだけ避けてください。金融機関の助けも借りながら担保提供者に納得してもらい、住宅ローンの手続きを進めましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。