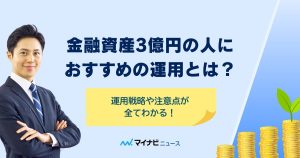- 手元にある1,000万円の運用方法に悩んでいる
- 資産運用のリスクが心配なため、安全な運用方法が知りたい
- 運用に失敗しないためのコツや注意点が知りたい
1,000万円の手元の資産を運用で増やしたいが、どんな運用方法があるのか、またリスクが低くリターンが大きい方法がわからない。
そんな悩みを抱えているなら、この記事はあなたの悩みを解決に導く、有力な手がかりになる。
資産運用にはリスクがつきものだが、可能な限り安全な運用方法を知りたいと思うのは、誰にも共通する思いだろう。
そこでこの記事では、資産運用に失敗しないためのコツや注意点を解説する。
手元の1,000万円の資産をうまく運用し、大きく育てる方法をお探しであればぜひご参考いただきたい。
手元の1,000万円を増やすには資産運用がおすすめ


手元の1,000万円を増やしたい場合、効果的な方法の一つが資産運用だ。
しかし資産運用に関して知識をお持ちの方なら、リスクを伴うことはご存知だろう。そしてリスクを回避したいと思うと、資産運用に一歩踏み出せない状態に陥りがちだ。
そこでまずは、手元の1,000万円を増やすために資産運用がおすすめな理由と、リスクを取ってでも資産運用を選ぶべき根拠について解説する。
銀行預金のみではリターンが得られない
これまでの日本では、たとえば1,000万円といったまとまった資金が手元にある場合は、銀行預金として預けるのが一般的であった。
しかし現代では、銀行に預ける方法ではお金を守りながら増やすことは難しい。その理由は、続く超低金利状態にある。
たとえば2025年7月時点で、1,000万円を三菱UFJ銀行のスーパー定期に10年預けた場合の利息は年利0.5%、
みずほ銀行でも利率は同じく年利0.5%だ。
2024年の3月に日本銀行が金利を引き上げし、日本の歴史的マイナス金利時代には終止符が打たれた。
短期金利のゼロから0.1%への引き上げは、これまでマイナス0.1%だった金利の引き上げにつながり、日本においては17年ぶりの利上げとなっている。
しかし日本銀行は2024年1月の声明文の中で、金融市場や日本経済への直接的な影響は小さいと述べた。実際マイナス金利時代は終焉を迎えても、超低金利の状態はいまだ続いている。
先に例に挙げた三菱UFJ銀行のスーパー定期に、手元の1,000万円を預けたと仮定しよう。
この場合10年後には、利息総額は500,273円になる。この数値は税金や手数料などを考慮していないため、実際の手取り額はこれより少なくなる。
また10年預けて50万円の利息とした場合、1ヶ月あたりの利息で計算すると4,100円程度だ。この金額では、生計を立てるのは難しい。不労所得としては不十分であろう。
インフレ対策としての資産運用
銀行預金のみではリターンが得られない理由の2つ目に、インフレによる実質的な目減りの可能性が挙げられる。
新聞やニュースなどでインフレという言葉をよく見かけるため、ご存知の方も多いだろう。
インフレとは、物やサービスの価格が上昇し、実質的なお金の価値が下がる状態だ。インフレになると、同じお金で買えるモノの量が減少する。
たとえば、物価が毎年2%ずつ上昇している状況を考えてみよう。
この場合、現在なら100万円で買えるモノは、5年後にはおよそ110万円出してようやく買える。
インフレの場合、現金で100万円を持っていても、5年後にはお金の価値が下がっているため、90万円程度のものしか買えないのだ。
IMF、国際通貨基金の推計によれば、2024年の日本のインフレ率(物価上昇率)は、1.99%と予測されている。
IMFによれば、日本のインフレ率は2025年から2029年にかけて、およそ2%で推移していくと予想されており、インフレによる貨幣価値の低下は避けられない状況だ。
こういった高いインフレ率が続くと推測される現在の日本において、現金のままでお金を維持する銀行預金という資産保有の方法に依存するあり方は、リスクになる可能性が高い。
長期的な運用で複利効果を活用するメリット
ここまでの解説で、銀行預金という資産保有の方法には、大きなリスクが伴うことはお分かりいただけただろう。
では、資産運用という方法を選んだ場合はどうであろうか。
資産運用の大きなメリットは、長期的な運用によって複利の効果を発揮できることにある。まずは資産運用の肝となる、複利について理解を深めよう。
複利とは、利息の計算方法の一つだ。一定期間ごとに利息を元本に含めた金額で利息が計算される。
利息は元本に対して付与されるものであるため、元本の金額が大きくなるほど利息額が増える。
長い期間運用するほど利息の額が増え、元本への充当額が増える。こうして、より大きな利息を得られる流れを作り出せるのが、複利のメリットだ。
資産運用を選択した場合、複利によるメリットを得られる。
とくに、運用期間が長くなるほどその効果は顕著だ。たとえば100万円を年利4%で30年間運用した場合、およそ324万円にまでお金を増やせる可能性がある。
1,000万円の資産運用で検討すべき投資先5選


1,000万円の資産運用で検討すべき投資先が、次の5つだ。
- 債券投資
- 株式投資
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
| 投資先 | 特徴 |
|---|---|
| 債券投資 | 債券を介して国や企業にお金を貸し利息を得る |
| 株式投資 | 企業が発行する株式を購入して利益の一部を配当金として受け取る 購入時より株価が上がれば売却して利益を得る |
| 投資信託 | 資産運用のプロが、投資家から集めたお金を運用し出た利益を分配する |
| ETF(上場投資信託) | 投資信託の一種株価指数などの特定の指標に連動することを目指す |
| REIT(不動産投資信託) | 不動産投資信託投資家から集めたお金を不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配 |
それぞれの投資先について、詳しく説明する。
債券投資
債券投資とは、国や企業が発行する債券を購入して、定期的に利息を受け取る投資方法だ。債券投資の中でもとくに国債は、国が発行する債券であることから信頼性が高い。
債券投資のメリット
・安全性が高い
・定期的に利息を受け取れる
・満期時には額面金額が返還され、元本割れのリスクが低い
・リスクの低減
・分散投資が可能
債券投資のデメリットは、安定性が高い反面でリターンが低めな傾向があるという点だ。
しかし1,000万円の資産運用の投資先として、おすすめできる選択肢である。
たとえば1,000万円規模の投資をおこなえば、安定した利息収入が期待できる。
また株式をはじめとする他の資産と組み合わせることで、ポートフォリオのリスクを低減することも可能だ。
仮に1,000万円の資金力をすべて債券投資に投じたとしても、低リスクで一定以上のリターンが期待できる。
株式投資
株式投資とは、企業が発行する株式を購入し、その株価の値上がりや配当金によって利益を得る投資方法だ。
1,000万円の運用先をとして株式投資を選ぶと、次のようなメリットが期待できる。
| 株式投資のメリットと詳細 | |
|---|---|
| キャピタルゲイン | 資産の売却によって得られる利益 |
| インカムゲイン | 株式や債券などの資産を保有中に 得られる利益 |
| 株主優待 | 企業が株主に向けて優待品を贈る制度 |
| 経営参加権 | 企業経営に関する重要事項の承認などを 通じて、間接的に企業経営に参加できる権利 |
成長性が高い株式投資は、多くのメリットを期待できる。しかしその反面、変動のリスクが高いのは弱点だ。
株式投資を資産運用の選択肢として検討する場合は、短期的な視点ではなく、長期目線での運用が欠かせない。
投資信託
投資信託は、資産運用が初めてで知識が少ない投資家におすすめの金融商品だ。資産運用の専門家が投資家からお金を集め、代わりに運用し、獲得した利益を分配する。
投資信託のメリット
・少額から投資可能
・積立投資にも対応可能
・資産運用のプロに任せられる
・知識が少ない初心者も挑戦しやすい
・基準価額が毎営業曜日ごとに公表される
・透明性が高い
・リスクの低減、月々の支出の負担を軽減長期的な運用が可能
ただし投資信託では、運用管理費用である信託報酬といった費用が発生する。また元本保証がないため、市場環境によっては損失が生じる可能性があるのもデメリットである。
手元の1,000万円の資産運用先として投資信託を選ぶ場合は、複数の資産クラスに分散投資するとよい。
また長期の運用によって複利の効果を得ながら、効果的に資産運用を進めるのに適している。
ETF
ETFとは、上場投資信託のことだ。低コストで分散投資し、長期的な資産形成を目指すための新たな投資手段として、注目されている。
また、ETF(Exchange Traded Fund)は、証券取引所に上場されており、株式と同じように市場でリアルタイムに売買できる。
「簡単・安い・分散できる」という投資の基本をしっかり押さえた商品であり、初心者が最初の一歩を踏み出すのに最適な投資対象だ。
ETFのメリット
・低コストで始められる
・分散投資できる
・値動きが分かりやすい
・リアルタイムの取引ができる
・リスクの低減や長期的な運用をしやすい
・リスクの低減初心者でも始めやすい
・初心者でもわかりやすい
・取引がスムーズ
一方でETFには、次のようなデメリットもあるので、あらかじめ把握しておこう。
- 分散投資する場合に自身で組み合わせを考える必要がある
- 資産の見直しや割合の調整を自分でおこなう必要がある
- 分配金を自動で再投資できない
- 積立投資に対応している証券会社の件数が少ない
- 株主優待がない
一般的な投資信託と異なり、ETFは自ら資産運用に関する知識を習得し、積極的に行動を起こさなければならないのが弱点だ。
ただ専門家が投資家に代わって資産運用をおこなう投資信託であっても、専門家に任せきりでは心もとない。徐々にであっても、知識を習得していくことが重要だ。
資産運用に関する経験値を高めながらお金を増やす方法として、ETFもまた有力な選択肢の一つである。
REIT
REITとは、不動産投資信託のことだ。
投資者から集めた資金で不動産の投資をおこない、そこから得られる賃貸資料収入や不動産の売買益をはじめとする利益を投資者に配当する金融商品である。
REITは、金融商品を通じて間接的に不動産のオーナーになれること、また資産運用するのが不動産のプロである点で、一般的な投資信託と異なる。
REITのメリットには、次のようなものがある。
REITのメリット
・少額から不動産投資できる
・分散投資可能
・不動産の維持費や税金がかからない
・安定した配当が期待できる
・流動性が高いのでお金に変えやすい
・不動産物件管理の手間がかからない
・リスクの低減で初心者でも始めやすい
・低コストで始められる
・定期的にリターン得られる
・現金化がスムーズ
・初心者でも始めやすい長期的な運用に便利
REITのデメリットには、災害や不動産の価格変動によるリスクがある。
しかし、維持費をはじめとするランニングコストをかけずに少額から投資を始めたい人にとって、REITは大きなメリットを享受できる投資先だ。
またREITは証券市場で取引されているため、現金が必要になった場合の売却もスムーズである。
手間と時間をかけずに安定した収益を得たい、また少額から投資を始めたい人にとって、REITはおすすめできる金融商品だ。
- 出典:三井住友トラストアセットマネジメント「REITとは」・女性のはじめての投資をガイドするサイト乙女の財布「REITって何?」・GALA NAVI「REIT・不動産投資、それぞれ向いている人とは?」
【参考例】1,000万円の投資ポートフォリオを紹介


1,000万円の投資ポートフォリオとして、次の3つのリスク許容度別の具体例を紹介する。
- 安定型
- バランス型
- 積極型
で紹介するポートフォリオは、基本形である現金30%、国内リスク資産40%、海外資産30%という分配比率を維持しながら、その内訳にバリエーションを持たせた内容となっている。
1.安定型
リスクを抑えながら安定的に収益を目指す安定型のポートフォリオでは、値動きが大きく収益が期待できる半面で元本割れをはじめとするリスクが想定される資産と、収益は限定的だがリスクも少ない資産の両方に分配することが重要だ。
そこで、次のようなポートフォリオを提案したい。
| 資産の種類 | 配分比率 | 配分金額 |
|---|---|---|
| 現金・預金 | 30% | 300万円 |
| 国内債券 | 20% | 200万円 |
| 国内株式 | 10% | 100万円 |
| 国内REIT | 10% | 100万円 |
| 先進国債券 | 15% | 150万円 |
| 先進国株式 | 10% | 100万円 |
| 先進国REIT | 5% | 50万円 |
上記のポートフォリオの特徴は、以下のとおりだ。
- 緊急時の資金需要に対応できるよう備えて現金で30%保有
- 国内債券で安定的なインカムゲインを期待
- 国内株式で適度に成長性を確保
- 国内REITで分散投資しながら安定した配当収入を確保
- 先進国債券で為替リスクを抑えながら収益の向上に期待
- 先進国株式グローバルな成長機会への備え
- 先進国REIT海外不動産市場への分散投資によるリスクの低減
2.バランス型
バランス型ポートフォリオは、ポートフォリオの資産構成のうち株式と債券で資産を保有するスタイルだ。
攻めすぎず守りすぎないスタンスで、適度なリターンを期待できるのがバランス型ポートフォリオである。
バランス型で、1,000万円の手持ちの資金を分配するなら、次のようなポートフォリオを提案する。
| 資産の種類 | 配分比率 | 配分金額 |
|---|---|---|
| 現金 | 30% | 300万円 |
| 国内債券 | 15% | 150万円 |
| 国内株式 | 20% | 200万円 |
| 国内REIT | 5% | 50万円 |
| 海外株式 | 20% | 200万円 |
| 海外債権 | 10% | 100万円 |
ポートフォリオの特徴は、次のような構成で組まれている。
- 株式を国内と海外に分散することで、安定性を維持しながら成長機会も捉えられる
- 債権を国内と海外に分散することで、安定的なインカムゲインと、為替リスクを考慮しながら高い利回りに期待
- REITを組み込むことで、不動産市場への分配投資と安定的な配当収入に期待
3.積極型
積極型ポートフォリオは、現金30%・国内リスク資産40%・海外資産30%の比率は維持しながらも、債券をはじめとするリターンが低い投資先への配分比率を下げて、利回りが高い投資先に注力する特徴がある。
積極型ポートフォリオで1,000万円の資金を投じるなら、次のようなポートフォリオが考えられる。
| 資産の種類 | 配分比率 | 配分金額 |
|---|---|---|
| 現金 | 30% | 300万円 |
| 国内債券 | 5% | 50万円 |
| 国内株式 | 25% | 250万円 |
| 国内REIT | 10% | 100万円 |
| 海外株式 | 20% | 200万円 |
| 海外REIT | 5% | 50万円 |
| 新興国株式 | 5% | 50万円 |
上記のポートフォリオの特徴は次のとおりだ。
- 国内外の株式保有の割合を増やして、高いリターンを期待
- 国内外のREITに資産を通して、不動産市場からの安定的な配当収入を狙う
- 国内債券は最低限度の配分に留めてリスクを分散
- 高リスク高リターンな新興国株式で、成長機会を追求
1,000万円の資産運用を成功させるためのポイント


1,000万円の資産運用を成功させるためには、次の3つのポイントを押さえることが大切だ。
- 「長期・積立・分散」が基本
- 資金性格や目標を設定し、自分に合ったポートフォリオを組む
- NISAやiDeCoなど有利な制度を活用
それぞれについて、詳しく説明する。
1.「長期・積立・分散」が基本
資産運用に成功するための基本は、「長期・積立・分散」である。
まず長期的なスパンで資産運用に取り組むことで、次の2つの効果が期待できる。
- 複利による効果を最大化できる
- 市場の変動に左右されにくい
また資産運用では、積立投資を活用することが重要だ。積立なら少額からスタートできるので、家計を圧迫しない。
初めて資産運用する人にとっても、心理的なハードルが下がるメリットもあるだろう。
これらと併せて、資産を分散しながら投資することが欠かせない。
分散投資には、投資にはつきもののリスクを最小化する効果が期待できる。資産運用を始める場合、回避できないリスクへの対策は必須だ。
一つの投資先に多額の資産をつぎ込むのではなく、各金融商品のバランスを見ながら、分散投資することが重要である。
2.資金性格や目標を設定し、自分に合ったポートフォリオを組む
資産運用に成功するためには、明確な目標設定と、それに基づいたポートフォリオの作成が欠かせない。
そして目標設定やポートフォリオを組むために前提となるのが、資産運用に投じることが可能な資産額を正確に算定することである。
このとき、資金の性格を基準に判断することが大切だ。
- 出典:MUFJ「はじめの一歩」
資金性格とは
資金性格とは、お金の種類のことだ。分類方法はさまざまだが、ここでは次の3つの資金性格を紹介する。
- 余裕資金
当面は使う予定がない資金 - 準備資金
数年後には使うことが決まっている資金 - 生活資金
日々の生活にすぐに使う資金
上記3つの資金のうち、資産運用に適しているのは余裕資金だ。準備資金も、資産運用に充当できないわけではない。
しかし準備資金を資産運用に活用する場合は、元本の安全性が確保されていること、また短期もしくは中期の運用でも一定の収益が期待できる金融商品に投じる必要がある。
こういった点を考慮すると、余裕資金がどれだけ手元にあるかによって、資産運用の元金を決定するのが妥当だ。
また、どのくらいの期間でどの程度までお金を増やしたいかの目標設定も、余裕資金をベースにおこなうとよい。
資産運用に成功するための目標設定のポイント
資産運用を成功に導くためには、具体的な目標を定めることが重要だ。このときの目標設定は、ライフプランを軸にすると、明確に定めやすい。
たとえば、何年後に教育資金としていくら必要であるか算定すれば、それまでにどの程度までお金を増やせばよいかわかる。
また老後の資金であれば、長期的な資産運用が可能だ。短期的な市場の動きに惑わされず、少額ずつでも積み立てながら運用する戦略を立てるとよいだろう。
資産運用の具体的な目標と期間が定まっていれば、どれだけの金額をどの投資先に投じればいいか逆算できる。
漠然とお金を増やしたい、ではなく、いつまでにいくらのお金が必要なのかを明確にすることが重要だ。
ポートフォリオを組んで資産の分配を決定
資産運用の目的と期間が明確になったら、手元の資産をどのように分配して投資するかを決定しよう。
このとき大切なのは、資産を分配しながら投資することだ。性格が異なる複数の商品に投資することで、相互に利益を保管し合う効果が期待できる。
逆に1つの金融商品にまとめて投資すると、リスクが大きくなる可能性があるため、ご注意いただきたい。
しかし的確に資産を分配するためには、各金融商品に関する知識が必要だ。どの商品にどれだけ資産を投じればよいか迷い、資産運用に踏み切れないケースは多々ある。
そういった場合は、資産運用のプロフェッショナルにアドバイスを求めるのが効果的だ。具体的なアドバイザーの探し方については後述する。
3.NISAやiDeCoなど有利な制度を活用
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった制度は、資産運用で出た利益を最大限手元に残すために効果的である。
資産運用するなら、NISAやiDeCoといった制度を存分に活用したい。
たとえば2024年の制度改定後のNISAには、次のようなメリットが期待できる。
- 資産運用で得た利益が非課税になる
- 非課税期間が無期限
- 非課税保有限度額が1,800万円に引き上げ(このうち成長投資枠は1,200万円)
- 年間投資上限額の引き上げ(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)
またiDeCoのメリットは、次のとおりだ。
- 資産運用で得た利益が非課税
- 積立時に所得税や住民税が軽減される
- 掛け金支払い時・運用時・受取の際に税制優遇措置を受けられる
長期的な運用の過程で利益が見込めるようになった際には、NISAやiDeCoといった制度の恩恵を受けられる。
資産運用を考えるなら、ぜひNISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用したい。
1,000万円を資産運用するときの注意点


1,000万円を資産運用するときは、次の4点に注意が必要だ。
- 余剰資金内で運用する
- リスク管理を適切におこなう
- 相場の変動に一喜一憂しない
- ポートフォリオは定期的に見直す
1.余剰資金内で運用する
資産運用は、余剰資金の範囲内でおこなうことが鉄則だ。
元金が増えるほど大きなリターンが期待できるため、手持ちの資金をできるだけ多く投じたいと考えることもあるだろう。
しかし、投資にはリスクがつきものだ。たとえば、生活費を資産運用に投じたものの、資産価値が大幅に低下した場合、日々の生活費の捻出に苦慮する可能性がある。
資産運用とは、将来の暮らしを豊かにするための備えである。しかしそのために現在の生活が苦境に追い込まれるのでは本末転倒だ。
また、資産運用は長期的な視点で取り組むことが欠かせない。余剰資金の範囲内で運用することが、無理なく資産運用を継続するための前提条件である。
2.リスク管理を適切におこなう
先に述べたように、投資においてリスクはつきものだ。悲観的になりすぎる必要はないが、許容しきれる範囲のリスクに留められるよう、管理することが大切である。
余剰資金内で運用することは、リスク管理の一環だ。この他にも、分散投資や少額から投資を始めること、少額ずつを積み立てることなどは、欠かせないリスク対策である。
資産運用は、小さく始めて長く続けることが重要だ。資産運用の過程で不可避なリスクも含めて、運用計画を立てたい。
3.相場の変動に一喜一憂しない
市場の相場は刻々と移り変わる。仮に資産価値が下がることがあっても、下がり続けて上がらないことはほとんどない。
また逆に、上がり続けることもない。上下動を繰り返すのが相場だ。
したがって相場の変動に一喜一憂するのは、労力の無駄遣いであろう。さらに市場の動きに惑わされ、慌てて売却、もしくは購入するのも危険である。
資産運用においては、常に冷静に、そして広い視野で大局を眺めながらどう行動すべきかを判断することが大切だ。
4.ポートフォリオは定期的に見直す
本記事でもポートフォリオを紹介したが、恒常的に正解であり続けるポートフォリオは存在しない。
ライフステージの変遷や市場経済の動きなど、さまざまな条件を加味しながら適宜見直す必要がある。
しかし、ポートフォリオを見直すべきタイミングを見極めることも、どのように見直せばよいのかも、容易ではない。適切に判断するためには、資産運用に関する豊富な知識と経験が必要だ。
そこで1,000万円の資産運用をする際の相談先について、次の項で具体的に紹介する。
1,000万円を資産運用するときの相談先


1,000万円を資産運用するときの相談先を具体的にあげながら、信頼できるアドバイザーを見極めるポイントについても解説する。
1,000万円を資産運用するときの相談先
1,000万円を資産運用するときの相談先には、次の3つがある。
- 証券会社
- FP:ファイナンシャルプランナー
- IFA:独立系ファイナンシャルアドバイザー
| 証券会社 | FP | IFA | |
|---|---|---|---|
| 相談できること | 資産運用に関する情報提供と相談 | ライフプランニング生活にまつわる お金の相談(年金や税金など) | 資産運用金融商品の提案・ 販売長期的なライフプランニング |
| 資産運用における専門性 | 金融商品に特化 | 幅広い金融知識 | 資産運用に特化 |
| 提案する金融商品の範囲 | 自社商品中心 | 限定的 | 幅広い商品から中立的に提案 |
| 依頼にかかる費用 | 取引手数料 | 相談料コンサルティング料 | 報酬型 (資産残高に応じた手数料など) |
| 中立性 | 低い (自社商品販売が中心) | 比較的高い | 高い |
| 継続的なサポート | 限定的 | プランニング中心 | 長期的なフォローアップが可能 |
証券会社は、自社が取り扱う金融商品のスペシャリストだ。特定の証券会社の金融商品にターゲットを絞り込めている場合は、効果的な情報を入手できる。
しかし、初めての資産運用の場合、どの証券会社の金融商品が自分に合っているかを見極める段階で、迷うことが多いだろう。
また証券会社の窓口まで訪れる時点で、かなりハードルが高いと感じる可能性がある。
FP(ファイナンシャルプランナー)は、資産運用に関する相談に対応可能だ。しかしあくまでも総合的な資産設計と、ライフプランニングの一環としての資産運用に限定される。
とくに、個別の銘柄に関するアドバイスを受けるのは難しい。
あくまでも、投資を含めた資産計画を立てる段階では、効果的なアドバイザーといえる。
IFAは投資や資産運用に特化したアドバイスを継続的に得られる。
手数料がかかるものの、初めて資産運用に取り組む人には心強いサポーターだ。
自分に合ったアドバイザーの選び方
資産運用に、絶対的な正解も勝ちパターンも存在しない。
投資家の数だけパーソナライズする必要があり、またライフプランのどの段階にあるかによっても、適切な資産運用の方法は異なる。
自分の置かれた状況を理解したうえで、的確な助言が可能なアドバイザーを選ぶためには、次の点をチェックしよう。
- 知識量と経験値の高さ
- スムーズなコミュニケーション
- 信頼関係を築ける相手であるか
- 自分の状況にあったアドバイスを受けられるか
- 料金体系に透明性があるか
- 予算に合っている
とくに重視したいのは、スムーズなコミュニケーションや信頼関係を構築できるか否か、また自分の状況にあったアドバイスを受けられるかという点だ。
資産運用には、さまざまな専門用語が存在する。いずれも日常的に利用するものではないため、初心者にとっては、専門用語を理解するだけで手一杯な状況に陥ることも珍しくない。
こういった状況にもかかわらず、意味のわからない言葉を並べ立て、理想論や正論ばかり述べられても、自分にとって最適な選択肢を導き出すヒントにはならないだろう。
仮に豊富な知識や経験があるアドバイザーであっても、ストレス源になりかねない。
投資では、大きな金額に関して重大な決断が求められるシーンは多々ある。
こういった状況を乗り越え続けるために、親身になって寄り添いながら、利益を最大化するために適切な助言ができるアドバイザーを選ぶことが大切だ。
自分に合ったプロに出会うなら「資産運用ナビ」
自分に合ったプロを早く見つけることが、資産運用に成功するためのポイントでもある。
そこで、効率よく自分にぴったりのアドバイザーを見つけるためにおすすめしたいのが、全国30社以上の金融機関から信頼できるアドバイザーを無料で紹介し、投資の悩みを徹底解決するマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」だ。
「資産運用ナビ」を利用すると、資産運用のプロと簡単にマッチングできる。使い方は簡単。資産状況やアドバイザーの条件を選択することで、簡単にプロとマッチング可能だ。
「資産運用ナビ」は無料で利用できるサービスである。気になるアドバイザーがいればその場で面談を申し込むこともできる。
1,000万円の資産運用と、大きなリターンが見込める分、リスクが大きくなる可能性は否めない資産運用に悩む場合は、「資産運用ナビ」を活用し、投資のプロフェッショナルのサポートを受けるのがおすすめだ。
「資産運用ナビ」で1,000万円の投資を成功に導くアドバイザーを見つけよう!


1,000万円の資金を守りながら増やすなら、資産運用は必須だ。
1,000万円の投資先には、債券投資・株式投資・投資信託・ETF・REITの5つがある。また、資産運用は長期・分散・積立が基本だ。
その上で成功させるためには、資金の性格や自身の目標に応じた最適なポートフォリオを作成することが重要である。
しかし投資には元本割れの可能性もあるため、知識と経験に基づいた慎重な選択が欠かせない。資産運用で不安がある場合は、プロに相談するのがおすすめだ。
「資産運用ナビ」は、無料で利用できる。まずは「資産運用ナビ」に登録して、自分だけのアドバイザーをみつけよう。