オフィスワークとテレワークの両方をカバーした「ハイブリッドワーク」時代の次のブレイクスルーはAI
2020年、世界規模での新型コロナウイルス流行を経て、ビジネスパーソンの働き方は大きな変革を遂げたと言える。日本においても緊急事態宣言等により、エッセンシャルワーカーを除いてオフィスに出勤できなくなるという事態に直面し、ビデオ会議ソフトウェアでのオンライン会議や、SaaS(Software as a Services)のようなクラウド経由で利用可能な業務ソフトウェアが急速に普及していく運びとなった。
オフィスに居なくても仕事ができるような働き方、「リモートワーク(テレワーク)」への対応が急速に進んだことは記憶に新しいだろう。
そうしたコロナ禍も、緊急事態宣言解除などの段階を経て2022年から徐々に落ち着きをみせ、2023年には通常のオフィス出勤体制が復活するなど、かつての状況に復帰しつつある。しかし、働き方の進化は不可逆だ。ビジネスパーソンはリモートワークのメリットを知ってしまっただけに、それを活用した働き方を手放す理由はどこにもないだろう。
しかし、その一方でオフィスにいくメリットを再発見したというビジネスパーソンも少なくない。たとえば家で仕事する際、住環境の都合で十分なIT機器を置けない(例えば大きな外部ディスプレーを置けないなどがその典型例だろう)、常に家族がいることで業務に支障が出る、などのさまざまな制約をうけることがあると思う。集中して仕事ができることや多様なIT機器を活用できるという意味で、リモートワークの弱点とオフィスワークのメリットも見えてきた。
このため、今では多くのビジネスパーソンが「ハイブリッドワーク」と呼ばれるリモートワークとオフィスワークを組み合わせた柔軟な働き方を選んでいる。1週間のうち2日は会議のためにオフィスに出勤するが、残りの3日は自宅やカフェなどでのリモートワークで通勤時間を節約する…そんな働き方が一般化してきているのだ。実際内閣府の調査では、2023年4月時点におけるテレワーク可能な人が都内において5割にのぼり、全国では3割と、コロナ前(2019年12月)の約3倍になっているという統計もある。日本HPの社内調査でも、コロナ前にはハイブリッドワークを実践している従業員は35%であったが、昨年の暮れから今年にかけての調査では全ての従業員がハイブリッドワークに移行していることがわかっている。
そのような時代を迎えた現在、HP本社の調査「HPワークリレーションシップ」では従業員が企業に求める要素はさまざまあるとしつつ、その中でも「ツール」を重要だと考える従業員は増えているという結果が出た。しかし、その一方で充実度がまだまだ十分ではないと考える従業員が多いことも浮き彫りになっている。
では充実度に不満を抱える従業員が注目するツールとは何なのか、それが「AI」だ。「AIは仕事との関係性の改善に重要な役割を果たす」という設問に対して、ビジネスリーダーの72%、ナレッジワーカーの53%が重要だと答えている。「AIは仕事を楽しむ新たな機会をもたらす」という設問に対しては55%がそうだと解答している。
このように、ハイブリッドワーク時代に、ナレッジワーカーの生産性を向上させるツールとして注目を集め始めているのがAIなのだ。
インテル® Core™ Ultraプロセッサーには高性能で低電力なAI処理に特化したプロセッサー、NPUが内蔵されている
現在、AIを活用する新しいPCの形として注目を集めているのがいわゆる「AI PC」だ。AI PCとは、簡単に言うとAIのアプリケーションをより効率的に実行できるようになったPCのことを意味しており、CPUやGPUといった従来型のプロセッサーに加えて、NPU(Neural Processing Unit)というAI処理に特化した新しい種類のプロセッサーを搭載していることが特徴だ。
その代表例が、インテルが提供する「インテル® Core™ Ultra プロセッサー」(以下Core Ultra)である。上段にロゴを掲載しているが、「インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー」もその1つだ。インテルのCore UltraはSoC(System on a Chip)と呼ばれる1つのチップでコンピューターを構成できる半導体製品になっており、その最大の特徴は「インテル AI Engine」と呼ばれるNPUを搭載している点である。NPUが搭載されたことにより、高負荷から低負荷までさまざまなAIによる負荷を、CPU・GPU・NPUそれぞれの特性にあわせて適材適所で処理するようになっている。
また、NPUはAIの処理をCPUに比べて高速に行なえるだけでなく、低消費電力で実行することを可能にした。つまり、AIの処理を行なう時の電力効率が高いということだ。このため、例えばバッテリー駆動時に、AIの処理をCPUからNPUにオフロードすることができれば、少ない電力で処理を行なえるようになり、バッテリー駆動時間の延長にもつながる。
その特徴をうまく利用しているのが、ビデオ会議の際によく使われる「背景のぼかし」などの機能である。一部のソフトウェアでは、そういったCPUの負荷が高いことで知られるビデオ会議中の動作を、NPUにオフロードさせることができ、「CPUがフル稼働することで気付いたらバッテリー残量が無くなっている」という定番のトラブルを避けることができる。
NPUを利用したアンチマルウェアツールやGPUを活用したクリエイターツールなどが出揃いつつある
また、「インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー搭載インテル® vPro®」をはじめとした、Core Ultraのビジネス向けとなる「インテル® Core™ Ultra プロセッサー搭載 インテル® vPro® プラットフォーム」(以下Core Ultra vPro)では、NPUを利用したマルウェア検知なども可能としている。マルウェア検知というのは、CPUへの負荷が高いことでも知られており、スケジューリングされているマルウェア検知中などにCPUの負荷が高まることによってPCが熱をもち、使いモノにならないということはPCの利用シーンではよく見かける事態だ。そこで、Core Ultra vProでは、そうしたマルウェア検知の処理をNPUにオフロードすることで、CPUの負荷を増やさずにマルウェアの検出が可能になる。
利用するにはマルウェア対策ソフト側の対応が必要であるが、BUFFERZONE Securityの「Safeworkspace Pro」が既に機能を実装しているほか、CrowdStrikeも開発意向表明を行なっている。
さらに、既にAIを利用したアプリケーションはPC向けに多数提供されており、Adobe Photoshop、Adobe Premiere Pro、Adobe LightroomのようなAdobeのアプリケーションはその代表例で、動画編集や写真編集のAI処理にGPUを利用して処理をしている。
インテルは、インテル® OpenVINO™ ツールキットと呼ばれる開発ツールを2018年から提供しており、Adobeなどのソフトウェアベンダーはそちらを利用してAIの実装を行なうことで、インテル製のさまざまなプロセッサーを活用してAIの処理を行なえるようにしている。加えて最新のOpenVINOではNPUにも対応してきた。そのため、既にCPU/GPUを活用したAIソフトウェアを開発するソフトウェアベンダーがNPUに対応するのは容易だと考えられ、今後多くのベンダーはAIアプリケーションをさらに送り出していくことになるだろう。
日本HPのインテル® Core™ Ultraプロセッサーを搭載したHP EliteBook 1040 G11は、前の世代に比較してグラフィックスもAIも大きく性能向上
そうしたAIの処理を高速化するNPUを持つCore Ultraを搭載した、日本HPのAIテクノロジー内蔵ノートPCが3月27日に多数発表されている。
その中でも、最もハイエンドで高パフォーマンスのモデルとなるのが「HP EliteBook 1040 G11」だ。その高性能の基礎となっているのが、インテルのCore UltraおよびCore Ultra vProである。Core Ultra/Core Ultra vProは、先述の通りNPUの追加はもちろん、CPUやGPUの性能も強化されており、前世代に比べて大きくパフォーマンスが向上していることが特徴だ。
また、このようなパフォーマンスを実現するため、「HP Smart Sense」と呼ばれる強力な冷却機構が採用されており、2つの高密度ターボフォンを搭載することで、40%静音を実現しながら40%性能をアップさせている。Core Ultraとそうしたユニークな冷却機構の採用により、グラフィックス性能は最大80%、AIビデオ編集では最大132%の性能向上を実現した。
さらにAI PCを象徴するような「Copilotキー」が標準搭載されていることも見逃せない。このCopilotキーを押すだけで、Microsoftの「Copilot in Windows」を呼び出して、さまざまなAIの機能をすぐに活用することができる。
同製品ではHPの「Endpoint Security Controller」(ESC)を基板上に実装していることも特徴としてあげられ、今回の製品では第5世代のESCへと強化されている。第5世代のESCでは「耐量子コンピューター」機能がサポートされており、仮に今後量子コンピューターを活用して、RSAのような重要なセキュリティーが破られても、ESCによるファームウエア保護は破られない仕組みが採用されているのも大きな進化ポイントのひとつだ。
ハイブリッドワーク時代のPCを象徴する機能としては、HPの傘下となったリモートワーク用機器を提供するブランド「Poly」がチューニングしたオーディオ機能やフロントカメラの画質も見逃せない。新しい世代の日本HPが提供するビジネスPCには「Poly Studio」というロゴがつけられるようになっており、Polyによるチューニングが施されていることが一目でわかる。
この他にも、AIを活用したバッテリー駆動時の電源管理、さらにはリサイクル素材を積極的に利用するなど、サステナブルなPCを意識して設計されたポートフォリオも展開している。
このように、日本HPがまもなく提供を開始するAIテクノロジー内蔵ノートPCは、従来世代のPCに比べて大きく性能が向上しており、AI処理に特化した高性能かつ低電力のNPUを搭載することでAIを用いた新世代のソフトウェアや機能を活用することが可能になっている。また、既に市場にはAdobeのPhotoshop/Premiere Pro/LightroomといったCPU/GPUを活用するAI機能を実装したアプリケーションも出そろいつつあり、これからのビジネスにおけるAI活用は必須と言えるだろう。
ハイブリッドワーク時代のいま、AI活用を加速させ、従業員の生産性をさらに向上させるソリューションのひとつとして、日本HPのAIテクノロジー内蔵ノートPCを、ぜひ検討してみてはいかがだろうか。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel vPro、インテルヴィープロは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
[PR]提供:日本HP





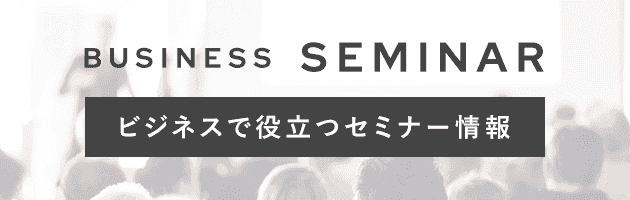



![Proselfの脆弱性対応に学ぶ、利用者本位の信頼回復プロセス [事故対応アワード受賞]](/techplus/article/20240618-secraward-proself/index_images/index.jpg/iapp)







