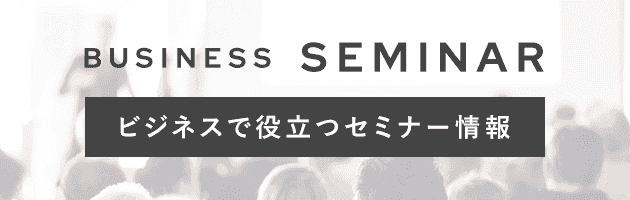10月19日に発表があった通り、11月21日よりRyzen Threadripper 7000シリーズ及びRyzen Threadripper Pro 7000 EXシリーズが発売開始となる。本当はこれに合わせてベンチマークデータをお届けしたかったのだが、機材の関係により、まずは製品紹介だけちょっとさせていただきたい。
以前の記事でも説明したが、Ryzen Threadripper 7000シリーズとRyzen Threadripper Pro 7000 EXシリーズはどちらも同じフォームファクタで提供される(Photo01)。現在のところRyzen Threadripper 7990X(仮)はまだ未発表(型番もこれで正しいかどうか不明)ということもあり、Ryzen Threadripper 7980Xは8 CCD、Ryzen Threadripper Pro 7995WXは12 CCDでの構成である(Photo02)。リテールパッケージもサイズは同じで色違い(Photo03,04)の形で用意される。
-
Photo01: 上がRyzen Threadripper 7980X、下がRyzen Threadripper Pro 7995WX。従来のRyzen Threadripper(や、Milan世代までのEPYC)と同じ寸法である。
-
Photo02: 以前のこのスライドから察するに、8 CCDなのはRyzen Threadripper 7980Xのみで、Ryzen Threadripper 7960X/7970Xは4 CCDと思われる。
さて今回はRyzen Threadripper 7970XとRyzen Threadripper 7980Xの2つが届いた(Photo05~07)。内部はウレタン製のインナーの表側にCPUが、裏側にCPUクーラーのブラケットとトルクレンチが搭載されている(Photo08)。CPUそのものはオレンジのガイドに装着される何時もの方式である(Photo09,10)。
-
Photo05: パッケージには型番は明記されないので、当然このアングルだと見分けがつかない。正直Ryzen Threadripper 1000~3000世代の大げさなパッケージよりこの方が好感が持てる。
-
Photo06: 裏面はCPUパッケージが覗けるようになっており、ここで見分けがつく形。
-
Photo07: 側面の注意書き。日本語での説明はまぁ当然なし。
-
Photo08: トルクレンチはRyzen Threadripper 1000~3000世代と共通であった。ブラケットも多分共通だと思うが確認していない。
-
Photo09: ヒートスプレッダの上下に隙間があるのが以前の世代との差である。
-
Photo10: 裏面は4つのブロックに分割。2分割だった従来世代とは寸法こそ一緒でも勿論互換性がない。
CPUクーラーとしては今回NZXTのKRAKEN 360が付属した(Photo11,12)が、これは汎用品であって別にRyzen Threadripper用のブラケットに装着できるクーラーなら何でも利用可能と思われる。
マザーボードはASUSのPro WS TRX50-SAGE WIFIがやってきた(Photo13~22)。またメモリとしてはG.SKILLのZETA R5 NEO(Photo23~26)が用意された。
-
Photo14: 寸法は280mm(幅)×310mm(高さ)、重量は2526.9g(いずれも実測値)。メモリは4ch。デュアル電源にも対応している。M.2スロットは3本。
-
Photo15: PCIeのスルーホールが下2つ分しかないことに注意。下から2番目はPCIe x8相当での接続の模様。
-
Photo17: これはPhoto15で上端に当たる部分。両側の金属カバーのついているのがATX12Vの8pin補助コネクタ。原則この両方に装着しないと動かない(片方だけだと赤色LEDで警告されて電源が入らない)。その脇は、PCIeの12pinコネクタ。要するにPCIeのラインからも電源が取れる仕様。相当な大電力に対応しているのが判る。
-
Photo18: 同じくPhoto15では右端に当たる部分。グレーが通常のATX12Vで、その右にあるのはセカンダリ電源用のATX12V、その脇はPCIeの12Vコネクタ。またグレーのちょっと左にも、PCIeの12V 8pinと12V 6pinが配されているのが判る。SATAは4ポートで、これだけはちょっと気に入らなかった(ここまで重厚なのだから、8ポートは欲しかった)。いや、Slim SASコネクタがあるので、こっちを使えということなのだろうが。
-
Photo19: 右の"Pro SERIES"とシルク印刷のあるカバーの裏にM.2が2スロット装着できる。もう一つはPCIeスロットの間である。一番下の中央には"LN2 Mode"のスイッチも見える辺りがいかにもである。
-
Photo23: 執筆時点ではまだこの製品はG.SKILLのサイトでは公開されていない。恐らくRyzen Threadripper 7000の正式発売にタイミングを合わせての公開になると思われる。ちなみにZeta R5は今のところIntelのXMP対応のみとなっており、EXPO対応のR5 NeoはAMD向けの新ラインナップの模様。
-
Photo25: Ryzen Threadripper 7000そのものは公式にはDDR5-5200までの対応だが、これはDDR5-6400 CL-32-39-39-102。ただし電圧は流石に1.4Vとなっている。
-
Photo26: Photo25で手前のDIMMが妙に膨らんでいると思われたかもしれないが、上からみるとこんな感じ。Registerが結構背が高い様で、それもあって膨らんで見えるのが判る。
ということでベンチマークはもう少々お待ちいただきたい...だけで話を終わらせるのも何なので、もう少し補足情報を。TRX90の方のプラットフォームは以前スライドをご紹介したが、TRX50の方は詳細が不明だった。実はまだ公式には情報が伝わってきていないのだが、どうもこのPro WS TRX50-SAGE WIFIの構造は図1の様になっているようだ。実際には他にAudioとかUSB 2.0ポートとかもあるが、この辺は省いている。製品ページによれば"three PCIe 5.0 x16 slots"となっているが、これは「物理的なスロットがx16」という話で、3本あるPCIeコネクタのうち1本(多分下から2つ目)はx8接続になっているものと思われる。殆どのPCIeレーンはCPUから出ており、TRX50チップセット自身はPCIeレーンを合計で8 Laneしか出せない模様だ。要するにこれ、B650そのものではないかと思うのだが、流石に借りもののマザーボードのヒートシンクを引っぺがす勇気はないので今回未確認である。
もう一つはOC特性である。実は先の記事の説明会の折に、(Ryzen Threadripper 7980Xではなく)Ryzen Threadripper Pro 7995WXを使ってのOCチャレンジも行われていた。面白いのは、空冷・水冷・LN2(液体窒素冷却)の3パターンが行われた事だ(Photo27~29)。
-
Photo27: 空冷システム。といってもCPUクーラーは4ファン構成で、更にVRM冷却用とチップセット冷却用にもファンを追加しており、もはや簡易水冷と大して変わらない気がする。マザーボードは恐らくAMD社内の評価用のものと思われる。
このOCの仕方であるが、Ryzen MasterでPPTのLimitを最大1000Wに設定する「だけ」で、後は一切いじっていない。テストではCineBench R23とR24、それと7zipの実行速度の比較を行った(Photo30,31)が、そのうちCineBench R23の結果を示すと
・空冷:118,642
・水冷:148,053
・LN2 :177,050
である。ちなみにこのチャレンジが行われた日(10月10日)におけるWorld RecordはEPYC 9654×2の147,668で、この記録をシングルプロセッサで17%上回るものとなった。というか水冷の結果ですらEPYC 9654×2を上回っているあたりで、OCのヘッドルームが十分ある事をうかがわせる結果となった。まぁOCチャレンジに挑みたいユーザーには丁度良い題材かもしれない。
ということでまずはPreviewをお届けした。ベンチマーク結果は今しばらくお待ちいただきたい。