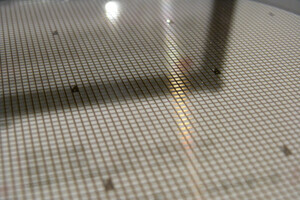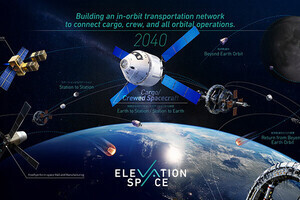本連載の第1回と第2回では、日本初の金星探査計画である「あかつき」がどのようにして生まれ、打ち上げられ、5年前の金星周回軌道への投入失敗が起きたのか。そしてそこからどのようにして再挑戦ができる道筋が見つかったのか、について紹介した。
また第3回では、「あかつき」のプロジェクト・マネージャを務める中村正人さんに、「あかつき」の計画がどのように立ち上がったのか、そして第4回では「あかつき」が完成するまで経緯、また人工衛星のプロマネというのがどういう仕事なのかについて話しを伺った。
今回は中村さんに、5年前の金星周回軌道への投入に失敗したときの状況と、そして原因調査で焦点となったセラミック・スラスターについてお聞きした。
(このインタビューは2015年11月19日に行われたものです)
中村正人さん
1959年生まれ。理学博士。JAXA宇宙科学研究所 教授。
1982年、東京大学理学部地球物理学科卒業。1987年、東京大学理学系研究科地球物理学専攻博士課程修了。ドイツのマックスプランク研究所研究員、旧文部省宇宙科学研究所助手、東京大学大学院理学系研究科助教授を経て、2002年より現職。惑星大気とプラズマ物理学が専門。
金星探査機「あかつき」では、計画の立ち上げから先頭に立ち、プロジェクト・マネージャとして開発から運用、5年前の失敗事故への対応、再挑戦に向けた計画策定を率いてきた。
打ち上げ、そして金星周回軌道投入の失敗
--2010年5月21日の打ち上げから同年12月7日の金星到着までは何も不安なところはなかったのでしょうか。
中村: 何もなかった。本当に順調でした。今考えると不気味な話ですね。
--2010年の金星周回軌道投入は、もう確実に成功するだろうと思っていらっしゃったのでしょうか。
中村: そうですね。だから「どうしたんだろう」と思ったんです。不思議でした。「これはもしかしてエンジンが爆発して吹っ飛んじゃったんじゃないか」って推進系の人たちには言ってたんだけど、今から考えると当たらずと雖も遠からずでしたね。
セラミック・スラスターが途中で千切れてくれたから良かったようなものの、あれが大爆発していたら衛星が壊れていましたから、あの程度で済んで良かったですよ。
そのあと、NASAのマドリード局のアンテナにつなぎかえて探して、通信が切れてから2時間ぐらいで再補足できたんですが、臼田宇宙空間観測所で山本善一先生がずっとオシロスコープで探していたんです。それで捕捉できて「あっ、あった」という声が聞こえてきたんですね。そのあと、セーフ・ホールド・モードに入ってることがわかりました。
爆発した痕跡はないんだけど、生きてたということが不思議で、逆に「何が起きているんだろう」と思いました。
--その2時間ぐらいの間というのはどういうお気持ちだったのでしょうか。
中村: 「俺、こんな運悪かったかなー」と思ってたかなぁ。こんなはずないぞ、と。落ち込む余裕もなかったかなぁ。どうなっているか状況が分からないからね。
ほら、女の子に確実にフラれたと思っても、まだ完全に「アンタ嫌いよ」と言われたわけじゃないなら、諦めきれないものじゃないですか。それと同じですよ(笑)。
--運用に関わっておられた、他の皆さんの反応というのはどういうものだったのでしょうか。
中村: 軌道の計算はすぐにでき、このまま行けば6年後には金星のそばを通るということはわかっていたので、先がないという状況じゃなかったですね。集まった人たちに「今は何もしない。6年先にまたみんな集まってください」というようなことを言ったような記憶があります。
そのときみんなはうなずいていたかな。まぁ、うなずくしかないですよね。各人それぞれ気持ちはあったでしょうが、ほとんどの人は「そうは言ってもたぶん駄目だよね」と思ってたんじゃないかな。
と言うのも、6年先に金星のそばに近付けたとしても、エンジンがぜんぜん噴けなかったら入れないじゃないですか。燃料が残っているかどうかもわからないし。だから単に金星のそばをもう1回通るチャンスがある、という期待だけで希望をつないだんです。人間ってそういうときには藁にもすがるものですね。
--海外の研究者からの応援や励ましなどはあったのでしょうか。
中村: いっぱい来ました。応援というよりは、我々と欧州のグループとは一心同体なんです。「ヴィーナス・エクスプレス」[*10]と「あかつき」は、関わっている人間が入れ子になってますから、他人事ではなくて「自分たちが衛星をロストした」という気持ちだったんじゃないかな。
ヴィーナス・エクスプレスのプロジェクト・サイエンティストは、僕がESAのオランダの研究所に勤めていたときの同僚ですからね。
あと米国のNASAに行って、この事故について説明したときに、ジム・グリーンというNASAの科学部門の部長に「それはとても貴重な情報だ」と言われたんですよ。でもよくよく顔を見ると「これはNASAは過去に同じ失敗をやったことがあるな」という気がしました。
NASAとはずっと以前から、僕らはNASAのアンテナ[*11]を毎日タダで使ってて、その見返りとしてNASAの科学者を受け入れて「あかつき」のデータを見せる、という協定を結んでいるんですね。だから同情というよりは、自分自身の問題と捉えていたと思います。
セラミック・スラスターは悪くない
--その後の調査で、セラミック・スラスターが壊れたのではないかという可能性が出てきます。ただ、セラミック・スラスターが悪い、というわけではないのですよね。
中村: そう、誤解している人が多いのですが、配管の中の弁で閉塞が起きて、燃料の供給量が少なくなり、理論的に最適な混合比率になってしまい、それで燃焼温度が上がって壊れてしまったんですね。だからニッケル合金製のスラスターだったらもっと早く、1分ぐらいで壊れていたでしょうね。
セラミック・スラスターは三菱重工と京セラが造ったんだけど、大変にきちんと開発されていて、非常に性能は良いものです。
--そもそも、「あかつき」にセラミック・スラスターを搭載するという話はいつごろ、どういう経緯で出てきたのでしょうか。
中村: 僕もよく知らないんですよ。最初は手堅い設計で行こうということで、そういう新技術の話はありませんでした。高利得アンテナも検討時はパラボラでしたしね。
スラスターはニッケル合金製が普通で、それで行くんだと思っていたら、いつの間にかセラミック・スラスターになってたんです。これは最後まで揉めたんですよ。なにが問題になったかというと、小さなデブリ(宇宙ごみや宇宙塵など)が当たったときに「パーン」と割れちゃうんじゃないか、という心配があったんです。
それでデブリの衝突確率を一生懸命計算して、「まず起こりえない」という結果を出して、採用することになったんです。
--従来型のスラスターでは性能不足だった、ということではなかったのですね。
中村: 今のスラスターは、燃焼温度を落とすために、酸化剤と燃料を理論的に効率が一番良い比率では燃やしていないんですね[*12]。今回は故障によって図らずも理論的に最適な燃焼になってしまって壊れましたが。
セラミック・スラスターは耐熱性が高く、燃焼温度を高く設定できるので、エンジンの効率を上げられるという点はありました。でも、その可能性は探りはしましたが、「あかつき」では従来どおりの比率で噴いていると思います。だからセラミック・スラスターを積んだのは、試験的な要素が大きかったと思いますね。
--しかし、セラミック・スラスターのような新技術は、本来であれば工学試験衛星で試験したいところだったのではないでしょうか。
中村: 「あかつき」は科学衛星ではありますが、工学的なチャレンジをやるという面もありました。他の惑星の周回軌道への投入ということ自体がチャレンジなことでしたから、その要となるエンジンを新しい技術でやるということに、精神的な抵抗というものはまったくなかったですね。
【取材協力:JAXA】
脚注
10. ヴィーナス・エクスプレス……欧州宇宙機関(ESA)が2005年に打ち上げた金星探査機。「あかつき」が予定通り2010年に金星に到着していれば、共同観測を行うことが計画されていた。2015年1月に運用を終え、金星大気に突入、役目を終えた。
11. NASAのアンテナ……NASAは米国とスペイン、オーストラリアに深宇宙通信用の大型アンテナをもっており、探査機が地球から見てどの位置にいても通信ができるようになっている。一方、日本は臼田宇宙空間観測所(長野県)と内之浦宇宙空間観測所(鹿児島県)にしか深宇宙用のアンテナをもっていないため、探査機の運用には米国の協力が不可欠になっている。
12. 酸化剤と燃料の混合比率……酸化剤と燃料を理論的に効率が最適な比率で混ぜ合わせて燃やすと、その温度が高くなりすぎ、スラスターが壊れてしまう。そこでわざと燃料を多めに混ぜて燃やすことで、不完全燃焼の状態にし、燃焼温度を下げている。今回の「あかつき」では、弁が閉塞した結果、スラスターに供給される燃料の量が少なくなり、意図せず理論的に最適な比率で燃焼したことでスラスターが破損したと考えられている。