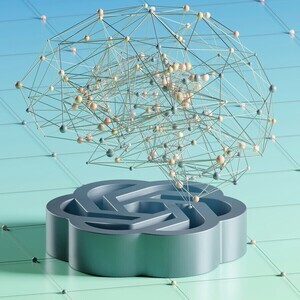多忙な経営者が、茶道や武道といった日本の稽古に打ち込んでいます。なぜ業界で活躍するような人物は稽古に励むのでしょうか? 本連載では『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか』(梅澤さやか著)から、一部を抜粋して紹介します。
第4回は「感性が磨かれる<稽古>の仕組み」です。「感性を磨く」とは、「膨大な知識を体系的に理解し、言語を超えて突き抜けること」だと筆者は言います。この方法を日常生活で実践する方法を今回は解説します。
興味が次のステージを切り拓く
まず、見る眼を鍛えるために知識を増やしたとしても、そもそもその情報が自分にとって重要でなければ、すぐに忘れてしまいます。たとえば、「あの人誰だっけ」と思い出せない人と、はっきりと名前を思い出せる人の違いは、その人の存在が自分にとってどれだけ意味を持っているかによります。
「感性」を磨くには、強い興味を持っていなければできません。本当に関心を持てる分野を見つけることが、効果的な稽古の第一歩です。サッカーが好きな人は、技術だけでなく戦術や戦略にも自然と興味を持ち、深い理解に至ります。
最初は単純な技術の習得から始まりますが、やがてチーム戦術や試合の戦略を考えるようになります。そして最終的には、サッカーというスポーツの本質的な仕組みを理解し、より高い視点から判断できるようになるのです。
この過程は、あらゆるジャンルにも当てはまります。判断ができない、進め方がわからないという場合、必要な知識が不足しているか、または情報を俯瞰的に見る視点が足りていない可能性があります。しかし、それ以前に、その課題に本当に興味があるかどうかを確認することが重要です。興味がなければ、上達は難しく、時間の無駄になってしまう可能性があります。
無意識の予測パターンが上達を妨げる
多くの人は、知識を増やすことで世界をよりよく理解できると考えています。たしかに、新しい情報を学ぶことで知っていることは増えます。しかし、実は知識が増えれば増えるほど、逆に見えなくなるものも出てくるのです。(中略)
私たちは目の前の世界をすべて見ているつもりでも、実際にはその全てを認識しているわけではありません。脳は自動的に情報を取捨選択しており、この選択プロセスは過去の経験や既存の知識に基づいて行われます。そのため、新しい情報や異なる視点を見落としがちなのです。
たとえば、古代エジプト人に現代の書籍を見せたとしましょう。彼らにとっては、それはただの奇妙な物体にしか見えないでしょう。白くて四角く薄いものに黒い模様がたくさん並んで束ねられている物体という認識はできても、「記録媒体」という概念を持ち合わせていないため、それが彼らの日常で使うパピルスと同様の機能を持つものだとは理解できないのです。
このように、私たちは自分の既存の概念に当てはまるものしか認識できず、当てはまらないものは認識の盲点として残り続けます。つまり「茶碗とはこういうもの」や「スマートフォンとはこういうもの」という概念が強固になるほど、それらの概念に当てはまらないものが見えなくなるというパラドックスが生じるのです。
なぜ、このような盲点ができるかというと、脳は、目で見たものや耳で聞いたものを、無意識のうちに自分にとって重要かどうかを自動的に振り分けているからです。情報が脳に入ってくると、海馬がその情報の処理を担当します。海馬は新しい情報を一時的に保持し、大脳皮質に保存されている既存の長期記憶と照らし合わせます。この過程で、海馬は新しい情報の重要性を評価し、それが長期記憶として保存すべきかどうかを判断する役割を果たします。
この情報処理の過程で、大脳辺縁系の一部である扁桃体が重要な役割を果たします。扁桃体は、いわば脳内の「感情ボリューム調整器」のようなものです。
たとえば、音楽を聴くときのボリューム調整を想像してみてください。好きな曲や印象的な音には自然とボリュームを上げたくなり、逆に退屈な曲や不快な音にはボリュームを下げたくなります。扁桃体も同様に、脳に入ってくる情報の「ボリューム」を調整しているのです。
脳にとって危険を感じさせる情報(例:突然の大きな音)や、報酬に関連する情報(例:好物のラーメンの匂い)に対しては、扁桃体が「ボリューム」を上げ、脳全体でその情報をより強く処理します。一方、生存や適応にとってあまり重要でない情報(例:日常的な背景音)に対しては、「ボリューム」を下げ、脳での処理を弱めます。
このように扁桃体は、情報の感情的な重要性に基づいて、私たちの脳内での情報処理の強さを調整しているのです。これにより、重要な情報により多くの注意を向け、「効率的」に対応することができるようになっています。
情報が最初に処理されたあと、脳のさまざまな部位が協力して、その情報の更なる分析と評価を行います。そうして、私たちの脳は過去の経験や学習に基づいた「予測パターン」を形成します。この予測パターンは、新しい情報を素早く理解し対応するのに役立ちますが、同時に「思い込み」や「先入観」のもとにもなります。
結果として、この予測パターンが強過ぎると、予想外の情報や新しい視点を見落としやすくなり、これが認知の「盲点」を生み出す原因となるのです。
重要なのは、これらの脳の働きのほとんどが私たちの意識の外で行われているという点です。たとえ脳のメカニズムについての知識があったとしても、多くの情報処理は無意識のうちに行われているため、私たちが意識的にそのプロセスを認識し、制御することは極めて難しいのです。
このことを踏まえると、「見る眼を鍛える」稽古をより効果的に行い、「感性」を磨くためには、私たちの脳の認知プロセスとそこから生じる「知っているほど知らないが生まれる」落とし穴を深く理解することが不可欠です。この理解を基盤として稽古に取り組むことで、より効果的に「感性」を育むことができるのです。
『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか 』(梅澤さやか 著/クロスメディア・パブリッシング 刊)
茶道や武道の「稽古」と聞くと、敷居が高く窮屈というイメージがあるかもしれません。しかし、多くの経営者は、多忙にもかかわらず、稽古に打ち込んでいます。どうしてでしょうか。
以下のような効能が稽古にあるからでしょう。
- リフレッシュ効果がある
- 心と体の健康を整えることで、より高いパフォーマンスを発揮するための基盤となる
- 創造力や問題解決力が自然と磨かれ、ビジネスに新たなアプローチが生まれやすくなる
- 肩書きや立場を超え、ひとりの人間として出会うことで、本質的な人脈が育まれ、深いコミュニケーション力も磨かれる
稽古は、仕事と人生を豊かにする「習慣」なのです。
本書では、経営者やビジネスパーソンが実践する「稽古」の事例にふれながら、稽古の魅力と効能を解明します。さらに、そのエッセンスを日々の仕事に応用する方法もご紹介します。
稽古は、AIが持っていない「身体」と「感性」を活かして、高度な知性を発展させる方法です。それこそ現代のエグゼクティブに求められる力です。また、海外からも大きな注目を集めている日本文化の豊かな伝統が凝縮されたものです。稽古によって日本文化を体得することは、これからの時代のブランディングにとって大きな力となるでしょう。
稽古に取り組んでいる方にも、未経験の方にもたくさんの発見がある一冊です。
Amazon購入ページはこちら