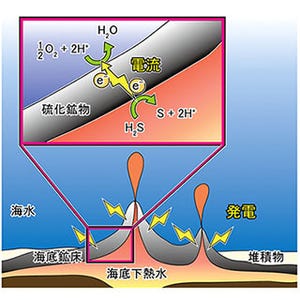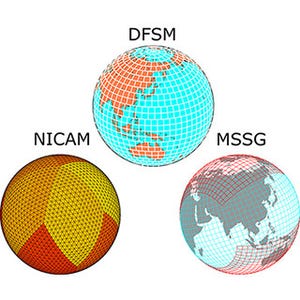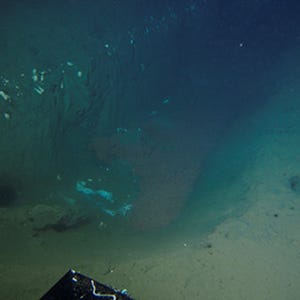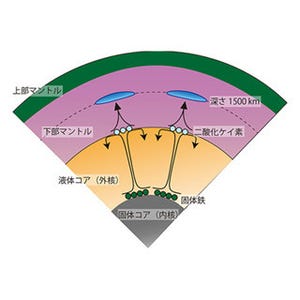海洋研究開発機構(以下、JAMSTEC)は、同機構アプリケーションラボの池田隆美特任研究員と長崎大学熱帯医学研究所の皆川昇教授らの研究グループが、熱帯太平洋や南インド洋の気候変動によりもたらされる南アフリカの降水量や気温の変動が、その数カ月後に生じるマラリアの発生率に影響を及ぼす可能性を示したと発表した。この成果は5月30日、英国のオンライン科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された。
南部アフリカでは、マラリアや肺炎などの感染症の流行し、人々の健康を脅かしている。特に南アフリカ北東部に位置するリンポポ州は、毎年雨期には多くマラリアが発生する。しかし、マラリアの時空間発生分布や発生変動要因については、これまであまり調査されていなかった。
リンポポ州は、マラリアが多く発生するモザンビークやジンバブエと国境を接しており、隣国からの患者流入によって常に大流行の危険性があるため、州マラリア予防対策センターでは、最新の高感度判定装置を導入したほか、媒介蚊の季節的消長を明らかにするための定期的な採集システムを導入するなどの取り組みを進めている。
そこで研究グループは、リンポポ州を対象にマラリアの発生変動と、南アフリカの気候変動および世界の海域でみられる気候変動現象の関係関係について調査したという。リンポポ州の医療関係機関より得られた17年間のマラリア患者情報を用いて、マラリア発生率の季節分布を調べた結果、リンポポ州のマラリアは、南半球の春(9~11月)に発生し始め、夏(12~翌2月)に最も流行していることが判明。マラリア発生率の季節分布と同様に、リンポポ州での降水量も9月から翌年5月まで多い状態が続くという。
次に、マラリアの発生率の空間分布を調べるため、季節ごとに自己組織化マップを解析した結果、リンポポ州のマラリア発生率は、平年より高い、低い、あるいは平年通りという3つのパターンに分類されることがわかった。
この3つのパターンに分類された年を用いて、マラリアが多く発生する年にはどのような気候条件が影響しているかを調べた結果、雨期の前半(9~11月)にマラリアの発生率が高い年は、南西インド洋から湿った東風が吹きやすく、6ヶ月前(3~5月)の降水量が平年より増加していることが確認できたという。その変動には、熱帯太平洋の気象変動現象であるラニーニャ現象が関わっていることが示唆されたということだ。
一方、雨期の中盤(12~翌2月)にマラリアの発生率が多い年は、2ヶ月以上前にモザンビークで降水量の増加と気温の上昇が見られたという。これらの変動には、南インド洋の気象変動現象である、「正のインド洋ダイポールモード現象」との関係がみられたとのことだ。
すなわち、南アフリカのリンポポ州におけるマラリアの発生率は、熱帯太平洋や南インド洋に見られる気候変動現象が南部アフリカにおいて、降水量や気温の変動を数ヶ月以上前にもたらすことと関係していることが示唆されたことになる。
また、モザンビークに集中していた降水量の増加により現地でのマラリア感染率が上昇し、モザンビークからマラリア感染者の南アフリカへの流入する割合が上がることが予想されるため、隣国からマラリア患者の流入を減らすことが重要だと対策であるとしている。
研究グループは今後、アプリケーションラボで開発された季節予測システム「SINTEX-F」で得られた気候変動の予測情報を用いて、機械学習をベースとしたマラリア発生率の予測モデルを開発し、リンポポ州におけるマラリア発生率がいつ、どこで、どの程度増えるかを予測していく予定。また、他の研究機関で開発されたマラリア発生率の予測モデルとともに、南部アフリカのマラリア早期警戒システムの構築を目指していくということだ。
今回使用した解析手法は、南部アフリカに限らず他の国や地域でも応用できる。また、マラリアだけではなく、蚊を媒介とするデング熱など他の感染症にも広く応用することができる。そのため、日本を含む世界の国と地域で、蚊を媒介とする感染症の変動要因の理解とその予測に貢献することが期待されると説明している。