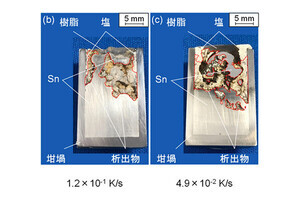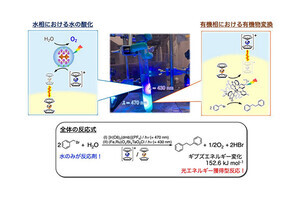虹は古来、多くの人々を魅了してきた。現代もなお新発見があったことに驚かされる。物質や人体を構成する原子核に虹が存在し、さらに副虹もあることを、大久保茂男・大阪大学核物理研究センター研究員(高知県立大学名誉教授)と平林義治・北海道大学情報基盤センター准教授が精緻な理論計算で明らかにした。原子核研究の新しい手がかりになる発見として、5月8日付の米物理学会誌フィジカルレビューに速報論文を発表した。
地上の虹と似た虹が極微の原子核の世界でも見えることは、米国のゴールドバーグらが1974年に実験で確かめ、大久保さんらが2004年までに、その仕組みと原子核の構造研究での意義を理論的に解明した。この虹は、日本人初のノーベル賞受賞者、湯川秀樹(1907~1981年)が解明した「強い核力」で、原子核への入射ビームの粒子が大きく曲げられる屈折だけで生じる。
通常の虹が水滴での屈折と反射によって生じるのに対して、反射回数がゼロのため、虹の仕組みを解明したニュートンにちなんで「ニュートンのゼロ次の虹」とも呼ばれる。また大久保さんは「湯川虹」と名付けた。この湯川虹には、地上の虹にあるような、2回の反射で起きてうっすら見える2番目の虹(副虹)はないと信じられてきた。
今回、研究グループはこの常識を覆し、原子核にも屈折のみで副虹が発生することを理論的に示した。酸素の原子核を炭素の原子核に高速の300メガ電子ボルトのエネルギーで衝突させた実験で、散乱角が70度付近の暗い縞模様の中にほのかに見えた明るい部分が副虹であることを証明した。
これまでは、虹をもたらす水滴に当たる炭素の原子核を球形とみなして計算してきた。今回、原子核がおむすびのように平べったい三角形で、回転や振動をしていることを取り入れ、原子核を構成する陽子や中性子の密度分布を精確に考慮した量子力学の精密計算で副虹の存在を導いた。
紀元前のアリストテレスから17世紀のデカルト、ニュートンに引き継がれた虹の研究で、屈折だけで2番目の副虹が生じることがわかったのは初めて。虹の研究史に残る発見でもある。
大久保さんは「10年以上かけて、原子核の虹の難問に挑み、副虹の存在に気づいて、ようやく解けた。われわれの精緻な計算によって、虹や副虹の存在だけでなく、酸素と炭素の原子核の間に働く力の謎も解け、原子核の反応や構造を研究する新しい道が開けた」と虹に夢を託している。