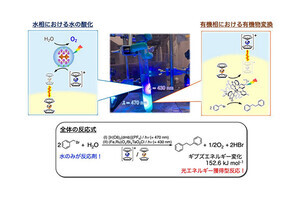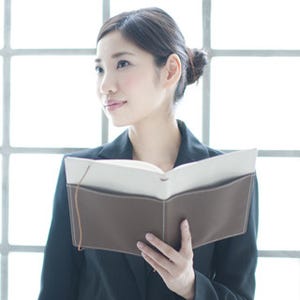西陣織や江戸切子、輪島塗など日本にはさまざまな伝統工芸品があります。手頃な日常品から行事で扱う特別な道具まで幅広く存在しますが、繊細な手わざが見える工芸品は海外でも話題。またおみやげとしても人気があるものです。
そこで今回は、日本在住の外国人20名に「日本の"伝統工芸(品)"で知っているもの」について聞いてみました。
■有田焼、備前焼、立杭焼、琉球グラス、小地谷縮、組紐、南部鉄瓶、石州瓦、熊野筆、備長炭。(シリア/30代前半/男性) ■薩摩焼、有田焼、薩摩切子、こけし、彫金、錦織など。(イタリア/30代後半/女性) ■瀬戸焼。(ポーランド/20代後半/女性)
有田焼をはじめ、瀬戸焼や備前焼、美濃焼など国内には多くの陶磁器の種類があります。釉薬や土の質、火の温度などの素材の掛け合わせが生み出す世界は、まさに日本ならではのもの。微妙な色や質感に興味を持つ人も多いようです。
■刀です。(インドネシア/30代後半/男性) ■刀。(スペイン/30代後半/男性) ■浄瑠璃人形、日本刀などいろいろ。(韓国/40代後半/男性) ■刀剣甲冑、七宝焼きなど。(スリランカ/60代後半/男性) ■日本人形などを知っています。(中国/30代前半/女性)
アニメやオタクといった新しい文化も知られてきた現在ですが、日本の印象で強いのは「侍」です。そのアイコンとも言える刀は、特に男性に人気。熱く熱した鉄が叩かれて美しい武器になる刀鍛冶の工程に驚く人も多いようです。そのほか、同時期の伝統装束やふるまいの美しさを残す浄瑠璃人形や日本人形などの名前も。
■浴衣、着物、けん玉、飾り玉。(オーストラリア/40代前半/男性) ■絹や機織り。(ブラジル/50代前半/女性) ■着物や下駄、扇子、浮世絵、お菓子。(ベトナム/30代前半/女性)
日本の伝統の代名詞とも言える着物も挙げられました。浅草や京都のお店では外国人向けの浴衣や下駄などもたくさん売られており、おみやげとしても人気の高いアイテムです。技の粋をこらした西陣織や友禅などをはじめとする織りや染めの実演は、見学コースとして男女問わず人気があるそうです。
■畳、水引、和箪笥、漆器。(イギリス/40代後半/男性) ■金沢に金箔と漆器を見に行ったことがあります。(フランス/30代後半/男性) ■鎌倉彫です。(ペルー/40代後半/男性)
行事ごとに使われる道具も外国人には珍しいもののひとつでしょう。漆器や水引などは、慶事の席やお茶席など風習に関連した場で使われるため、より興味深く感じられるのかもしれません。鎌倉彫は彫刻漆器の一種。現在は日用品として使われますが、仏具から茶道具へと受け継がれてきた側面から見れば、同じ出自にあるものと言えそうです。
■三味線、和紙作りなど。(スウェーデン/40代後半/女性) ■和紙やヘアピンなどが有名だと思います。和紙の作り方はとても興味深いです。(ロシア/20代後半/女性) ■和紙など。(ドイツ/30代後半/男性) ■和紙や漆喰など。(アメリカ/30代後半/男性)
最も多くの人が挙げていたのが和紙。千年は保つという強度がありながら、優雅さと繊細さを兼ね備える質感や表情の豊かさに惚れ込む人が多いそう。また、液体がいつの間にか紙になるという手すきによる製造工程も魅力的。注目度が高いのも頷けます。
日本が古来より育んできた伝統工芸品とそのわざ。しかし、今の私たちはそうした重要な存在を見過ごしてはいないでしょうか。外国人のみなさんの視点を介して改めて日本のよさに気づく。そんなことを感じるアンケートでした。