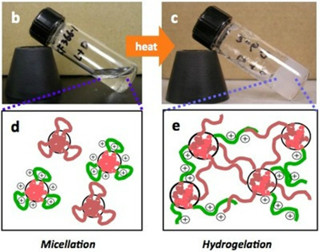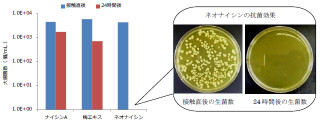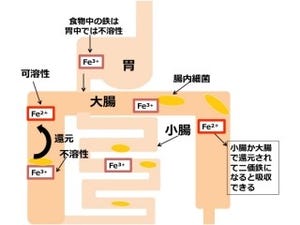東京工科大学は8月27日、抗生物質や合成抗菌剤が効かない「薬剤耐性細菌(耐性菌)」が、多摩川での現地調査から都市河川に多く存在することを確認したと発表した。
同成果は同大応用生物学部の浦瀬太郎教授らによるもので、詳細は2013年11月に開催される土木学会「環境工学研究フォーラム」において発表される予定だという。
抗生物質は、感染症治療に活用されてきたが、その過度の使用が耐性菌を発生させることが知られている。こうした話題は主に、病院内の問題として考えられきたが、、近年、院内感染とは無縁のはずの外来患者から基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌などが検出される例が報告されるようになってきており、その原因として、自然環境が「薬剤耐性化」していると考えられるようになっている。
今回、研究グループは、大半が無害だが、薬剤耐性が「プラスミド」に乗って容易に他の細菌に移っていく性質を持つ「大腸菌」を調査対象に、現在の感染症治療の主力となっている抗生物質に対する耐性菌を、2011年から2012年にかけて代表的な都市河川である多摩川をフィールドとして調査。
そうして得られた3452株の大腸菌のうち75株が第3世代セファロスポリン系の抗生物質が効かない細菌(ESBL産生菌と大きく重なるグループ)であることを突き止めた。また、秋川や高尾山など、水道水源としても使用される小河内ダム放流水にはほとんどこのタイプの耐性菌は存在しなかったが、中流以降では多く存在していることが判明したほか、75株のうち25%がフルオロキノロン系の多剤耐性大腸菌であり、病原化した場合には治療に手間のかかる性質のものであることも判明したという。
なお、研究グループは、今回の結果を受けて、水環境中の耐性菌問題は、医療面、下水処理などのインフラ面、河川環境管理など、複雑な問題が絡んでいるため、解決は容易ではないが、例えば、抗生物質の中でも切り札的な抗生物質については、使用用途を限定するなど、耐性菌の発生を抑制し、その抗生物質の有効性を温存することに社会が取り組む必要があるとコメントしている。