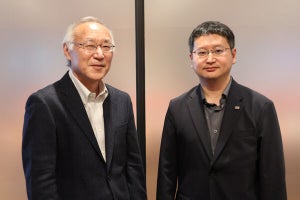Font for eveyone. |
Googleは「Open Standard Color Font Fun for Everyone」において絵文字を白黒ではなくカラーで表示できるようにするためのカラーフォントの標準化に向けた取り組みを進めていることを発表した。絵文字はもともと日本の携帯電話で頻繁に利用されるようになった文字表現のひとつで、Unicode 6.0に取り込まれてからは世界中で利用されるようになった。iOSやMac OS Xでは独自に拡張を実施しカラー表示を可能にしているが、Googleはこれを標準化し利用範囲を広げる取り組みを続けている。
GoogleはOpenTypeフォントに色データを追加できるようにする仕様を提案している。さらにフォントのレンダリングにおいて重要になるオープンソースソフトウェアのいくつか(freetype2、skia、cairo)に対して実装を提供しており、カラーフォントを表示するための準備を進めている。
カラー情報を埋め込んだフォントは、たとえば絵文字をカラフルに表現するといった目的以外にも、Webページの高速配信やWebデザイン上の利点が存在する。Webブラウザのレンダリングにはベクトルデータのフォントが活用されている。ベクトルデータはビットマップデータと異なり、サイズを大きくしても表示が汚くなるといったことがない。また、大きなサイズで表示させてもデータそのもののサイズが増えるといったこともない。
このため、色データを含んだフォントデータをうまく活用すると、配布するデータサイズを抑えながらも、表現力が高くさまざまなデバイスに対しても表示が綺麗にスケールする(レスポンシブWebデザイン)ページを制作しやすくなる。現在のフォントでは単色での表現が基本となるため、どうしてもデザインは単色での構成になりやすい。色データをフォントデータそのものに仕込めるようになると、デザインの表現の幅を大きく広げられるようになる。色データを含んだフォントに関しては互換性などの面で課題もあるが、仕様の標準化と実装の普及が期待される分野でもある。