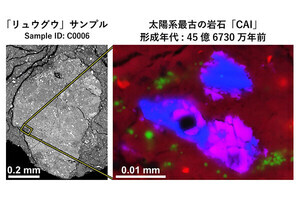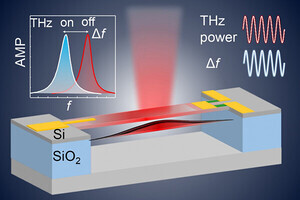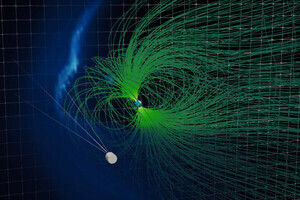「iPS細胞(人工多能性幹細胞)の移植によって、拒絶反応が起きた」とする米国研究チームの実験報告に対し、放射線医学総合研究所の荒木良子・遺伝子・細胞情報研究室長や鶴見大学歯学部などの日本の研究チームは同様な実験を行い「絶反応は起きない」とする反論をまとめた。論文は英科学誌「ネイチャー」(10日、オンライン版)に掲載された。
自分の体細胞から作ったiPS細胞や受精卵を使うES細胞(胚性幹細胞)の利用により、拒絶反応のない再生医療の実現が期待されている。ところが、米カリフォルニア大学サンディエゴ校のチームは2011年5月、マウスのiPS細胞を元のマウスに移植したときに“異物”として認識されて、リンパ球による免疫反応が誘導され、ES細胞ではそのような現象は観察されなかったとの結果を、ネイチャー誌に発表した。
しかし同チームの実験ではES細胞が1株しか用いられず、さらに、実際の医療ではiPS細胞から分化させた細胞を移植するにも関わらず、iPS細胞そのものを移植したことなど、実験手法の問題点が指摘されていた。iPS細胞・ES細胞を移植すると「奇形腫」という腫瘍が形成されるおそれがあるという。
荒木室長らのチームは、米国チームによる研究と同様に、奇形腫形成率を比較した。iPS細胞7株とES細胞5株を用いて、同系統のマウスの皮下に10回ずつ未分化の細胞を移植し、腫瘍の出現頻度、出現した場合は腫瘍の大きさの変化を調べたところ、iPS細胞とES細胞に有意な差は見られなかった(出現頻度はiPS細胞82.9±2.9%、ES細胞74.0±5.1%)。また、移植による免疫反応を確認するために、腫瘍に集まるリンパ球を定量的に解析した。iPS細胞、ES細胞ともにリンパ球による免疫反応はほとんど誘導されず、生じても極めて軽微だった。このことは、米国チームの研究結果とは異なり、iPS細胞とES細胞に対する免疫反応に差がないことを示す。
米国チームはさらに、iPS細胞やES細胞の移植に伴い、拒絶反応を受けて縮小しているような奇形腫や皮膚組織が観察され、それらの組織では免疫反応の原因となる「Hormad1」や「Zg16」という遺伝子が異常に活性化しているとのデータを示していたが、荒木室長らのチームによる解析では、自家移植した組織において、これらの遺伝子の活性化はほとんど検出できなかったという。
荒木室長らは「iPS細胞も、自家移植の場合に拒絶反応を考慮する必要がないことが示され、臨床応用の前提条件が確認できた」と話している。
|
関連記事 |