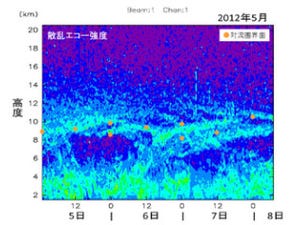北海道大学(北大)、琉球大学、山形大学、国立極地研究所(極地研)の4者は10月4日、アイスコア(氷床コア)に保存されていた大気中に浮遊する微粒子「水溶性エアロゾル」を1粒ごとに観察する手法を開発し、同手法を用いて南極で採取された「ドームふじアイスコア」に含まれる「硫酸塩エアロゾル」を測定したところ、過去30万年間の「氷期-間氷期サイクル」において、「硫酸塩フラックス」と気温の指標(酸素同位体比)の間に逆相関(気温が低い氷期に硫酸塩フラックスが大きい)が見られたことを発表した。
また、同時に、今回の事実が、硫酸塩フラックスが大きい時代は、エアロゾルの間接効果が気温低下をもたらしていることを示唆し、南極で約8℃の変化と考えられている最終氷期最盛期(約2万年前)から現在の間氷期(現在~約1万年前の温暖期)への気温変動の内、硫酸塩エアロゾルの間接効果による寄与は最大で5℃と見積られ、硫酸塩エアロゾルが氷期-間氷期の気温変動に寄与したことを解明したとも発表した。
今回の成果は、北大 低温科学研究所の飯塚芳徳 助教、北大理事・副学長の本堂武夫教授、琉球大の植村立 助教、極地研の本山秀明教授、同・三宅隆之氏(現:滋賀県立大学研究員)、同・平林幹啓 特任研究員、山形大の鈴木利孝教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、10月4日付けで英国科学誌「Nature」に掲載された。
南極のアイスコア(画像1)には、過去数十万年分の気温変動や二酸化炭素などの温室効果ガスといった環境指標が保存されている。ドームふじアイスコアは日本が所有しているそうしたアイスコアの1つで、1995年から1997年にかけて極地研が中心となって行った「南極氷床ドームふじ深層掘削プロジェクト」によって採取されたものだ。今回の研究で測定したアイスコアは長さ2503mに及ぶ。
エアロゾルは、地球の気温変動に大きな影響を及ぼす要素の大気中に浮遊する微粒子だ(画像2)。その1つとして、エアロゾルが雲の凝結核となり、雲の発生量を増加させるといった作用がある。雲は太陽光を跳ね返し、気温を下げる働き(グローバル・ディミング)をするのだ。
画像2は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)で報告された、産業革命前(人為的な温暖化傾向以前)の気温と比較した、最終氷期最盛期(約2万年前)の気温低下の要因とその科学的理解度(2007年時)。
右から2列目の棒グラフはエアロゾルが気温変化に与える寄与であり、気温変化に対して第3の要因であるにも関わらず、その科学的理解は低いままであった(出典:気候変動に関する政府間パネル第一作業部会第四次評価報告書「気候変動の物理科学的根拠」)。
南極のアイスコアに含まれる硫酸エアロゾルには、液体の硫酸(H2SO4)と、それよりも間接効果により放射強制力が大きい固体の硫酸塩(Na2SO4、CaSO4)が含まれている。
これまでの研究では、アイスコア中の硫酸エアロゾルはこれらの成分を分離せずに測定していたために、氷期-間氷期スケールの放射強制力(気温変化)への影響は小さいと考えられてきた(画像3・4)。
画像3と4は、従来の解釈である硫酸イオンフラックス(黒)と今回明らかとなった硫酸塩フラックス(青)の氷期- 間氷期の気温変化との関係。硫酸イオンフラックス(黒)は気温に無相関であるが、硫酸塩フラックス(青)は気温と逆相関であることがわかる。
他方で、地球と生物が相互に関係し合い環境を作り上げているとする「ガイア仮説」があり、海洋生物活動によって増減する大気中の硫酸エアロゾルが気候を支配するというガイア仮説の1つである「CLAW仮説」の検証が求められていた。
CLAW仮説とは、海洋生物活動が活発になることで大気中に放出される硫酸エアロゾルが増え、それが気温を低下させ、その結果、寒冷化が生物活動を抑制するという、ある変化に対してその変化を抑制する方向に作用する「負のフィードバック」によって、生物活動が気候変動を安定化させるという説だ。
南極のアイスコアに含まれる硫酸エアロゾルのほぼすべては、南大洋の海洋生物(植物プランクトン)活動によってもたらされる。南大洋は生物生産が活発な地域の1つであり、南極のアイスコアに含まれる硫酸エアロゾル変動は「CLAW仮説」の検証に適した指標だ。
今回の研究では、氷に含まれる硫酸塩(Na2SO4、CaSO4)粒子(画像5)を測定する手法が開発された。氷を低温のまま昇華させ、残留した微粒子を「エネルギー分散X線分光法(Energy dispersive X-ray spectrometry:EDS)」で測定するというものだ。
同手法を用いて、南極ドームふじアイスコアに含まれる硫酸塩エアロゾルを測定し、過去30万年間の硫酸塩の存在割合を得た。その存在割合をもとに、過去30万年間の硫酸塩フラックスを復元した。
画像5は、今回開発された手法で観察したエアロゾル微粒子の「冷陰極電界放射型走査電子顕微鏡」写真。背景の黒い丸は微粒子を載せているフィルターの穴である。研究グループが北大量子集積エレクトロニクス研究センター 福井研究室の協力を得て撮影した。
この結果、過去30万年間の硫酸イオンおよび硫酸塩エアロゾルのフラックスと、気温の指標(酸素同位体比)の間の相関に明らかな違いが見出された(画像3・4)。従来の指標であった硫酸イオンのフラックスは気温と相関がないのに対して(画像3)、固体の硫酸塩エアロゾルのフラックスには負の相関が見られた(画像4)。
すなわち、海洋生物(植物プランクトン)に由来する硫酸エアロゾルと気温変動にはカップリングは認められないにも関わらず、硫酸エアロゾルから生成される硫酸塩エアロゾルと気温変動には明確なカップリングがあることが示された形だ。
寒冷期に硫酸塩エアロゾルが多いという結果は、硫酸塩エアロゾルが寒冷化を増幅していること(正のフィードバック)を示唆するものだ。この結果は、CLAW仮説が提唱する、寒冷化に伴って硫酸エアロゾルが少なくなることで、寒冷化を抑制するというプロセスが成り立っていないことを示す。そうなると、今度は硫酸イオンのフラックスに変動がないのに、硫酸塩エアロゾルのフラックスが気温と明らかな負の相関を持つことに対する疑問が湧く。
少なくとも、気温が高い間、硫酸塩エアロゾルの生成量は、大気中の海塩の量に依存する。そのため、大気中に放出される海塩の量が増加することが、硫酸塩エアロゾルの生成量増加のカギと考えられるという。
すなわち、画像4の負の相関は、CLAW仮説が想定するような生物系と物理系の相互作用の結果ではなく、海塩の量という大気海洋物理学的な作用の結果と考えることができるというわけだ。
過去30万年間の硫酸塩フラックスと気温の逆相関は、硫酸塩フラックスが大きい時にエアロゾルの間接効果による負の放射強制力が強まり、硫酸塩が気温低下に寄与していることを示唆する。
その結果、南極で約8℃の変化と考えられている最終氷期最盛期(約2万年前)から現在の間氷期(現在~約1万年前の温暖期)にかけての気温変動の内、硫酸塩エアロゾルの間接効果による寄与は概算で0.1~5℃と見積られた。
将来の地球温暖化に対するエアロゾルの間接効果による放射強制力の算出は不確実性が最も高く、影響評価の定量化に向けて活発な研究が行われているところだ。
1950年から数10年にわたって、二酸化炭素濃度は上昇しているのに、気温が低下した時期があり、エアロゾル(大気汚染)によるグローバル・ディミング(地球薄暮化)だという説もある。今回の成果は、人間活動の影響のない氷期-間氷期変動において、大気中のエアロゾルが気温変動に寄与していたことを示すはじめての結果となった。
過去数10万年の気候変動については、気温や二酸化炭素濃度などの変動が明らかになりつつあり、今回の研究も硫酸塩エアロゾルの変動という新たな知見を提供した形だ。これは、過去の大規模な気候変動が起こった際のメカニズムを理解することにつながり、将来の気候変動をコンピュータで予測する際の精度向上にもつながると期待されると、研究グループは述べている。