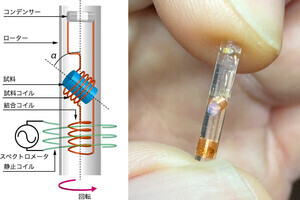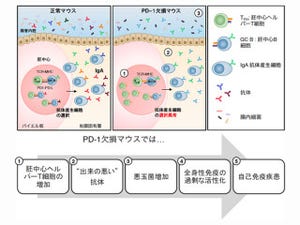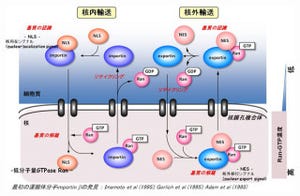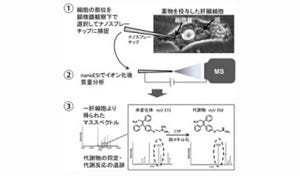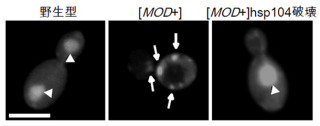理化学研究所(理研)は、不整脈の中で最も頻度の高い心房細動発症に関わる遺伝子の発見を目的とした国際共同研究グループ「心房細動ゲノム解析研究コンソーシアム(AFGen consortium)」に、文部科学省委託事業「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」の一環として、東京医科歯科大学と参画し、欧米人集団と日本人集団を対象としたゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施。その結果、欧米人集団では発症に関わる6個の新規遺伝子を同定するとともに、欧米人の既知の関連遺伝子3個と合わせた9個のうち、4個が日本人にも共通して関連することを突き止めた。同成果は、理研ゲノム医科学研究センター 疾患関連遺伝子研究グループ循環器疾患研究チームの田中敏博チームリーダー(副センター長兼務)、尾崎浩一上級研究員らの研究グループによるもので、科学雑誌「Nature Genetics」オンライン版に掲載された。
心房細動は、心房に負荷がかかっている状態で発症しやすいと知られている、そのような負荷が無くても頻繁に発症し、これまでの疫学的研究から、遺伝的要因の関与が知られていた。2007年以降、欧米人に関して3個の関連遺伝子(PITX2、ZFHX3、KCNN3)が報告されていたが、これまでに日本人集団を含めた大規模解析は行われておらず、欧米で同定されている遺伝子が日本人の心房細動に関連するか、あるいは新規の関連遺伝子があるかどうかは不明であった。
今回、研究グループは、まず国際共同研究グループ「心房細動ゲノム解析研究コンソーシアム(AFGen consortium)」の欧米人集団から得られた6,707人の心房細動患者と52,426人のコントロール集団のデータを用いて、ヒトゲノム全体に分布する約261万個のSNPと心房細動との関連を調べる大規模ゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施した。
この解析により3個の既知遺伝子(PITX2、ZFHX3、KCNN3)を含む10個の遺伝子領域が心房細動に関連することを確認。次に、この解析結果を異なる欧米人集団(患者5,381人、コントロール集団10,030人)で検証した結果、6個の新規遺伝子(PRRX1, CAV1, C9orf3, SYNPO2L, SYNE2, HCN4)が、欧米人の心房細動発症に関連することを突き止めた。さらに、これらの結果を日本人集団(患者843人、コントロール集団3,350人)を対象にしたGWAS結果と照合した結果、日本人と欧米人に共通した4個の関連遺伝子(PITX2、PRRX1、CAV1、ZFHX3)を同定した。
興味深いことに、これら4個の遺伝子のうちPITX2、PRRX1、ZFHX3が作るタンパク質構造には、生物の発生段階で機能する転写因子が持つホメオボックスドメインと同様な構造が存在し、これらの分子が類似した機能を持つ可能性が示された。またPITX2は、心臓の電気刺激に関連する遺伝子の転写を司ることや、この遺伝子の機能を抑えたマウスでは不整脈を発症することが報告されている。一方のPRRX1、ZFHX3やCAV1の心臓での機能についてはあまり分かっていないが、これらの分子は機能的に相互作用すると考えられるという。
なお研究グループでは今後、同定した遺伝子を対象に研究を進めていくことで、心房細動の原因解明が進むことが期待できるとするほか、これら遺伝子上のSNPを用いた疾患リスクの予測など、個々人に合わせたオーダーメイド医療への応用への期待できるとしている。