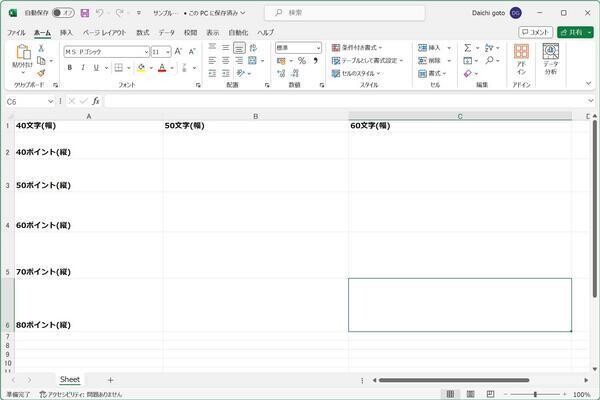新たなメディア環境の整備が、総務省と経済産業省の手で進められている。新しい世界にNHKや民放は、どのように適応してゆこうとしているのだろう。
いま、民放テレビ業界の前には三つの壁が立ちはだかっている。
民放による下請けへの制作費カット、総務省が調査開始
第一が、番組制作会社との契約関係の見直し問題。これは著作権の扱いと、それに関連する「ソフトとハードの分離」にも発展しかねない。第二は本格的多チャンネル時代への対応。最後がIT社会への適応不全症である。
昨年から総務省がテレビ業界への「請負業法」適用のためヒアリングを始めたことに、関係者は神経をとがらせている。これまで業界の高収益体質は、市場を民放五系列で独占してきたこと、番組制作を下請けの製作会社に「投げてコストを叩いてきた」ことに支えられてきた。
昨年からの不況で、下請けへの制作費を突然、50%カットするなど目に余る動きが出てきたため、総務省も重い腰を上げた。
具体的には、番組制作についての放送局と制作会社との間の契約の有無(これまでは、ほとんどが口約束で記録すらなかったという)や、局が制作費を、どの程度"中抜き"しているのか――などを調査している。
制作会社への著作権の譲渡範囲拡大は、民放にとって"悪夢"
一方で人気タレントを抱えたプロダクションとテレビ局の力関係は"逆転"していて、いかにもいびつだ。いずれにしても、「経営内容も商慣行も、あまりに前近代的で改善は急務」というのが経産省幹部の感想だ。
同省では昨年暮れ、不況対策の一環として番組制作会社に信用保証協会の保証が受けられるよう作業してみたが、多くの会社に「売上高」「経費」など、経営の基礎的データがなく適用できなかったという。同じ時期に、零細・中小出版社、新聞販売店には適用されたのだから、この業界がいかに多くの問題を抱えているかが分かる。
テレビ局と番組制作会社の契約関係を見直し業界の近代化を図ることは、著作権の扱いにも発展する。
現在、ニュース報道番組を含めてテレビ局の放送番組で制作会社が関与していないものは皆無と言っていいだろう。ドキュメンタリー番組など制作プロダクションが完成品の形で放送局に納入した作品については、すでに「全著作権、あるいは共同著作権をもらっている」(全日本テレビ番組製作社連盟)という。
この範囲が広がることは、放送局側にとっての"悪夢"である。何故なら、本業が天井を打った感のある放送局側にとって、頼りの放送外収入は、番組の映画化、CD化、出版などの売上だからである。
フジ・メディア・ホールディングスの日枝久会長は、昨年の認定持ち株会社発足に当たり、「速やかに放送外収入比率を、五割程度にしたい」と表明している。この目算が根底から狂ってくる。
「ソフトとハードの分離」問題に発展する可能性
著作権問題は、扱いによっては米国で1950年代に確立された「ソフトとハードの分離」に発展しかねない。
米連邦通信委員会(FCC)は、ハリウッドの映画産業がテレビに押されて衰退するのを防ぐため、NBC、ABC、CBSの三大ネットワークから、コンテンツ制作を切り離した(フェンシン・ルール)。
三大ネットワークは、ニュース番組制作を除き、全米の系列ローカル局に番組を配信するネットワーキング業務に特化したのだ。一方でハリウッドは、映画制作の経験から、コンテンツ二次利用のノウハウがあるので、日本で問題になるような、「原作者、脚本家、出演者のすべてを回り許諾を得る」という厄介な作業がない。
日本も五つの在京局がネットワーク業務をしているように見えるが、これはニュース協定が発展したもので、法律的には、関東ローカル局が便宜的にやっているものにすぎない。それだけに、「在京局には分離すべきハードなどない。あえて言うなら免許だけだ」というのが総務省の見方である。
コンテンツの制作、二次利用の権利も手放したくない。ところが、ほとんどのコンテンツ(ソフト)は制作会社に作らせている――というゆがんだ関係を、どのように"整形"してゆくのかが問われる。
破綻しかねない「広告で稼いで無料で番組提供」のモデル
本格的な多チャンネル時代への対応も大変だ。総務省は、2009年6月頃までに、新たに12~20局のBS放送免許を割り当てる予定。すでにディズニー、米NBC、住友商事のジェイコムなど、53社(2008年11月現在)が手を挙げている。
これまでは、BSといえど新規免許はキー局の系列で抑えて「護送船団方式」を守ってきた。しかし、前回の認可でビックカメラ資本のBS11、三井物産資本のBS12が参入、消費者の選択肢は増え、逆に一局あたりのパイは、次第に小さくなる傾向にある。
IT時代への対応はさらに難しい。ワンセグ放送であるとかNHKやフジも始めたコンテンツのインターネット配信は、「終わりの始まり」にすぎない。最大の問題は近い将来、国民の共通情報端末が「次世代携帯になる」ということなのだ。そこでは、国民が自ら検索し、コンテンツを選ぶ時代となる。
つまり、「広告収入で稼いで無料で番組を提供する」という、これまでの民放ビジネスモデルが破たんしかねないのだ。
執筆者プロフィール
河内 孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。著書に「新聞社 破綻したビジネスモデル(新潮新書)」、「YouTube民主主義(マイコミ新書)」がある。