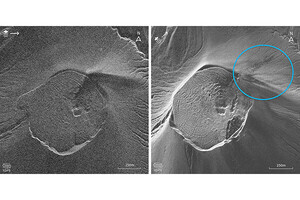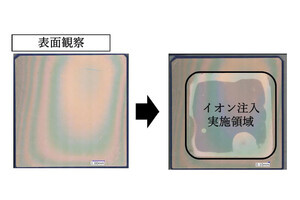富士通、東北大学災害科学国際研究所、東京大学地震研究所、川崎市の4者は24日、11月17日に実施される川崎市津波避難訓練において、津波避難におけるAI活用の実証実験を行うことを発表した。
富士通ら4者は、2017年11月より「川崎臨海部におけるICT活用による津波被害軽減に向けた共同プロジェクト」を進めており、今回の実証実験はその一環として実施するもので、2018年12月に実施した津波避難におけるICT活用の実証実験に続く第二弾となる。
同プロジェクトでは現在、地震発生後に時々刻々と入手される情報を基に、現在位置の浸水可能性を判定するAIを構築し、AIによる判定結果を各個人のスマホ画面に表示することで、避難を後押しするスマホアプリを開発しているという。
今回の実証実験では、住民がスマホアプリ(試作版)を利用した避難訓練を体験することで、スマホを通して提供された災害情報が避難行動に与える影響や、効果的な情報提供手段のあり方について検討するという。
この実証実験で得られたデータや知見を、ICTを活用した防災対策の検討に活かすことで、国内外の地域防災力の強化に貢献するとしている。
実証実験の日時は、11月17日 9:00〜12:00(川崎市津波避難訓練・川崎区総合防災訓練と同時開催)、場所は川崎市立四谷小学校及び周辺地域。参加者は80名を予定している。
神奈川県が設定した「慶長型地震モデル」による津波を想定し、浸水可能性を判定するAIと避難を後押しするスマホアプリの有効性を確認。避難訓練後には防災講座を実施し、実証参加者と当日の避難行動を振り返る予定となっている。