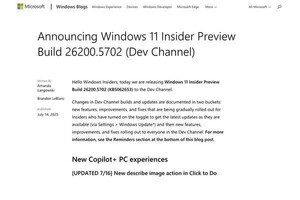日清紡HDの事業変革
かつて、日本の〝十大紡績〟の中心的立場にあり、繊維・日本の発展を支えてきた日清紡ホールディングス(創業1907年=明治40年)。
同社は、綿紡績の名門とされ、戦後の復興期から高度成長期にかけて、同社を牽引した桜田武氏(1904年―1985年)は日経連(日本経営者団体連盟、現経団連)会長も務めた財界リーダー。
桜田氏は、永野重雄(元日本商工会議所会頭)、小林中(日本航空会長、東急電鉄社長などを歴任)、水野成夫(元国策パルプ工業、産経新聞社長)と共に〝財界四天王〟と呼ばれ、労使間の正常な関係構築に尽力した。
そうした人物を輩出した日清紡ホールディングスが時代の変化に対応して、新事業構造の構築を推し進めている。現在、無線・通信、半導体材料、精密機器などが同社の主力事業で、ブレーキ摩擦材、繊維事業は今や全体の7%しかない。
2019年から今年3月まで社長を務め、事業ポートフォリオ変革を進めてきた村上雅洋さん(1958年生まれ、現会長)が語る。
「2006~7年頃、当時、強烈な危機感がありました。このままじゃ、この会社の将来はないよねというのが、わたしが秘書をやっている時の社長の意見でした」
危機感が、事業構造を変革させる原動力になったという村上さんの指摘。
企業は社会の公器
企業は社会の公器と言われる。新事業領域を開拓する場合、「まさに企業は公器で、公のものです。だから世の中に貢献するような事業をしなければ」と村上さん。
日本国内はこの『企業は社会の公器』で納得してもらえるが、海外の関係者に説明する時は一工夫が要ると村上さんは語る。
「プライベートな会社がなぜ、パブリックなんだと。企業は民間だろうとか散々言われましてね」
結局、ESG(環境、持続性、統治)などの概念や考え方で説明し、納得してもらったという。グローバル化の中では、丁寧な対話と相互理解が必要だという村上さんである。