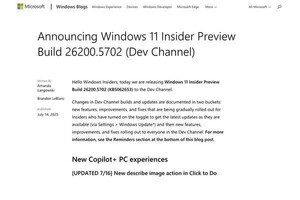いずれの社長も、多かれ少なかれ、答えのない危機に直面した経験をお持ちである。
以前この連載でご紹介したタビオの越智直正さんも、倒産の危機に直面されたと聞いた。販売を委託していた先から取引停止を宣告され、生産した靴下の返品を受け、売り先もない状態になり、会社の負債を返すために、道路脇に立ち、走るダンプに向かって身を投げようと思ったそうだ。
『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「靴下にかけた人生」
しかし、いざ身を投げようと思った時に、「いや。まだ何かできることがあるかもしれない」とふと思いとどまり、ある人に電話をしたところ、その場で、売り先が決まったそうだ。この時を振り返り、越知さんは、「神様は乗り越えられない試練は与えない」と思ったそうだ。
また、北海道のホワイトチョコレートで有名な六花亭が、花畑牧場の急速な人気上昇で、売り上げが激減した際の当時の社長の小田豊さんは、連日稼働していた工場を週3日停止させる決断をされた。
しかし、業績は一向に回復することなく、結局、再び社員に毎日会社に出社するように呼びかけ、会社の現状と苦悩を伝えたそうだ。その結果、社員から新たな販売アイデアが提案され、1年経たずして、従来の業績を回復した。
この時を振り返った小田さんは、「これまでも社員を信じていると思っていたけれど、今回の一件で、これまでは、心の底から社員を信じていなかったのかもしれない」とおっしゃった。
社長の最も大きな責任は、決断することだ。決断をしなければ、会社が存続できなくなる。ナンバー2と社長の違いは、この決断に対する責任の差であり、その差は果てしなく大きい。
決断を誤れば、会社を失うかもしれない。それ以上に、社員たちを路頭に迷わせることになるかもしれない。その責任が社長ひとりの肩にのし掛かる。
「いざという時は自己破産すればいい」と言う人もいるが、そんな簡単なものではない。借金を棒引きしてもらって、社長が負担する経済的負担は消えても、一緒に働いてきた仲間たちの生活や人生への責任「感」は消えない。日々、それを感じながら、社長たちは命をかけて経営をしている。
社長のもう一つの大きな役割は、未来を指し示すことだ。それは、ある意味、社長自身の夢でもある。だからこそ、その夢を一緒に実現してくれる仲間へ責任感が決断する力を与え、仲間への感謝が決断を成功へと導き、度重なる試練にも乗り越えられる自信を与えてくれる。
これは逆も真なりで、社員を軽んじたり、馬鹿にしたり、兵隊のように扱う社長の会社は、危機に弱い。