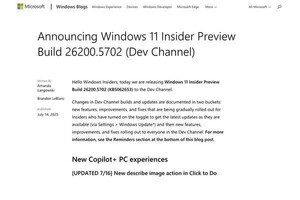混沌とした状況下 問題の落とし所を探る
「今は世界中が混沌とし、デカップリング(分断)の時代だと言う人もいますが、そういう事はもう出来ない時代だと思うんです。互いに、それほどまで深く関わり合っていると」
東レ会長・日覺昭葊氏(1949年=昭和24年1月生まれ)はこう語り、1980年代末まで米国と旧ソ連の両大国の対立が続いた〝冷戦時代〟とは違う現在の米国と中国の関係について次のように述べる。
「実際に米中間の貿易は伸びているし、米国も安全保障関連は除いて中国のモノを買っているし、中国もやはり米国の生産物、農産物を買っているわけですから。そういった点もあるので、米中両国とも、どう言い合おうとも、落し所があるというのを考えているのだと思います」
確かに、『米国ファースト』を掲げ、自国第一主義を旗降るトランプ米大統領は高関税を口にする。隣国のカナダ、メキシコからの輸入品に25%の高関税をかけるとしながら、「実施は1カ月延期する」と表明。ディール(取引)の展開次第によっては、妥協点があるという姿勢を示す。
日覺氏にインタビューしたのは、今年1月下旬、トランプ氏が大統領に返り咲き、正式に就任した直後の事。日米首脳会談(2月7日)の直前で、日本製鉄によるUSスチール買収問題もあり、まさに混沌とした状況下であった。
落し所を探る─。国益を追求するのは、どの国の政治も同じ。ただ、この世界にあって、どの国も単独では生きてはいけない。そこで通商、外交面での交渉、ディール(取引)ということになる。
件のUSスチールの件でも、バイデン・前大統領は離任直前の今年1月、日本製鉄による買収を「絶対阻止」する姿勢を公表したばかり。トランプ大統領もこれまで断固阻止の姿勢であったが、2月7日の石破茂首相との会談で、「日本製鉄の買収ではなく、投資ならば……」という姿勢に転換。
USスチール問題は第2幕にステージが移り、決着は今後のディール次第ということになった。
こうした混沌とした状況に、今後わたしたちはどう向き合っていくべきか─。
「そうですね、いわゆるウィン・ウィン(Win-Win)の関係をつくっていく事が大事ではないかと僕は思います」
日覺氏は、「一方的に自分の利益だけを主張するという事は、それこそ相手が反発する事になってしまい、関係がおかしくなる」として、「譲るべきは譲ると。お互いにそういう面は持っていると思うんです」と語る。
高関税、不法移民対策が 今後、世界に与える影響
問題の本質は何かということを冷静に見極めることが今は大事。トランプ大統領はタリフ(Tariff、関税)マンと言われ、とにかく外国からの輸入品に関税をかけて、自国産業を守ろうとする。しかし、それが本当に米国民のプラスになるのかどうかということである。
「最終的に、そのツケを払うのはアメリカ国民なので、インフレ要因になり、逆に景気も悪くなると。そういう状況になりそうになったら、彼は恐らくブレーキを踏むと思うんですが」
米国を含め、それぞれの国がそれぞれの課題を抱える。要は、その課題解決に向けて、どのようなスタンス(基本姿勢)で対応していくかということである。
貿易摩擦を経験して 始まった対米投資だが…
日米間では長い間、通商面で貿易摩擦という問題を抱えてきた。今のトランプ政権は『貿易収支赤字』を憂慮し、関税を武器に国際産業保護を声高に打ち出すが、過去を振り返っても、米国は日本に通商・貿易面で圧力をかけ続けてきた。
その端的なものが、日米繊維交渉。戦後の復興期から1960年代、70年代初めの高度成長期にかけて、日本の繊維産業は輸出に注力し、外貨を稼いだ。日本製品は、品質が良く、かつ安いということで人気があった。
米国の視点で見ると、米国内の繊維業者は輸入品に押されて、衰退の道をたどり、繊維輸出国・日本に対する不満が募っていった。
それが頂点に達したのが、1972年の日米繊維交渉であった。時の佐藤栄作政権下、米ニクソン政権との交渉に当たった田中角栄・通産大臣(現経産大臣、その後首相に就任)は、強く自国の主張をするも、輸出割当制を呑まされることになった。
これにより日本国内の中小の繊維業者が倒産や休業に追い込まれるのを防ぐために、日本政府は財政支援を余儀なくされた。
この日米繊維交渉は鉄鋼や、電気・自動車の通商交渉へとつながり、日米構造協議にまで発展。
こうした交渉、協議を経て、多くの日本企業は、輸出という形ではなく、直接、米国に投資、生産拠点(工場)を作り、米国内の需要に応え、同国内の雇用増にも貢献するという形で、市場開拓を進めてきた。
米国の製造業衰退は 背景に…
トランプ政権が高関税政策を取ろうとする背景には、米国の製造業が衰退してきているという現状がある。
米国ではインフレ高進もあって、国内での製造コストが高くなり、賃金などの安い隣国のメキシコやカナダに生産拠点を構え、米国に輸出したほうがコストが抑えられるとして、日本の自動車メーカーなどは長年、そうした生産体制を取ってきた。
そこへ、トランプ政権がメキシコ、カナダからの輸入品に高関税をかけると表明。実施時期は1カ月延期するということだが、高関税が実施されれば、日本企業への影響も少なくない。また、メキシコ、カナダ両国は〝報復関税〟をちらつかせており、緊張感が漂う。
東レは航空機の有力素材である炭素繊維の最大メーカーであり、ボーイング社など航空機メーカーがある米国との縁は深い。東レが同国内での炭素繊維事業を展開するにあたって、今、関税問題とは別に、航空機メーカーの〝内部事情〟の影響も受けている。
コロナ禍が明けたら 航空機産業は人手不足に
パンデミック(感染症の世界的大流行)となったコロナ禍で、世界的に人の往来が〝蒸発〟し、特に航空業界、ひいては航空機製造産業は大打撃を受けた。
米ボーイング、欧州のエアバスなど、大手航空機メーカーは受注がパタリと止まり、完全休業状態に追い込まれた。
待っていたのは、従業員の解雇。欧米企業は日本企業と違って、景気の変動に合わせて、雇用停止、レイオフ(一時帰休)など、ドラスティックな動きに出る。
日本の企業は概して、厳しい経営環境にあっても、何とか雇用を維持しようとする。
2023年前半、コロナ禍が明けてみると、人の往来も復活し、航空需要は急増。日本へのインバウンド(訪日観光客)数も、2024年は約3477万人となり、コロナ禍前の最高記録約3188万人(2019)を大きく上回っている。
今年(2025年)は3600万人以上のインバウンドが見込まれている。これだけ人の往来が多くなると、人を運ぶ航空機への需要も高まるので、航空機産業も潤うだろうと思われるのだが、現実はそうなっていない。
なぜ、そうなのか?
コロナ禍で、米ボーイングや欧州エアバスなどの航空機メーカーは一斉に人員整理に動いた。
前述のように人的態勢をドラスティックに変化させる欧米の企業は、好景気の時は人員増に動き、不景気を迎えれば即、人員削減に打って出る。
経営を維持するために、徹底した人員削減に動くのだが、一旦削減すると、好況期を迎えて人員を採用しようとしても、専門人材はすぐには集まらない。
これによる打撃は大きく、欧米の航空機メーカーが、コロナ禍が明けた今もなお、元に戻れずにいる背景には、こうした雇用事情がある。
世界的な炭素繊維メーカーの東レ自身は、いつでも炭素繊維を増産できる態勢にあるが、大口納入先である欧米航空機メーカーの態勢が整っていない。今は、もどかしい状況が続く。
人の雇用に対する 欧米と日本の考え方の違い
「航空機産業は自動車産業と比べても、供給網が大きい。だから、それを隅々まで見ると、早い話が一つの部品が入らなくても、飛行機を組み立てられないわけなんです」と日覺氏。
飛行機を組み立てるのに必要な部品は約300万点と言われる。自動車の約3万点と比べても、ケタ外れに部品が多い。安全・安心を最も求められる業種の一つ、航空機の製造に、一つでも部品が揃わないと航空機は組み立てられない。
「彼ら(航空機メーカー)にとってみたら当たり前、コロナ禍で2020年にはもう航空機需要がゼロになってしまった。だから従業員は要らないということで、削減に動いてしまった」
日覺氏は日米企業の行動様式の違いに触れながら語る。 「日本の場合は仮に需要が無くなったら、他の所に出向させるとか、いろいろな手を打ちながら雇用を守るじゃないですか。そうすると(イザという時に)垂直的に立ち上げができる。人材を切ってしまうと、今度戻るのに10年はかかるということをずっと言ってきたんです」
経営の在り方、もっと言えば、経営の根本思想の違いで、共同歩調が取れなくなっている。
航空機製造の現場にしろ、空港の作業現場にしろ、欧米は専門職の人材の整理・削減をしたために、様々なトラブルや障害が起きている。
ヨーロッパの空港でも、旅客は戻ってきたものの、トランジット(乗り継ぎ)で荷物が中継できないというトラブルが頻発。
コロナ禍で削減した人員を穴埋めするために、人材を急遽採用しても、スタッフが扱いに不慣れなため、トラブルが起こっているということ。
では、製造現場はどうか? 「だから部品を作っているTier1(ティア・ワン)などは数さえ揃えればいいというものではなく、やはり現場にベテランのワーカーがいなくなってしまうと、効率が落ちるということです。今、ボーイングもエアバスもなかなか飛行機を作れない。もう需要はいっぱいあるというのにですね」
Tier(ティア)は、産業の深層を表す言葉。自動車や航空機などの製造業で〝一次請け〟という意味で使われる。Tier1のプレーヤーは重要な部品を最終製品メーカーに供給するポジションにある。
炭素繊維という軽くて、堅固な航空部材を開発してきた東レや、日本の重工業関連メーカーは供給体制が整っているのにも拘わらず、最終組み立てを担う欧米の航空機メーカーがそれに応じられていないという現状。
もちろん、航空機メーカーも立て直しは進めている。米ボーイングは2026年までには、月の生産機数を10機まで戻す計画(ちなみにコロナ禍前の2019年は月14機の生産機数)。
こうした経営の違いに、今後どう対応していけばいいのか。
研究開発に注力し 『技術の極限』を追求
東レの創業は1926年(大正15年)1月で、今年が創業100年目になる。合成繊維(ナイロン、ポリエステル、アクリル)の製造を祖業に出発し、今は繊維、機能化成品(樹脂やフィルムなど)、炭素繊維、環境・エンジニアリング、ライフサイエンスと、日本を代表する総合化学会社として発展。
「東レの強みは研究開発力と技術力」と日覺氏は語り、〝極限追求〟をモットーに、グループ会社を牽引してきた。
日覺氏は1949年(昭和24年)1月生まれ。技術畑の出身で、2010年(平成22年)、社長に就任。2023年(令和5年)6月、社長職は営業畑出身の大矢光雄氏(1956年=昭和31年6月生まれ)に交代し、会長に就任。現在に至る。
極限追求経営では、『ナノデザイン』戦略を実行。ナノ(nano)は長さを表す国際単位。1ナノは100万分の1ミリという、まさに極限の世界。
同社は、繊維の薄さや断面、経常、複合など全てをナノレベルでコントロールして商品を製造。カジュアル衣料にしても、これまでと全く風合いの違う素材を提供。
また、樹脂(プラスチック)の領域では、『ナノアロイ』(NANO ALLOY)というテクノロジー・ブランドを展開。ナノレベルで、複合ポリマー(樹脂成分などの高分子)をアロイ(alloy、混合)する特殊な技術も開発。例えば、自動車の衝突事故による被害を軽減させる衝撃吸収材などに活用している。
2025年3月期の業績は、機能化成品の回復、前述の炭素繊維の航空機向け需要が徐々に回復し始めたことで、増収増益となった。
売上高は約2兆5900億円(前期比5%増)、最終利益は前期比4倍の約880億円。「営業畑出身の大矢社長が営業面での踏ん張りを実現してくれて」という日覺氏の説明。
市場の評価を見ると、株式の時価総額は1兆7685億円。PER(株価収益率)は19.73倍、ROE(自己資本利益率)は1.34%、PBR(株価純資産倍率)は1.01倍という数字である。
東レは言わば研究開発型の企業。「素材には社会を変える力がある」が日覺氏の持論で、先述の『ナノデザイン』戦略のように、極限の研究開発力、技術力を活かして、社会に貢献していこうという考えである。
現場を支えるのは「人」
日覺氏は、1973年(昭和48年)、東京大学大学院工学系研究科産業機械工学修士課程を修了し、東レに入社。人事部から研究所勤務を命ぜられたが、本人は「生産現場で働きたい」と訴え、現場の技術開発に没頭。
この頃から、現場あっての生産会社の経営という考え方を強め、〝経営と現場の関係〟を追求してきた。
現場を支えるのは「人」である。日覺氏は社長時代に、経営のグローバル化が進む中、人を大切にする『東レ理念』をまとめている。その骨子とは何か?
「社会を良くしていくために、企業には社会的責任が問われます。企業は社会の公器であるということで、一番大切なことは、従業員を大事にすることだと思うんですよ。従業員が満足して幸せに生きる。そういう生活基盤があって、初めて仕事にも力が入ると思うんです。そういう事をしっかりやっていくのが企業の責任だと思います」
日覺氏は、今、問われているのは経営のあり方だという見方を示す。そして、「大事なのは、公益資本主義の考え方だと思います」と訴える。
「今のマネーゲーム的な、行き過ぎた資本主義というのは問題であると。人を忘れてしまっていると内外の人々が気付き、それでいわゆる日本的な公益資本主義的なことを考えて勉強していると思ってきました。ただ、その流れが弱まり、おかしくなっているような気がするんです」
これまで50年余の世界の流れを見ると、1971年にニクソン・ショックが起きた。世界の基軸通貨・ドルが金本位制から離脱。つまり、ドルと金との兌換(交換)が廃止され、米国は自由にドル札を刷ることができるようになった。
円とドルとの関係も、それまでの固定相場制(1ドル=360円)から変動相場制に移行。円は切り上げられ、円高となり、日本の産業界は輸出中心主義の変更を余儀なくされ、海外に投資をして、現地で生産する体制へと向かっていった。
「全体的に、マネーゲームの世界に向かうことになり、株主資本主義、金融資本主義になってしまったということですね」
その後、東南アジアの通貨危機、リーマン・ショック(世界的金融危機、2008)が起き、世界規模で経済運営の見直しが進められた。
Bコーポレーション(BはBenefit=利益)といって、環境や社会に配慮した企業経営を志向した動きも現れ、2019年には、BRT(ビジネスラウンドテーブル)が株主利益の実現だけでなく、顧客、従業員、地域社会などの全てのステークホルダー(利害関係者)への気配り、配慮が必要と提言。
「2021年には、例のダボス会議がグレート・リセット(大転換)を提言したりしましたね。ただ、そうした動きが最近弱まっている気がします」と日覺氏は危惧する。
マネーゲームではなく「人への投資」を
今、生成AI(人工知能)が喧伝され、一大投資ブームを巻き起こしている。
「今、そういうIT関連の企業やベンチャーも含めて、株式の時価総額もすごく大きいですね。われわれの素材は、鉄鋼にしろ、化学・繊維にしろ、製品価格が1割、2割は上がっても、一足飛びに10倍やそれ以上になることはありません。株価も同様です。しかし、ITなどのソフト産業ではすぐ売上が10倍、100倍になる企業も世界にはあり、株価も大きく動きます」
日覺氏は、生成AI関連と製造業や素材産業の市場評価の違いについて、次のように続ける。
「確かに、事業として、しっかりとした利益をあげるというのは大事なことですが、本当に今の時価総額とは何なのか、その実態を反映したものなのかということ。マネーゲームになり、バブルの要素も強いとの見方もある。この辺りの所をしっかり見極める必要があると思います」
経営の基本は「人」であるというのは日覺氏の変わらない認識。
「これまで東レはほとんど新卒一括採用で、社内で人材育成をやってきました。海外では買収もあり、経験者採用もあるので、そういった人たちに、ちゃんと東レの経営の考え方が分かるようにということで、東レ理念をまとめています。海外の事業は、経営形態は違うが、やはり人を基本にするという根本にある考え方は同じです」
人への投資を基本に─という日覺氏の経営理念である。