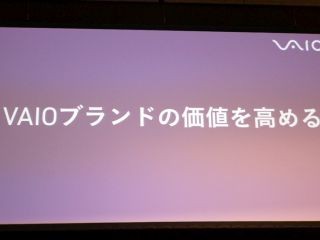VAIOはソニーのPC部門が切り離されて誕生したPC専業のメーカーだが、設立から3年が経ち、PCビジネスをコアにしながらも受託生産事業やソリューション事業などをスタートしている。そのVAIOの社長に6月15日に就任したのが、吉田 秀俊氏だ。日本ビクターの社長を務めるなど、家電の世界での経験が豊富な経営者で、自らPC好きと自称するほどPCにも造形が深い。
同社の新しいリーダーとして、PC事業や新事業の舵取り役を担うことになる吉田氏に、社長就任の経緯とVAIOのこれから、成長戦略について話を聞いた。
ソニーから切り離されて誕生したVAIO、大幅な規模縮小も黒字化を実現
よく知られているとおり、VAIOは2014年7月にソニーからPC事業部が切り離され、日本産業パートナーズというファンドが出資する形でPC専業のメーカーとして誕生した企業だ。
ソニー時代のVAIOと言えば、他のメーカーが出さないようなユニークなPCを出すPCメーカーとして認識されており、コアなファンを獲得しているPCのブランドだった。しかし2010年代前半、グローバルに展開するPCビジネスは利益の出ないビジネスとなってしまい、赤字部門が状態化していた。結果的に日本以外の地域のPCビジネスは終息となり、日本のPCビジネスだけがVAIOへと引き継がれることになった。
そのVAIOだが、船出当時は当然ながら厳しいスタートだった。初年度は赤字であり、出荷台数もソニー時代から大幅に台数を減らすことになった。しかし、2年目以降はビジネス向けに特化した新モデルを投入し、エンタープライズ向けの販売網を整備するなどの戦略がハマったほか、PC以外のビジネスとしてロボットなどの受託生産を開始するなど、PC以外のビジネスの柱を少しずつ構築し、2年目からの黒字転換に成功した。
そうした状況にある新しい舵取り役の吉田氏は、1980年に日本ビクターへ入社。ビデオ事業や海外事業などを担当し最終的に社長まで務めた経歴を持っている。日本ビクター時代にはPC事業やWindows CE事業といったIT機器のビジネスも担当しており、「PCという機器も個人的に好きで興味があった。このため、オファーをいただいて二つ返事で引き受けた」(吉田氏)とのことで、相思相愛で今回VAIOの社長に就任することになったということだ。
VAIOにとってのコアビジネスは依然としてPCビジネス
吉田氏は「VAIOに入社してわかったことは、PC生産の固定費を下げつつも、新しいビジネスモデルのロボット生産などを展開し、ギリギリの中でも生き残れる算段をつけるようにやってきたことがわかった」と話す。つまり、前社長である大田 義実氏の元で行われた構造改革により、VAIOが会社として存続できる基盤が構築されたという見解だ。
この3年で、PCビジネスの固定費を下げながら安定して収益を出すビジネスへと転換し、ロボットの受託生産など新しいビジネスも立ち上がってきた、そう評価しているということだ。
吉田氏は「VAIOにとってPCはコアビジネスで有り続け、それは5年後も変わらないと考えている。では、5年後にもPCビジネスが安定したものかと言えば、B2Bの領域こそ『そうだ』と言える。生産性を重視するユーザーは3年経とうが、5年経とうが減らないからだ」と話す。近年VAIOが重視しているB2Bのユーザー数は今後も減らず、その領域は安定したビジネスが期待できるということだ。
一方でPCビジネスに課題がないわけではない。
「PCビジネスが筋肉質になっているかと言えば、そこまではたどりついていない。現状では固定費を下げるというダイエットをやったところ。少し痩せすぎている部分もあるので、栄養を取り、体力をつけて骨格を築いていくことが大事だ」(吉田氏)
既に説明したとおり、VAIOの2年目(2015年7月~2016年6月)と3年目(2016年7月~2017年6月)に関しては黒字化を実現しており、その最大の理由はPC事業にかかっていた固定費を減らしたことあることはVAIO自身も以前の記者会見などで説明している。ただ、例えば、3年目には新製品があまり登場せず、やや守勢に回った感があることは否めないのも事実だ。
その点について吉田氏は「確かに外から見るとそう見える面もあるとは思う。固定費をただ減らしたわけではなく、バランスをとっているだけであり、必要な開発費は使っており、無駄をそぎ落としただけだ。新製品のサイクルも確かにB2Cが中心だった時代に比べると長くなっているのは事実だが、今はB2CをやりつつB2Bにフォーカスした製品作りを行っており、その意味ではそれにふさわしい製品作りを目指している」と答える。
製品のサイクルは従来よりも長くなっているのは事実だが、それはむしろB2Bの商品サイクルに合わせたものであり、製品開発自体にはコストをかけているというのだ。