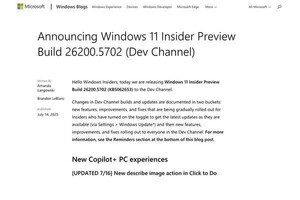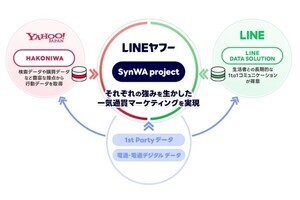日本音楽著作権協会(JASRAC)とネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)などは6日、インターネットでの音楽配信の際の権利者情報を一元的に管理する「著作権情報集中処理機構」を設立した。これまで配信事業者が個別で調べなければならなかった楽曲の権利者情報を集中的に管理。配信事業者の権利処理コストを削減し、ネットでの音楽配信を円滑にする。
現在、国内でインターネット上での音楽配信事業を行っているのは約1,000社。音楽配信サービスの数自体は約10,000サービスあると言われている。だが、これらの事業者がネット上で音楽配信をするためには、事業者が個別で楽曲についての権利者情報を調べる必要があり、作業にかかる人件費や時間が膨大なものとなっていた。
一方、音楽著作権を管理する管理事業者の側でも、問題がある。例えばJASRACでは、99.9%の楽曲については「フィンガープリント」と呼ばれる音源データによる照合システムで楽曲を特定できているが、「7万~10万曲ある残りの0.1%の楽曲の権利情報を特定するのに、膨大な時間とコストがかかっている」(JASRAC常務理事の菅原瑞夫氏)のが現状。
今回、配信事業者と管理事業者双方のコストを削減し、ネットでの音楽配信を促進するための組織「著作権情報集中処理機構」が設立された。
楽曲データを一元化、権利者情報の取得容易に
同機構のシステムでは、JASRACなどが管理する楽曲の権利者情報と音源データを登録。配信事業者が楽曲を使用したい場合は、使用楽曲データを送ると、権利者情報が分かる仕組みになっている。配信事業者はこの情報に基づいて、権利者に楽曲の許諾要請や使用料支払いを行うことになる。
管理事業者側にとっても、一旦システムに楽曲情報を登録しておけば、配信事業者からの権利情報の問い合わせなどに個別に応じる必要はなくなり、コストの大幅な削減につながる。
東京都千代田区で5日開かれた著作権情報集中処理機構の設立総会では、音楽配信事業者団体のネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)代表世話人の佐々木隆一氏があいさつ。
同機構の理事にも選ばれた佐々木氏は、「現在膨大なものとなっている権利処理の実務を、音楽配信事業者と管理事業者が共同機関を作ることで負担を軽減する夢のようなプロジェクト。日本のコンテンツビジネスモデルを大きく成長させる礎(いしずえ)としたい」と抱負を述べた。
また、同じく理事に選ばれたJASRACの菅原氏は、「権利処理が進まないから必要なのではなく、音楽配信事業が進んでいるからこそ必要となって設立されたのがこの機構。配信事業者と管理事業者が一緒になって権利情報を一元管理するというのは、おそらく世界初の試みではないか」と述べ、その意義を強調した。
JASRAC以外の管理事業者も参加予定
また、設立発起人を代表して、元NHKキャスターで湘南ビーチFM(逗子・葉山コミュニティ放送)の社長を務める木村太郎氏もあいさつ。「湘南ビーチFMでは1日300曲の楽曲を配信しているが、権利処理は全て手作業で大変な負担。小さなコミュニティ放送などにとって、今回のような動きはぜひ積極的に進めてほしい」と期待を示した。
著作権情報集中処理機構には、イーライセンスやジャパン・ライツ・クリアランスなどJASRAC以外の管理事業者、第一興商やUSENなどの配信事業者が幹事として参加予定。放送事業者との契約では他の管理事業者の参入を阻害しているとしてJASRACが排除措置命令を受けたが、同機構設立により、ネットでの音楽配信では、他の管理事業者が参入しやすい仕組みづくりが期待できそうだ。
同機構では2009年4月以降、本格システムの構築に向け入札を実施、2010年4月にはシステムを本格稼動させる予定となっている。