宅地建物取引士の資格は、合格率15%から17%を誇る難関試験です。
年に1度しか実施されない国家試験であることから「一発合格したい」という方も多いのではないでしょうか。
また、宅建資格試験は独学でも十分合格を目指せるのか疑問に感じている方もいるでしょう。
今回は「宅建の効率の良い勉強法」ご紹介します。
宅建試験に合格する方の勉強法には共通点があるため、一発合格するための効率の良い勉強法や学習計画、科目別の攻略法を参考にしてください。
この記事でわかること
- 独学でも合格できるのか
- 試験攻略のための勉強法
- 試験難易度
- 勉強時間
- おすすめのテキスト・過去問
- おすすめのアプリ
当サイトに掲載されている宅建士の通信講座についての記事と併せてご覧ください。
宅建士資格は独学で合格できる?
これから宅建試験の勉強を始めようと考えている方の中には、独学でも合格できるのか不安に感じる方もいるかもしれません。
実際、独学の方が予備校に通うよりも費用の負担が少ないため、金銭的余裕のない方や予備校に通う時間がないといった方は、できるだけ独学で合格を目指したいという気持ちを持つでしょう。
結論から言うと、宅建は独学でも充分に合格は狙えます。
ただ独学の場合、テキスト選びから学習計画、疑問点があったときの情報収集など、全てを自分の力だけで解決していかなければなりません。
そのため、予備校などを利用する時よりも、勉強以外にやらなければならないことが多いため、負担が大きくなってしまいます。
一方、予備校や通信講座を利用すれば、いつでも講師に質問ができるため、学習する上での悩みもすぐに解決可能です。
また、予備校や通信講座の受講生が切磋琢磨している姿を見れるため、「自分も頑張ろう」とモチベーションを保つことにもつながります。
さらに、決められたスケジュール通りに勉強が進むため、学習のペース配分のコントロールも容易になるのもメリットです。
何より、効率的に勉強を進められるため、独学で思うように勉強が進まないなどといったストレスは感じにくいでしょう。
もちろん、独学に比べると多少の費用はかかってしまいますが、効率良く学習を進めて、確実に一発合格したいなら、予備校や通信講座の利用をおすすめします。
単純に独学の方が勉強時間もかかり、合格率も低い傾向にあるというのも理由の一つです。
取得することがゴールではなく、取得してからのスキルを磨く方が大事であるため、自分の将来への先行投資だと割り切ってしまった方が賢明でしょう。
もし、独学で合格できる自信が無いということであれば、予備校や通信講座を利用するのも一つの方法です。
おすすめの宅建士資格勉強法
宅建試験の合格を目指すべく、勉強に取り掛かろうとしたけれど、どうやって勉強を進めていけば良いのかわからないといった方もたくさんいるでしょう。
そこで、宅建資格試験の勉強法をご紹介します。
- 試験科目を知ろう
- 科目に優先順位をつけよう
- 過去問をひたすら解く
- 模擬試験を受験する
- ノートの活用法
ポイント①:試験科目を知ろう
宅建資格試験をクリアするにあたり、まずは「試験内容を把握すること」が大切です。
ただ勉強をすれば良いというものではなく、無計画な勉強は効率的ではありません。
宅建の資格試験に合格するには、どんな試験内容でどんな対策が必要なのかをしっかり理解した上で、計画的に学習を進めるのがポイントです。
試験内容を理解していれば、それに対してどのような準備をすれば良いのか自ずと明らかになります。
そこで、試験の内容と科目、配点や難易度を確認しておきましょう。
試験科目
まずは試験科目です。
宅建業法(第7条)によると、宅建試験は「宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定する基準」とする試験として位置づけられており、試験の内容としては、次の7つの点が規定されています(宅建業法第8条)。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
そして、これら7つの内容を問う試験として、宅建では次の4つの科目が設定されています。
- 権利関係
- 法令上の制限
- 宅建業法
- 税・その他
試験はマークシート方式で、全部で50問(50点満点)です。
科目ごとの問題数は毎年ほぼ決まっており、「宅建業法」と「権利関係(民法など)」の2つで、全体の7割を占めています。
つまり、この2つの科目をしっかりおさえて試験に臨むのが得策でしょう。
試験の難易度と各科目の配分
宅建は難関試験に分類される国家資格であり、決して満点をとる必要はありません。
大事なのは「合格すること」です。
満点がとれなくても、合格基準点をクリアすれば合格できます。
合格基準点は過去5年間の動向から35点から38点くらいです。
とはいえ合格基準点は、その年の受験者の成績によって上下します。
たとえば高得点者が多い年は合格基準点も上がり、逆に高得点者が少ない年は合格基準点も下がるという仕組みです。
- 権利関係:14問(第1問~第14問)
- 法令上の制限:8問(第15問~第22問)
- 宅建業法:20問(第26問~第45問)
- 税・その他:8問(第23問~第25問、第46問~第50問)
宅建は、わずか1点の差が合否を左右します。
満点を狙う必要はありませんが、獲得できる問題については確実に正解できるようにしましょう。
確実に合格したいなら40点を目標するのが一つの目安です。
ポイント②:科目に優先順位をつけよう
試験科目と合格基準点について解説しました。
とはいえ、実際に学習を進めるにあたって大事にしたいのは「勉強範囲に優先順位をつける」ことです。
宅建は難関資格であるため、「完璧にやろう」という考えは捨てましょう。
合格基準点に達するためには、学習に優先順位をつけるのがポイントです。
科目別優先順位
- 権利関係(民法など)
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 税・その他
宅建試験の問題出題配分を見ると「権利関係」と「宅建業法」の2科目だけで34問出題されています。
全体の68%を占有する重要科目となるため、勉強時間も多めに確保しておくと良いでしょう。
「権利関係」は苦手意識を持ちやすい科目であり、理解するのに時間がかかる内容です。
権利関係の勉強を後回しにすると試験日に間に合わないということもあり得るため、早めに取り組んでおくのが良いでしょう。
逆に「宅建業法」は、比較的得点が狙いやすい科目のため、全問正解も夢ではありません。
得点源にすべき科目であるため、時間をかけて丁寧に取り組むのがおすすめです。
優先順位をつけて勉強を進めていけば、結果的に学習効率も格段に上がるでしょう。
また、優先順位をつけて勉強を進める際に意識するポイントがあります。
そもそも、全てを完璧に覚えようとすると、いくら時間があっても足りません。
必要な部分とそうでない部分はさっさと取捨選択してしまうのが賢明です。
確実に合格するためには「重点的に勉強すべき部分」を明確にしましょう。
ポイント③:過去問をひたすら解く
効率の良い勉強を進めるには、試験内容を把握することや優先順位をつけることがポイントだと解説してきましたが、宅建試験の勉強における何にも勝る必勝法は、過去問をひたすら回答することです。
宅建試験は5人に4人が落ちる超難関試験ですが、合格者には何度も繰り返し過去問を回答しているという共通点があります。
過去10年分の過去問を使って、試験日までに最低でも3周こなすのを目安にしましょう。
合否の運命を決めるのは、10年分の過去問を何周できたかと言っても過言ではありません。
はじめは、なかなか正解できないだけでなく、「そもそも問題文の意味がわからない」ということもあるでしょう。
しかし、それでも気にする必要はありません。
- 過去問を解いてみる。
- わからなければ、調べる。
- もう一度、解いてみる。
これを繰り返し行うことで出題傾向や試験内容を徐々に理解でき、正答率も上がります。
どうしても難しいようであれば「基本問題集」を使用するのもおすすめです。
「学習マンガ」や「学習アプリ」を利用するのも良いでしょう。
そうして問題に慣れてきたら、また過去問に再挑戦してください。
宅建試験を制するなら、過去問を制することが合格への近道です。
ポイント④:模擬試験を受験する
宅建資格の勉強は「過去問の繰り返し演習」が基本だということはすでに解説しました。
何度も何度も過去問を繰り返し、理解できていない部分やなかなか得点できない部分をひとつずつ潰していきましょう。
その上で、ぜひ活用すべきなのが「模擬試験」です。
宅建の試験直前期になると、色んな資格学校や予備校が模擬試験を開催しますが、昨今では「オンライン受験」という形式もあります。
しかし、ぜひ挑戦してほしいのが「会場受験」の模擬試験です。
「会場受験」の模擬試験なら、本番さながらの環境を事前に体験できます。
また模擬試験で出題されるのは、一流予備校講師が考案した「良質な予想問題」です。
これにより本番に近いような環境で実力が試せるため、明確に自分の現在位置と実力を図れます。
本番同様の受験ができる模擬試験は数多くあるため、時間の許す範囲で試してみると良いでしょう。
ポイント⑤:ノートの活用法
効率の良く勉強を進めるために最後におさえておきたいポイントが「ノートの活用法」です。
ノートを上手に使えるかどうかで、学習効率は大きく変わるでしょう。
ノートの使い方は、人によってさまざまで、「サブノートは作らなかった」という方もいます。
もちろん人によって向き不向きがあるため、ノートの活用術に正解はありません。
そもそも勉強の最終目的として大事なのは、ノートをどう使うかではなく、今まで勉強してきたことを試験で出し切ることです。
ノートを活用することで理解が進むなら万々歳ですが、中には「キレイなノートを作成すること」が目的になってしまっている方もいるかもしれません。
宅建試験の試験範囲は膨大なため、テキストの内容をきれいに要約してまとめるといった方法だと、時間がいくらあっても足りなくなってしまいます。
ノートの使い道としては、「わからない問題」「間違った問題」「なかなか覚えられない項目」などに限定して記録していくといった認識を持つと良いでしょう。
決して「きれいなノートをつくる」ことが目的ではないという点は忘れないで下さい。
科目別勉強法を知ろう
ここまでは、宅建試験合格のために効率的に勉強するにはどうしたら良いかと学習上のポイントを重点的に解説してきました。
今度は、科目別の学習ポイントを見ていきましょう。
権利関係
- 理解にするのに時間を要する科目のため、早めに勉強に取り掛かる
- 丸暗記をするのではなく、内容を理解することが重要
試験科目の内、苦手意識を持ちやすいのが「権利関係」ですが、この科目は試験全体の3割を占めるため、2番目に重要な科目でもあります。
とはいえ、暗記だけで得点するのはとても難しく、理解するにも時間がかかる内容がたくさん含まれているのが特徴です。
そのため、早めに取り組んでおくことが合否の勝敗を分けるでしょう。
不動産登記法や建物区分所有法、借地借家法などが主なテーマで、民法では意思表示や代理、相続、抵当権などが出題されます。
法律用語の出題も多く、難易度も高いため、満点を目指す必要はありません。
ある程度捨てても良い問題があるため、しっかり正解する問題とそうでない問題を正確に見極めて着実に得点獲得を心掛けると良いでしょう。
目安として、14問のうち7点から10点は得点しておきたいところです。
特に民法は取り扱う範囲が膨大で、1,000以上もの条文があるため全てを暗記することは不可能なうえ、「これは民法の条文に記載されているかどうか」といった問題も出題されます。
こうした問題に対処する方法は、「法律の考え方」を理解することです。
法律の仕組みを理解できていれば、「こういう事例は、このように解釈する」と推測できるようになります。
逆に言えば、「法律の考え方」さえ身につけば、解答しやすい問題ばかりです。
ひたすら丸暗記しようとするのではなく、意味を理解して、仕組みを頭に入れましょう。
この科目は苦手意識を持つ受験生が多いため、この科目を得意分野にできれば周りに差をつけられます。
法令上の制限
- 暗記科目
- 範囲自体はさほど広くない
- 試験1か月前からでも十分対策できる
「法令上の制限」は、暗記力で対処できる科目です。
第15問~第22問までの合計8問が出題されますが、確実に合格したいなら5点から7点は狙いましょう。
出題されるテーマは都市計画法や国土利用計画法、建築基準法や農地法などで、前述の「権利関係」に続き苦手意識を持つ受験生が多い科目ではあるものの、覚えるべきポイントをしっかり暗記できれば、得点が稼げる科目です。
住宅や土地に関する規制、役所への届け出や開発行為に関するルールなど、細かいルールも多く、抽象的でイメージしづらい内容もあります。
また、似たような内容の法律も多く、「この事例はどんな規制が適用されるのか?」と混乱することもあるでしょう。
覚えるのは大変かもしれませんが、きちんと暗記さえすれば確実に得点源にできます。
過去問を繰り返しこなしながら、少しずつ記憶と経験を積み重ねていきましょう。
宅建業法
- 暗記科目
- 権利関係科目と同様早くから勉強した方が良い
- 出題配分が一番高い分、徹底的におさえておきたい科目
- 難易度はさほど高くないため、得点源にしやすい
宅建業法は、宅建士や宅建業者が仕事を行う上でのルールを定めたものです。
試験の全50問のうち、第26問から第45問までは「宅建業法」出題されます。
合計20問で全体の4割を占めるため、しっかり取り組んで得点源にしましょう。
宅建業法の問題自体はさほど難しくなく理解しやすいのですが、暗記すべき箇所が膨大です。
そのため、テキストと過去問を何度も繰り返す勉強法が一番効果的といえます。
地道に積み重ねていく学習となるものの、テキストと過去問を繰り返しこなせばこなすほど自然と実力はついてくるでしょう。
宅建業法でテーマとなるのは、不動産売却や賃貸の契約書である「37条書面」や、買主や借主が契約前に知っておくべき事柄を説明する「重要事項説明」、住宅瑕疵担保履行法などです。
また、注意点を強いて挙げるならば、数字などの暗記を要するものが多い点ですが、これも問題演習を繰り返せば、自然に暗記できます。
時間をかけて取り組めば、得意分野にすることは難しくありません。
税・その他
- 暗記科目
- 過去問で繰り返し問題を解く
- 「税額計算」は、繰り返し学習で対処できる
- 「統計問題」については予備校の「直前対策講座」や「予想問題」などを参考にする
「税・その他」は「法令上の制限」と同様、合計で8問が出題されます。
合格のためには、4点から5点を確保したい科目です。
「税・その他」も暗記力が問われますが、出題範囲が広いため全てを完璧にしようとするのではなく、科目の中でも優先順位をつけて学習する必要があります。
難問は捨ててしまっても構いませんが、頻出問題については確実に解けるようにしておきましょう。
過去問を上手く活用するのが必須となります。
主な出題内容は以下のとおりです。
- 第23問から第25問まで
税金に関する問題(不動産取得税、固定資産税、登録免許税、印紙税、所得税、贈与税など) - 第46問から第50問まで
不動産関連の直近の統計
(地価公示価格、土地白書、不動産価格指数、法人企業統計年報など)
や景品表示法など
「税金に関する問題」では、税額計算に対処できるのが大切です。
繰り返し問題を解いて問題に慣れていきましょう。
また、「不動産関連の直近の統計」については最新の統計データから出題されます。
色んな資格学校が、試験直前期に「対策講座」を行っているため、ぜひ参考にすると良いでしょう。
勉強時間はどれくらい?学習計画を立てよう
宅建試験に合格した方の学習スタイルには明確な戦略があります。
宅建試験に合格したいなら、科目に優先順位をつけることはすでに解説したとおりですが、実際に宅建試験対策をするためにはどのような学習計画を組めば良いのでしょうか。
勉強時間はどれくらいかかるのかと併せて、具体的に説明していきます。
勉強時間は300時間確保しよう
試験は原則として毎年10月の第3日曜日です。
宅建に合格するには、300時間の勉強が必要だと言われています。
まずは試験実施日までの間に「300時間」の勉強時間を確保してください。
300時間の勉強時間を確保して、効率の良い勉強ができれば、そう難しいものではありません。
とはいえ、すでに宅建に関する知識があるなら、もっと短い勉強時間でも合格できるでしょう。
しかし、余裕をみて300時間を確保することがおすすめです。
また、合格者の勉強法には共通のポイントがあり、適切な勉強をすれば誰でも合格できます。
宅建の出題内容や出題傾向は決まっているため、「合格するために勉強しておくべきこと」は明確です。
優先順位をつけて、計画的に学習をこなしさえすれば心配は要りません。
そのためには、まずは300時間を確保するようにしましょう。
あとは残り期間に応じて科目と時間の配分を決めていくだけです。
科目ごとの勉強時間の目安
| 科目 | 問題数 | 目標点 | 勉強時間 |
| 権利関係 | 14問 | 7~10点 | 100時間 |
| 法令上の制限 | 8問 | 5~7点 | 35時間 |
| 宅建業法 | 20問 | 18点 | 180時間 |
| 税・その他 | 8問 | 4~5点 | 35時間 |
このうち重点的に学習すべき科目は、「民法など(権利関係)」と「宅建業法」です。
配点割合の7割近くを占めるため、ここをどれだけ得点源にできるかが勝負になります。
前述したとおり、宅建業法は比較的得点をしやすい科目のため、満点近くを狙える科目です。
ただ、暗記量が膨大であるため、勉強時間は多く確保する必要があるでしょう。
また、「民法など(権利関係)」は多くの受験生が苦手とする分野です。
できるだけ早めに勉強を開始させ、時間をかけて学習するのをおすすめします。
どれくらい前から始めれば良い?
300時間の学習を確保できるとしても、どれくらい前から学習をスタートしたらよいのか悩んでしまう方もいるかもしれません。
そこで試験の1年前、6ヶ月前、3ヶ月前からスタートさせる場合の勉強法も紹介します。
これを読めば、きっと自分に合った勉強スケジュールのイメージが見えてくるはずです。
「1年前」から始める場合
まずは試験の1年前から学習をスタートさせるというパターンから見ていきます。
試験が行われる毎年10月の第3日曜日から300時間逆算しましょう。
たとえば1年であれば、1ヶ月に25時間が確保できれば「300時間」に到達します。
1週間で約6時間、1日で約50分という計算です。
1年もあれば、学習期間としては十分な時間の余裕があるため、理解に時間を要する「権利関係」から学習すると良いでしょう。
しかし、時間の余裕があるために、学習が中だるみしやすくなるというデメリットもあります。
「まだ時間があるから大丈夫」と後回しにしていると、充分な勉強ができないまま、あっという間に試験日を迎えることになるでしょう。
まずは1日15分や30分という、短い時間でも「毎日の勉強を習慣化する」ことを意識してください。
学習が習慣となれば、だんだん1日あたりの勉強時間も増えていくでしょう。
学習の手順としては、以下の順番で取り組むのがおすすめです。
- 過去問を眺める
- テキストを読む
- 過去問を解く
まず「過去問を眺める」ことで、どんな問題が出るのかを把握します。
勉強していない段階のため、回答できなくても全く問題ありません。
全体像が把握できたら、テキストを読み込んでいきます。
1つのテーマの学習を終えたら、そのテーマに関する過去問を回答していき、不明点があればまたテキストに戻りましょう。
最後まで学習が進んだら、過去問を3周以上は繰り返し解いたうえで試験日に臨みます。
「6ヶ月前」から始める場合
試験日まで6ヶ月が残っている場合、1ヶ月に50時間が確保できれば「300時間」に到達します。
1週間で約12時間、1日で約1時間40分という計算です。
6ヶ月というのは決して十分な時間とは言えません。
毎日1時間40分の勉強量となるため、1日怠けてしまうと次の日のしわ寄せが大変です。
隙間時間を活用しつつ、毎日コンスタントに学習するよう心がけましょう。
学習の手順は前述の「1年前から始める場合」と同じです。
- 過去問を眺める
- テキストを読む
- 過去問を解く
基本的には、10年分の過去問を何周できるかが勝負です。
なお試験直前には、色んな資格学校や予備校が模擬試験を開催します。
できればそれまでに3周できるようスケジュールを組むのが理想です。
「3ヶ月前」から始める場合
最後に「試験まで3ヶ月しかない」という場合を紹介します。
「3ヶ月で合格は不可能だ」と諦めてしまう方もいるかもしれませんが、やり方次第では十分に合格は可能です。
残り3ヶ月という場合、1ヶ月に100時間が確保できれば「300時間」を確保できます。
1週間で24時間、1日で3時間20分という計算です。
「1日3時間は厳しい」と感じるかもしれませんが、短期合格のためにはやるしかありません。
平日に3時間20分を確保するのが難しいなら、土日や隙間時間も活用するようにしてください。
たとえば次のようなイメージです。
- 平日は3時間ずつ:土日は5.5時間ずつ
- 平日は2時間ずつ:土日は8時間ずつ
- 平日は1時間ずつ:土日は10時間30分ずつ
また時間が限られているため、あえて「難問は捨てる」というのも一つの方法です。
頻出の問題に絞って学習し、誰もが得点できるような問題は確実に得点できるようにしておきましょう。
また、過去問は3周できないかもしれませんが、可能な限りチャレンジするようにしてください。
どうしても難しそうなら、頻出度の高い過去問だけを繰り返し学習するようにしましょう。
合格に近づきたいなら、せめて2周はしておきたいところです。
移動時間や会社の休み時間など、隙間時間があれば1問でも多く回答することを心がけてください。
学習計画作成時の注意点
勉強スケジュールの作り方を解説してきました。
スケジュールの作成にあたっては、いくつかの注意点があります。
そのうち、もっとも大事なことは次の2点です。
- 勉強範囲に優先順位につける
- 振り返りの時間も作る
勉強範囲に優先順位につける
1つ目に大事なことは「勉強範囲に優先順位につける」ということです。
宅建の試験範囲の全てを完璧に覚えようとすると、いくら時間があっても足りません。
効率よく確実に合格するには、勉強すべき範囲を明確にすることが重要です。
たとえば過去問を見ると、頻出問題となっている分野もあれば、たまにしか出題されない分野もあります。
よく出される問題は重点的に学習し、あまり出題されない問題については後回しにしましょう。
誰もが得点できるような問題は絶対に押さえておかなければいけませんが、マニアックな問題であれば得点できなくても問題ありません。
振り返りの時間も作る
そして、もう1つ大事なことは「振り返りの時間も作る」ということです。
勉強することは大事ですが、どんなに勉強しても記憶に定着しなければ意味がありません。
「勉強したことが本当に身についているか」を確認するために、「テキストを読む」というインプット作業だけでなく、「問題を解く」というアウトプット作業を心がけましょう。
もし不正解した問題があれば、なぜ間違えたのかという「理由」を調べるようにしてください。
間違えた原因がわからなければ、人間誰しも同じ失敗を繰り返すものです。
一つひとつの正答と誤答を振り返ることで自然に実力は上がっていきます。
事実、宅建に合格できる方の多くは「振り返り」を大事にしており、実力がついたかどうかをしっかりチェックしているからこそ、自分の苦手分野を把握しています。
苦手分野を把握し重点的に勉強することで「穴」は一つずつ無くなり、合格に近づけるはずです。
宅建士資格の勉強におすすめ!過去問3選!
宅建試験に合格するには、過去問とテキストを往復してひたすら問題を解くことが最適な勉強法だと前述しましたが、実際にどんなテキストや過去問を選んだら良いのでしょうか。
宅建試験に合格するためには、テキストや過去問の選び方がとても重要です。
自分の学習スケジュールや学習スタイルに合わないテキストだと、スムーズに勉強が進まず合否にまで影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
そこで、宅建試験に向けておすすめのテキストや過去問をご紹介します。
ぜひ試験勉強の参考にしてみてください。
| タイトル | 料金 | 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
みんなが欲しかった!宅建士シリーズ
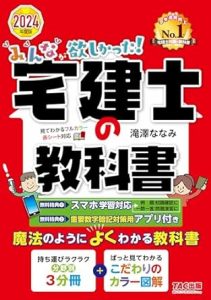
みんなが欲しかった!宅建士の教科書:3,300円
みんなが欲しかった!宅建士の問題集:2,750円
みんなが欲しかった!宅建士の12年過去問題集:2,860円
とにかく解説が分かりやすいのが特徴で、図解が多くフルカラーで見やすく、情報量も抜群に掲載されているため、辞書として使用するのにとても良いテキストです。
権利関係などの文字だけでは理解できない複雑な解釈も分かりやすく解説してくれます。
また、学習度や理解度などもメモできる仕様になっているため、知識の定着度を図れるのもポイントです。
わかって合格(うか)る宅建士 シリーズ

わかって合格(うか)る宅建士基本テキスト:3,300円
わかって合格(うか)る宅建士一問一答:1,980円
わかって合格(うか)る宅建士過去問12年PLUS:2,860円
わかって合格(うか)る宅建士分野別過去問題集:2,750円
解説ページには選択肢別のテーマが書いてあるため、今どの分野のどの箇所について聞かれているかが分かるのがメリットで、回答にたどり着けなかった時や復習をする時にとても便利な機能です。
この問題集の解説ページには、「頻出」「難」「ひっかけ」というマークが選択肢についていることがあります。
宅建試験でもよく出る「ひっかけ」問題の傾向や、出題のされ方を把握できるため、同じような問題に出くわした時に対応できるのは魅力です。
宅建学院過去問宅建塾
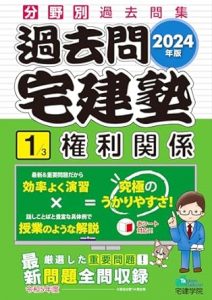
宅建士問題集 過去問宅建塾〔1〕~〔3〕
各1,980円
らくらく宅建塾:3,300円
分野別で3冊に分かれており、見開き左が問題、右が解答・解説となっている問題集です。
3冊あるだけに問題の収録数も多く、解説も十分なボリュームがあります。
とはいえ、3冊購入というのは金銭的にデメリットといえるでしょう。
また、たとえば外出先で、宅建業法だけでなく権利関係も勉強したいといった場合には、2冊持ち歩かなければならないため、いつでもどこでも勉強したい方にとっては使いにくいテキスト問題集かもしれません。
しかし、内容は「らくらく宅建塾」と合わせて充実感のあるものとなっており、この3冊が完璧に解けるようになれば間違いなく合格できます。
実績のあるおすすめの問題集と言えるでしょう。
宅建士資格の勉強におすすめ!アプリ7選!
宅建の資格取得に向けて、学習のさらなる効率化を図るべく、人気のアプリを7種類厳選しました。
アプリは隙間時間を利用して手軽に学習しやすく、限られた時間の中でも効率的に勉強するには非常に便利な教材です。
ぜひともフル活用して役立ててみてください。
宅建過去問集スタケン問題編
 「スタケン」の愛称で親しまれる宅建過去問題集は、完全無料で利用できるアプリです。
「スタケン」の愛称で親しまれる宅建過去問題集は、完全無料で利用できるアプリです。
宅建の試験の出題範囲全てを網羅しており、出題形式は○×式の二者選択方式で、丁寧な解説も付いています。
宅建の基礎知識を学んだ後で、じっくりと取り組みたいアプリで、学習時間や日数、正解率までグラフデータで確認できる機能も魅力です。
宅建士 過去問題 (受験用)
 宅建の基礎知識から応用までしっかり学んだ後に、試験直前の総まとめとして活躍するアプリです。
宅建の基礎知識から応用までしっかり学んだ後に、試験直前の総まとめとして活躍するアプリです。
480円と有料ですが、法令上の制限や権利関係など二択・四択の出題形式で、便利な暗記ノート機能を活用するとより効率良く学習できます。
オンスク.JPアプリ
 オンスク.JPは宅建だけでなく、簿記をはじめとした15個の講座を1つのアプリで受講できます。
オンスク.JPは宅建だけでなく、簿記をはじめとした15個の講座を1つのアプリで受講できます。
宅建と合わせて他の資格取得も目指す人におすすめです。
安心の月額制で使った分だけ支払うシステムになっており、講師の授業をいつでも動画で視聴できます。
お試しにおすすめの無料サービスも展開されているので活用してみましょう。
耳勉
人は音を聴くとき、少し雑音が入った方がより集中して聴こうとする傾向があるそうで、「耳勉」はこれを上手く活用しています。
宅建の学習上の重要ポイントを何度も聴いて確認し、着実に知識を身につけられるでしょう。
宅建士試験過去問題集SmartAI
 TAC出版監修のSmartAI には過去12年間の試験問題が収録されており、試験直前にぜひ活用したい無料アプリです。
TAC出版監修のSmartAI には過去12年間の試験問題が収録されており、試験直前にぜひ活用したい無料アプリです。
出題数は2,226問以上あり、「解答の解説が丁寧でわかりやすい」と好評を博しています。
各科目に的を絞って効率良く学習ができ、マイページで学習の進捗状況を確認することで、得意な分野を伸ばしながら苦手な部分を克服できるでしょう。
宅建過去問2024

宅建過去問2024には過去10年間の試験問題が収録されている究極の無料宅建問題集アプリです。
基本の一問一答から、分野別4択や10年分の過去問演習まで、たっぷり3761問もの問題が収録されています。
全問題に解説が付いており、チェックを入れた問題をまとめて復習できる機能もあるほか、直近の法改正にも対応している優れものです。
全問解説付宅建士一問一答問題集
 「全問解説付宅建士一問一答問題集」に収録されている問題には、全てに詳細でわかりやすい解説がつけられています。
「全問解説付宅建士一問一答問題集」に収録されている問題には、全てに詳細でわかりやすい解説がつけられています。
目次に表示される回答履歴でどこまで進んだのかもわかるため、達成感を持って学習を続けられるでしょう。
さらに、完全版へアップグレードすると、問題数が約250問に増加し、ランダム出題機能も使えるようになります。
追加される問題は過去の出題から頻出論点の良問が厳選されているので、合格に必要な知識を効率よく身に付けられるでしょう。
適切に章分けもされているため、科目ごとの集中的な学習も可能です。
ランダム出題機能では過去に間違った問題や未回答の問題が優先的に出題されるため、受験直前の総仕上げや知識の維持に効果があります。
まさに宅地建物取引士資格試験向け問題集アプリの決定版と言えるでしょう。
まとめ
宅建資格試験の効率の良い勉強法について解説してきました。
宅建資格は難関資格ですが、300時間程度の勉強時間を確保し、適切な勉強方法で地道に積み上げていけば、誰でも合格できる試験です。
一発で試験に合格するための効率的な勉強法や注意点、科目別の攻略法も紹介しました。
大事なのはやみくもに勉強するのではなく、「合格するための勉強法」を継続することです。
- 確実に正解する部分を把握しておくこと
- ひたすらテキストと過去問を往復すること
- 難問は捨てること
- 学習に優先順位をつけること
宅建試験の勉強を始めるにあたって、この記事で解説してきたことに加えて、当サイトに掲載されている宅建士の通信講座についての記事も、ぜひ併せて参考にしてください。





