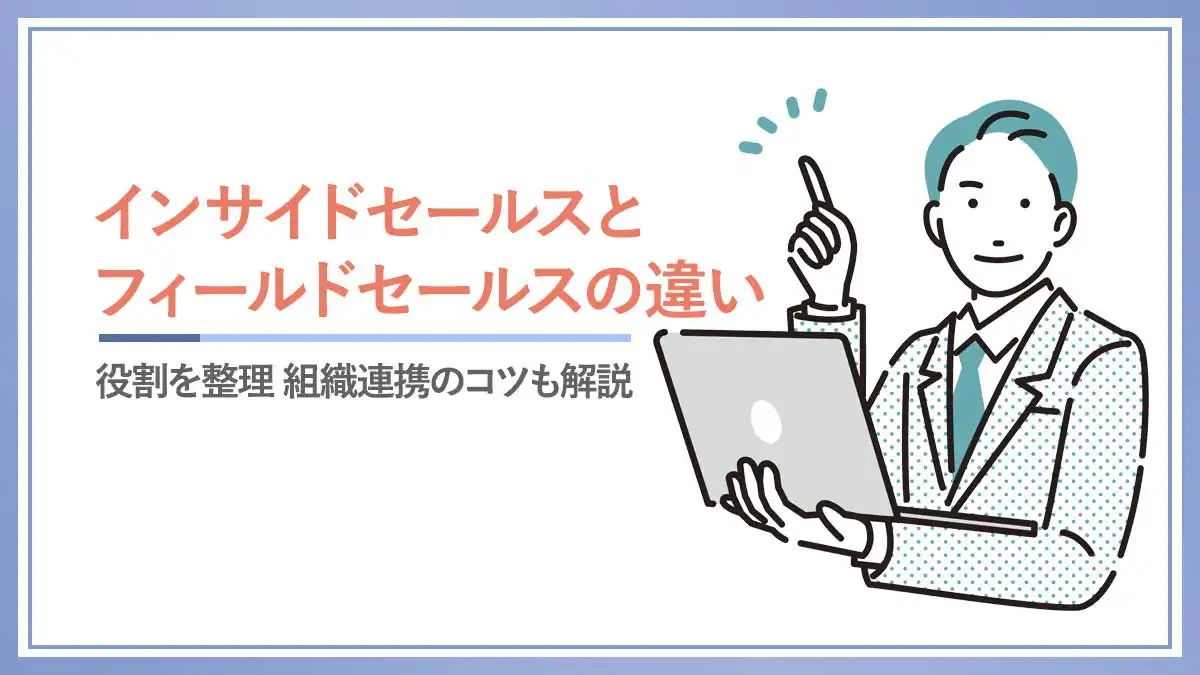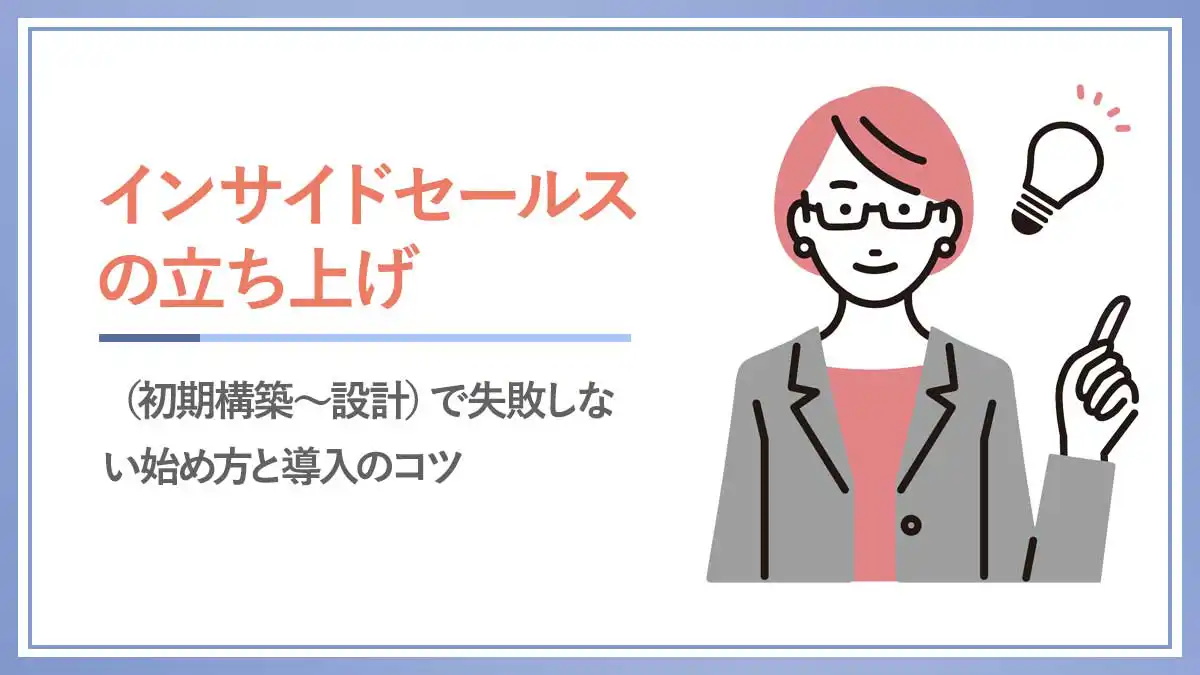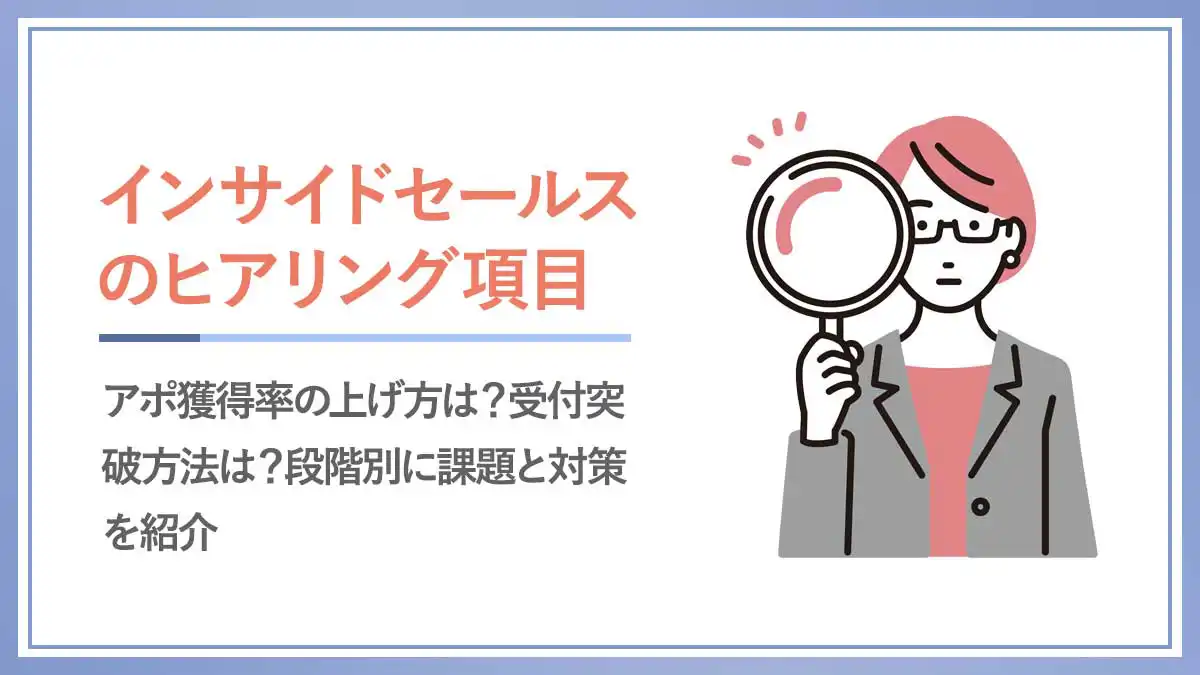【比較表付き】5分で分かる!インサイドセールスとテレアポの違い
マーケティング
【TECH+マーケティング責任者】谷合 祐馬 [2022.09.21]
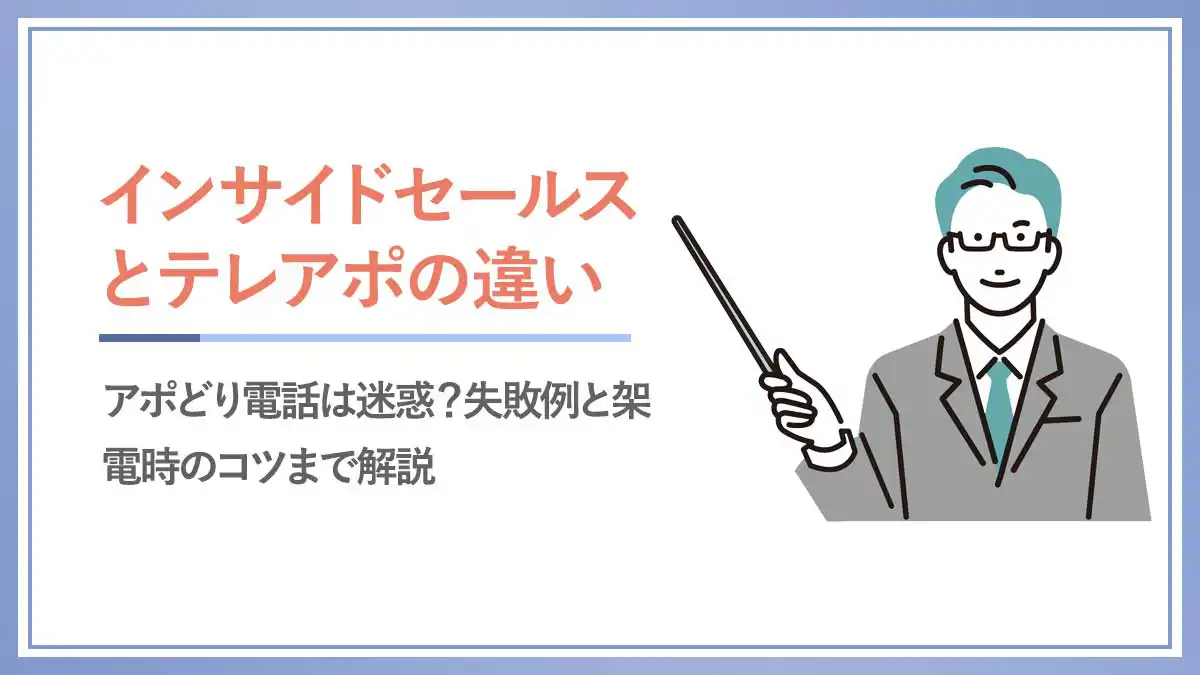
インサイド
下記の記事でインサイドセールスについて詳しく解説しています。
・インサイドセールスとは?役割や業務、メリット、体制構築/目標設計から事例までわかりやすく解説
インサイドセールスとテレアポの違いは3つ
インサイドセールスとテレアポの違いは、目的、目標指標、時間軸(効果測定期間)の3つです。
インサイドセールスは、電話を利用したコミュニケーションも行う点からテレアポと同様の業務内容と誤解されることがありますが、それぞれの役割は異なります。
|
インサイドセールス |
テレアポ |
|
|
目的 |
顧客育成 |
アポ獲得 |
|
目標指標(KPI) |
条件を満たすアポ獲得件数など |
アポ獲得件数 |
|
時間軸(効果計測期間) |
長期 |
短期 |
上記の表は、インサイドセールスとテレアポにおける電話営業の役割を書き出した物です。ここからは、それぞれの項目について違いを見ていきましょう。
1.目的の違い
テレアポは顧客とのアポイントを獲得する目的で電話をかける業務ですが、インサイドセールスで架電をする際の目的は顧客育成(ナーチャリング)であることが一般的です。
インサイドセールスは通常の営業と目的に違いはないため、最終目標はアポイントの獲得や契約獲得が目的です。
しかし、テレアポと違い電話だけでその目的を達成することを目指さず、あくまでも顧客との関係性を構築することを重要視したコミュニケーションを行う場合が多いです。
また、通常のフィールドセールスとの違いは移動時間や交通費の削減がインサイドセールスでは可能であることや、フィールドセールスでは属人化しやすい営業のノウハウなどを社内に共有しナレッジとして蓄積しやすい点などがあげられます。
2.成果指標の違い
インサイドセールスとテレアポでは成果指標も異なります。一般的にテレアポは「電話業務の中で何件アポを取れたか」を成果指標として設ける場合が多く、質の良し悪しではなく量が評価軸になります。
なぜならテレアポはドアノック営業の要素が強く、顧客の検討ステータスに関わらず多くのリストに対してアプローチし、短期間で興味を引き出し成果に繋げることを目的にしているためです。
一方、インサイドセールスは顧客の検討ステータスが明確である場合が多く、成果指標もアプローチする顧客の状況ごとに変わります。
例えば、すでに具体的な提案をしている顧客に対してアプローチする際は、契約獲得が成果指標になり、契約締結後の顧客へのコミュニケーションをする場合は契約の継続やアップセルが成果指標になるでしょう。
3.時間軸(成果検証期間)の違い
インサイドセールスとテレアポでは、その施策によりどれだけの成果が上がったかを検証する期間についても異なります。
テレアポでは1週間や1日単位など短期的にアポの獲得件数を検証し、トークスクリプトの改善や架電リストのブラッシュアップを行うことが一般的です。テレアポのPDCAサイクルが短いのは、テレアポの施策が電話をかけてから切るまでの時間で成果が決まるため、検証するための情報が短期間で蓄積されやすいからです。
一方、インサイドセールスは長期的な目線で顧客育成に取り組むため、その場の電話営業だけでは契約やアポなどの成果に直結しない場合が多いです。そのため、成果を検証する期間も短くても1ヶ月単位で行われ、長ければ半年〜1年単位で効果を検証するケースもあります。
インサイドセールスはテレアポを混同した時に起きる失敗例
前述の通り、インサイドセールスとテレアポには明確な違いがあります。しかし多くの企業では、市場の変化に合わせてインサイドセールスを立ち上げたものの、管理者や責任者の認識の誤りからテレアポ部隊化してしまうケースがあります。その理由や対策方法を紹介します。
指標設定が誤り、迷惑電話になることも・・・
インサイドセールス部門における評価軸などの指標を、アポ獲得件数やコール数、商談数などの行動数で設定してしまっているケースが多くあります。
これらの指標だけを評価軸に設定すると、所属メンバーはインサイドセールスの本来の目的を忘れ、ヒアリング内容や質にこだわらなくなり、コール数や行動数をこなすことに注力するようになります。
最終的には、指標を達成するために受注確度の低い案件なども強引にアポを取るようになり、結果的にフィールドセールスも質の低いアポイントメントや商談に振り回され、非効率な業務フローが生まれてしまうのです。
顧客にとっても無駄な時間を割くことになり、会社の評判を下げてしまう迷惑な営業電話になってしまいます。
指標設定が誤っているときの対策
このようなケースを防ぐためには、指標を設定する際にアポ数や行動数だけに注目せず、見込み度を段階的に評価した指標を取り入れると良いでしょう。
たとえば「潜在層→顕在化→アポ見込み→アポ獲得」といったようにアポ獲得までの指標を段階的に表現し、顧客をどこからどこまでステータスアップさせたのか、という視点で評価を行います。
指標は自社内で独自に設定することもできますが、マーケティングオートメーションツールなどに汎用的なステータスがテンプレートとして初期設定されているものもあるため、参考にするのも良いでしょう。
下記の記事でインサイドセールスのKPIについて詳しく解説しています。
・インサイドセールスのKPI・目標設定と効果を最大化するポイントとは?メリット、デメリットも併せて紹介
適切なヒアリングができていない
テレアポと同一認識されている部門や組織では適切なヒアリングができていない可能性があります。
具体的には、電話でのヒアリングにおいて、トークスクリプトなどにまとめられている質問の内容が「はい(Yes)」と「いいえ(No)」で答えられるようなクローズドクエスチョンになってしまっているということです。
たとえば、「自社の○○という商品に興味はございますか?」「弊社の広告はご覧いただけましたでしょうか?」などです。このような質問だけでは、見込み顧客が抱えているニーズを引き出すことは難しいでしょう。
適切なヒアリングができていないときの対策
インサイドマーケティングには、オープンクエスチョンが必須です。
たとえば、「自社の○○という商品にはどのような印象をお持ちですか?」「弊社の広告ごご覧いただいた感想はいかがでしたでしょうか?」など、相手が自由に回答できる質問を投げかけ、その回答に合わせてトークを掘り下げることで、見込み顧客の現状や課題を汲み取ります。
また、ヒアリングを行う上では、「BANT情報」と呼ばれる情報を収集することで、潜在層の見込み度合を判断できます。
- 【B】Budget:予算はあるか、どのくらいか
- 【A】Authority:決定権を持つのは誰か
- 【N】Needs:企業としてニーズを感じているか
- 【T】Timeframe:具体的にいつごろ導入したいか
情報を漏れなく聞き出すためには、事前に質問内容をまとめたヒアリングシートなど用意するのも良いでしょう。テレアポ部隊になることを防ぐためにも、BANT情報についても知識をつけておくことをおすすめします。
下記の記事でインサイドセールスのヒアリング項目について詳しく解説しています。
・インサイドセールスのヒアリング項目設計は?アポ獲得率の上げ方は?受付突破方法は?段階別に課題と対策を紹介
下記の記事でインサイドセールスに向いている人ついて詳しく解説しています。
・インサイドセールスに向いている人、不向きな人の特徴4つ 採用で抑えるべきポイントも解説
まとめ
インサイドセールスの役割はテレアポと違い、電話営業により顧客との関係性を構築する目的が主体となり、ただアポイントを獲得するだけではありません。
この役割の違いから、テレアポを行う部署とインサイドセールスの部署が分かれて組織されている企業もあります。本稿を参考にしていただき、テレアポとは異なるインサイドセールス部署が行うべき役割を理解しましょう。

【TECH+マーケティング責任者】谷合 祐馬
2018年から広告やリードジェネレーションに関してのソリューション営業を経験。 2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。 現在はTECH+マーケティング責任者として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。