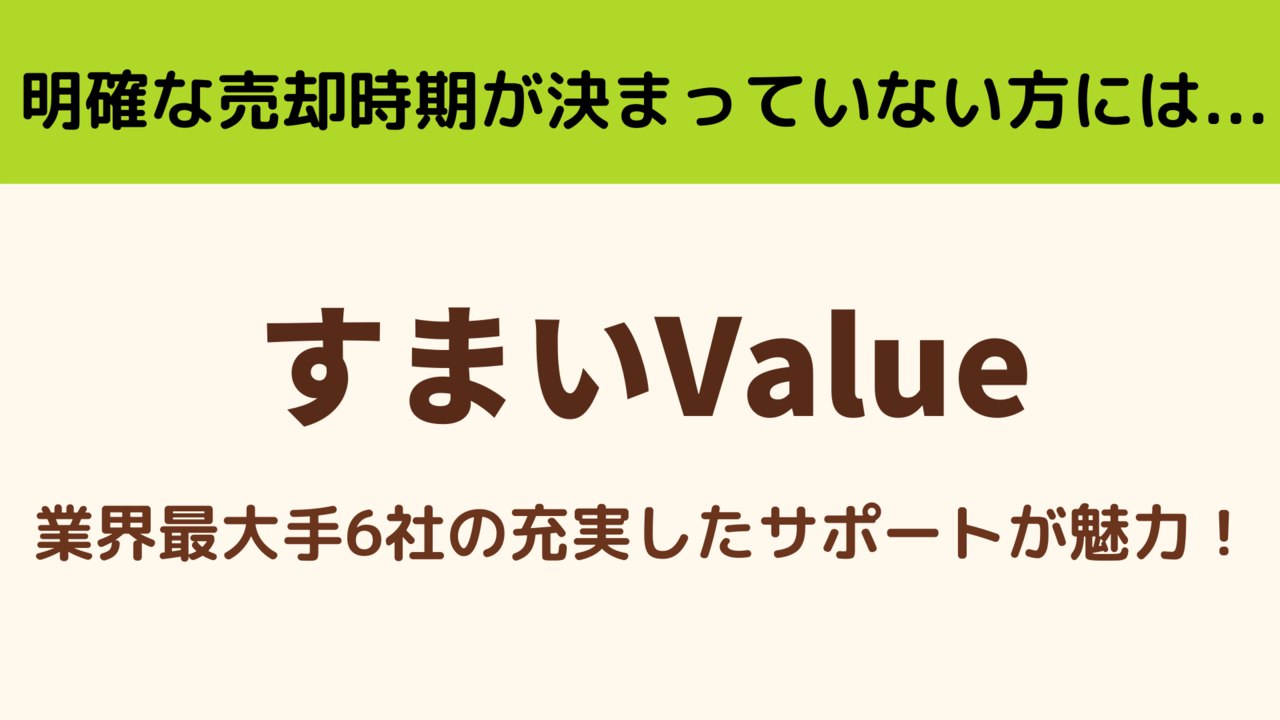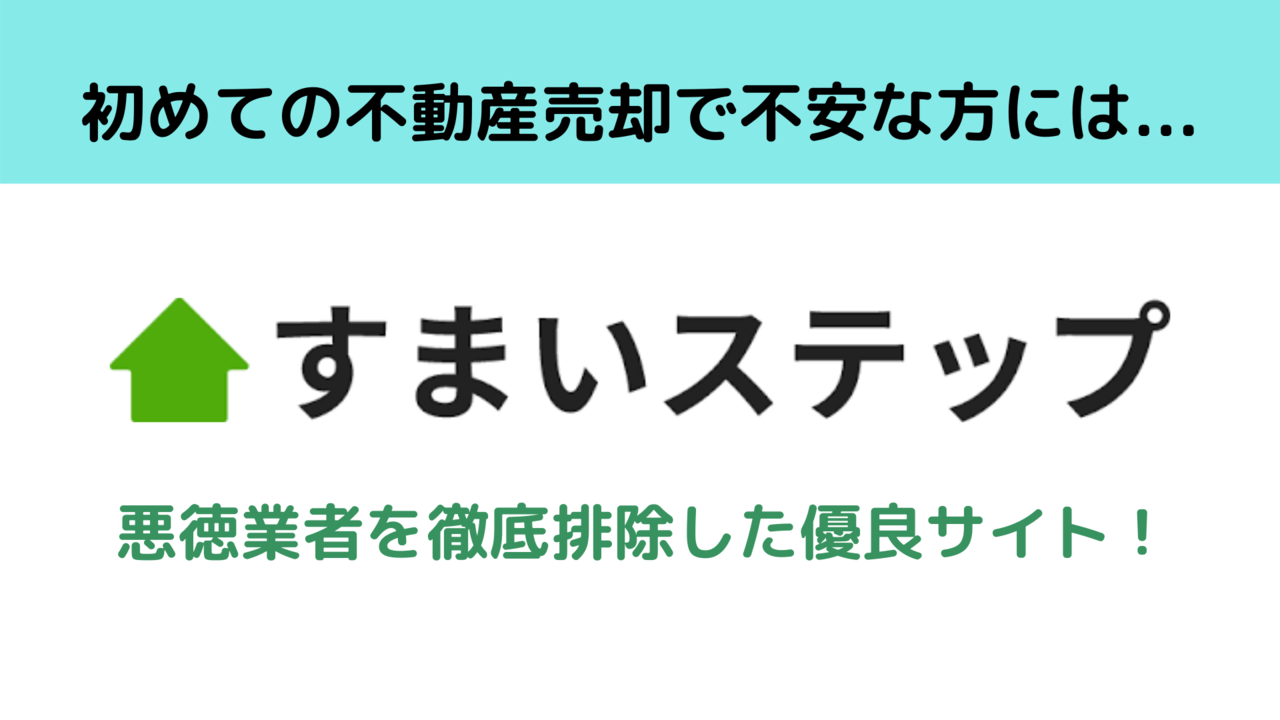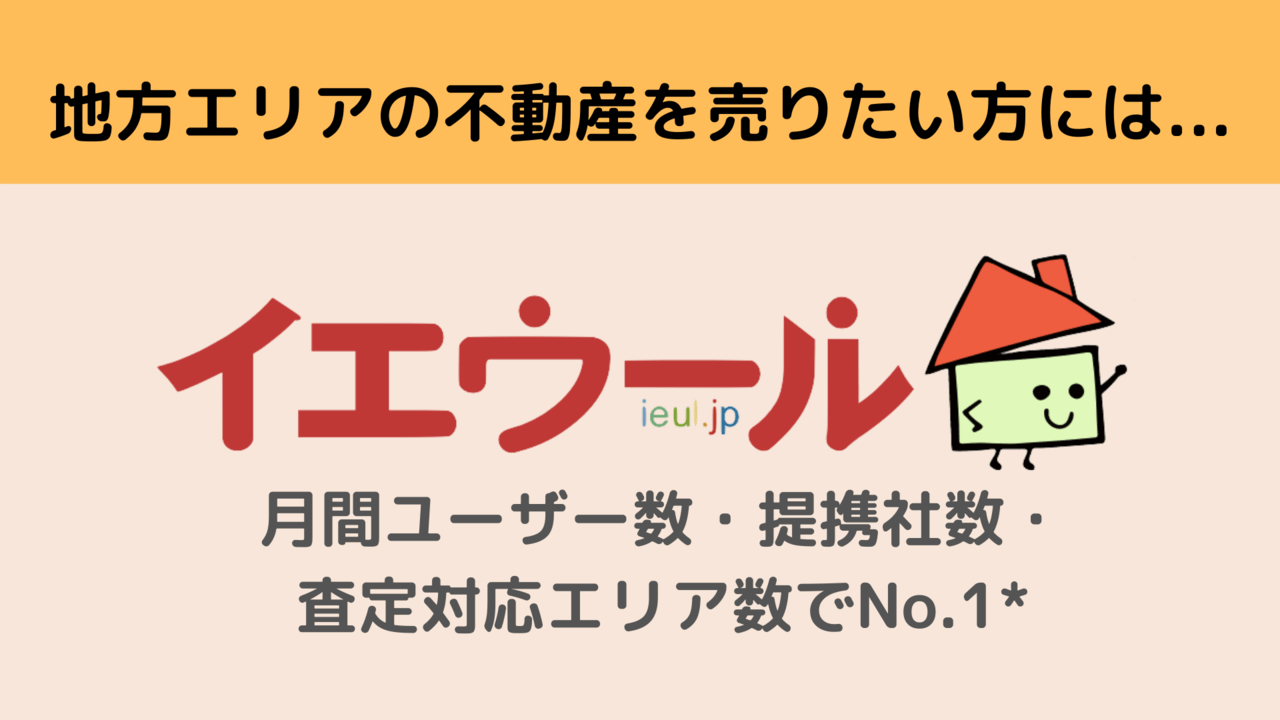離婚をすることになったら、夫婦になってから形成した財産を分けなければなりません。そのことを財産分与と呼び、お互いが納得できる形で分配できるように話し合いで決めます。しかし、新しい生活のためにお互いができるだけ財産を多く確保したいと思い争いになってしまうこともあります。
そんな財産分与の対象となる財産の中に、どちらかが両親などから相続した遺産があった場合は、どのように財産分与されるのでしょうか?
この記事では、財産分与での相続した遺産の扱いについて詳しく解説していきます。
基本の法律も知らずに財産分与をしようとすると、話し合いがまとまらなかったり大幅に損をしたりするかもしれません。遺産分割との違いまで解説するので、ぜひ財産分与をする前に参考にしてみてください。
【あなたに合うのはどれ?】おすすめ不動産一括査定サービス
まずは不動産がいくらで売れるか手っ取り早く知りたい方は、不動産一括査定サービスがおすすめです。不動産会社まで足を運ぶことなく、複数の会社にネットでまとめて査定を依頼できます。 ここでは、編集部おすすめの3タイプの不動産一括査定サービスをご紹介します。それぞれのサービスに特徴があるので、自分の状況に合うものを選ぶと良いでしょう。”*(2020年7月時点)出典:東京商工リサーチ「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」”
次の記事では、より多くのサービスを含めたランキングや「おすすめのサービスTOP3」「査定結果の満足度TOP3」「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別のランキングを作っております。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。
財産分与では、相続した遺産は基本的には対象外
 相続した財産も分与しなければならないのかは、相続した財産をどのように扱ったかによって決まるのですが、基本的には自分が相続したものは自分の取り分と考えても良いでしょう。ただ、現在相続した遺産をどうしているかによっては財産分与の対象となるものもあります。まずは、そもそも財産分与の対象になる財産について解説していきます。
相続した財産も分与しなければならないのかは、相続した財産をどのように扱ったかによって決まるのですが、基本的には自分が相続したものは自分の取り分と考えても良いでしょう。ただ、現在相続した遺産をどうしているかによっては財産分与の対象となるものもあります。まずは、そもそも財産分与の対象になる財産について解説していきます。
相続した遺産は自分の取り分
夫婦の財産は、民法の法定財産制に従い、結婚中に形成された「共有財産」と、夫婦の協力なしに形成された「特有財産」の2種類に分けられます。このうち特有財産は財産分与の対象外です。
相続した遺産は特有財産になり、財産分与の対象に含めません。高額になりやすい不動産や金融資産、貴金属や自動車などの動産を相続していても、財産分与はされずにすべて自分の取り分にできることがほとんどです。
離婚する相手が、相続した遺産まで財産分与するように主張してきても、基本的には断ってください。これは、将来相続予定の財産であっても同様です。感情に流されてよく分からないまま財産分与をしてしまうと後悔するでしょう。
財産分与できるものとは
それでは財産分与の対象になる共有財産には、どのようなものが含まれるのでしょうか?その条件は夫婦になってから形成した財産であることで、たとえ名義が夫や妻だけの財産でも対象となります。
対象の財産は、例として以下のようなものがあります。
- 預貯金・手元にある現金
- 加入している保険
- マイホームや土地などの不動産
- 国債や株などの金融資産
- 自動車や家財、骨董品などの動産
- 結婚中に受け取った退職金や年金
- 住宅ローンの残債
- 未払いの家賃や損害賠償金
預貯金や現金、不動産や動産なら財産と認識しやすいですが、負債である借金や未払いの家賃なども対象になる点には注意しましょう。ただし、夫婦での生活のための負債だけが財産分与の対象になり、趣味のギャンブルや嗜好品などの浪費による負債は除外されます。
負債まで考慮して財産分与をしておかないと、均等に分けたつもりでも将来の支払いで大きな差がついてしまいます。住宅ローンの残債があるときの離婚前の確認事項について、詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。

判断が難しいケース
基本的に特有財産である相続した遺産は、財産分与の対象外です。しかし相続した遺産の状況によっては、財産分与の対象になります。
例えば、現金を相続した場合は通常の預貯金と分けてあることは稀で、生活費や子供の教育費などに割り当ててしまいます。財産分与の段階では、相続した遺産分が残りの預貯金の何割を占めているのかが判断できないことが多く、全て合計して財産分与の対象となることがあります。
消費された遺産分を、離婚時点の預貯金などから差し引いて財産分与したいと主張しても、認められないケースが多いです。たとえ不動産を相続していても、売却などで現金化して使ってしまっていれば、売価そのものを財産分与の取り分として主張することは難しいことを覚えておきましょう。
財産分与で悩む、相続が絡んだトラブル事例

相続した遺産がそのままの形で残っていたとしても、財産分与の対応で悩むことはよくあります。特に不動産やペットを相続したときにトラブルになることも少なくありません。そこで、ほかにもどんなトラブルがあるのかと、どのように財産分与が行わるのかを解説していきます。
相続した土地に夫婦で建てた建物がある
マイホームの購入は人生でもトップクラスの出費なので、少しでも節約しようとします。もし相続した土地があって立地や広さなどに問題がなければ、そこに家を建てようと考えることは当然の流れです。
問題になるのは、財産分与のときに家をどのようにするかです。土地は相続した人のものですが、家があると土地は自由にすることができません。このようなケースの場合は、以下の3つのパターンで財産分与が行われます。
相手が住み続けるなら借地代を請求する
自分は家から出て相手が住み続ける予定なら、相続した土地は売約や運用が自由にできないので、借地代を請求するようにしましょう。無料で土地を利用させていては固定資産税の負担が続き、土地活用によって資産を増やす機会も失ってしまいます。
借地代を決める方法は4種類あり、それぞれの特徴は以下のようになっています。
| 借地代の決め方 | 特徴 |
| 固定資産税を参考にする |
|
| 路線価を使う |
|
| 積算法で期待値を見積もる |
|
| 賃貸事例比較法を使う |
|
建物部分は相手が所有することになるので、財産分与で相応の価値のあるものは受け取っておきましょう。借地代が得られれば不労所得で生活に余裕が生まれ、土地にかかる税金の支払いで困ることはありません。
自分が住み続け相手に家の評価額の半分を支払う
自分が相続した土地なのだから、相手に出て行ってもらうという選択肢もあります。この場合は、財産分与で家の評価額の半分に相当する財産を、相手に渡す必要があります。家以外にも十分な財産があれば、この方法で家に住み続けることが可能です。
家の評価額を手軽に調べるなら、一括査定を受けることをおすすめします。情報を一度入力するだけで複数社に査定依頼ができ、簡易査定なら結果もすぐに出してもらえます。
家の評価額で折り合いがつかないのなら、不動産鑑定士に評価してもらってください。戸建てで20万円程度はかかってしまいますが、評価された額は裁判でも根拠のある数字として使えます。
家を売却し利益を半額ずつ分ける
借地代の未払いが不安であったり、財産の中に家の価値と同額のものがなかったりした場合は、家を売却してしまったほうがよいです。現金なので均等に分けられますし、離婚後にやり取りをする必要もありません。
家の売却は基本的に土地とセットで行うので、相続した土地部分の利益は自分のものになります。売却したときの価格に内訳を明記しておけば、建物部分だけの利益を均等に分けることが可能です。両者が納得できるよう、最新の相場は一括査定サイトを利用して調べておきましょう。
相続した遺産以外の財産分与方法について、詳しく知りたい人は以下の記事がおすすめです。

おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する
その他の一括査定サイトや選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

相続した建物で一緒に経営していた
財産分与の段階で、相続した遺産が生活費などに混じることなく残っていても、その維持に相手の協力が不可欠なら事情は変わってきます。
たとえば、旅館やペンションなどを相続して夫婦で経営していた場合は、相手の協力なしに財産を維持することは困難です。特殊な例ではありますが、財産分与の割合は相手の貢献度を評価して決めることになります。
しかし、相続した土地に建てたお店で協力して経営をしていた場合は、土地が財産分与の対象外になることがあります。どうなるかは一概に判断できないので、損をしたくなければ自分だけで結論を出さないようにしましょう。
離婚をした当人が財産分与前に亡くなった場合
財産分与は、離婚をした当人が存命中に終わらない場合があります。亡くなった側に子供がいれば、どのように財産分与が行われるのでしょうか。
財産分与されるかどうかは請求権の種類で変わりますが、財産分与の請求権の特徴は以下のようになっています。
| 財産分与の請求権の種類 | 特徴 |
| 清算的財産分与請求権 | 結婚中に形成された財産を平等に分ける |
| 慰謝料的財産分与請求権 | 離婚原因の精神的負担などを和らげるための請求 |
| 扶養的財産分与請求権 | 離婚による生活困窮を避けるため、他の財産分与では不足分を請求する |
清算的財産分与の分は財産なので、通常の遺産相続と同様に子供でも適用されます。慰謝料的財産分与の精神的負担は子供には関係ないのですが、最高裁の判例で相続の対象になっています。
扶養的財産分与に関しては夫婦本人同士の問題として扱われ、基本的に子供にまで請求権は相続されません。ただし、わずかですが相続を認めた判例は存在するので、どうしても必要なら専門家に相談してみてください。
相続したペットは財産分与の対象になるか
ペットは生き物ですが法律上は物扱いとなり、相続される遺産の一部として認められています。財産分与でも相続したペットは物扱いなので、特有財産に分類されるため相続した人のものです。
結婚してから購入したペットなら、共有財産で財産分与の対象になります。しかしペットが成長した犬や猫なら、買い手が付きにくいので評価額は0円になりやすいです。ペットが幸せに暮らせるように、話し合って財産分与をしてください。
相続した財産の相続でもめるなら調停

財産分与は基本的に夫婦での話し合いで決めますが、なにかともめるケースがあります。離婚の原因によっては冷静な話し合い自体ができずに、感情の折り合いが付けられないでしょう。
そこで決着をつけるためにも、裁判所での調停を利用するのがおすすめです。調停にはどんなメリットがあるのかや申し立ての手順を解説していきます。
調停で財産分与をするメリットとは
財産分与の調停は、裁判官や調停委員が離婚する夫婦の話をそれぞれ聞いて、解決のための助言をしてくれます。調停のため、申し立ての手間や費用がかかりますが、以下の3つのメリットがあります。
- 利害関係のない第三者による公平な判断
- 離婚相手と直接話す必要がない
- 調停で合意した内容には強制力がある
1つ目のメリットのおかげで、相続した遺産の所有権を法律的に正しく主張することができます。離婚の原因が自分にあり慰謝料の負担があった場合でも、極端に不利な状況にはならないでしょう。
2つ目のメリットのおかげで、冷静に自分の主張を話すことができます。相手が目の前にいると感情的になりやすく、威嚇されれば十分に主張することはできません。しかし調停なら話す相手は裁判官や調停委員なので、今まで相手には言えなかった主張も好きなだけ伝えられます。
3つ目のメリットのおかげで、強制執行までの手間が省けます。財産分与について離婚協議書を作成していても、強制執行のためには裁判を起こさなければなりません。しかし調停で作成する調停証書を使えば、隠されている財産まで差し押さえることができます。
調停で財産分与をする注意点
財産分与には財産分与の請求が可能な期間として、除斥期間と呼ばれるものがあります。除斥期間は離婚をしてから2年間あり、時効に似ていますが調停をしている期間もカウントは進んでいきます。
調停の期間中であれば、除斥期間を過ぎたとしても財産分与の請求は可能です。しかし調停に失敗したときに問題が起き、裁判を起こす場合には調停を取り下げる必要があります。除斥期間を過ぎていると、調停を取り下げた段階で財産分与の請求権がなくなってしまいます。
調停をしても話がまとまる保証はありません。失敗する可能性が少しでもあるなら、除斥期間に余裕があるうちに調停を始め、裁判まで覚悟しておきましょう。
調停を申し立てるのに必要なもの
財産分与で調停を申し立てるには、以下の書類と費用が必要です。
- 調停の申立書とその写しを各1部
- 除籍の記載がある戸籍謄本
- 財産分与するものの目録
- 夫婦の財産に関わる資料(給与明細、通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)
- 収入印紙1,200円
- 郵送用の切手
申立書の原紙は、裁判所の「財産分与請求調停の申立書」からダウンロードできます。記入する内容は、申立人と相手方の住所氏名、生年月日、申立ての趣旨と理由などで、専門的な知識はいらず簡単に作成できます。
調停を申し立てる先は、基本的に相手が住んでいる地域を管轄している家庭裁判所ですが、地域によっては家庭裁判所の支部になる場合もあります。管轄がどこになるのかは、裁判所の公式サイトから確認してください。相手が合意してくれれば、指定した家庭裁判所でも申し立てることは可能です。
郵送用の切手は、どれだけ必要なのかは家庭裁判所によって変わります。各裁判所の公式HPを見るか電話で問い合わせをして、確認をしておきましょう。
財産分与を調停で話し合う手順
申し立てをしてから調停が成立するまでの手順は、以下のようになっています。
- 書類を揃えて調停の申し立て
- 調停をする日程を知らせる書類が郵送されてくる
- 期日に1回目の調停
- 成立しなければ期間を空けて2回目以降の調停
- 調停の成立(不成立)
1回目の日程は、申し立てをしてから1~2週間程度で書類が郵送されてきます。1回目の調停の期日は、申し立てから1~2ヶ月が目安です。調停での話し合いは1回当たり2時間程度で終わります。2回目以降は調停から1~2ヶ月空けて行われ、成立するまでのトータルの期間は6~12ヶ月が目安と考えましょう。
もし離婚する前に、相続した遺産での財産分与で調停を行いたいなら、夫婦関係調整調停となります。提出する書類は夫婦関係調停申立書に変わりますが、その他の手順は財産分与請求調停と同様です。話し合える内容は、財産分与だけでなく慰謝料や親権など多岐に渡るので、成立までの期間は長くなるかもしれません。
調停で話がまとまらないなら裁判
財産分与で裁判をして判決が出るまでの手順は、以下のようになっています。
- 調停委員会から不成立の通達
- 財産分与についての裁判の提起
- 口頭弁論の日程の連絡
- 期日に1回目の口頭弁論
- 期間を空けて2回目以降の口頭弁論
- 裁判の判決
口頭弁論は1ヶ月に1回程度行われ、判決がでるまでの期間は6ヶ月~2年が目安です。かかる費用は調停より高く、提起するだけで約20,000円、弁護士に依頼する場合は追加で数十万円は覚悟しておきましょう。
裁判で何か主張する場合は根拠となるものを示さなければならず、調停中に相手に問題があったとしても、内容は裁判に引き継いでもらえません。調停の段階から裁判で勝つための根拠を集めていないと、自分に有利な判決を勝ち取ることは難しいです。
裁判は調停より手間も費用もかかりやすいので、可能なら調停の段階で決着をつけるようにしましょう。調停が不成立でも、協議した内容をあらためて夫婦で話し合えば、新たな妥協点が見つかるかもしれません。
財産分与と相続財産の分割は違う

相続財産を親類で分けることを、財産分与と考える人がいます。しかし相続遺産を分けることは遺産分割が正しく、財産分与とは内容がまったく違います。
ここでは財産分与と遺産分割の違いや、遺産分割のやり方について解説します。親族であとからもめないために、証拠になる書類の作成もしましょう。
財産分与は離婚時に行われる
財産分与とは離婚する際に、夫婦で築いた財産を公平に分けることです。基本の割合はそれぞれ財産の2分の1ですが、財産形成の貢献度によっても変わり、お互いが合意できれば自由に割合を決められます。
対象になる財産は結婚してからのものが前提で、結婚前から所有しているものや結婚中に相続した遺産は除外されます。たとえば、住宅ローンやクレジットカードの未払い分といった負債は、財産分与の対象です。
負債も含めた財産をすべてリストアップしてから、夫婦で話し合いをしてください。離婚前に決着をつけておくと、除斥期間の心配をせずにすみます。
遺産を兄弟で分けるのは遺産分割
遺産分割とは、遺言書を残さずに亡くなった人の遺産を、相続人である兄弟や親族で分けることを指します。誰がどれだけの割合で遺産を相続するかは決まっていて、亡くなった人との間柄で以下のようなパターンがあります。
| 相続人 | 遺産分割される割合 |
| 配偶者と亡くなった人の親 | 配偶者2/3、亡くなった人の親1/3 |
| 配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2 |
| 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 配偶者だけ・子供だけなど | 相続人にすべて |
子供が複数人いるなら相続する遺産をさらに人数分で割りますが、兄弟姉妹や親の場合も同様です。遺言書が残っていれば、指定された割合で遺産は相続されることになります。
財産分与との大きな違いは、兄弟姉妹や親族にも取り分があることです。具体的にどの遺産を誰が相続するかは、相続人で協議してください。協議で決着がつかなければ、財産分与と同様に調停や裁判を行って合意を目指します。
遺産分割の種類
分割される遺産は、財産分与のときと同様にさまざまな形のものが対象になります。現金なら平等に分割しやすいのですが、不動産などは簡単にいきません。遺産を分割する方法によって、以下の4種類があります。
| 種類 | 特徴 |
| 現物分割 | 不動産や株券などをそのままの形で相続 *不平等が生じやすい |
| 代償分割 | 一方が分割できない財産を相続し、もう一方が相当する金額の遺産を相続 *代償できるだけの遺産がない場合がある |
| 換価分割 | 不動産や株券を現金化して分割 *現金化するまでに時間がかかる場合がある |
| 共有分割 | 遺産を共同で所有する *遺産を自分だけの判断で売却などができない |
どの分割方法も一長一短があり、どんな遺産があるかや親族で納得できる分け方ができるかなどで、ベストな選択肢は変わってきます。また、分割方法によってかかる税金も変わるので注意しましょう。
遺産分割をする方法
財産分与との違いを理解したら、次は実際に遺産分割をする方法について見ていきましょう。裁判での決着まで想定して、以下のような流れになっています。
- 遺言書がないかを探す
- 戸籍などから相続人をリストアップ
- 遺産分割の話し合い
- 話し合いでまとまらない場合に遺産分割調停
- 調停が不成立なら遺産分割審判
- 決定した内容に沿って遺産分割
相続人には、誰も把握していなかった離婚相手との子供も含まれるので、戸籍は必ずチェックしてください。親族での話し合いで分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。相続人全員の署名や捺印が必要ですが、分割の割合や手続きの期限を明記することで、手続きのトラブル防止になります。また、調停や裁判になってしまったときにも効力はあります。
相続人に入っているが遺産はいらないという場合は、相続放棄ができます。遺産に負債が多いときは、相続放棄をしたほうがお得です。放棄するなら、遺産相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄を家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をしたときに、ほかに相続人がいない場合は相続財産管理人を決めてください。決まるまでは管理責任があり、トラブルの対処もしなければなりませんが、弁護士や司法書士に依頼をすればスムーズに手続きが完了します。
まとめ

相続した遺産の財産分与は、法律できちんとやり方が決まっていますが、知識がないと夫婦での話し合いで損をするかもしれません。夫婦で築いた財産と相続した遺産を可能な限り分けて、自分の取り分は確保しましょう。
財産分与は、基本的にお互いの話し合いで決着をつけます。どうしても決着がつかないなら、調停を申し立てて第三者に公平な判断をしてもらいましょう。裁判までになると費用も期間もかかるので、調停までで妥協点を探すことをおすすめします。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。